公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
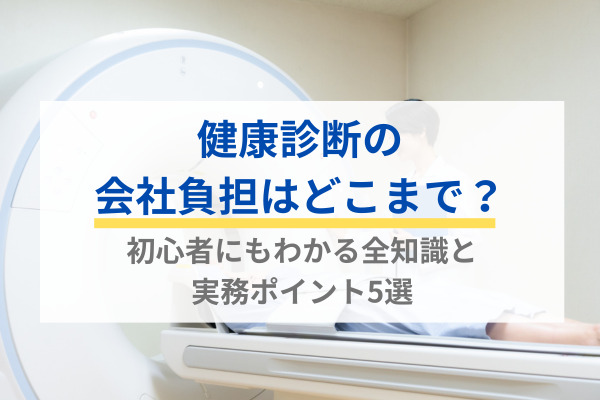
健康診断には、雇入時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者など複数の種類があり、その都度費用が発生します。
企業にとっては決して小さくない負担であり、「どの程度の予算を確保すべきか」と悩む担当者も少なくありません。
この記事では、健康診断の費用が会社負担となるケースや、定期健康診断以外の検査費用の扱いなど、企業が知っておくべき基本ポイントをわかりやすく解説します。
あわせて読みたい
原則として、従業員の健康診断の費用は会社負担です。
健康診断の実施は、労働安全衛生法によって会社に義務付けられています。
特に、一般定期健康診断は、すべての常時使用される労働者に対して年に1回以上行うことが求められています。
この義務は、従業員の健康状態を定期的に把握し、早期に健康問題を発見することで、労働者の健康を維持し、労働環境を改善することを目的としています。
会社が健康診断を負担する理由は、従業員の健康管理が企業の責任であるとされているからです。
健康診断を実施することで、従業員の健康状態を把握し、必要に応じて適切な対応を取ることが可能になります。
また、健康診断の結果を基にした健康管理は、企業にとっても長期的なコスト削減につながります。
従業員の健康問題を早期に発見し、適切に対処することで、病気による長期休職や医療費の増加を防ぐことができるためです。
このように、健康診断の会社負担は、企業にとっても従業員にとってもメリットのある取り組みとなっています。
ここでは、会社が負担するべき健康診断の範囲について詳しく解説します。
労働安全衛生法に基づき、企業は従業員に対して定期的な健康診断を実施する義務があります。
この法律では、一般定期健康診断の費用を会社が負担することが求められています。
具体的には、血液検査や視力検査、胸部X線などの基本的な検査が含まれます。
法律で義務付けられていない健康診断も存在します。
たとえば、人間ドックや特定のがん検診などは、通常、会社負担の対象外です。
これらの検査は、個人の健康維持や早期発見を目的とするものであり、法律上の義務には含まれません。
こうした検査を希望する場合、従業員自身が費用を負担するケースが一般的です。
ただし、企業によっては、福利厚生の一環として一部を補助することもあります。
健康診断の際に追加されるオプション検査は、通常、会社負担の対象ではありません。
オプション検査とは、標準的な健康診断に加えて行われる追加検査のことです。
たとえば、骨密度測定やアレルギー検査などが該当します。
これらの検査を希望する場合、個人での負担が求められることが多いです。
ただし、企業によっては、オプション検査費用も一部補助を行う場合もあるため、事前に確認しましょう。
従業員の家族の健康診断費用については、通常、会社負担の対象外です。
会社が負担するのは、あくまで従業員本人の健康診断に限られます。
家族の健康診断は、個人で手配し、費用を負担する必要があります。
しかし、福利厚生として家族の健康診断をサポートする企業もあります。
この場合、企業が一部または全額を負担することもあり得ますので、福利厚生制度を確認することが大切です。
契約社員やパートタイムの従業員に対しても、労働時間や契約内容によっては、会社に健康診断の実施義務が生じる場合があります。
一般健康診断の場合、無期契約または契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者については、企業に実施義務があります。
また、週所定労働時間が2分の1以上4分の3未満のパートタイム労働者については、法令上の義務規定はないものの、実施が望ましいとされています。
一方で、週所定労働時間が正社員の2分の1未満のパートタイム労働者や、契約期間が1年未満の有期契約者については、健康診断を実施する法的根拠はありません。
ここでは、健康診断の内容と費用負担がどこまで及ぶのかについて詳しく解説します。
前述したとおり、一般定期健康診断は、労働安全衛生法に基づき企業が従業員に対して年に一度実施することが義務付けられています。
この費用は原則として会社が全額負担します。
具体的な検査項目には、身長・体重測定、血圧測定、視力検査、聴力検査、胸部X線検査、血液検査などが含まれます。
また、企業によっては追加の健康診断項目を設ける場合もありますが、その際の費用負担については事前に確認が必要です。
追加検査がある場合、それが会社負担になるかどうかは企業の方針によります。
特定業務従事者向け健康診断は、特定の業務に従事する従業員に対して6ヶ月以内ごとに1回(年2回)実施されるもので、その費用も会社が負担します。
対象となる業務には、深夜業(午後10時〜午前5時の時間帯を含む業務)、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく寒冷・暑熱な場所での業務、重量物の取扱い業務などが含まれます。
例えば、鉛や有機溶剤などの危険物を扱う場合、定期的な血液検査や尿検査が行われます。
健康診断を受けた後に必要となる健康診断書の発行手数料についても、会社が負担するケースが一般的です。
診断書は、従業員が健康であることを証明するために重要な書類であり、企業がその発行手数料を負担することで、従業員の負担を軽減します。
ただし、診断書が個人的な利用目的で必要な場合、その発行手数料は自己負担となることが多いです。
そのため、個人利用か業務利用かによって費用負担が異なる点に注意が必要です。
健康診断を受ける際の勤務扱いについては、一般健康診断の場合、法律上は労働時間と定められていないため、企業の判断によります。
ただし、多くの企業では勤務時間内に実施し、出勤扱いとしています。
特殊健康診断の場合は労働時間として扱われます。
また、健康診断を受けるためにかかる交通費については、企業によって対応が異なります。
会社指定の医療機関で受診する場合は交通費を支給する企業が多いですが、事前に確認しておくことが重要です。
健康診断の結果、再検査や精密検査が必要となった場合、その費用負担については法律上の義務がないため、原則として自己負担となります。
ただし、特殊健康診断の再検査については会社負担が義務とされています。
また、一般健康診断の再検査についても、従業員の健康管理と安全配慮義務の観点から、費用の一部または全額を負担する企業も増えています。
さらに、一定の条件を満たす場合は「労災保険二次健康診断等給付」の対象となり、無料で受診できるケースもあります。
詳細は各企業の就業規則や健康保険組合の制度を確認することが推奨されます。
A: 労働安全衛生法により、企業には従業員に対して年1回の定期健康診断を実施する義務があります。
そのため、一般的に健康診断の費用は会社が全額負担します。
ただし、任意で追加するオプション検査(人間ドックなど)は自己負担となる場合があります。
A: 健康診断の種類によって異なります。
一般健康診断の場合、受診時間の賃金支払いは労使間の協議によって定められます。
ただし、円滑な受診のため、多くの企業では勤務時間内の受診を認め、賃金を支払っています。
一方、特殊健康診断(有害業務従事者向け)の場合は、労働時間として扱われ、賃金の支払いが必要です。
就業規則や人事部門に確認しておくと安心です。
A: 自己負担で健康診断を受ける場合、一般的な基本検査(身長・体重・血液・心電図など)で5,000〜15,000円程度が相場です。
人間ドックなどの精密検査を含む場合は、内容により3万円〜10万円前後になることもあります。
自治体による助成制度を活用できるケースもあります。
A: 通常、会社が指定する健康診断を勤務時間内に受ける場合は欠勤扱いにはなりません。
ただし、個人の都合で別日に受ける、または任意で受診する場合には、欠勤や有給休暇扱いになることもあります。
会社の就業規則や人事部門の指示を確認して対応しましょう。
健康診断の会社負担について、従業員は基本的に会社が負担することが法律で義務付けられています。
労働安全衛生法に基づく最低限の負担範囲や、負担義務のない健康診断、オプション検査費用の扱いなど、会社がどこまで負担するかを理解することが重要です。
また、契約社員やパートタイム労働者の対応についても知識を持っておくと良いでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

サーベイツールを徹底比較!

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
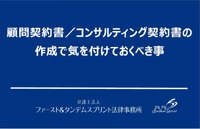
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

【中堅社員の意識調査】成長実感が低いほど、離職意向が高まる傾向

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
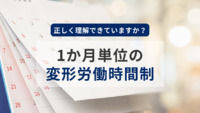
1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?
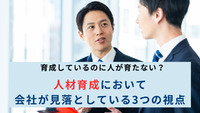
育成しているのに人が育たない?人材育成において会社が見落としている3つの視点

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説

【中堅社員の意識調査】管理職志向のない中堅社員、管理職を打診されたら8.3%が「承諾」、25.1%は「辞退」

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
公開日 /-create_datetime-/