公開日 /-create_datetime-/
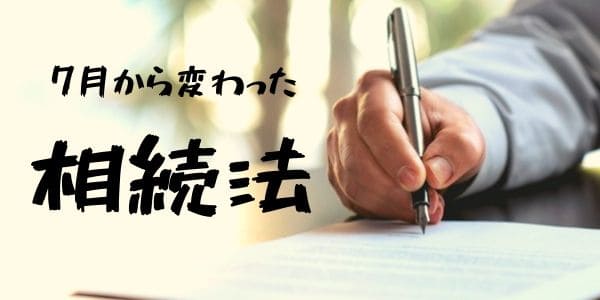
2018年7月、相続に関する民法を改正する法律が成立しました。約40年ぶりとなる相続法の大幅な見直しで、大半が2019年7月から施行されています。
高齢化社会の実態を意識した今回の改正は、「残された配偶者」を保護するための内容が多いことが特徴です。相続法がどのように変わったのか、主な内容を解説します。
目次【本記事の内容】
住居の生前贈与が相続財産の対象外に
これまでの相続法では、被相続人が生前に配偶者へ住居の贈与をした場合、遺産が先渡しされたものとみなされ、相続において分配される総額が贈与分だけ減らされていました。そのため、配偶者が生活に困らないようにとの意味合いで、被相続人が住居を生前贈与しても、配偶者が分配される遺産総額は生前贈与をしない場合と変わりませんでした。
しかし、今回の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で、配偶者に対し生前贈与された住居は、遺産相続の対象から除外されることになりました。これにより、配偶者はより多くの相続財産を得られ、これまで以上に生活を安定させられるようになります。
例えば、評価額2,000万円の住居を配偶者に生前贈与し、その他6,000万円の財産を残して夫が亡くなり、配偶者と長男が相続するケースを考えてみましょう。今までの相続法では、総財産8,000万円のうち住居分2,000万円は既に配偶者が受け取り済みとされていたため、配偶者の法定相続分である4,000万円のうち、新たに受け取れる分は2,000万円でした。
しかし、新制度では、住居分の2,000万円は遺産分割の対象外と扱われるため、その他6,000万円を長男と半分に分け、配偶者は前制度の場合より1,000万円多い3,000万円相続できるようになります。
被相続人の介護に貢献した親族は相続人に対し金銭請求が可能に
長男の配偶者が同居の義父母を長年介護するといったケースは珍しくありませんが、これまでは義父母の死後も配偶者は遺産分配に参加できず、一方で長男の兄弟は介護と関係なく財産を得られていたため、不公平であるとの指摘がなされていました。
相続時に長男がまだ生きていれば、相続人である長男の配偶者として相続の恩恵にあずかれる側面もありましたが、既に長男が亡くなっている場合は、配偶者が遺産の分配を主張できませんでした。
今回の改正ではこのような不公平をなくすため、相続人以外の親族が被相続人の介護に貢献し、被相続人の財産の維持や増加に対し特別に寄与した場合には、相続人に対し金銭を請求できるようになります。
ただし、遺産分割自体はこれまで通り相続人のみで行うこととされるほか、請求金の具体的な基準や目安は示されておらず、判例などを参考に決定するとみられています。
被相続人名義の預貯金が一部引き出せるように
今回の改正では、遺産分割前に発生しがちなお金の問題にも配慮されています。これまでは、葬儀費用の支払いや相続債務の弁済など、被相続人の死後お金が必要になった場合でも、遺産分割完了まで相続人単独では遺産のうち預貯金が引き出せないという問題がありました。
被相続人が自分の葬儀費用として蓄えていたお金も、いざ葬儀となった際にすぐ用意できないケースや、諸事情により遺産分割協議の時間がかかる場合に、相続人の生活費や納税などに困るケースは少なくなかったでしょう。
しかし、この度の改正により、このような相続人の資金需要に対応できるよう、相続人単独でも一つの金融機関あたり法定相続分の3分の1(最高150万円)まで、家庭裁判所の判断を経ることなく引き出せるようになります。
また、裁判所が必要と認めた場合は、他の相続人の利益を害しない範囲で無制限に引き出すことが可能です。引き出した金額は、その後の遺産分割協議の中であらためて精算することになります。
相続後も生活の安定が図れる「配偶者居住権」の創設
相続法に新しく創設された「配偶者居住権」は、2020年4月から施行されるルールですが、今回の改正において最も注目される内容であるため、併せて紹介します。
従来の制度では、住居が配偶者以外の者に遺贈されたり、被相続人が配偶者に住居を使わせない遺言を残していたり、配偶者が相続放棄したりすると、配偶者はそれまで住んでいた住居に住めなくなっていました。
また、配偶者が遺産分割で被相続人の住居を相続すると、財産の金額や内容によっては、現金など他の財産を受け取れず、生活費が足りなくなるなどの問題がありました。
しかし、今回の改正により、配偶者はこれまで住んでいた住居に最低でも半年間は住み続けられるようになるため、突然住む場所を失ってしまうようなことがなくなります。また、住居の相続に関し、配偶者が「配偶者居住権」、他の相続人が「負担付き所有権」をそれぞれ取得することで、配偶者はそれまで住んでいた住居にそのまま住み続けられるうえ、受け取れる他の財産の額も増加させられるようになります。
まとめ
今回の法改正における特徴は、高齢者時代に対応し、保護されるべき対象者が拡大された点が挙げられるでしょう。これにより、配偶者の立場が向上し権利が守られ、義父母への介護に対しても前向きに臨めるようになることが期待されます。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください
関連記事:事業承継ってなに?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
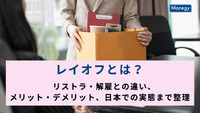
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
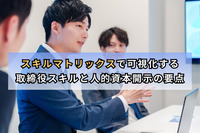
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース



































