公開日 /-create_datetime-/
上場企業で株主が一番多い企業はどの企業?
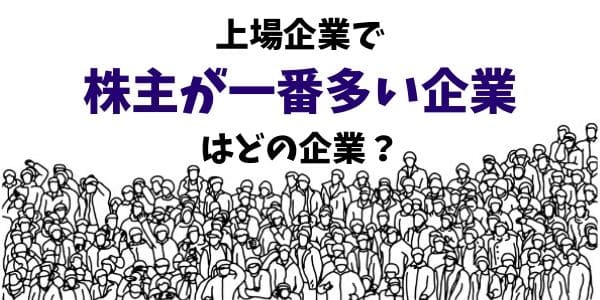
日本の上場企業のうち、株主が最も多い企業はどの企業かご存知でしょうか?
2014年1月に、年間120万円までの投資額について分配金や売却時の譲渡益が非課税となる「NISA」がスタートしたこともあり、最近では株式投資が若年層の資産運用手段とみなされるようになっています。また、今ではスマホで簡単に株式を購入できるので、以前に比べると個人・一般人が株主となるハードルはかなり低くなっており、「株主」の数が増えていると言えるでしょう。
今回は、日本における株主数はどのくらいか、株主が多い企業はどこなのか等について解説していきます。
そもそも株主とは?保有する権利と責任
株主とは、株式会社が発行している株式を所有している、会社への出資者のことです。株主は保有している株式数の割合によって「株主権」が生じます。株主権には「自益権」と「共益権」とがあり、自益権として認められているのは、「利益配当請求権」をはじめ、「新株発行差止請求権」、「残余財産分配請求権」、「新株引受権」、「株式買取請求権」、「名義書換請求権」等です。一方、共益権としては、「経営参加権」、「株主提案権」、「代表訴訟提起権」などが認められています。
ただ、株主には権利も発生しますが、株式の購入額、すなわち「出資金」の範囲内で「有限責任」を負わなければなりません。株式を保有する会社が法に反する行為を行った場合、株主がその法的責任を問われることはありませんが、その不祥事により会社が倒産する等の事態が起こったら、出資した金額が戻ってこないことを覚悟する必要があります。
株主の種類は法人株主、個人投資家、機関投資家、外国人株主
株式会社の株主となるのは、主に親会社や金融機関、取引先企業などの「法人株主」、顧客からお金を集めて投資活動を行う「機関投資家」、個人で株式を所有する「個人株主」、外国に住む株主である「外国人株主」等です。法人株主は、主に傘下・関連企業に経営上の影響力を行使することを目的として株式を保有しています。一方、機関投資家や外国人投資家などは、資産運用によって利益を上げることが株式所有の主な目的です。個人株主の場合は、創業者一族等が自社を所有するために株式を保有する、あるいは個人で株式を売買して利益を得ることを目的とする「個人投資家」のケースなどがあります。
現在、各株式会社が出資者として目を付けているのが、個人投資家、それも少額の投資を行う一般人の投資家です。2014年1月に少額投資非課税制度(NISA)がはじまり、2018年には積み立て型の少額非課税制度(つみたてNISA)も開始。今や普通のサラリーマンや主婦が、税金を気にせずにスマホで気軽に少額投資できる時代となっています。これら少額の個人投資家を取り込んで資金調達を行うべく、近年各株式会社は「インベスター・リレーションズ(IR:投資家向け広報)」や「株主優待」に力を入れるようになってきました。
日本に株主はどのくらいいるのか
少額非課税制度とそれに伴う企業の個人投資家に対する広報活動の活発化等の影響もあり、ここ数年、個人株主の数が増えています。東京証券取引所の『株式分布状況調査』によると、株主数の延べ人数は2005年頃に4,000万人を越え、その後2008年頃から横ばいの状態が続いていましたが、NISAがはじまった影響で2015年から一気に急増。2017年度初めに5,000万人を突破しています。2017年度における株主数(合計で5,272万3,528の人または組織)の内訳は、「政府・地方公共団体」が1,331(0.0%)団体、「金融機関」が10万1,562社、「証券会社」が9万900社、「事業法人等」が74万6,105社、「外国法人等」が48万3,678社、「個人・その他」が5,129万9,952です。出資額はともかく単純に株主数だけでみると、「個人・その他」が全体の97.3%を占めています。
個人マネーをひき付けている企業は2015年以降における株主数の増加率が非常に高く、2015年3月末時点から2018年3月末時点にかけて、例えば「日産自動車」では2.2倍、「オリックス」では3.3倍、「ヤマダ電機」では3.7倍、「味の素」では3.2倍も株主数が増加しました(「日本経済新聞」2018年7月3日より)。
株主が多い日本企業のランキング
では、株主数が多い企業はどこでしょうか。日本企業の第1位から第10位までを順に以下に列挙してみましょう。
順位 | 企業名 | 株主数 |
| 第1位 | みずほフィナンシャルグループ | 99万9,139 |
| 第2位 | ソフトバンク | 82万2,811 |
| 第3位 | 第一生命ホールディングス | 76万629 |
| 第4位 | イオン | 73万2,420 |
| 第5位 | 三菱UFJ | 67万948 |
| 第6位 | 日本電信電話(NTT) | 63万7,155 |
| 第7位 | 日本郵政 | 62万2,647 |
| 第8位 | トヨタ自動車 | 61万3,379 |
| 第9位 | 日産自動車 | 55万8,085 |
| 第10位 | ANAホールディングス | 46万818 |
(2019年6月21日時点 「StockWeather」の調査より)
日本を代表する企業がランクインしていますが、株主数が最も多いのは金融機関である「みずほフィナンシャルグループ」です。トヨタ自動車はグループでの年間総売上高は約29兆(2018年3月期決算より)で他者を圧倒していますが、株主数の点ではソフトバンクやイオンの方が多くなっています。第2位ともかなりの差があり、突出して株主数が多いと言えるでしょう。第2位のソフトバンク、第4位のイオンは、個人株主への株主優待が充実していることでも知られています。
まとめ
今や個人がスマホで気軽に投資できる時代です。しかし出資した金額は、株価の変動次第では元本割れをする、もしその企業が倒産すれば投資額が返ってこなくなる、というリスクがあることを承知する必要があります。個人で投資をする場合は、メリットだけでなくデメリットも十分に検討した上で、慎重に決断するようにしましょう。
関連記事:資本金が最も多い企業はどこでいくら!?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道
ニュース -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題
ニュース -

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方
ニュース -
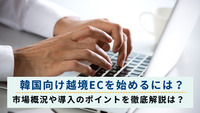
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース




































