公開日 /-create_datetime-/
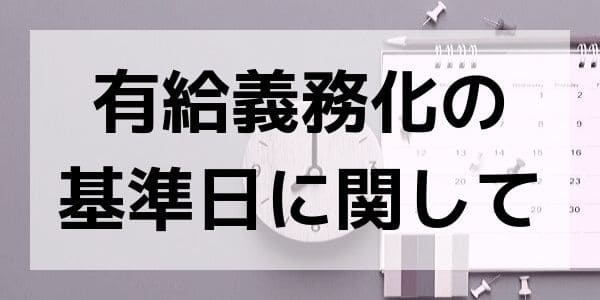
労働基準法改正に伴い、2019年4月から、すべての企業(使用者)は、対象労働者に対して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
労務担当者には、義務違反にならないよう慎重に対応することが求められます。義務違反を行ったすべての企業は、罰則として30万円以下の罰金が科せられるからです。
今回は、有給義務化における基準日や注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
有給義務化の対象となる労働者と改正ポイント
有給義務化は、労働者が会社や職場の同僚に遠慮して請求しにくく、有給が有効活用されていないことを背景に、制度化されたものです。従業員が、スムーズに有給取得できるようにすることが目的です。
有給義務化の対象となる労働者は、「年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者含む)」です。
雇い入れから6ヶ月継続勤務をし、全労働日の8割以上を出勤している場合、年次有給休暇が付与されます。
付与日数が10日以上のアルバイトやパートタイム労働者も対象者であり、所定労働日数に応じた有給の比例付与義務が課せられているので注意してください。
改正のポイントは、対象労働者には年次有給休暇日数のうち、「基準日から1年以内に年5日、使用者による時季指定」が義務付けられたことです。
ただし、すでに年次有給休暇を5日以上取得している労働者に対しては、時季指定は不要となります。
有給休暇基準日のケーススタディ
有給休暇の基準日の設定には、いくつかのパターンが考えられます。ケースごとに分けてどのように対応すればよいのか、例を挙げて解説します。
ケース1:法定どおりの基準日
法定どおりの基準日であれば、雇い入れ日から起算して6ヶ月以上の継続勤務後に、年次有給休暇を付与します。
新卒者のみ採用する企業であれば、基準日に関して混乱することなく、年5日取得の義務を果たせるでしょう。
例)4月1日入社→法定基準日の10/1に10日を付与→翌9/30までの1年間に5日の取得時季を指定する
ケース2:入社日に前倒しで有給を付与する場合
入社日に前倒しで5日間付与し、3ヶ月後に5日間付与するパターン例を挙げます。
4/1入社日に5日間の有給休暇を付与
↓
7/1に5日間の有給休暇を付与(第一基準日)
上記のようなケースでは、10日間の有給休暇が付与された日を第一基準日と設定し、向こう1年間に最低でも5日間の有給休暇を取得させる義務があります。
第一基準日以前に取得した有給休暇日数は、取得義務5日間から差し引いて問題ありません。
ケース3:入社日にかかわらず一斉付与する場合
中途採用者やパートタイム労働者などを多く抱える企業において、法定どおりの基準日だと管理自体が煩雑になりがちです。
基準日が労働者によってばらばらのため、入社日に関係なく付与日を統一した「一斉付与方式」をとる企業が多くあります。
入社日にかかわらず全員の有給休暇を、特定日(第二基準日)に一斉付与するパターン例を挙げます。
例)入社日は6/1だが毎年4/1に一斉付与する
例のように、4/1など特定日に第二基準日を設け、有給休暇の付与日を統一することで管理が容易になり、付与漏れによる罰則のリスクを回避することができます。
この方法は労働者にとっても、気兼ねなく有給消化しやすいメリットがあります。
有給義務化におけるダブルトラックについて
一斉付与方式などをとった場合、入社年と翌年の付与基準日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じます。
こうしたケースでは、当該期間に取得させることが認められています。
例)4/1入社の労働者に、1年目は法定基準日の10/1に10日付与し、2年目は4/1の一斉付与日(第二基準日)に11日付与する場合
当該期間は、10/1から翌々年3/31までの18ヶ月となり、【5日÷12×Nヶ月】の計算式で管理することができます。
例の場合なら、5日÷12×18ヶ月=7.5日間以上取得させることになります。
また、上記例で第一基準日までに仮に2日の有給休暇を取得している場合の義務日数の計算は、以下のとおりです。
(18÷12×5)-2=5.5日
年次有給休暇の管理について
対象者に最低でも年5日の年次有給休暇を確実に取得してもらうには、基準日を含めた書類管理が大切です。
改正法施行に伴い、労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられ、3年間の保存義務が課せられています。
有給の基準日や利用状況などを管理できる用紙が必要ですが、勤怠管理システムなどを利用するとよいでしょう。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -
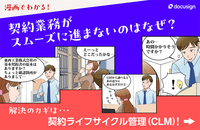
マンガでわかる!契約業務の課題と解決策 〜解決のカギはCLMにあり〜
おすすめ資料 -
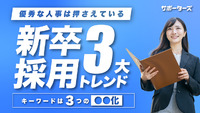
【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

育休明けの有休付与|付与日数計算・年5日取得義務・2025年10月法改正まで人事担当者向けに徹底解説!
ニュース -

高齢労働者の「転倒」を防ぐために~2025年度の全国安全週間が始まりました~
ニュース -

中堅・中小企業における海外進出のメリットとは
ニュース -
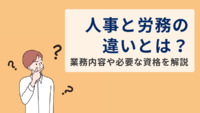
人事と労務の違いとは?業務内容や必要な資格を解説
ニュース -
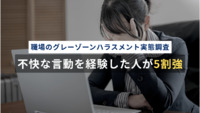
【職場のグレーゾーンハラスメント実態調査実施】ため息や舌打ち、飲み会や接待への参加強制、無視や仲間外れ等不快な言動を経験した人が5割強、抑制を規定する企業3割程度
ニュース -
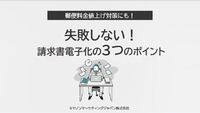
【郵便料金値上げ対策にも!】失敗しない!請求書電子化の3つのポイント
おすすめ資料 -
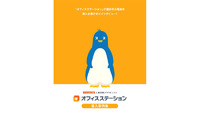
オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -
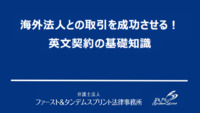
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -
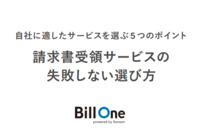
請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
おすすめ資料 -

社会保険の随時改定とは?「月額変更届と算定基礎届ではどちらが優先されるか」などのポイントも解説します
ニュース -

企業の経理部門が押さえるべき“コスト削減”の実態。「ペーパーレス化」に「IT投資」…優先すべき施策とは?
ニュース -

2025年3月期決算(6月27日時点) 上場企業「役員報酬1億円以上開示企業」調査
ニュース -
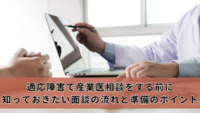
適応障害で産業医相談をする前に知っておきたい面談の流れと準備のポイント【医療法人社団惟心会/株式会社フェアワーク】
ニュース -

エンゲージメントを高めるマネジメントが企業価値の最大化を実現する
ニュース









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました


