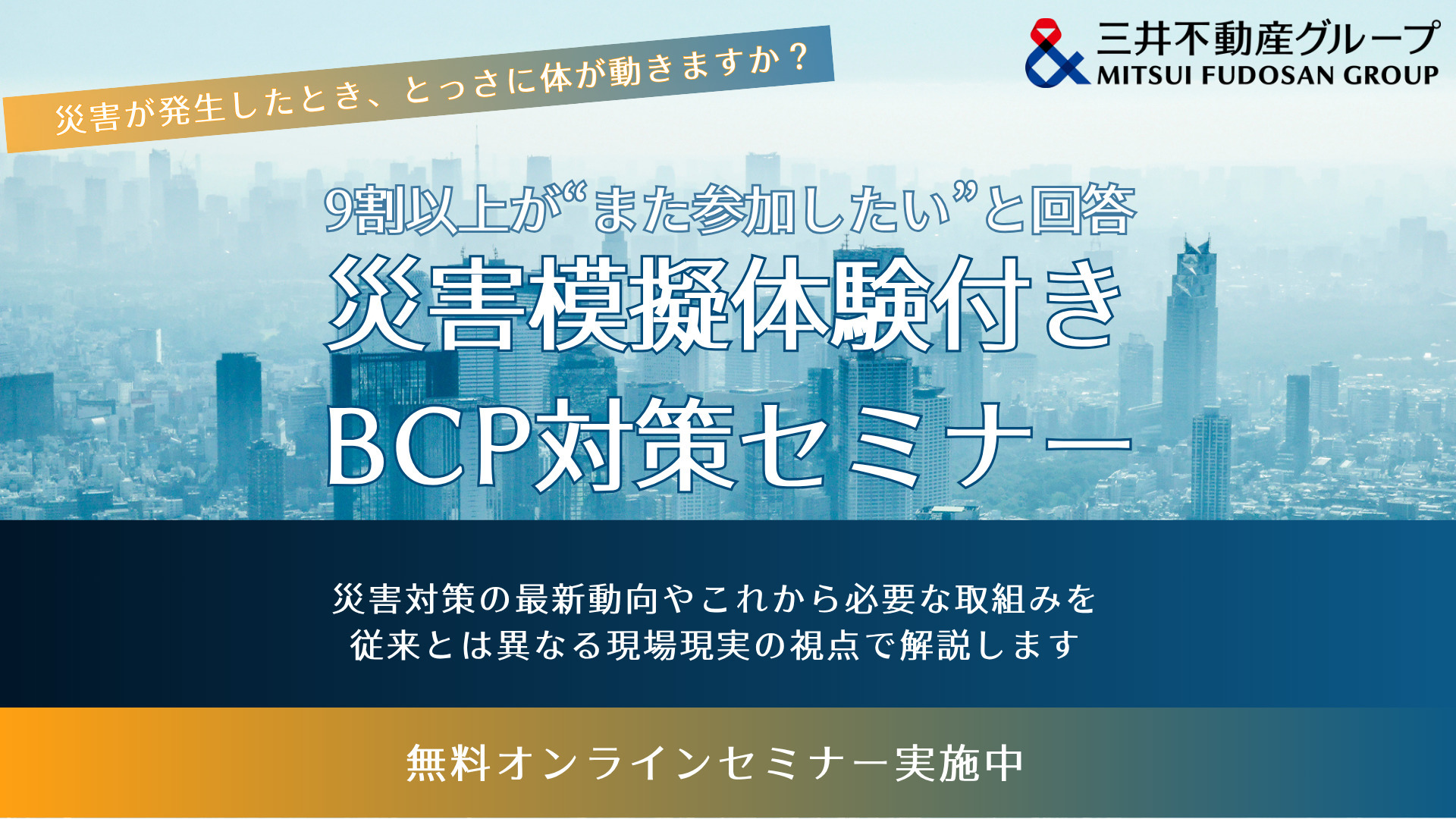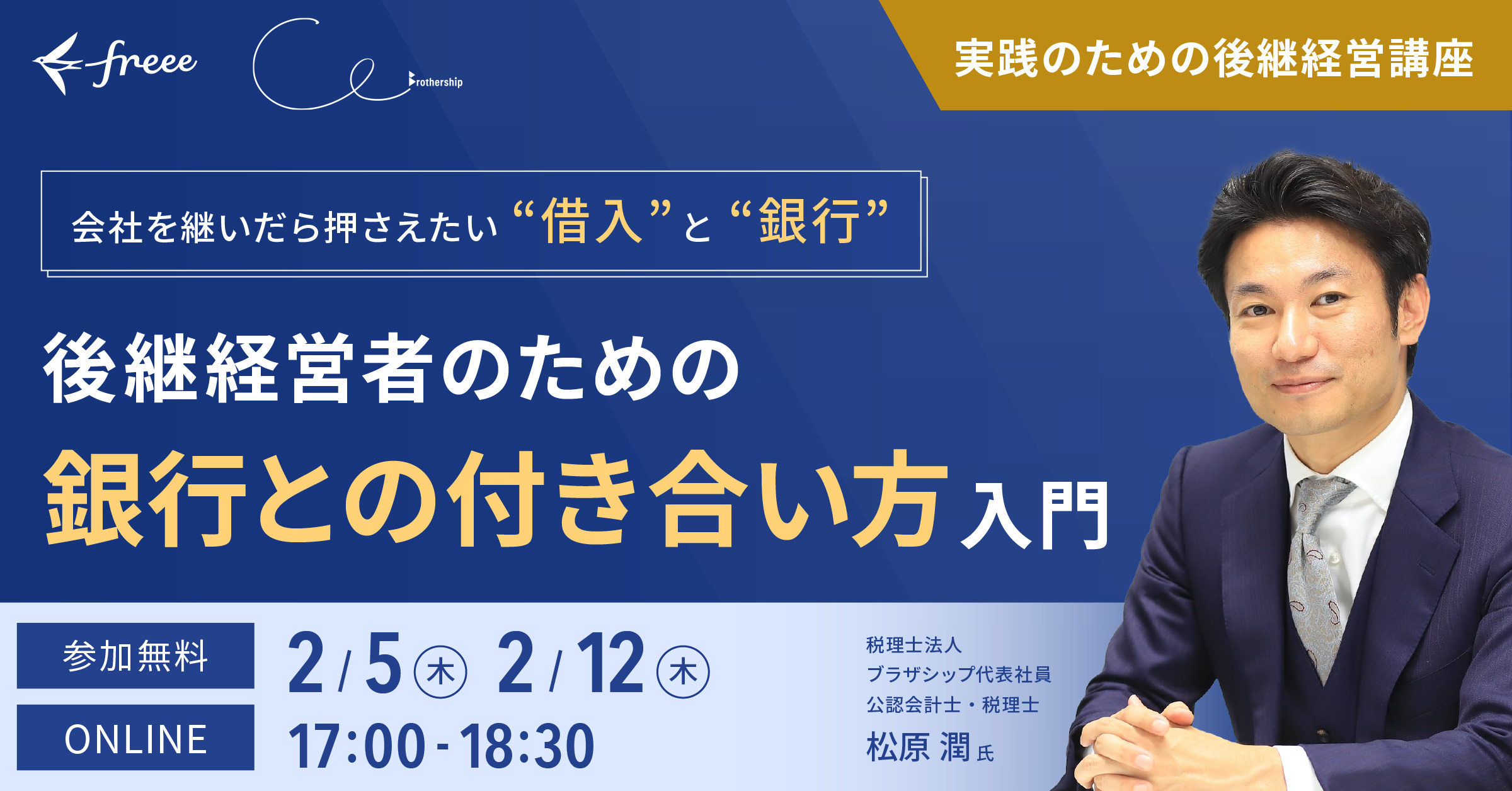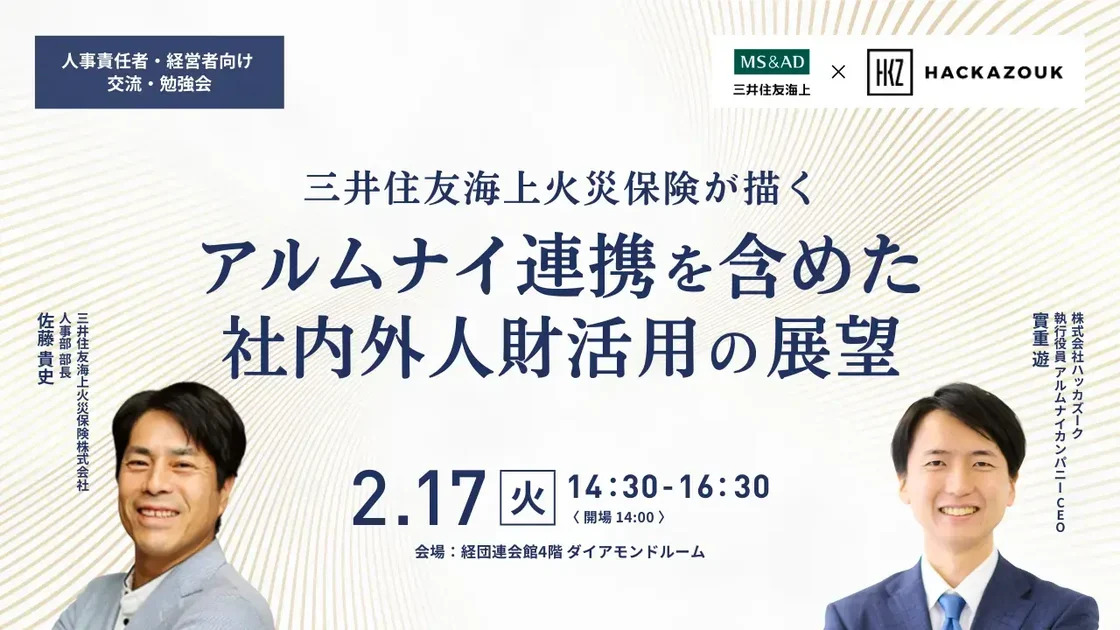公開日 /-create_datetime-/

喫煙者によるタバコの煙が、周囲の非喫煙者に迷惑をかけるという指摘は、日本社会の中でも以前からいわれてきたことです。しかし現在、受動喫煙対策が強化された改正健康増進法が昨年国会で成立する(2020年4月施行)など、禁煙に向けた動きが加速しています。スモークハラスメント(スモハラ)に対する社会の目も、より厳しくなりつつあるといえるでしょう。
今回はスモハラとは何か、職場ではどのような行為がスモハラに該当するのか、スモハラを防止するにはどうすればよいか、などについて解説します。
スモークハラスメントとは
スモハラとは、職場等において喫煙者が非喫煙者に対して煙による害を与える行為、および喫煙に関連した嫌がらせ行為のことです。喫煙者から生じるタバコの煙を吸ってしまうことは「受動喫煙」といいますが、非喫煙者にとって受動喫煙は「たばこの煙を吸わなくてよい自由」の権利が侵害されることを意味します。非喫煙者にとってはタバコ煙そのものが不快ですし、受動喫煙によって非喫煙者が健康を害するリスクも高まるので、セクハラやパワハラと同様、ハラスメントの一種としてスモハラが位置づけられるようになりました。
スモハラが原因で裁判になったケースもある
2008年に日本青年会議所の事務局に勤務を始めた女性は、職場で受動喫煙にさらされていることから、同事務局が立地する日本青年会議所に対して、対策を取るように求めました。しかしその後も状況に大きな変化は見られず、やがて女性は2016年頃から体調不良により休職し、2017年4月には解雇されたのです。
女性は受動喫煙によって喘息の症状が出て悪化するようになったとして、日本青年会議所を相手取り、解雇無効を求める労働裁判を東京地裁に申し立てました。裁判では日本青年会議所における分煙体制の不備などが指摘され、結果として「解雇は無効」という審判で和解が成立(2018年6月29日)。支払われていなかった給与分については、解決金として440万円女性に支払われることになりました。ただ、女性が復職しようとしても、勤めていた頃と職場環境があまり変わっていなかったので、結果として合意退職という形になっています。
スモークハラスメントに該当する行為の具体例
裁判になったケースのように職場で分煙体制が不十分であることは、当然ながら受動喫煙を生むためスモハラを引き起こす要因となります。しかし喫煙を行う各従業員が配慮を欠くことで、非喫煙者に対してスモハラとなるケースも少なくありません。典型的なスモハラ行為の1つが喫煙の強要です。強い立場にいる上司が、弱い立場にいる部下に対して喫煙を要求することは、スモハラに該当します。例えば禁煙中の部下に対して、上司の地位を背景として喫煙するよう迫ることはスモハラ行為です。仮に上司自身に悪気がなくても、「上司に勧められたタバコは断れない」という圧迫感を部下が受け、その結果、無理に吸ってしまう恐れがあります。
他にも、喫煙者である上司が、喫煙できる居酒屋に非喫煙者の部下を連れていくなど、タバコの煙を否応なく吸ってしまう場に連れていくこと、非喫煙者の部下、同僚の近くで歩きタバコをすることも、スモハラとみなされやすいです。ただ、禁煙が規定されている場でない限りは喫煙者には喫煙の権利もあるので、ハラスメントか否かの境界線を引くことが難しい場合もあります。
スモークハラスメントの防止方法
2018年7月に改正健康増進法が成立したことで、企業が社内において受動喫煙を防止するために行うべき取り組みは、2020年4月からそれまでの「マナー」から「ルール」へと変更されます(学校、病院など一部の施設については、2019年7月から施行が開始)。同法の施行により、「屋内は原則禁煙」、「20歳未満は喫煙エリアに立ち入り禁止」、「屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要」、「喫煙室に標識掲示を行う」などが義務化され、違反すると罰則が科せられるので各企業は注意が必要です。
まずはこの法律を順守することによって、制度上定められている最低限のスモハラ対策を各企業は実施できます。
また、社内でスモハラ防止体制を整えるだけでなく、喫煙をする各従業員が非喫煙者である他の従業員に配慮した行動を取ることも必要です。屋外など喫煙ができる場であっても、同行者の許可なく喫煙することは控えることが求められます。
ただし上司の場合、断れない雰囲気の中で部下に対して「吸ってもいい」と聞くことはスモハラになりかねないので注意が必要です。非喫煙者である部下の前ではタバコを吸わないようにするなど、気遣いの心を持つことも重要でしょう。
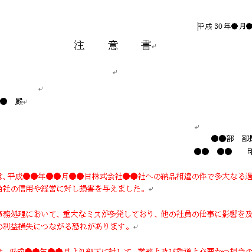
注意書(業務ミス・ハラスメント)
本人の過失により会社に損害を与えたときや、セクハラ・パワハラなどで周囲に迷惑をかけた社員に対し、いきなり懲戒処分を実施するのではなく、まずは注意書で通知しましょう。あわせて注意承諾書など注意を受け入れたことに同意する書類があると、裁判になった場合に安心です。※赤字の箇所をアレンジしてお使いください【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修:社会保険労務士 西方 克巳
無料でダウンロードするまとめ
喫煙者本人は気をつけているつもりでも、周囲の人が煙によって苦痛を受け、結果としてスモハラの加害者となっている場合もあります。もし勤務中に喫煙をするのであれば、他の従業員に迷惑がかからないか、細心の注意を払うことが大切です。
企業には、スモハラを受けた場合に相談できる窓口を設けることを含め、スモハラが起きない環境作りをしていくことが、ますます求められます。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。
あわせて読みたい
- 喫煙者は就職できない!?喫煙者を採用しない会社を紹介
- 「えっ?これもハラスメント!?」職場で起きうるハラスメントの種類とは
- 『エイハラ(エイジハラスメント)』とは何?
- 『エイハラ(エイジハラスメント)』とは何?
- レイハラ(レイシャルハラスメント)とは?
- 職場の空気でハラスメント?! エアーハラスメント(エアハラ)ってどんなハラスメント?
- 職場の雰囲気を悪化させる、フキハラ(不機嫌ハラスメント)への対処法とは?
- 「男らしさ」「女らしさ」も一歩間違えるとハラスメントに!セクハラの注意点
- スモークハラスメントに関して
- パワハラを例に考える、ハラスメント認定されないための言葉の使い方
- 時短ハラスメント(ジタハラ)ってなに?
- 職場でのハラスメント対策向上について、知っておくべきパタハラの現状と対策
- ハラスメント対策研修の効果的な実施方法とその重要性
- あなたの対応大丈夫?企業に求められるパワーハラスメント定義の再確認!
- 性別による不当な差別、ジェンダーハラスメントの実態と対処法
- パワハラの一つ「レリジャスハラスメント」とは?
- ハラスメントで休職した社員には傷病手当と労災のどちらを適用すべきか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -
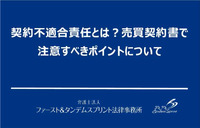
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
ニュース -
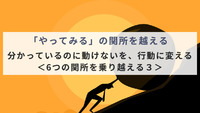
「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>
ニュース -
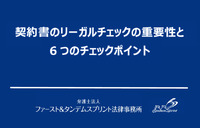
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
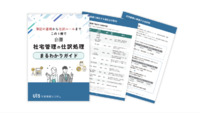
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -
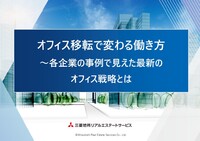
オフィス移転で変わる働き方
おすすめ資料 -

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド
ニュース -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース -
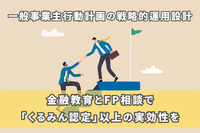
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を
ニュース -

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】
ニュース