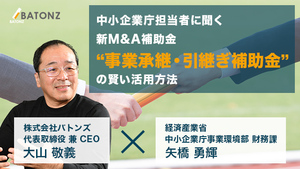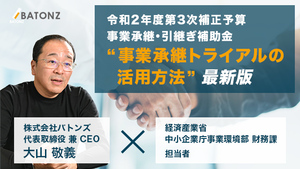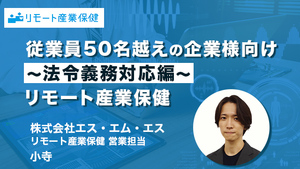公開日 /-create_datetime-/

贈与税は、個人から贈与された財産に課せられる税ですが、相続税との違いを理解できている人は少ないのではないでしょうか。また、贈与を受けても、贈与税が発生する場合と発生しない場合があります。課税方法や贈与税の成り立ちを、簡単に振り返ってみましょう。
「暦年課税」と「相続時精算課税」
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当している場合は「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から、基礎控除額(110万円)を差し引いた額に対して課される税です。ですから、110万円以下(1年間)なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告をする必要もありません。
相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、軽減された贈与財産に対する贈与税を支払い、その後相続時に、贈与財産とその他の相続財産を合計した相続税額から、支払った贈与税額を精算する制度で、相続を受ける子・孫が選択することができます。
相続時精算課税の特別控除額は2,500万円ですから、こちらの方も選んだ方が得なような気がしますが、特別控除額の適用を受けるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
1. 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上
2. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
3. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする
4. 相続時精算課税を選択しようとする最初の贈与を受けたときに届出書を提出
などです。また、前年以前にも特別控除の適用を受けている場合は、2,500万円からその金額を差し引いた残額が、その年の特別控除限度額となります。
贈与税がかからないケース
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的によっては、贈与税がかからないこともあります。
以下のような場合は、贈与税はかかりません。
1. 法人からの贈与により取得した財産
2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費の目的で取得した財産
3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産
4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品
5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
6. 公職選挙法の適用を受ける選挙で、公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品
9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
12. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
こうみてくると、意外に贈与税を免れる道がありそうですが、たとえば会社・法人からの贈与は、贈与税はかかりませんが所得税がかかります。また、生命保険金も、自分で保険料を負担していない場合は贈与税、自分が保険料を負担していた場合は相続税の対象となります。
贈与しやすくなるか「相続時積算課税制度」
ところで、日本では贈与税の負担が重いと指摘されてきました。それは、所得税の補完的役割として扱われてきたからです。
相続税の創設は明治38年で、当時は遺産税方式でした。贈与税は昭和22年の創設ですが、昭和25年のシャウプ勧告で税制が大幅に改正となり、遺産税方式から遺産取得税方式へと移行しています。
当時の贈与税は、一生累積課税方式でしたが、それが廃止となり、相続及び包括遺贈は相続の都度、遺産取得税方式となり、受贈者課税とする贈与税に改正されました。
その後も、何度か改正されてきましたが、贈与税が大きくクローズアップされるようになったのは、平成15年度の税制改正で創設された「相続時積算課税制度」です。
これまでは、相続税回避を防ぐために、贈与税の税負担が高水準に設定されていたことから、生前贈与を行いにくい状況にありました。しかし、「相続時積算課税制度」によって、親から子への財産贈与が円滑に進めば、景気拡大につながっていくという期待感があるようです。
まとめ
高齢社会では、高齢者が所有する財産の活用が景気拡大の特効薬のようですが、税と実際の財産移転のバランスを見ながら、制度が調整されています。今後相続を受ける立場にある世代のビジネスパーソンは、贈与税を上手に活用していく知恵を身につけていくことも大切になるかもしれません。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください
関連記事:税の種類と歴史「固定資産税」
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
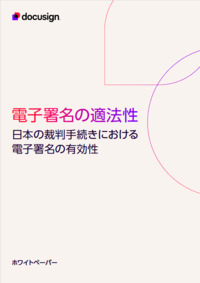
電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -
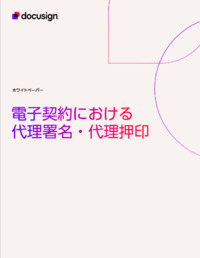
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -
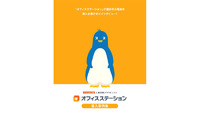
オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -
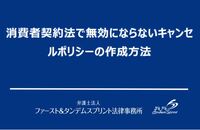
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

【会計】金融資産の減損における期中期間の簡便処理、検討─ASBJ、金融商品専門委 旬刊『経理情報』2025年7月20日号(通巻No.1749)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

【2025年版】ビジネス実務法務検定2級 合格率・難易度・出題傾向・勉強法は?最新データで合格の道筋を解説!
ニュース -

【対談インタビュー】採用から組織を変える力を育てる。マクロミルと外部人材が共創する人事と組織のかたち。
ニュース -
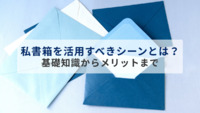
私書箱を活用すべきシーンとは?基礎知識からメリットまで解説
ニュース -

1-6月の「人手不足」倒産 上半期最多の172件 賃上げの波に乗れず、「従業員退職」が3割増
ニュース -
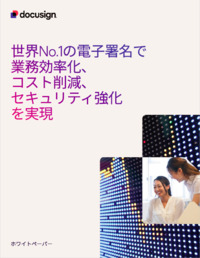
世界No.1の電子署名で業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化を実現
おすすめ資料 -
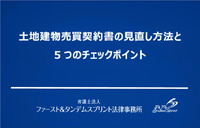
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
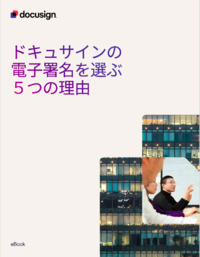
2,000人の経営幹部に聞く!電子署名導入のメリットと懸念点を徹底解剖
おすすめ資料 -
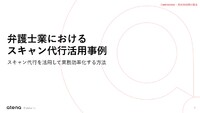
弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

法人向けクラウドストレージのバックアップサービスとは
ニュース -

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に
ニュース -

大規模プロジェクトに最適なクラウドストレージへのデータ移行手順
ニュース -

アフターコロナで対面増、ジャケット着用が半数超に 夏のビジネス現場や就活に広がる「汗の不安」
ニュース -
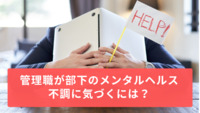
管理職が部下のメンタルヘルス不調に気づくには?
ニュース
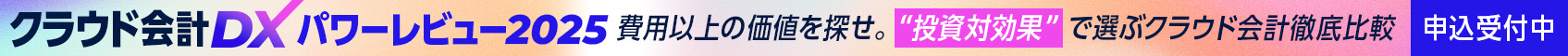









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました