公開日 /-create_datetime-/
所得申告を怠った場合の末路とは!?

2019年10月、お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実さんが、自ら設立した個人会社の申告漏れと所得隠しを東京国税局から指摘され問題となりました。長年に渡り期限内に申告していなかったことや、個人的な支出を会社の経費にしていたことも明らかになり、重加算税などの追徴課税は支払ったものの、社会的影響から芸能活動の自粛に追い込まれています。記者会見での「ルーズ」「怠慢」「だらしなさ」といった発言も話題となりました。
一般の会社員であれば、税金は会社を通して支払われるため、意識する機会は少ない問題といえます。しかし、個人事業主やフリーランスにとっては「ルーズ」では済まされない問題であり、会社員でも副業や投資を行っている人は注意が必要です。
所得申告が必要なケース
大半の給与所得者は、所属する会社で行われる年末調整により税額が確定します。しかし、給与以外に一定基準額以上の所得がある場合は、自分で確定申告を行い、所得の申告をする必要があります。
確定申告の義務がある場合の主な例は以下の通りです。
・主となる給与所得以外に副業などで20万円以上の所得がある場合には、会社での年末調整だけでなく、確定申告を行う義務があります。
・正社員と並行したアルバイトや、契約社員の2社掛け持ちなど、2カ所以上で働いている場合は、メインの職場で年末調整を受け、2社目以降の所得を申告する必要があります。
・競馬や競輪などギャンブルで20万円以上の利益を出した場合は申告が必要です。ただし、宝くじの当選金は非課税であるため対象外です。
また、住宅ローンや医療費、ふるさと納税などに関しては、確定申告を行うことで税の還付を受けられる場合があります。控除申告自体は義務ではありませんが、控除申告をする場合には20万円以下でも所得の申告が必要です。
20万円以下の臨時収入も注意が必要
臨時収入などで得た収入が20万円以下であったとしても、申告の義務がないのは所得税だけであり、住民税については各市区町村に申告する必要があります。
かつては、所得税が無申告なら、その分の住民税も実質的に徴収できないケースが多々あったようですが、現在はマイナンバーによりしっかりと徴収される可能性が高くなっています。
申告をしなかった人の末路は?
所得申告を全くしないことや、都合よく勝手な解釈をして納税額を不当に少なくすることは、脱税の対象となりペナルティが課されます。税務調査を通して多額の追徴課税を命じられるほか、脱税額が高額である場合や過度に悪質な脱税行為だと判断された場合は、逮捕に至る可能性もあるのです。
追徴課税には以下のような種類があります。
・延滞税
脱税により課税されなかった額に対し、本来の納付期限から改めて納付するまでの期間に対する利息として課される税です。
・過少申告加算税
課税額を過少申告した場合に課される税であり、50万円以下の場合は10%、50万円を超えた部分については15%が加算されます。ただし、税務調査の通知が来る前に正しく修正申告をすれば課されないこととなっています。
・無申告加算税
申告していない場合に課される税であり、50万円以下の場合は15%、50万円を超えた部分については20%が加算されます。過少申告加算税と異なり、課されない条件は定められていません。
・重加算税
事実を仮想したり隠蔽したりするなど、意図的に税金を少なくしたとみなされた場合に課される税であり、税率は35%、無申告に値する場合は40%が加算されます。追徴課税の中で最も重いペナルティです。
また、通常ではありえないような不自然な商取引の形式を採用するなどして税金を安く抑えようとする「租税回避」と判断された場合は、違法行為の対象とはならないものの、修正申告の対象となる場合があります。
面倒なら税理士に依頼しよう
確定申告が面倒だという人は、税理士に依頼するのが得策です。税理士には「税務代理」「税務書類の作成代行」「税務相談」といった三つの独占業務があり、これらの業務は有償無償に関わらず税理士しかできないことになっています。裏を返せば、それだけ自らの仕事に責任を追わなければならない立場にあるといえるのです。
税理士に頼めば、書類さえ渡してしまえば全ての手続きを終わらせてくれます。節税に関する知識も豊富であるため、支払う税金をできるだけ安く抑えることもできるでしょう。
また、副業など働き方の多様化に伴い、税理業務も複雑化していく中で、特定の職種に特化した税理士も増えてきています。ネットで検索するなどして、自身が行っている職種に強い税理士を見つけることができれば、より手続きが効率化されたり、税金を安く抑えたりできる可能性が高まります。そもそも、申告せずに結果としてペナルティを課されることに比べれば、税理士に費用を払った方が安く済む場合が多いでしょう。
まとめ
雑収入や臨時収入などがある場合は、たとえ少額であったとしても、それが収入である以上は課税の対象となる可能性を考えるべきです。所得の申告はしなければならないという認識をしっかりと持った上で、確定申告に関する正しい知識を身に付けることが重要だといえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
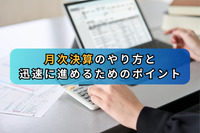
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
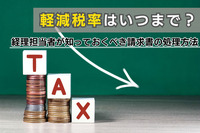
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース




































