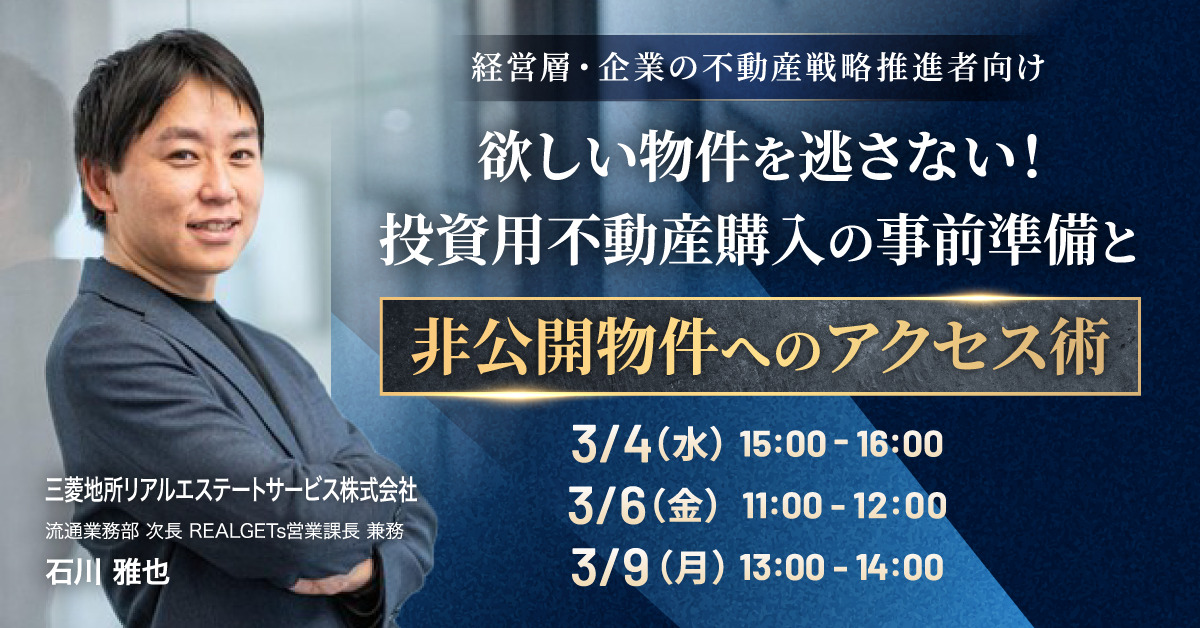公開日 /-create_datetime-/
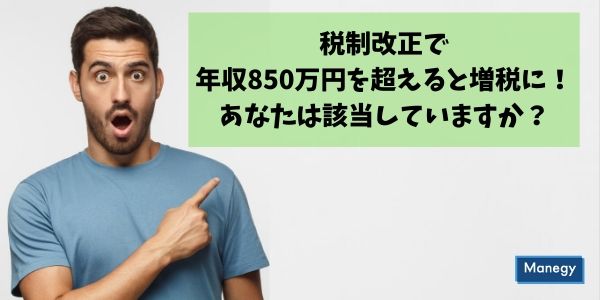
2018年度の税制改正により、2020年の1月から所得税を計算する際の「基礎控除」、「給与所得控除」、「公的年金等控除」の3つの控除が見直されました。今回の見直しで、年収850万円を超える会社員や公務員は、22歳以下の子どもがいる場合や特別障害者控除の対象者がいる場合を除いて増税となります。一方、フリーランスなどの自営業者は減税となりましたが、いまひとつわかりにくい今回の税制改正。見直された控除ごとに、簡単に整理しておきましょう。
控除額が増えた基礎控除
基礎控除とは、納税するすべての人に認められていて無条件に差し引くことができる所得控除です。改正前は一律38万円でしたが、今回の改正で10万円増額され48万円になりました。つまり基礎控除に関しては、減税されているわけです。ただしこの基礎控除には条件があります。所得の合計額によっては基礎控除が無くなってしまいます。
| 所得金額の合計 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2500万円超 | 0 |
所得金額に応じて基礎控除額が減っていくとはいえ、所得が2,400万円以下の人は今回の減税対象となるので、ほとんどの方が基礎控除に関しては増税にはならないでしょう。それでも増税となってしまう人は、何が違うのでしょう?
給与所得控除では年収850万円超が分かれ目
給与所得とは、給料、賃金、賞与など、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
正社員や契約社員はもちろん、パートやアルバイトであっても、その給与は課税対象となります。
表を見ていただければわかるとおり、850万円以下の収入に関しては税制改正後、給与所得控除が10万円減額されています。先述した基礎控除と合わせるとこれは実質相殺となり、変化がありません。問題は赤色の部分で、「850万円超~1,000万円以下」から上の収入に該当する人は、控除額が引き下げられ増税になっているのです。たとえば年収が900万円であれば年間15,000円程度、1,000万円で45,000円程度、1,500万円で65,000程度の増税になります。
ただし22歳以下の子どもがいる場合や、特別障害者控除の対象者がいる場合、最大150,000円の「所得金額調整控除」の対象となるため、増税にはなりません。
また給与所得者ではないフリーランスや自営業の方は、基礎控除が減税となるため所得が2,400万円以下であれば減税となります。
公的年金を受給している場合はどうなるのか?
公的年金を受給している人には公的年金等控除がありますが、今回の税制改正ではこちらも見直されました。まず公的年金等控除は、給与所得控除と同様に一律10万円控除額が引き下げられます。しかし先述のとおり、基礎控除が10万円引き上げられているので実質は変わりません。加えて、年金以外に給与所得がある人も控除が二重に適用されることはありませんので、ここまでは公的年金受給をされている人も税制改正の影響は受けない、ということになるでしょう。
ただし、年金収入が1,000万円を超える人には控除額の上限として195万5000円が設定されています。また年金以外に役員報酬などを受け取っていて、年金以外の所得が1,000万円を超える場合には10万円、2,000万円を超える場合には20万円、控除額が減額されます。
整理すると、年金以外の所得が年間1,000万円を超える場合か年金収入が1,000万円を超える場合、どちらかに該当する人は公的年金等控除が減り、実質増税ということになります。
何のための税制改正なのか?
財務省の試算によれば、負担が増える(実質の増税になる)人は、給与所得者で約230万人、全体の4%程度。年金受給者で約20万人、年金受給者全体の0.5%程度になるそうです。対象者数の多い少ないに関わらず、国民生活に大きな影響を与える税制改正。今回の税制改正は何のために行われたのでしょうか?
税制の専門家は今回の税制改正の目的を、「多様化する働き方に対応するため」と分析しています。
少し前の日本では終身雇用が当たり前、正社員になって定年まで勤め上げるのが美徳とされてきました。ところが現在では、非正規社員(アルバイト、パート、契約社員等)やフリーランス、起業する人が増える一方、企業内でも働き方改革が始まり働き方の多様化が進んでいます。現在の税制は、刻々と変わっていく新しい働き方に追いついていないのが現状なのです。ここに生まれるのが税の格差、不公平感で、今回の改正は働き方の違いによる税負担の差を減らすことを目的としています。
まとめ
年収が1,000万円を超える人は日本国民の4%程度、850万円を超える人は10%程度といわれています。今回の税制改正で、国と地方合わせて860億円程度の税収が増える見込ですが、その大半は高所得者への増税といえます。
今回は年収が850万円以下、もしくは介護・子育て世帯の会社員、1,000万円以下の年金受給者には税額の変更がありませんが、今後も税負担の格差是正を目的に改正は行われていくものと思われます。決して他人事とは思わず、常に税制の改正には興味を持ち続けていきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
ニュース -
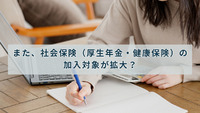
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース