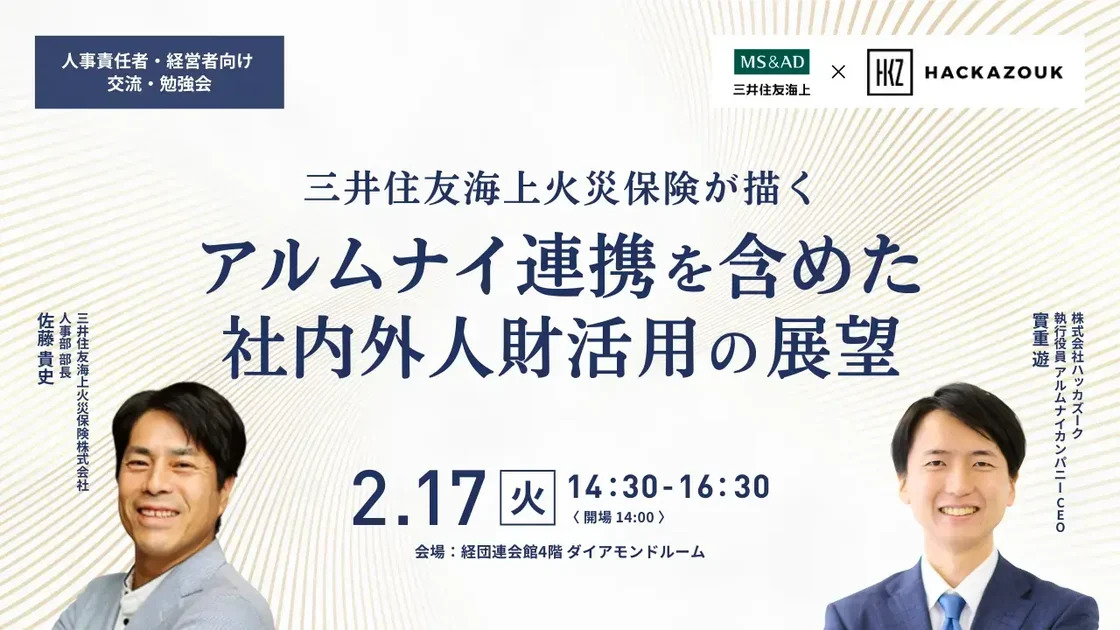公開日 /-create_datetime-/

財務諸表の一つである貸借対照表の読み方をご存じでしょうか。貸借対照表は、会社の財務状態の概要を把握でき、バランスシートとも呼ばれています。会計・経理部門の人ならば当然読めるでしょうが、それ以外の部署の人も、表の内容を理解しておきたいものです。そこで今回は貸借対照表の基礎的な読み方について解説します。
目次【本記事の内容】
貸借対照表とは?
法人は決算期になると財務諸表を作成しますが、損益計算書、キャッシュフロー計算書と並んで作成されるのが貸借対照表です。貸借対照表は大きく分けて、「資産の部」、「負債の部」、「純資産の部」という3つの部分から構成されています。資産の部は貸借対照表の左側(借方)、負債の部と純資産の部は右側(貸方)に記載するのがルールです。
なお、左側の合計額と右側の合計額は同額、つまり「資産の部=負債の部+純資産の部」という構図になっています。会社が保有する資産を表の左側に記載し、その資産を所有するために要した負債、自己資本が表の右側に記載されているわけです。
資産の部には会社が保有する財産が記載、流動資産と固定資産で構成
貸借対照表の左側に記載される資産の部は、「流動資産」と「固定資産」とで構成されています。
流動資産は一年以内に現金化できる資産のことです。具体的には、現金、預金、売掛金、受取手形、有価証券、商品、貸倒引当金などが該当します。
売掛金とは商品を売却したものの、まだ相手方から代金を受け取っておらず、支払期日まで待っている状態のことです。受取手形は商品などを売った得意先から受け取り、支払いの期日、支払いが行われる銀行、支払額などが記載されている手形のことをいいます。
一方、固定資産とは、一年以上使用することを目的に保有する資産のことです。土地、建物、投資有価証券、機械、ソフトウェアなどが当てはまります。
固定資産は複数年保有されるため、機械や設備など日々使用され続けるものについては、減価償却が必要です。減価償却とは、固定資産の耐用年数ごとに費用を案分するという会計上の処理のことをいいます。例えば100万円で耐用年数5年の機械を購入したとすると、一年あたりの減価償却費は20万円となるわけです。
負債の部には会社が負っている債務が記載、流動負債と固定負債で構成
貸借対照表の右側上段に記載されるのが負債の部です。流動負債と固定負債が記載されています。
流動負債は、一年以内に支払期限がくる債務・未払い費用・前受収益などのことです。買掛金、支払手形、短期借入金などが該当します。買掛金は商品を後払いで購入することで、支払手形とは支払期日に手形の額面金額を支払うことを約束した手形のことです。
一方、固定負債は債務期限が一年を超えている負債のことをいいます。具体的な勘定科目としては、長期借入金、社債、退職給与などです。長期借入金は、長期にわたって返済する義務のある金融機関からの融資などが該当します。
純資産の部には、返済の義務のない資本金などが記載
貸借対照表の右下に記載されているのが、純資産の部です。純資産の部は、返却・支払いの義務などがある負債の部とは異なり、返す必要のない資本金などが記載されています。
具体的な勘定科目は資本金、自己株式、利益剰余金などです。資本金は創業時に経営者が持つ運転資金のことで、株式会社であれば株主がその会社に出資した金額のことです。また、内部剰余金とは、社内に蓄積された営業活動で得た利益のことを指します。
事業活動で得た純利益は株主への配当などに充当されます、残った分については内部留保として社内に蓄積されるのが通例です。日本企業は内部留保が多い傾向にあり、財務体力の強さの源泉となっています。
貸借対照表からわかる会社の財務指標
資産の部、負債の部、純資産の部から構成される貸借対照表からは、会社の財務状態を示す指標を読み取ることができます。以下でその一部を紹介しましょう。
①流動比率=(流動資産÷流動負債)×100
すぐに返済義務のある負債に対して、すぐに返済に充当できる流動資産がどのくらいあるのかを示します。200%以上あれば、返済能力が高い状態です。
②当座比率=(当座資産÷流動負債)×100
当座資産は預金・現金、売掛金、受取手形、有価証券など、流動資産の中でも特に現金化しやすい勘定科目のことです。比率が100%以上あれば、流動負債への返済能力は高いといえます。
③固定比率=(固定資産÷自己資本)×100%
自己資本とは資産の部に記載されている返済の義務のない勘定科目のことで、資本金や利益剰余金などが該当します。固定比率が100%以下であれば設備投資などに無理がなく、自己資本に余裕があると判断できます。
おわりに
貸借対照表は、会社の財務指標として最も基本的な書類です。「資産=負債+純資産」が基本的な構図であり、資産には流動資産と固定資産、負債には流動負債と固定負債に分かれます。純資産は資金調達や利益の内部留保などで集められた、返却の義務のない純粋な資産のことです。流動比率や当座比率、固定比率からは、大まかな企業の返済能力、自己資本の余裕の度合いなどがわかります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
ニュース -
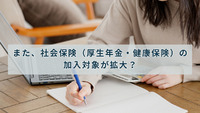
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース