公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
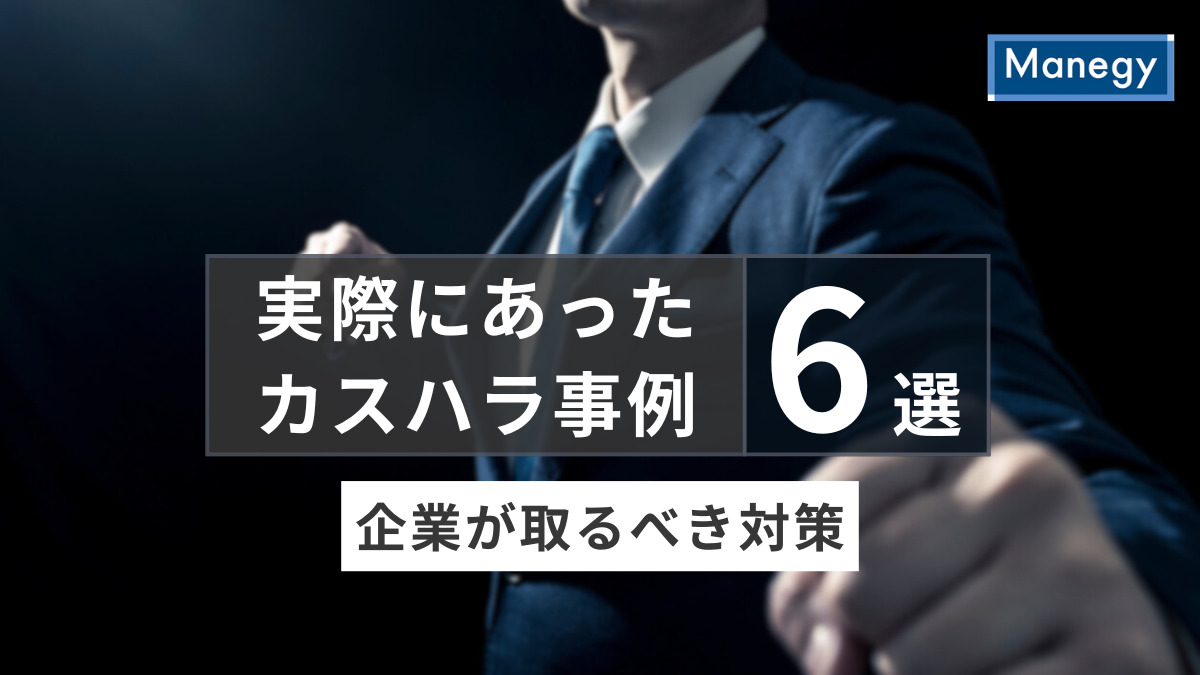
近年、企業や従業員に対する顧客の理不尽な要求や威圧的な言動、過度なクレームが問題視されており、「カスハラ(カスタマー・ハラスメント)」が社会的な課題となっています。
こうした状況を受け、東京都では全国で初めてカスハラ防止条例の制定を検討する動きが報じられ、注目を集めています。本記事では、カスハラの定義や具体的な事例、企業が取るべき対策について解説します。
東京都、全国初のカスハラ防止条例成立 25年4月施行
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0141C0R01C24A0000000/
カスハラは「カスタマーハラスメント」の略称で、顧客が企業に対して理不尽な言動を行なうことを指した言葉です。例えば、無理難題な要求や法的根拠などのない言いがかり、従業員の心身にダメージを与えるような暴力的言動や嫌がらせ、侮辱的な方法による要求などが、カスハラに該当します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)が発生する背景には、さまざまな要因が関係しています。
まず、「顧客第一主義」の誤解が挙げられます。多くの企業は顧客満足を重視していますが、一部の顧客がこれを「どんな要求も受け入れられるべき」と誤認し、過剰なクレームや不当な要求を行うケースがあります。
次に、「匿名性の高さと対面機会の減少」も要因の一つです。電話やネット通販の普及により、対面でのやり取りが減ったことで、顧客が従業員に対して責任のない立場から攻撃的になりやすい環境が生まれています。
また、「ストレスのはけ口」としてクレームを入れる人もいます。社会的な不安や個人的な不満を発散するために、弱い立場の従業員に対して威圧的な態度を取るケースが見られます。
さらに、「SNSや口コミの影響」も大きいです。企業が悪評を恐れて過剰に顧客対応を優先すると、一部の顧客がそれを利用し、理不尽な要求を通そうとすることがあります。
こうした要因が複雑に絡み合い、カスハラが発生しています。
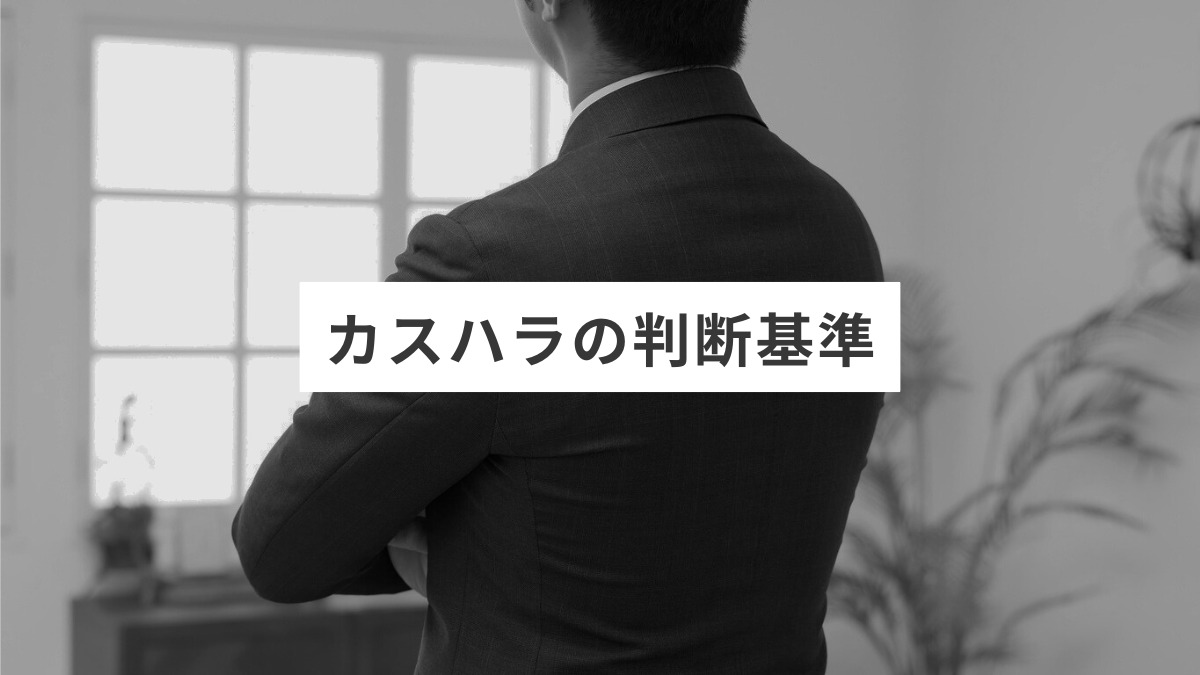
本章では、カスハラの判断基準を5つのポイントにわけて紹介します。
①クレームの内容が合理的かどうか
正当なクレーム: 商品やサービスに関する適切な指摘や改善要望
カスハラ: 企業の過失と関係なく、感情的な怒りや嫌がらせを目的とした要求
▶ 例
- 「商品の不具合を交換してほしい」 → 正当なクレーム
- 「店員の態度が気に入らないから謝罪しろ」 → カスハラの可能性
②言動や要求が常識の範囲を超えているか
許容範囲: 冷静かつ礼儀を持った苦情・意見
カスハラ: 大声で怒鳴る、執拗な謝罪要求、従業員の人格を否定する発言
▶ 例
- 「対応が悪かったので、もう少し丁寧な接客をお願いしたい」 → 許容範囲
- 「お前は無能だ、仕事を辞めろ」 → カスハラ
③身分を利用した威圧的な行動があるか
正当なクレーム: 立場に関係なく、冷静な話し合いを行う
カスハラ: 「顧客だから」といって、立場を利用して過度な要求をする
▶ 例
- 「責任者と話をさせてほしい」 → 通常のクレーム対応
- 「俺はVIP客だから、お前は土下座しろ」 → カスハラ
④精神的・肉体的な負担を与えているか
正当なクレーム: 相手を尊重し、建設的な対話を行う
カスハラ: 従業員に過度なストレスを与え、業務に支障をきたす
▶ 例
- 「改善してほしい点をメールで送ります」 → 適切な対応
- 「営業時間外に何度も電話する」「SNSで悪評を拡散すると脅す」 → カスハラ
⑤不当な金品要求や個人情報を求めているか
許容範囲: 正当な返金・交換対応の要求
カスハラ: 過剰な金銭・特典の要求や従業員の個人情報を聞き出そうとする行為
▶ 例
- 「この商品、壊れていたので交換してほしい」 → 正当な要求
- 「お詫びとして、商品を無料にしろ」「担当者の自宅を教えろ」 → カスハラ
コンプライアンスも扱う法務が業務に活かせる資料はこちら(無料)
クレームは「要求、苦情、主張」などを意味する言葉で、一般的には特に「苦情」という意味で使われることが多いでしょう。通常、クレームはあまり良くないニュアンスで用いられますが、企業にとって必ずしも“悪い”ものばかりではありません。なかには正当な申し出や要求、企業にとって有意義な意見などもあります。
しかし、カスハラは「ハラスメント=嫌がらせ」であり、企業にとって“負”かつ“悪い”ものです。この点が、クレームとカスハラの大きな違いです。
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント事例集」の中から、一部抜粋の上カスハラ事例を紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001266535.pdf
情報通信業
・顧客が(サポートデスクに)「徹夜で明日までにバグを開発チームと直せ」「2000万払え」といった過剰な要求を行った。
運輸業、郵便業
・運転見合わせ時に、お詫び放送を繰り返していたところ、旅客から「いつ発車するのか放送しろ」としつこく詰問を受けた。運転再開見込みがわからない旨を伝えたが、旅客は納得せずスマホで車掌の対応を無断で動画撮影した。
卸売業、小売業
・顧客がプリペイドカードを購入後、返金を申し出たが、従業員が店舗で返金できない商品である旨を説明したところ、「店長を出せ」「店長権限で返金しろ」など同じ内容で長時間(2時間30分)詰問した。翌日も店舗で同様のやりとりがあった後、当該企業の本社代表電話への架電、及び同社本社へも来訪し、クレームを述べた。
宿泊業、飲食サービス業
・顧客が宿泊のたびに客室の清掃不備を指摘し、客室のグレードアップや顧客の前で清掃することを要求した。
生活関連サービス業、娯楽業
・顧客の安全を配慮し、サービス(靴の加工)を丁重に断ったところ、フロア全体に響き渡る程の大声で怒鳴り散らす、暴言を吐く、靴を投げる、椅子を叩くなど2時間にわたり威圧的行動を取った。また、それ以降も不定期にその顧客が売場を訪れ怒鳴り散らすことが続いており、従業員が怯えている。
医療、福祉
・利用者が看護師をたたく、つねる、唾をはく、看護師にものを投げる、看護に必要な物品を破損する等した。
①自治体職員への暴言・過剰な情報公開請求に関する事例
概要: 大阪市の職員が、特定の住民から暴言や侮蔑的な発言を受け、さらに特定職員の略歴に関する情報公開請求を合計53回行われ、多い時には1日に5~6回もの電話を受けるなどの過剰な要求を受けた事例です。
判決: 大阪地方裁判所は、住民による業務妨害を認定し、市側の面談強要行為の差し止めと80万円の損害賠償請求を認めました。
参考URL
https://ivry.jp/column/customer-harassment-solutions/
②宅配便の誤配送に対する土下座強要事例
概要: 2023年、大分市内の運送会社で、男性が宅配便の誤配送トラブルが2回続いたことから、営業所長に対し「どう責任とるんか」「ミスした奴をクビにしろ」などと大声で怒鳴り、土下座を強要し、その様子を携帯電話で撮影した事例です。
判決: 裁判所は、男性の行為を「クレームの域を明らかに超えた非難に値する行為」として、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
参考URL
https://www.tis.amano.co.jp/hr_news/4221/

カスハラ被害による精神疾患が労災として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①対象疾病の発病
ICD-10のF2からF4に分類される精神障害であること。
②業務による強い心理的負荷
発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
例:顧客からの暴言や執拗なクレーム、土下座強要、長時間拘束など。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因の排除
業務以外の要因で発病したものとは認められないこと。
企業は、カスハラによる労災認定の可能性を考慮し、被害に遭った従業員の適切なケアを行う必要があります。
厚生労働省の基準では、以下のような業務要因が精神障害の発病リスクを高めるとされています。
①長時間労働:1か月に80時間以上の時間外労働がある場合。
②パワーハラスメント:上司や同僚からの暴言、無視、過剰な業務負荷。
③顧客からの理不尽な要求:暴言や土下座強要、威圧的なクレーム対応など。
④業務の急激な変化:突然の配置転換や、責任の大きい業務の負担増加。
これらの要因が重なると、心理的負荷が強まり、精神疾患の発症リスクが高まります。
企業がカスハラ対策を怠ると、以下のような深刻な影響が生じる可能性があります。
①従業員の精神的・肉体的負担が増える
カスハラに適切な対応ができない職場では、従業員が理不尽なクレームや暴言、威圧的な態度にさらされ続けることになります。これにより、ストレスの増加やメンタルヘルスの悪化、最悪の場合は休職や退職に追い込まれるケースも少なくありません。
②人材流出・採用難が起こる可能性が高まる
カスハラ対策が不十分な企業は、従業員から「働きづらい職場」と認識され、離職率が高まります。また、求職者にとっても「労働環境が悪い企業」として見られ、新たな人材の確保が難しくなる可能性があります。
③職場の士気や生産性が低下する
カスハラに適切に対応できないと、従業員のモチベーションが下がり、職場全体の士気が低下します。結果として、業務効率や生産性の低下、さらには顧客対応の質の低下にもつながり、悪循環に陥る可能性があります。
④企業イメージやブランド価値が下がる
カスハラに対して無防備な企業は、従業員がSNSなどで実態を発信するリスクもあります。「従業員を守らない企業」との印象が広まれば、企業イメージが悪化し、顧客離れや取引先との関係悪化を招く恐れがあります。
⑤法的リスクが高まる
今後、東京都をはじめとする自治体でカスハラ防止条例が制定されると、企業には対策を講じる義務が求められる可能性があります。これに適切に対応しない場合、行政指導や法的責任を問われるリスクも高まります。
では、企業がカスハラから自社の従業員を守るためにできる対策には、どのようなものがあるでしょうか? 例えば、以下はどの企業でも取り組みやすい対策の一例です。
①社内相談窓口を設置する
従業員がカスハラ被害を受けた際に迅速に相談できる窓口を設置し、適切な対応ができる体制を構築する。
②メンタルヘルスケアを強化する
・定期的なストレスチェックを実施し、従業員のメンタルヘルスを把握。
・産業医やカウンセラーとの連携を強化し、メンタルケアの支援を行う。
③カスハラ防止ガイドラインを策定する
・企業としての対応方針を明確化し、従業員に周知徹底。
・顧客との適切な距離感を保つためのマニュアルを整備。
④法的対応の準備する
・弁護士との顧問契約を結び、必要に応じて警察への通報や訴訟対応を検討。
・証拠保全のため、通話録音システムを導入。
なお、厚生労働省ではカスハラに関するガイドライン「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」を発表しています。このガイドラインには、カスハラの定義やカスハラ対策の必要性、企業が取り組むべき具体的な対策内容などについて詳しく記載されています。
自社でカスハラ対策を担当している人はぜひ、内容を確認してみましょう。
カスハラは従業員の精神的・肉体的負担を増やし、職場の士気や企業の信用にも悪影響を及ぼします。企業が適切な対策を講じなければ、人材流出やブランド価値の低下、さらには法的リスクを招く可能性もあります。
特に人事・総務・労務・法務担当者は、従業員を守るために社内相談窓口の設置やメンタルケアの強化、法的対応の準備など、企業全体で取り組んでいきましょう。厚生労働省のガイドラインを活用し、持続的に安全な労働環境を整えていくことが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
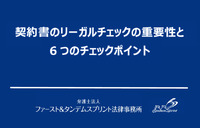
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
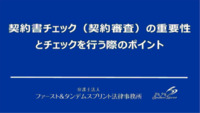
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

「インシビリティ」が組織を蝕む。“微細な非礼”の悪影響と防止法を解説

雑収入とは?仕訳方法・具体例・税金の扱いをわかりやすく解説
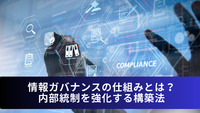
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
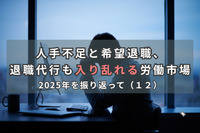
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)
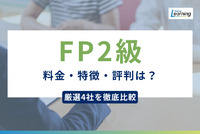
FP2級講座を厳選4社ご紹介|各講座の料金・特徴・評判を徹底調査
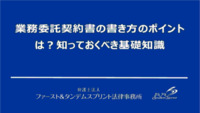
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
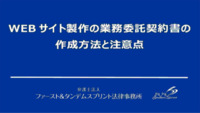
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

オフィスステーション導入事例集
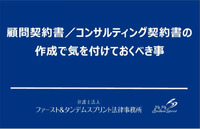
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア

決算書が赤字の時に見るべき場所とは?原因の読み解き方と改善策を徹底解説

専門人材向けに「ジョブ型人事制度」を本格導入した三井住友カード。“市場価値連動型”の評価・処遇でデジタル人材獲得へ

令和7年度 法人税申告書の様式改正

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用
公開日 /-create_datetime-/