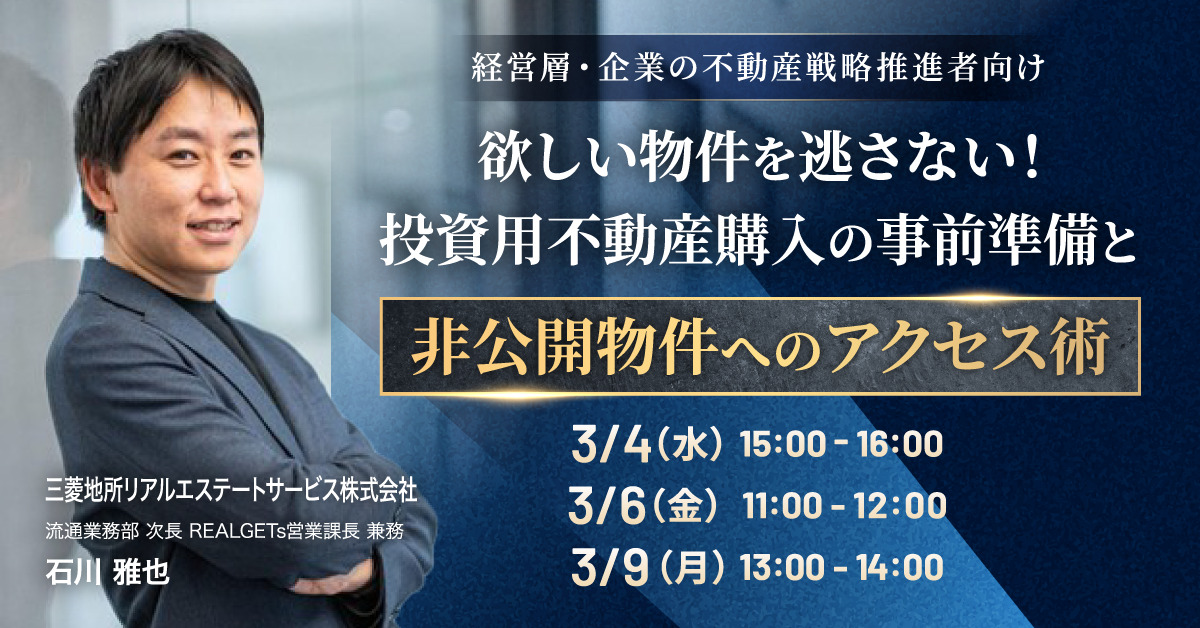公開日 /-create_datetime-/

主に国や自治体が事業者や個人を対象に、資金的・金銭的な支援を行うしくみが補助金制度です。現在さまざまな補助金があり、多くの企業や個人事業主、研究機関などが利用していて、原則的に返済する必要もありません。
しかし本来厳格にしかも適正に活用されるべき補助金が、利益誘導のため不正に利用されることも少なくありません。これから補助金の利用を検討中の皆さんのためにも、不正利用という負の側面から、補助金制度について考えてみましょう。
補助金の主な種類
現在国や自治体では補助金以外にも、「給付金」や「助成金」という支援制度があります。それぞれ規定に違いがあるようですが、原則として返済不要な制度については、ここからは補助金とひとくくりにして解説します。
補助金の対象者や対象事業は非常に幅広く、補助金を支給する省庁や自治体も多岐にわたるため、補助金には簡単には分類できないほど多くの種類があります。
一例として中小企業庁のホームページを見てみると、「経営サポート」「金融サポート」などの項目があり、企業の人材育成に関わるものから、販路開拓、IT導入支援など実に細かい名目で補助金が公募されています。
他にも補助金には災害支援が目的のものや、新規事業や研究などを後押しするものがあり、全容をつかむことはほとんど不可能でしょう。つまり支援を受ける側としては、それだけ多くのチャンスがあるということです。
補助金の受給条件と審査基準
補助金の申請にあたっては、受給条件に詳細な規定があり、まずは応募者の概要・経営計画・補助事業計画などについて複数の書式を作成して提出しなければなりません。また対象となる受給者についても非常に細かい規定があり、それらすべてをクリアしていなくてはなりません。
公募の基準を満たして提出書類に不備がなければ、第三者機関も含めた審査委員会で厳格な審査が行われます。審査内容については原則非公開ですが、基礎審査・加点審査にヒアリング等も交えて補助金の交付が審議されます。
このように補助金の申請から交付決定までには、極めて厳格で煩雑な手続きが必要であり、意図的な補助金の不正利用は事実上不可能に思えます。
補助金不正利用に対する罰則基準
補助金の適正な利用については「補助金適正化法」によって、補助金交付の条件から罰則まで細かく規定されています。ここでは不正利用の事例をもとに、罰則の具体的な内容を紹介しましょう。
文部科学省のホームページには、科学研究費補助金の不正利用に関する事例が挙げられています。具体的な内容は以下のような補助金の不正利用です。
・応募、受給資格のない研究者が不正に補助金を受給
・実際に申請した補助金の用途に合わない不正使用
・架空の取引を計上して、実際には業者に補助金を管理させる「預け金」
・実体をともなわない出張旅費を請求する「カラ出張」
・実体をともなわない作業の謝金を請求する「カラ謝金」
こうした不正利用が明らかになった場合、罰則としてはまず研究機関・事業所・事業主などの情報開示による「行政的罰則」が課せられます。さらに補助金の取り消し・返還などの「民事的罰則」や、場合によっては「刑事的罰則」も課せられます。
実際に文部科学省のホームページでも、補助金の不正利用については、補助金の返還命令と一定期間の応募資格停止措置、刑事罰が課されると明記されています。不正が発覚した場合には、当該事業所や研究機関は大きなダメージを負うことになるでしょう。
補助金不正利用の実態
補助金申請の手続きは非常に煩雑なため、事業者や個人に代わって、国家資格を持つ社会保険労務士が行うケースが多いと言えます。他に補助金事業に関わる業者が仲介するケースもありますが、こうした仲介者が不正利用を促した事例もあります。
災害支援事業に関わる補助金申請では、被災地での工事を受注した施工業者が、工事代金を水増し申請して、差額分を不正に受給するケースが多数報告されています。こうしたケースでは詐欺罪として、刑事告訴される可能性もあります。
他にも不正利用が発覚して公表された事業所情報から、不正利用の実態をいくつか紹介しましょう。
・特定求職者雇用開発助成金について、すでに就労中の労働者を新規雇用として虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給した事例。(厚生労働省東京労働局)
・キャリアアップ助成金及び人材開発支援助成金で、虚偽の申告書類を作成し、助成金を不正に受給した事例。(厚生労働省兵庫労働局)
・キャリアアップ助成金の申請で、正規雇用の転換日を偽って申請を行い、助成金を不正に受給した事例。(厚生労働省神奈川労働局)
これらの事例では事業主情報が公表された上で、受給した補助金については返還命令が出されています。
補助金不正利用の実例
補助金をめぐる実例としては、国の補助金不正受給でニュースになった、いわゆる「森友学園問題」が記憶に新しいでしょう。
この事件では国有地への小学校建設をめぐって、工事代金を水増しして補助金を申請、補助金を不正に受給した容疑で、籠池夫妻が詐欺の罪で起訴されました。さらに現在では政治問題にまで飛び火し、政権基盤を揺るがしかねない大問題にまで発展しています。
まとめ
現在日本国内では、多種多様な名目で補助金が支給されています。災害のような苦境から脱するためや、企業や個人事業主に対する経営支援、さらに新しい技術の研究開発促進のためなど、補助金はさまざまなシーンで社会に貢献しています。
しかしそうした補助金を不正利用する事例も後を絶ちません。これは社会的な見地からして、決して許される行為ではありません。過去の不正利用に関しても、そのほとんどが厳しい罰則の対象になっています。
これから補助金の申請を検討する場合は、その財源が国民全体の財産であることを考慮して、絶対に不正利用に関わらないことを約束するべきではないでしょうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道
ニュース -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
ニュース