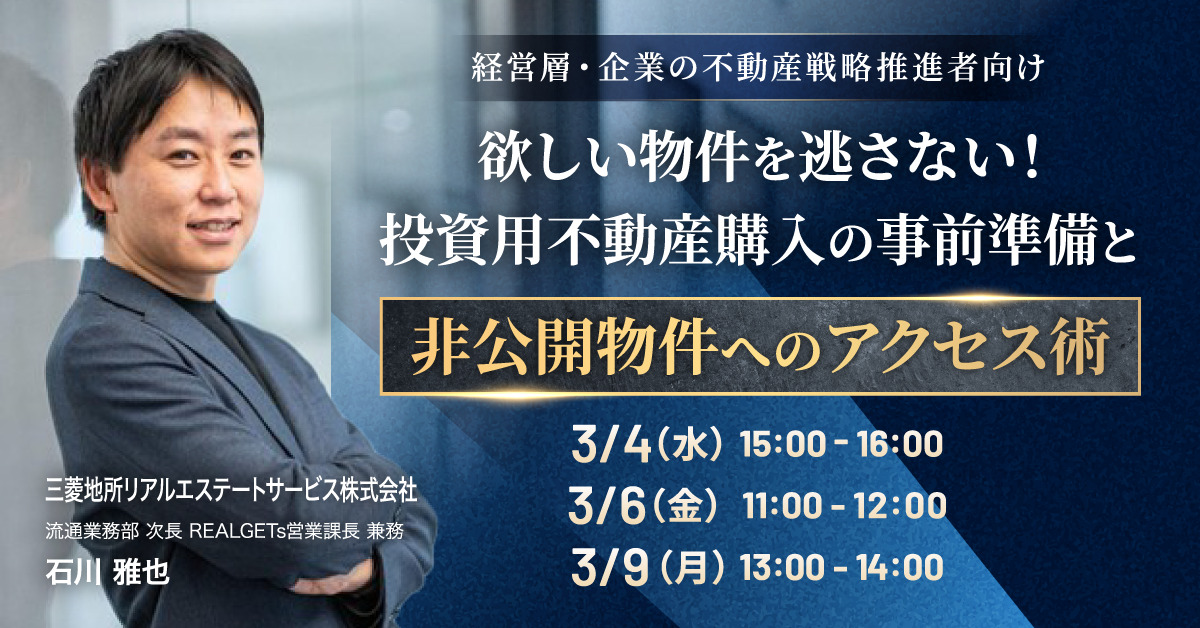公開日 /-create_datetime-/
コロナ感染拡大による緊急経済対策「10万円給付金」の目的と支給方法とは
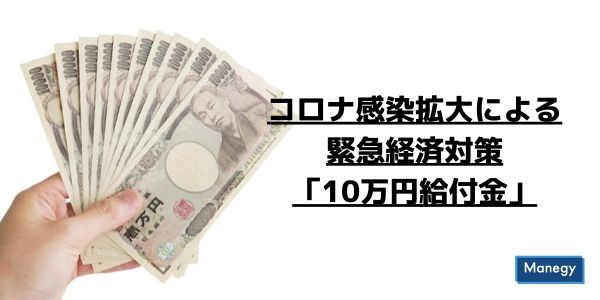
新型コロナウイルスによる感染症が全世界で猛威を振るっています。日本でも政府が非常事態宣言を出し、不要不急の外出を控えるよう求める外出自粛要請や幅広い業種を対象にした休業要請が都道府県知事からなされました。
こうした感染症拡大防止策によって経済活動が落ち込む中、政府は緊急経済対策の一つとして「国民一人当たり10万円の給付」(特別定額給付)を決めました。提出間際の補正予算案を組み替えての決定という異例の展開が注目を集めた「10万円給付」ですが、政府の目的はどこにあるのでしょうか。給付方法や今後、同様の給付が行われるのかを含めて解説しましょう。
目次【本記事の内容】
10万円給付の目的とは
経済対策として「一人当たり10万円給付」が必要だという声は、日本での患者増加が始まった当初からあがっていました。しかし、政府はいったん「減収世帯に30万円支給」(生活支援臨時給付金)という方針を決め、「30万支給」を盛り込んだ補正予算案も決定しました。
ところが、「30万円給付」は収入が大幅に減少した世帯が対象で、給付世帯が限られることから評判が悪く、与党の自民党や公明党からも「一人10万円給付」を求める声があがるほどでした。
政府が当初、「一人10万円」を見送ったのには、大きく2つの理由があります。
1つは財政の悪化です。日本の人口は1億2000万人を超えます。一人当たり10万円を給付すると必要な予算は12兆円以上。最終的に事務経費と合わせた事業費は12兆8800億円にのぼりました。この財源は、赤字国債。つまり借金です。
このため、10万円給付で国の借金が増えたら、結局は将来、借金を返すために増税しなければならなくなるという反対意見も聞かれました。
もう1つは、「支給しても貯蓄にまわり、効果が薄いのではないか」という懸念です。経済対策である以上、10万円を支給された人にはいろいろな使途に使って、経済を下支えしてもらわなくてはなりません。さらに、景気が刺激されることになれば上出来です。
しかし、日本人は貯蓄を好む国民性がありますから、ほとんどを貯蓄にまわしてしまうかもしれません。それでは、物やサービスを買う人が増えず、経済対策の意味がありません。
日本ではリーマンショック後の2009年にも、国民一人当たり1万2000円の給付を行いました。しかし、このときは多くが貯蓄にまわり、経済的な効果は薄かったとされます。
当時、首相だった麻生太郎財務大臣も「当時の現金給付策は失敗だった」と述べ、今回の「一人10万円」には反対だったと伝えられています。
しかし、今回のコロナウイルスはリーマンショックとは比較にならない悪影響を経済に及ぼし、多くの人が当座をしのぐための現金を求めています。富裕層にも現金が支給されることを問題視する人もいますが、条件を設けず一律に支給しなければ、スピーディーに現金を届けることはできません。
政府が10万円給付に舵を切ったのは、リーマンショック時とは比較にならないほど多くの人が一日も早い現金給付を望んでいて、対象を限定すれば、かえって国民の不満が高まる恐れがあったからです。
今回は、そうした世論に政府が応えた(屈した?)といえそうです。
給付の対象者と申請の方法は
気になる10万円の給付対象者ですが、今年4月27日時点で住民基本台帳に記載されているすべての人です。国籍は問わず、短期滞在者や不法滞在者を除く外国人も対象となります。給付の受給者は世帯主で、世帯の人数分を一括して受け取ります。
ただし、家庭内暴力が原因で別居している人については、避難先の市区町村で手続きをすれば、世帯主でなくても受け取ることができます。
申請については、手続きはすべて市区町村が行います。
市区町村が申請書を作成し、各家庭に郵送。世帯主などが必要事項を記入し、本人確認書類を同封して返送すると手続きが完了します。マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの手続きも可能です。
手続きや給付の進め方はすべて自治体に任せられていますので、市区町村によって手続きの時期は異なります。
どの市区町村も一日も早い支給を目指して準備を急いでいますが、人口が多いほど申請書作成などの事務が増えるため、大都市ほど受付時期が遅れる傾向にあります。概ねオンライン申請は5月初めから開始し、申請書の郵送は5月中旬から下旬頃という自治体が多いようです。
給付はいつから?追加給付はあるの?
給付の開始も市区町村によって5月中旬から6月中旬とまちまちです。オンライン申請の方が早く受け取れるのですが、手続きの際に必要な暗証番号を忘れてしまった人が続出。暗証番号の再設定をする人で、マイナンバーカードのシステムが一時ダウンするというトラブルも発生しました。
一方、市区町村の中には、国から事業費を交付される前に独自で費用を立て替え、支給を急ぐところもあります。特に困窮している世帯を対象に早期支給を行っている自治体もありますので、「事情があり一日も早く支給してほしい」という人は、市区町村の窓口に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
紆余曲折を経て、支給が決まった「一人10万円」の給付金ですが、緊急事態宣言が長期化する中、さらなる経済支援を求める声もあがっています。
「もう一度、一人10万円」と期待する人もいるかもしれませんが、さすがにそれは難しいでしょう。本来、政府の経済対策とは公共工事を増やしたり、企業に補助金や助成金を出したりして、企業が経済活動をしやすくして好景気を生み出し、その恩恵を個人にもたらすといもの。個人への現金給付は非常手段です。
今後、個人給付が行われるとしても、所得制限を設けたり、収入が大幅に減少した人や中小企業を対象にしたりするなど限定的になるでしょう。
まとめ
新型コロナウイルス感染症拡大による経済の落ち込みに対応するため行われる「一人10万円給付」。経済対策としての実効性を疑問視する声もありますが、収入が激減し、現金を必要としている人がいるのも事実です。一方で、富裕層にも支給されるのは不公平だという声もあります。
もし、経済的な影響はあまり受けておらず、金銭的に余裕があるのであれば、支給を申請しないというのも一つの判断です。しかし、10万円を使って普段はできない贅沢をするのも、経済支援として正しいやり方なのかもしれません。
それぞれが事情に合わせて申請を行い、家計支援や経済対策としての目的にあった使い方をするのが国民の正しい行動だといえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
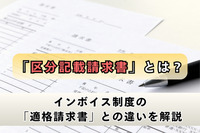
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
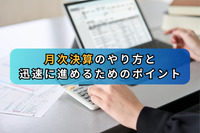
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース