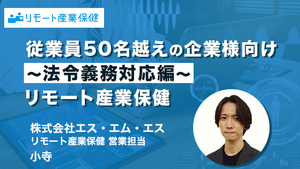公開日 /-create_datetime-/
年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
知っているようであまり知らない!?印紙について徹底解説
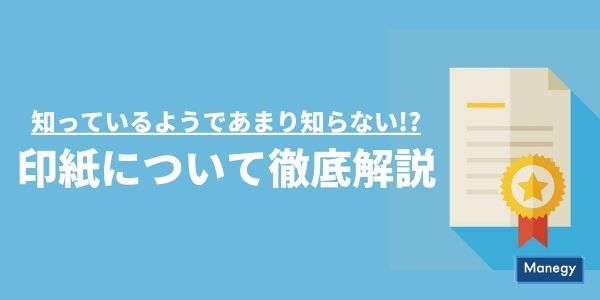
普段から契約書などを扱っている人ならよく知っている印紙ですが、そうでない人にはいったい何のために貼られ、そもそも何に貼るべきなのか、わからないことも多いと思います。実は印紙は、正しく使わないと脱税になってしまう可能性もあるほど重要なもの。今回は印紙の概要や、貼らなければいけない書類、必要な金額など印紙にまつわるよくある疑問についてご紹介していきます。
印紙ってそもそも何?貼るのは何のため?
印紙は、正式な名称を「収入印紙」といいます(以下は印紙と表記)。印紙は、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票で、印紙税法によって貼るべき書類や、金額が定められています。印紙は、1円〜100,000円の額面で31種類が発行されています。
印紙税法という言葉からもわかるように、私たちは印紙を購入して書類に貼ることで、税金(もしくは公的なサービスに対する手数料)を納めているのです。税金というからには、納めるのが遅れたり、逃れれば当然罰せられることになります。
印紙を買っただけでは納税にならない
印紙を貼らなければならない文書に、印紙を貼って消印をしなかった場合には印紙税法 第20条の定めにより過怠税が課されます。
印紙税法 第20条 印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収
「第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。」
ここで確認していただきたいのは条文内の「納付しなかった場合には」という言葉です。印紙は郵便局やコンビニ、法務局の印紙さばき所で購入することができますが、印紙を買っただけでは印紙税を納付したことにはなりません。「え!?お金を払ったのに納税したことにならないの?」と思う人もいるでしょう。
実は印紙は、印紙を貼らなければならない文書(印紙税法で定められた課税文書)に、印紙を直接貼り、かつ消印をしなければ納税したことにはなりません。消印は、印鑑で割り印をしなくても、ボールペンなどでサインすればよいです(鉛筆など消せるものは不可)。また契約書でよくある、契約者双方が割り印する必要もありません。要するにしっかりと課税文書に貼られた状態で、消印により二度と使えないようにされていればよいのです。
印紙を故意に貼らなかった場合は「一年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と印紙税法で決められていますので、決してあなどってはいけません。印紙は購入するだけでなく、貼付し使えない状態に消印することで、はじめて納税したことになると覚えておきましょう。
印紙を貼らなければいけない書類、課税文書とは?
課税文書は、国税庁が発行する印紙税額一覧表に1号から20号まで規定されています。いくつか代表的なものを挙げておきましょう。
●1号文書
不動産の売買契約書や消費貸借契約書(ローンなど)等が、1号文書になります。契約書に記載された金額で印紙の額は変わり、契約金額が1万円未満であれば非課税です。
●2号文書
請負についての契約書(ソフトウェア開発や工事の請負契約書等)が2号文書に該当します。注文請書なども2号文書に含まれるので、会社などで比較的よく目にするかもしれません。契約金額が1万円未満であれば非課税です。
●3号文書
約束手形や為替手形は、3号文書です。金額が記載されていないものや記載金額が10万円未満のものは非課税ですが、あとから記載され、かつ10万円以上であれば印紙を貼らなければなりません。
●17号文書
売上代金の金銭または有価証券の受取書、領収書などは17号文書です。私たちが普段の生活の中で、一番目にする課税文書は17号文書かもしれません。5万円以上のものには印紙を貼る必要があり、100万円を超えると400円、200万円を超えると600円というように、金額で印紙の額は変わります。
現金だけでなく、商品券やプリペイドカードで商品などを購入し、領収書を発行してもらった場合でも印紙が必要です。ただし、クレジットカードで商品などを購入した場合の領収書には印紙は必要ありません。金銭または有価証券の受領がない、というのがその理由ですが少しややこしいですね。
印紙を貼り忘れると契約書は無効?
それでは印紙を貼り忘れたり消印を忘れたりした場合には、契約書や領収書は無効になってしまうのでしょうか?結論からいうと、これは無効にはなりません。印紙は先述のように納税に関わる証票であり、文書の内容や当事者間の約束事を担保するような性質のものではないからです。もちろん金額を間違えた場合でも、文書は無効にはなりません。
まとめ
課税文書と印紙の金額は国税庁により細かく定められているので、すべて覚えておくことはなかなか難しいでしょう。自分の扱う書類が課税文書かどうか、課税文書ならいくらの印紙を貼ればよいのか、必要であれば経理担当者などに確認の上、貼付と消印を忘れないようにして正しい金額を使うように心がけましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。
【関連コンテンツ】電子契約を導入して印紙税を削減!電子契約サービス一覧はこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
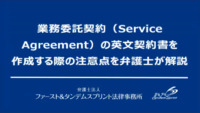
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
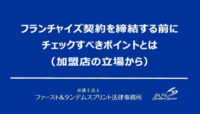
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -
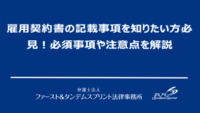
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -
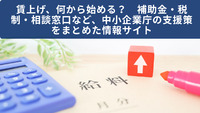
賃上げ、何から始める? 補助金・税制・相談窓口など、中小企業庁の支援策をまとめた情報サイト
ニュース -

「企業間取引の“ムダ”をDXで断つ」――インフォマートが描く、業務改革の次なる進化とは
ニュース -

プロジェクトの遅延を防ぐ!失敗しないファイル管理戦略
ニュース -
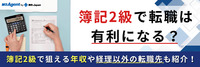
簿記2級で転職は有利になる?簿記2級で狙える年収や経理以外の転職先も紹介!
ニュース -
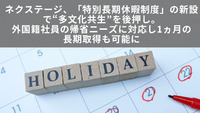
ネクステージ、「特別長期休暇制度」の新設で“多文化共生”を後押し。外国籍社員の帰省ニーズに対応し1ヵ月の長期取得も可能に
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

人材育成の課題と解決のための5ステップ|階層別のポイントやフレームワークも紹介
ニュース -
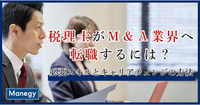
税理士がM&A業界へ転職するには?必要スキルとキャリアチェンジの方法(前編)
ニュース -

ハラスメント研修を実施し、事前に防止したい
ニュース -

福利厚生の充実予定企業は47.6% 帝国データバンク調査で中小企業の課題も明らかに
ニュース -

越境サブスクとは?越境ECとサブスクリプションの掛け合わせが注目される理由と注意点を解説
ニュース





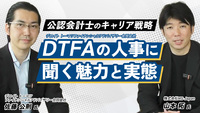















 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました