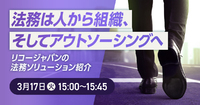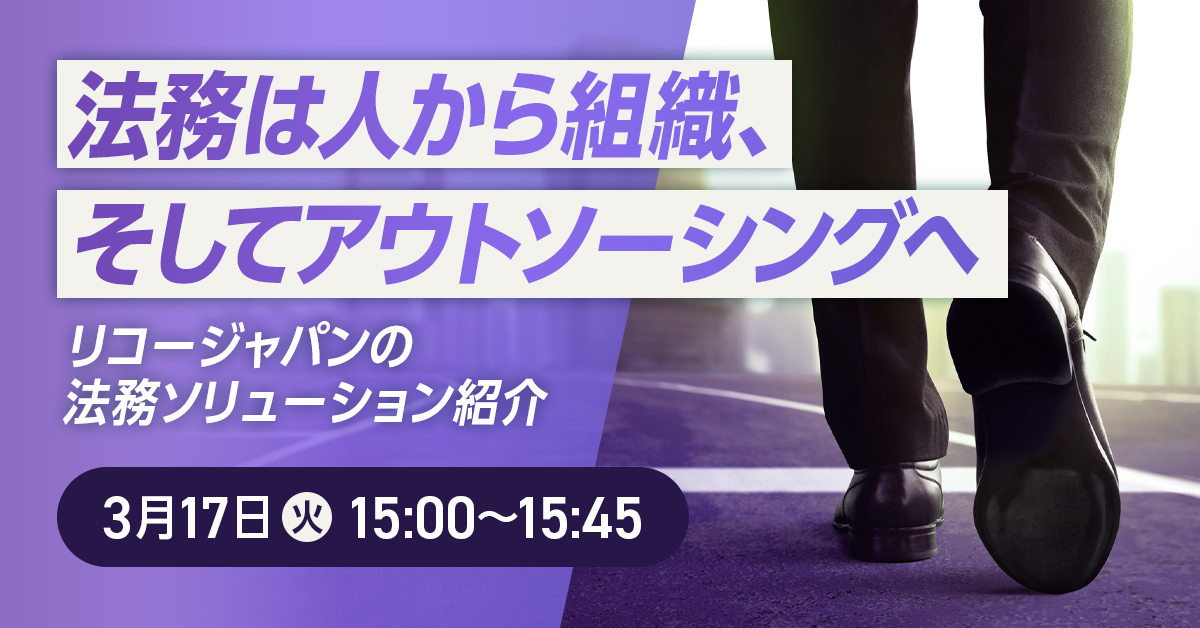公開日 /-create_datetime-/
「話が長い」と言われる人の改善策

誰でも一度くらいは、「話が長い」「わかりにくい」と言われたことがあるでしょう。中には2度や3度で済まずに悩んでいる人もいるかもしれません。
友達や家族との会話ならが長くてもよいのですが、ビジネスの場ではそうはいきません。
今回の記事は、「話が長い」と言われる人の改善策について解説します。
目次【本記事の内容】
伝わりやすい話し方のポイントは?
まずは相手に伝わりやすい話し方とはどのようなものなのかを理解しましょう。
伝え方の上手い人は次の4つのポイントを押さえて話をしています。
①自分が伝えたいことを明確にする
伝えたい内容とは、話のゴールであり、結論です。ゴールのない会話は、聞いている人はもちろん、話している本人ですらどこを目指しているのかがわからなくなってしまいます。
まずは一番相手に伝えたいことを明確にしてから話を始めることが重要です。
②5W1Hを意識して構成する
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)は、相手に理解しやすく話をするときの基本です。5W1Hを骨格として内容を構成すると、伝えるべきことが整理されてわかりやすくなります。
自分にとっては自明な情報でも、聞いている相手も同じように知っているとは限りません。登場人物が多いときは主語を、時間の経過がめまぐるしい話は時系列をはっきりさせるなどして整理する必要があります。
③情報量は最小限にする
人は話を聞くときに、要点を理解するための情報を拾い集めて頭の中にストックしています。情報量が多すぎると、ただ話が長くなるだけではなく、聞く側の情報処理の負担になってしまいます。
情報量は、伝えるべきことと関係のある必要最低限のものに抑えることが大切です。
④具体例で噛み砕きやすくする
抽象的な内容や自分の専門外の話でも、具体例を示すことでイメージしやすくなります。
情報量は最小限にすべきですが、相手が理解できない場合は具体例で噛み砕いてあげることも必要です。
ただし、具体例は相手がよく知っていることや馴染みのある話題でなければ意味がありません。聞く人がどういう具体例だとイメージしやすいのか、年齢層や趣味などに合わせて話題を選ぶ想像力が求められます。
基本的に、他人は「あなた」が思っているほどには「あなた」のことに興味を持ってはいません。何か相手に伝えたいことがあったら、そもそも他人の話などには興味がないことを前提に話す必要があります。
「我慢して聞いてもらっている」「貴重な時間をいただいている」という配慮があると、話は自然と短く、的確な内容になっていくものです。
話が長い人の特徴
次に「話が長い」「わかりにくい」と言われてしまう人の特徴を見ていきましょう。
耳の痛い話かもしれませんが、まずは自分の弱点を自覚することが改善の第一歩です。
伝えたいことを本人が理解していない
何を伝えたいかを本人がわかっていないと、会話自体が結論を探す旅になってしまうので、当然ながら長くなってしまいます。
話している本人には「伝えたいこと」があるのかもしれませんが、言語化できていないケースもよくあります。「伝えたいこと」があるときは、まず自分の頭の中で、5W1Hなどで明確化してから話し始めるとよいでしょう。
自分視点のプロセスで説明する
なぜそういう考えや結論に至ったのかを、自分の視点で順を追って説明する人は話が長くなりがちです。それは、伝えたいことはあるけれど、伝えるべきポイントが整理できておらず、話しながら結論までの道筋を整えているからです。
「自分がなぜその場所に行ったのか」「自分とその人とはどういう関係か」など、自分視点の情報を過剰に入れこんでいませんか。
伝えたいことを説明するために、その情報は本当に必要なのか。自問自答しながら取捨選択していく必要があります。
「伝えたい」より「こう思われたい」が優先している
話を伝えるときに重要なのは「相手が理解できるかどうか」です。もしかすると話を伝えることよりも、相手からの評価を優先している可能性があります。
「相手によく思われたい」「怒られたくない」などが目的になると、不安や恐怖から過剰に説明が多くなりがちです。情報過多になればかえってわかりにくくなり、結局は自分の評価を下げてしまいます。
情報が足りなければ相手から補足説明を求められます。「そのときに対処すればいい」と腹を括ることも大切です。
話を短くするための改善策
話を短く、わかりやすく伝えるために、具体的にできることを今から実践してみましょう。
結論を先に言う
話を端的に伝えるためには結論を先に言ってしまうことです。結論を最初に伝えると、相手にどういう視点で話を聞くべきかを示すことができます。結論が示されずに話が進むと、一つひとつの情報をどのように解釈すべきか、聞いている相手が迷ってしまうので疲れしまうのです。
自分にとってのゴール設定にもなるので、迷子にならずに話を進める指標とすることができます。
適度に「。」で区切る
人は一度に理解できる情報量には限界があります。たとえ同じ会話の中であっても、適度に区切りをつけることで整理しやくなります。
区切り方は読点「、」ではなく、句点「。」にしましょう。一旦文章を終わらせることが重要です。
「1つの文章に主語は1つ」とか「並列する項目は箇条書きみたいに1つずつ」といったようなルールを自分なりに作っておくとよいでしょう。
小論文で構成の練習をする
受験や資格試験などで小論文を勉強した経験がある人は多いでしょう。小論文は制限された字数や時間の中で書ききらなければならないので、構成や情報の取捨選択のいい練習になります。
小論文の基本構成は、「序論→本論→結論」です。
序論では、どういう話題で、どういうことを自分は言いたいかを伝えて、文章を読むスタンスを説明します。
本論では、なぜそのような考えに至ったかの根拠となる事例やデータなど、説得する材料を提供します。
結論では、本論で提供した材料から、自分が言いたいことへの道筋をまとめます。
会社でプレゼンをしなければならないときなどは、小論文の参考書をヒントにすると伝わりやすい構成が作れるかもしれません。
自分の声を録音する
とにかく自分がどういう話し方をしているかを客観的に知ることです。実際に話しているところを録音して聞いてみましょう。
いくらがんばって話を構成してみても、無我夢中になっているときはどこかで客観性を失っているものです。会社でのプレゼン、事例報告会、面接のための自己紹介など、実践的なものほどチェックしてみる価値があります。
録音はスマホのアプリなどを使うとよいでしょう。録音してから少し時間を置いてから聞くと、さらに客観的に聞くことができます。
自分の話し方や声を聞くことは気恥ずかしいかもしれませんが、格段に効果があります。
まとめ
話を短く、わかりやすく伝えるためには、聞く人の身になって伝え方を考えることが重要です。
最も効果的な方法は、結論を先に言ってしまうこと。結論とは話のゴールであり、一つひとつの情報を聞くときの立ち位置を決めることです。
相手に伝えるべきことがあるときは、まずは事前に結論をできるだけ具体的に言語化してみましょう。言語化する作業そのものが、わかりやすい話をするためのファーストステップになるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -
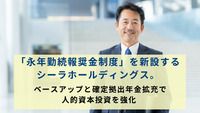
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -
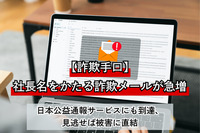
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース