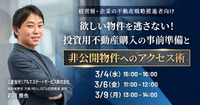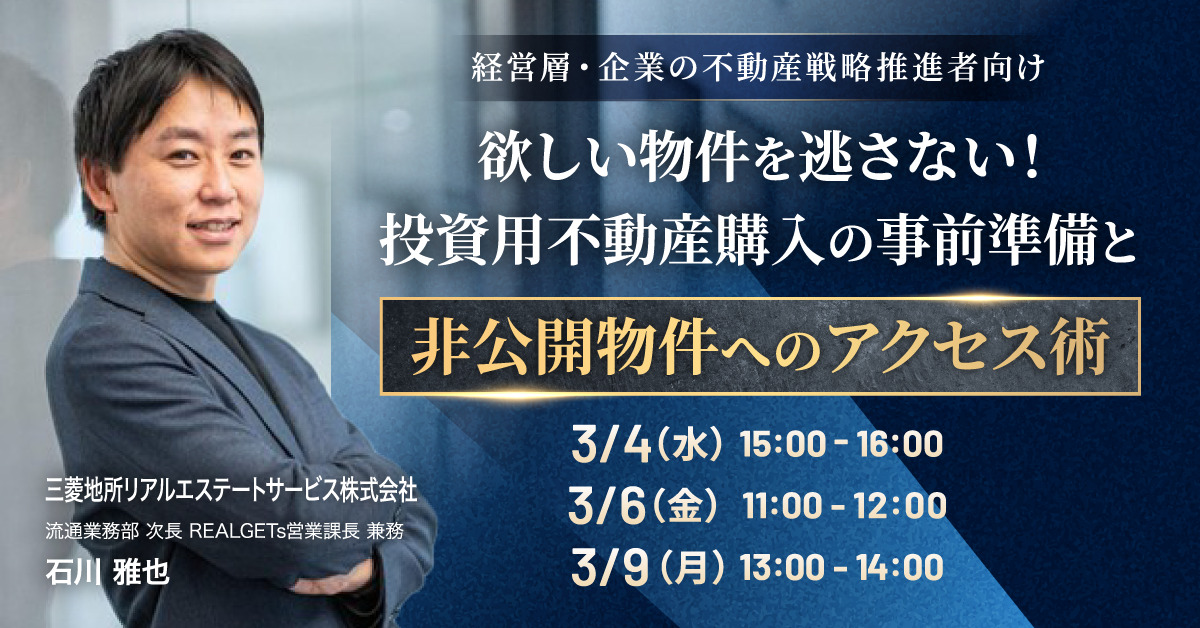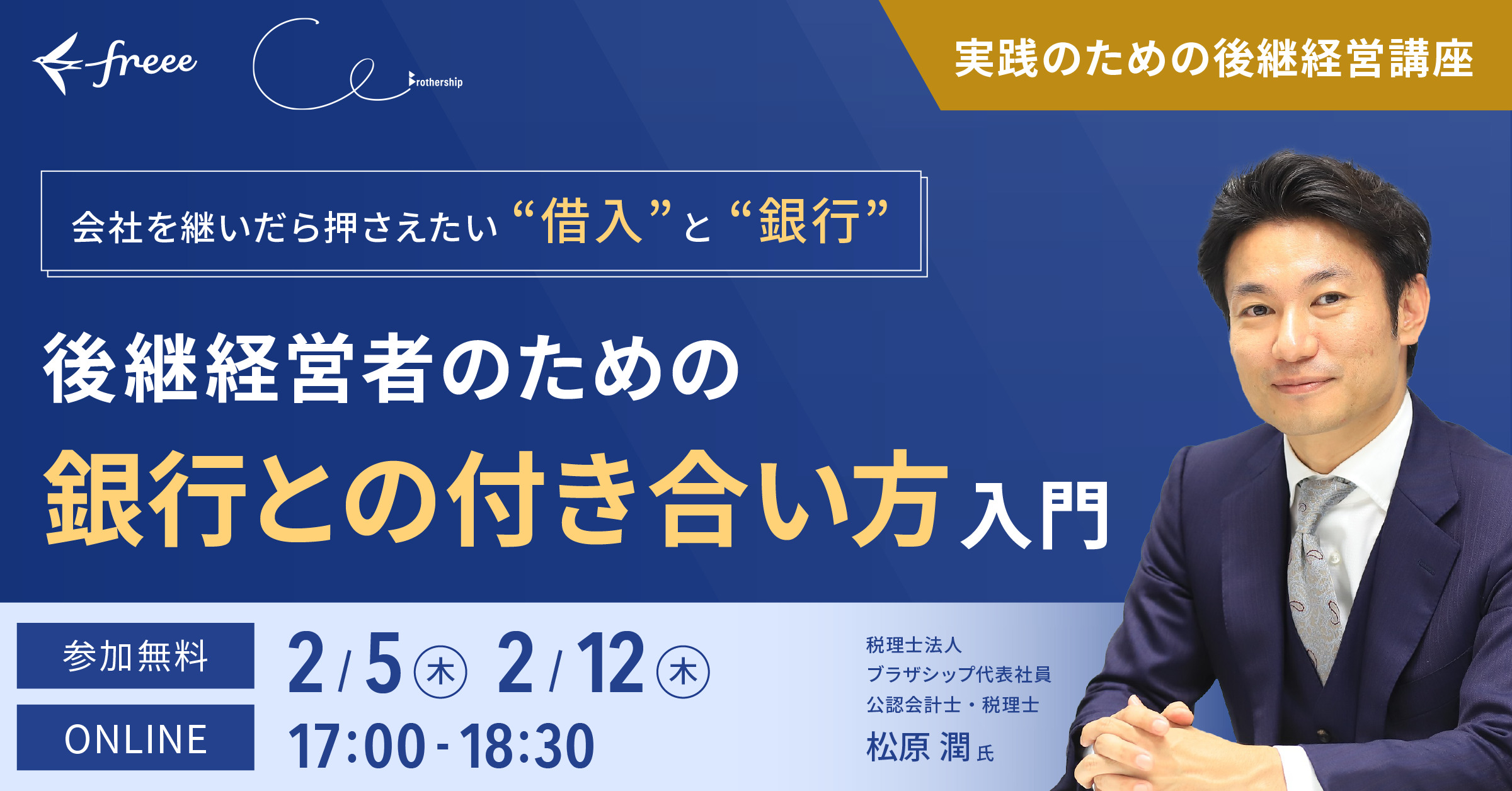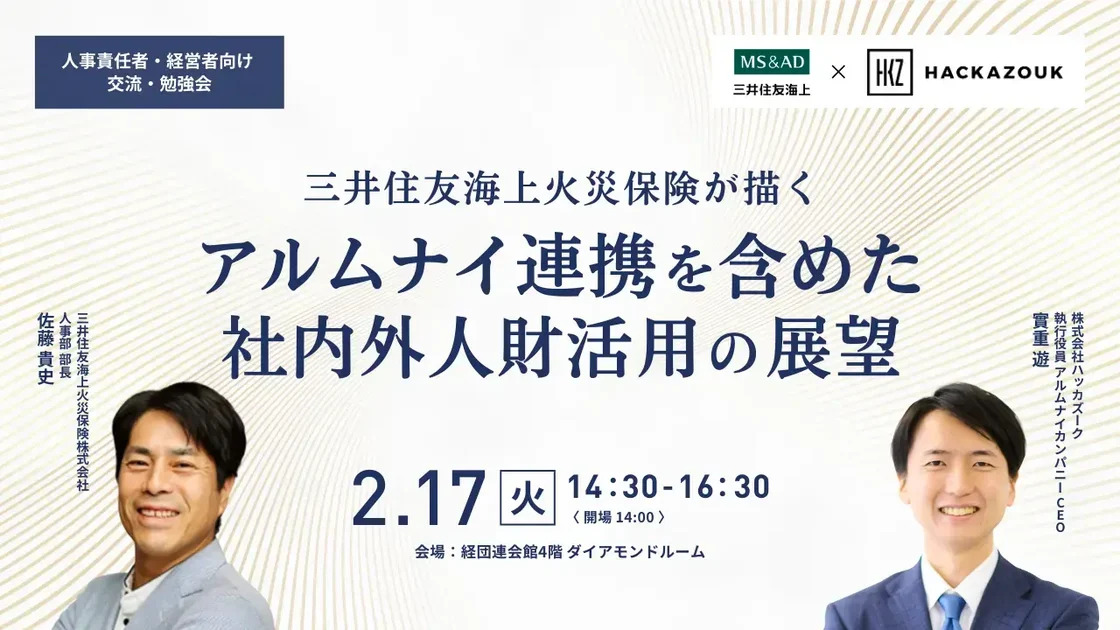公開日 /-create_datetime-/

国内の中小企業は、日本の経済基盤を支えるうえで重要な存在です。しかし現在、中小企業は人手不足などの慢性的な悩みを抱えており、生産性の向上が大きな課題になっています。
こうした課題を解決するために、国が中心となり中小企業を支援する取り組みが「ものづくり補助金」の制度です。この記事ではものづくり補助金を申請するためのポイントについて解説します。
ものづくり補助金の概要
ものづくり補助金は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のことで、名称からイメージするのは製造業ですが、実際には業種を問わずに利用することができます。
対象となる経費もさまざまで、設備投資資金をはじめとして、外注費や外部コンサルティング費用など幅広い使い方が可能です。また従来の「一般型」に加えて、「グローバル展開型」も新設されました。
ものづくり補助金の補助額と補助率
一般型
一般型の補助金は、金額や補助率が大きく3つに分けられます。
1.一般型(通常)
補助額は100~1,000万円で、補助率は1/2以内です。条件によっては2/3が適用になる場合もあります。
2.企業間データ活用型
補助額は100~1,000万円で、補助率は2/3以内です。企業の連携体としても利用でき、その場合は200万円×連携体数が、補助金額の上限に上乗せされます。
3.小規模型
設備投資のみのケースと、試作開発等のケースに分かれていますが、どちらも補助額は100~500万円で、補助率は1/2以内です。
グローバル型
補助額は1,000~3,000万円で、補助率は1/2~3/4です。
ものづくり補助金の対象となる事業
ものづくり補助金の対象になる事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
1.中小企業であること
業種により中小企業の定義が違いますが、おおむね資本金3億円以下(業種によっては5,000万円以下)であることが求められます。
2.認定支援機関の支援対象になっていること
国が認定して、中小企業への支援事業を行う認定支援機関によって、現在支援を受けている必要があります。主な認定支援機関は、商工会・商工会議所・金融機関などです。
3.国内で事業を行っていること
日本国内に本社を置き、事業を行っている中小企業が対象になります。ただしグローバル展開型は条件が異なります。
ものづくり補助金の申請
公募期間
通常ものづくり補助金の公募は3ヵ月ごとに行われます。公募開始から受給が確定するまでは、余裕を見ておよそ半年間と考えておくとよいでしょう。
必要な書類と申請方法
ものづくり補助金の申請には、以下の4つの書類が必要です。
・事業計画書
・賃金引上げ計画の表明書
・決算書等
・その他加点に必要な資料(任意)
事業計画書は3~5年分策定し、付加価値額の増加と賃上げに関する要件を必ず盛り込む必要があります。特に賃上げの面では、給与支払い総額を年率平均で1.5%以上増やすことと、事業場内最低賃金を、地域別最低賃金プラス30円以上にしなければなりません。
また直近の最低賃金と給与支給総額を明記して、それに従業員が合意していることも証明する必要があります。従業員の合意を得ていないことが判明すると、罰則が科されることになるので注意が必要です。
申請する時には、まず経済産業省が管轄するGビズIDを取得します。これは「gBizID」のサイトから取得できます。次に補助金申請サイトの「jGrants」を使って、すべて電子申請システム上で手続きを行います。
重要ポイント
ものづくり補助金の認定率は、約30~50%と言われています。認定を受けるためには必要な書類をすべて準備するだけではなく、「その他加点に必要な資料」で将来性や革新性をアピールすることが重要です。
加点要素になるのは、経営革新計画や経営力向上計画の承認を取得していること、積極的に従業員の賃上げに取り組むこと、小規模事業者であり創業後間もないことなどが挙げられます。特に革新性に関しては、新商品の開発、新たな生産方式の導入などが盛り込めると評価が高まるかもしれません。
また自然災害に被災している場合や、新型コロナウィルス問題で経営に大きな影響を受けている場合も加点要素になります。他にも加点要素はいくつか考えられるので、支援機関に相談することをおすすめします。
新型コロナウィルス問題に対する特別措置
2020年8月時点での公募要領では、ものづくり補助金に新型コロナウィルス問題に対応するための特別枠が設けられています。この枠で申請すると、補助率アップや対象経費の拡充、優先的な採択などのメリットが生じます。
テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換など、いくつか追加の要件が必要になりますが、検討する価値は充分にあります。
まとめ
ものづくり補助金は、業種に関わらず中小企業が全般的に利用できる制度です。以前に比べて公募要領の内容が緩和され、申請に必要な書類が大幅に簡略化されるなど、ずっと利用しやすくなりました。
しかし加点要素の見極めなど、事業者自身が判断して申請書を準備するのは依然として難しい状況です。受給対象として選ばれるためには、中小企業診断士のような専門家への相談も検討する必要があるでしょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -
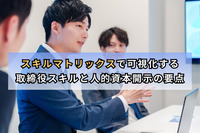
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース -

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由
ニュース -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説
ニュース -

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較
ニュース -
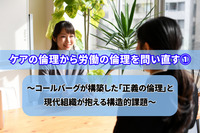
ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表
ニュース