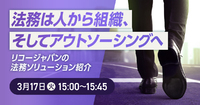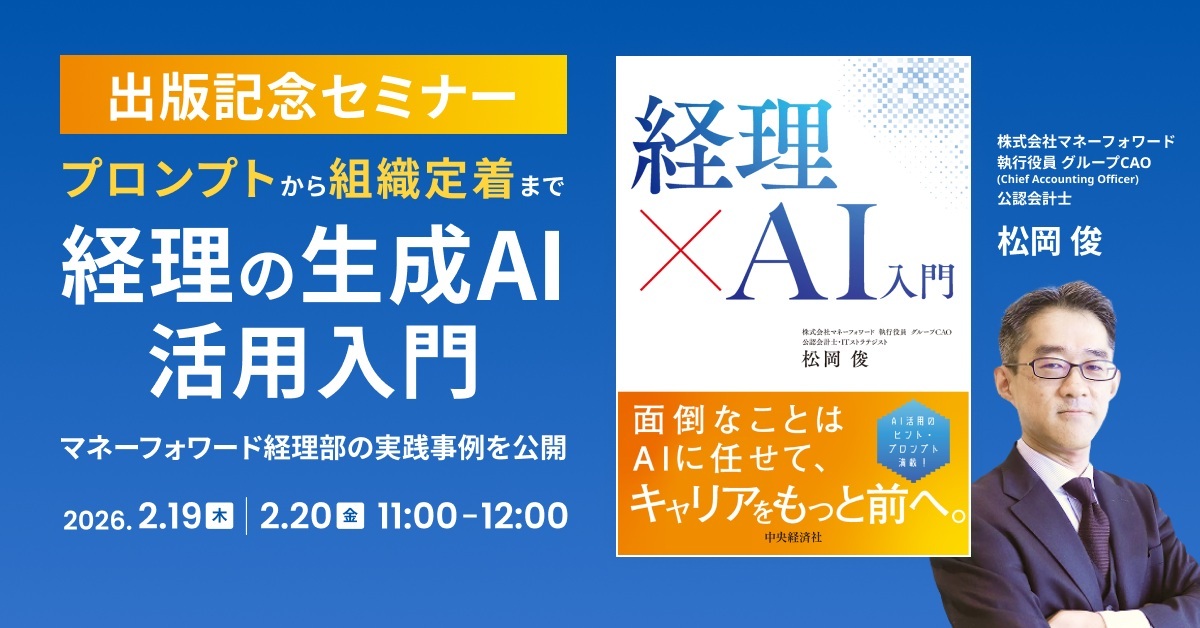公開日 /-create_datetime-/
新卒採用で重視される傾向にある「社会人基礎力」とは?
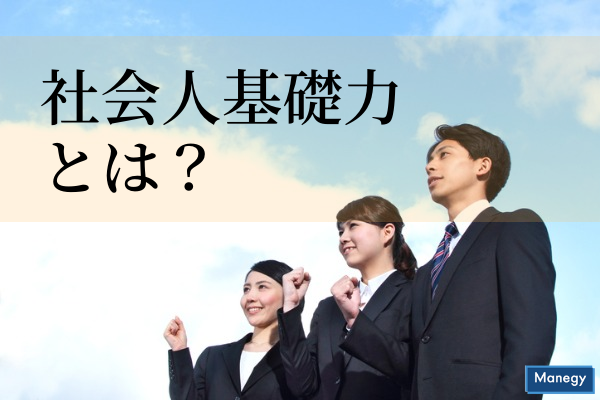
最近、新卒者の採用で「社会人基礎力」を重視する企業が増えています。社会人基礎力とは社会人として働く上で身につけておくべき基礎的な能力を指しますが、実際に就職活動をする学生側にとっては、どのような能力が求められるのか、戸惑うことも多いのではないでしょうか。
企業はどのような人物像を期待していて、なぜこのような能力を求めるのか、社会人基礎力の具体的な内容と、それが求められる背景について説明します。
社会人基礎力が求められる背景
社会人基礎力とは、2006年に経済産業省が提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことです。
当時は「就職氷河期」と呼ばれる企業の採用縮小がようやく終わりをみせた頃で、大量採用された団塊の世代が定年に到達し始める2007年を前に、企業が人材の確保に動き始めていました。ところが、就職氷河期の間に企業の終身雇用制度が崩れ始め、企業は非正規雇用者の活用で雇用の調整を図るようになりました。このため、社員の年齢構成がいびつとなり、先輩が後輩に仕事を教えるという従来の人材育成システムが機能しなくなっていました。
一方、学生の側にも深刻な課題が生じていました。少子化によって高学歴化が進み、大学進学率が5割を超えたものの、逆に若者の学力不足、コミュニケーション能力や問題解決能力の低下が指摘されるようになったのです。
日本ではこれまで、社会人としての基礎的な力の育成が家庭や地域社会の中で行われ、子供の成長とともに自然に培われていくと考えられていました。しかし、核家族や地域コミュニティの希薄化によって、子供が多くの大人と接し、社会のルールやコミュニケーション力を学ぶ機会も減ってしまいました。そのため、社会的基礎力を身につけないまま、社会に出ていく若者が増えたのです。
こうした状況に、日本の経済活動を支える人材の確保・育成が急務だと考えた経済産業者は「社会人基礎力に関する研究会」を設置して、今後の職場で求められる能力や、人材採用・育成の課題について検討を行いました。その結果、まとめられたのが社会人基礎力です。
必要とされる3つの能力
経済産業省によると、社会人基礎力には「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力があります。そして、能力はそれぞれいくつかの能力要素から構成されています。
各能力の定義と能力要素は次の通りです。
【前に踏み出す力(アクション)】
一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力
(能力要素)
・主体性…物事に進んで取り組む力
・働きかけ力…他人に働きかけ巻き込む力
・実行力…目標を設定し確実に行動する力
社会に出ると、答えはいつも1つとは限りません。ですから、失敗を恐れずに試行錯誤しながら、一歩踏み出す行動力が求められます。そして、失敗しても他人と協力しながら、粘り強く取り組む忍耐力も必要とされます。
【考え抜く力(シンキング)】
疑問を持ち、考え抜く力
(能力要素)
・課題発見力…現状を分析し目的や課題を明らかにする力
・計画力…課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
・創造力…新しい価値を生み出す力
仕事のやり方などを改善しながら物事を進めるには、常に問題意識を持ち、課題を発見することが求められます。そして、その課題を解決するための方法やプロセスについて十分納得するまで考え抜く力が必要です。
【チームで働く力(チームワーク)】
(能力要素)
・発信力…自分の意見を分かりやすく伝える力
・傾聴力…相手の意見を丁寧に聴く力
・柔軟性…意見の違いや立場の違いを理解する力
・情況把握力…自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
・規律性…社会のルールや人との約束を守る力
・ストレスコントロール力…ストレスの発生源に対応する力
職場や地域社会では仕事の専門化や細分化が進んでいて、個人や組織としての付加価値を創造するには多様な人たちと協働する必要があります。自分の意見を的確に伝え、意見や立場が異なるメンバーにも敬意を払いながら目標に向けて協力しなければなりません。
個人にも学び努力する姿勢が求められる
社会人基礎力を高めるために、経済産業省は企業や大学などに、個人の成長段階に則した教育・育成システムを求めています。これを受け、大学ではキャリア教育やインターンシップに力を入れるようになり、企業もインターンの受け入れや社員研修制度の充実に取り組んでいます。また、採用の際には、企業側が求める人物像を明確にするともに、学生の側も自分の強みや仕事に対する考え方などを自らの言葉でアピールことが求められるようになりました。
こうした社会人基礎力を若者が身につけるには大学や企業はもちろん、家庭や地域、行政を含めた社会全体の取り組みが欠かせません。そのために、社会人基礎力の概念を社会に浸透させる必要があります。そして、個人の努力も大切です。
個人でも学生の頃から、社会人基礎力を自分の問題としてとらえ、向上や自己評価に取り組まなければなりません。そして、自分の特性や考え方にあった学校や職業を選択することが大切です。このために、経済産業省はインターンシップなどの体験型プログラムや地域社会でのボランティアなどに積極的に参加することを勧めています。
これからは社会人全般に求められる能力に
社会構造の変化にともなう企業の採用活動や若者らの変化に対応するために提唱された社会人基礎力ですが、提唱から10年経った2018年に内容が見直されることになりました。これは高齢社会の進展によって「人生100年時代」といわれる社会の変化を受けたものです。
健康な高齢者が増え、「老後」という概念も変わり定年後も働く人が増えました。国も社会保障制度の維持のために、高齢者の雇用を積極的に後押ししています。こうした社会の変化のもとで、社会人基礎力はより重要性を増しており、「人生100年時代」ならではの切り口、視点が必要だとして見直しが行われました。
従来の社会人基礎力は主に、新卒採用にスポットが当てられていましたが、見直しでは「長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力」と再定義されました。そして、3つの能力に加え、新たに「どう活躍するか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の3つの視点が加えられました。3つの視点については、「能力を発揮するには、目的、学び、組み合わせのバランスが、キャリア形成のうえで必要」とされています。
つまり、生涯にわたって会社や地域で活躍し、貢献し続けるには年齢や成長段階に応じて、学び続ける姿勢が大切だということです。
まとめ
バブル崩壊後の長いデフレ経済と少子高齢化という社会の変化によって、「日本型終身雇用」と呼ばれた日本企業特有の雇用形態も大きく変化しました。これまでは、高校や大学を出て後、就職した会社や組織に長年貢献して老後を迎えるという人生が当たり前でした。しかし、今は転職を繰り返してキャリアアップを図るという生き方やフリーランサーという働き方が珍しくなくなり、定年後も第二の職場の一線で働き続ける人も増えてきました。
このような働き方をするには、常に新しいことを学び、時代の変化に適応していくことが欠かせません。長く働き、社会に貢献し続けようと思えば学び続ける姿勢が必要なのです。
社会人基礎力とは、学校の勉強だけでなく広く社会から学び続け、知識を吸収し続けることで自らキャリアを形成していく力だといえるでしょう。今、社会や企業はそうした人材を求めているのです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -
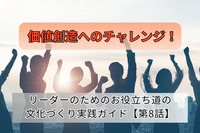
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
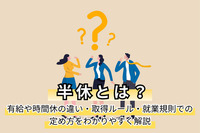
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説
ニュース -

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -
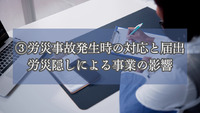
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
ニュース -
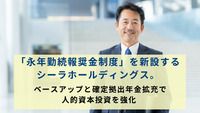
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -
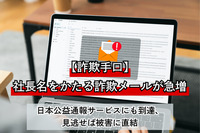
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
ニュース