公開日 /-create_datetime-/

半年に一度もらえるボーナスは、頑張ってきたご褒美のようで嬉しく感じますよね。
しかし、ボーナスはなぜ夏と冬に支給されるのか、疑問に思ったことはありませんか?そもそもボーナスとは?誰でも夏と冬にもらえるの?など、今回はボーナスについてご紹介します。
ボーナスとは
夏や冬に支給される、正規の給与以外の特別手当を「ボーナス」「賞与」「夏季・年末特別手当」などと呼称します。
これはどの会社も支給しているというわけではなく、法律で決められているわけでもありません。
給与規定や就業規則に賞与についての記載がある会社もあれば、「支給されることもある」といった、業績に応じて支給の是非を決定できるように記載がされている会社、または賞与についての記載がない会社などさまざまです。
また、夏や冬以外に臨時手当として支給されるボーナスがあったり、そもそもボーナス自体を年2回ではなく、1回や3回などとしている会社があったり、ボーナスの形態も多種多様です。
ただ、日本におけるボーナスとしては、夏と冬に支給されるものが圧倒的に多いことは言うまでもありません。
「ボーナス」の語源は、ラテン語の「bonus(ボヌス)」であると言われています。ローマ神話に登場する、成功と収穫の神「Bonus Eventus(ボヌス・エヴェントス)」からくるbonusには「良い」という意味があるそうです。
ボーナスの起源
ボーナスの起源は、江戸時代の習慣「お仕着せ」であると言われています。
お仕着せとは、主人が奉公人に着物を与えることを言い、住み込みで働く奉公人が唯一の休みである盆や正月に田舎へ帰る際、身ぎれいにしてお帰りなさいといった意味を込めて主人から支給されるものです。
また、暮れには主人から奉公人に対して「餅代」と記された包み金が与えられました。この頃の奉公人には年間を通じて給与は与えられず、「餅代」などといった恩恵的な給与が与えられていたとされています。ちなみに「仕着せ」よりも「餅代」の方が、小遣いとしての額は大きかったそうです。
これらの「仕着せ」や「餅代」が時代と共に変化し、現在の夏と冬のボーナスになったと言われています。
賞与制度としてのボーナス支給は岩崎彌太郎が初めて
岩崎彌太郎とは、三菱財閥の創業者です。
三菱の資料によると、明治7年、世界各国と海運ビジネス競争を繰り広げていた三菱は、再三に渡る諸外国からの猛攻に耐え、ビジネス競争において勝利を勝ち取りました。この時熾烈な価格競争に勝ち抜くため、三菱は大胆なリストラやコストカットを断行しました。もちろんその中には岩崎彌太郎自身の給与50%カットという項目もあり、社員はそれに倣って給与の3分の1を返上しました。これにより価格競争を勝ち抜いた三菱でしたが、その勝利は社員の奮闘による賜物とし、それぞれの働きを上中下で査定し年末に賞与として支給しました。これが現代の会社で支給される賞与の始まりだと言われています。
ただしこれがすぐに賞与制度として定着したわけではなく、毎年決まって支給されるようになったのは、三菱社報によると明治21年からだということです。
また、ボーナスには利益配分といった特性がありますが、江戸時代にはすでにこのような形態が見られていたということです。
これが時代の変化と共に、労働需要高騰時の定着率向上のため賞与と銘打った手当を支給するなどさまざまな紆余曲折を経て、昭和に入り経済が安定し出した頃から再び利益配分的要素が復活し、現在のボーナス支給事情へとつながっていきます。
世界のボーナス事情
日本では夏と冬にボーナスが支給されるのが一般的ですが、海外ではどうなっているのでしょうか。
アメリカではボーナスが存在しますが、全ての従業員が支給されるわけではないようです。管理職などの従業員は、決算ごとに業績に応じてボーナスが支給されます。
他にも、イタリアやオランダ、オーストリアなど、ボーナスの支給が法律で義務付けられている国があったり、中国では現金の支給以外に現物支給でボーナスとされていたり、国によってさまざまなようです。
一方、日本国内における2018年夏のボーナス支給状況ですが、日本経済新聞によると支給額ナンバー1はソニーの1,668,500円だそうです。東証1部上場企業のボーナス水準としては、全産業平均746,105円と、前年と比較して2.2%の上昇であったそうです。
今年夏のボーナスは、いかがだったでしょうか。半年間頑張った自分へのご褒美として何か特別なことをして、今年の下半期への活力にするのも良いでしょう。ずっとやりたいと思っていた勉強を開始するのもいいかもしれません。今年の夏のボーナスが、将来のみなさんを豊かにする、実りあるボーナスとなるといいですね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題
ニュース -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
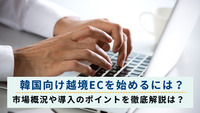
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース




































