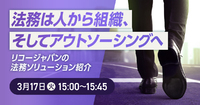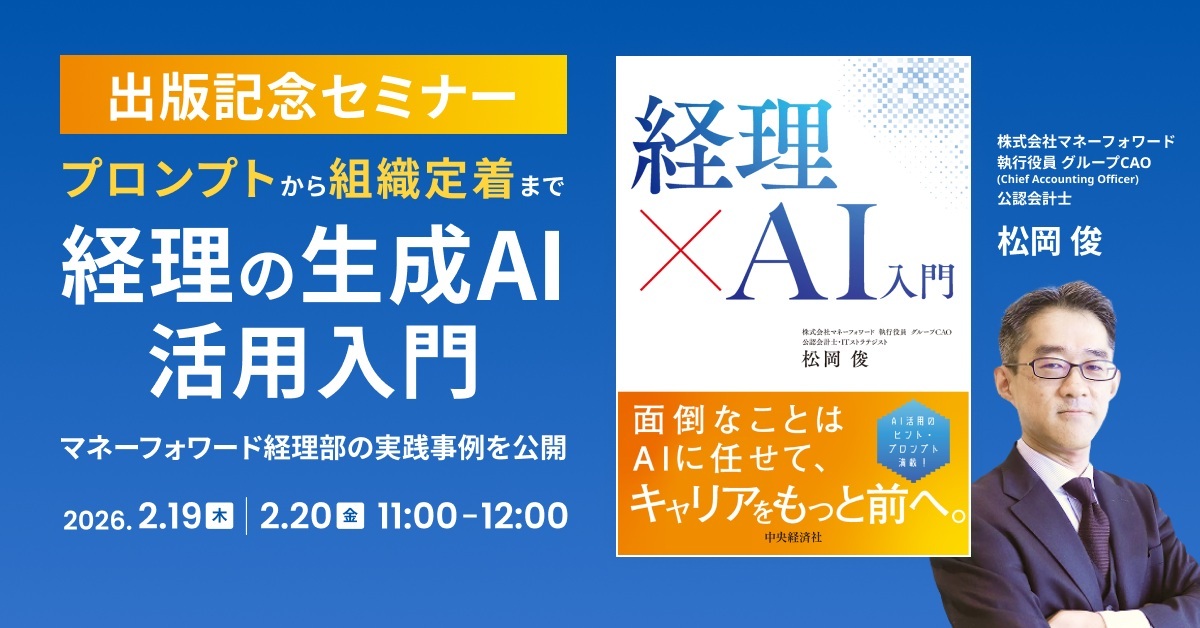公開日 /-create_datetime-/
在宅勤務で打刻忘れが増加…?どうすれば減らせるのか
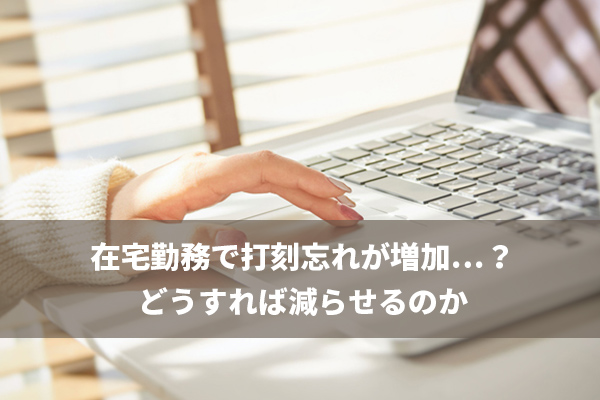
在宅勤務やリモートワークによって、打刻忘れをする人が増えています。今までと違う働き方によって、既存の勤怠管理ルールや方法が通用しなくなっていることが背景にあります。
そもそも打刻忘れには、どのような問題があるのでしょうか。じつは働き方改革によって、始業・終業時刻を客観的に把握することが、法律的に義務化されました。全企業が対策を迫られています。
そこで今回は打刻忘れが増えている企業に向けて、その原因と対策について解説します。
目次【本記事の内容】
打刻忘れが増える背景
従業員の打刻忘れが増える企業には、1つの傾向が見られます。
それは働き方が多様化していることです。近年は通常のオフィスワークだけではなく、リモートワークや在宅勤務、さらには時差出勤、フレックスタイム制など、働く場所や時間などの自由度が高くなっています。
従業員は、さまざまな場所・時間で出退勤をするようになりました。この影響で、今までの勤怠管理方法が有効ではなくなってきたのです。
打刻忘れが起きる原因
では、なぜ打刻忘れが起きてしまうでしょうか。
会社側と従業員の問題で考えてみましょう。
<会社側>
既存の勤怠管理ルール・方法が通用しなくなっていることが原因です。社内で勤務をする従業員だけであれば、タイムカードだけで十分に対応できます。
しかし在宅勤務や直行直帰をする従業員は、タイムカードを使用できません。その代わりに、自己申告や手入力したExcelデータの提出で管理をしている企業もあるでしょう。
勤怠管理のルール・方法が統一されていなかったり、現状に適応していなかったりする場合、打刻忘れが起きる原因となります。また集計ミスや勤怠時間の改ざんも起こりやすくなります。
このように勤務開始時間と終了時間の管理や集計をする仕組みが整っていないことが、問題として挙げられます。
<従業員側>
遠隔で打刻をする習慣がない人は、打刻を忘れやすくなります。とくに勤怠時間を自己申告に委ねている企業であれば、毎日報告をするのは手間がかかります。
例えばExcelで手入力をしている場合、わざわざ1日ごとに作成するのではなく、1か月分をまとめて入力した方が手軽です。しかし、このような方法では、勤怠時間の把握がおろそかになるでしょう。
また勤怠管理方法がルール化されていても、今までとは違う働き方に慣れないうちは、なかなか打刻が根付きません。
打刻をする必要性とは
そもそも、なぜ打刻をする必要があるのでしょうか。
企業の勤怠管理が重視されていることが背景にあります。これには、2019年4月1日から施行されている「働き方改革関連法案」(働き方改革を推進する法律案)が関係しています。
もっとも重要なのは、労働安全衛生法改正において、企業が従業員の労働時間を客観的に把握することが義務付けられたことです。
これは労働基準法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)が適応される、すべての事業場に義務付けられています。
また対象となる労働者は、「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除く全ての者」です。
(引用 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省)
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認して、記録しなければなりません。その原則的な方法は、以下の通りです。
(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、 記録すること。
また企業は労働時間の記録に関する書類を、労働基準法第109条に基づいて、3年間保存しなければなりません。
このような理由で、正確な打刻をする必要が企業にはあるのです。
打刻忘れを防ぐ方法
打刻忘れを防ぐ方法について、3つ紹介をします。
① ペナルティを課す
打刻忘れをした従業員に対して、ちょっとしたペナルティを課す方法です。例えば、始末書の提出があります。
しかし、打刻忘れが何度も続くような場合は、減給や減俸などの措置をとるのも1つです。どのようなペナルティを、どんな条件で課すのかを、就業規則でしっかりと規定しておきましょう。
② アラーム通知
パソコンのアラーム機能を使って、始業時刻・終業時刻に通知する対策です。
またGoogleカレンダーなどの時間管理ウェブアプリケーションを使って、打刻予定をタスクとして組み込むのむ有効です。
③ 勤怠管理システムの導入
スマートフォンやタブレット端末と連動して、打刻ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。GPS機能を使った打刻や、アラート機能によって、打刻忘れを防ぎます。
また勤怠時間を管理するだけでなく、集計・分析が可能です。さらには給与計算システムと連動させて、自動的に給与計算ができるシステムもあります。人事部・総務部など担当部門の作業効率化やコスト削減にも期待ができます。
まとめ
在宅勤務やリモートワークなど、働き方が多様化する中の打刻忘れ問題について、解説しました。
企業は勤怠管理を徹底していかなければなりません。つまり早急に打刻忘れを減らす必要があるということです。
社内でできる対策をしながら、勤怠管理システムを導入することも検討していきましょう。将来的に、在宅勤務を実施予定の企業も、今から対策をとっていくことをおすすめします。
編集部おすすめの勤怠管理のお役立ち資料
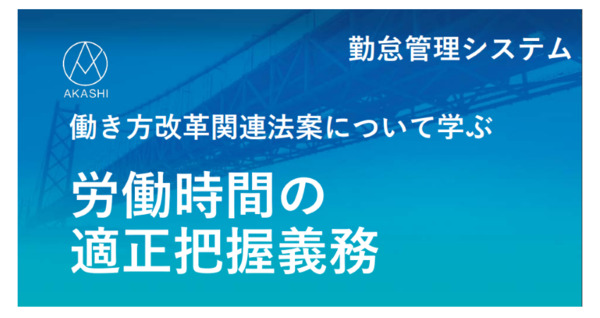

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -
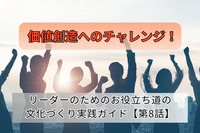
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
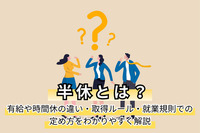
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説
ニュース -

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
ニュース -
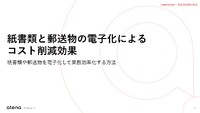
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -
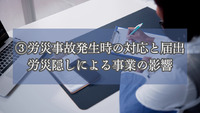
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
ニュース -
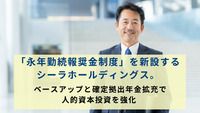
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -
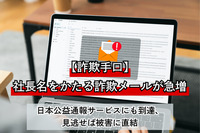
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
ニュース