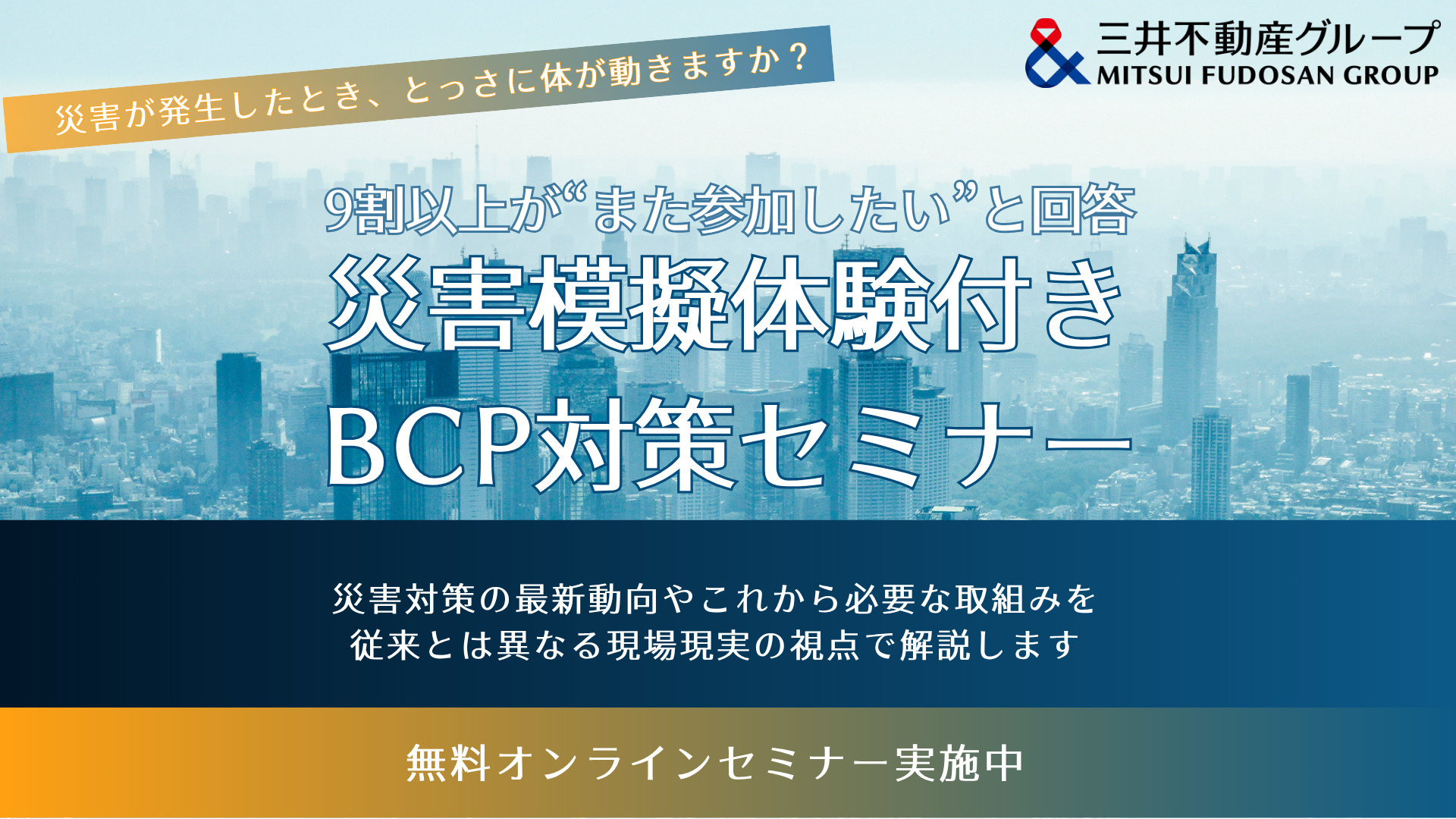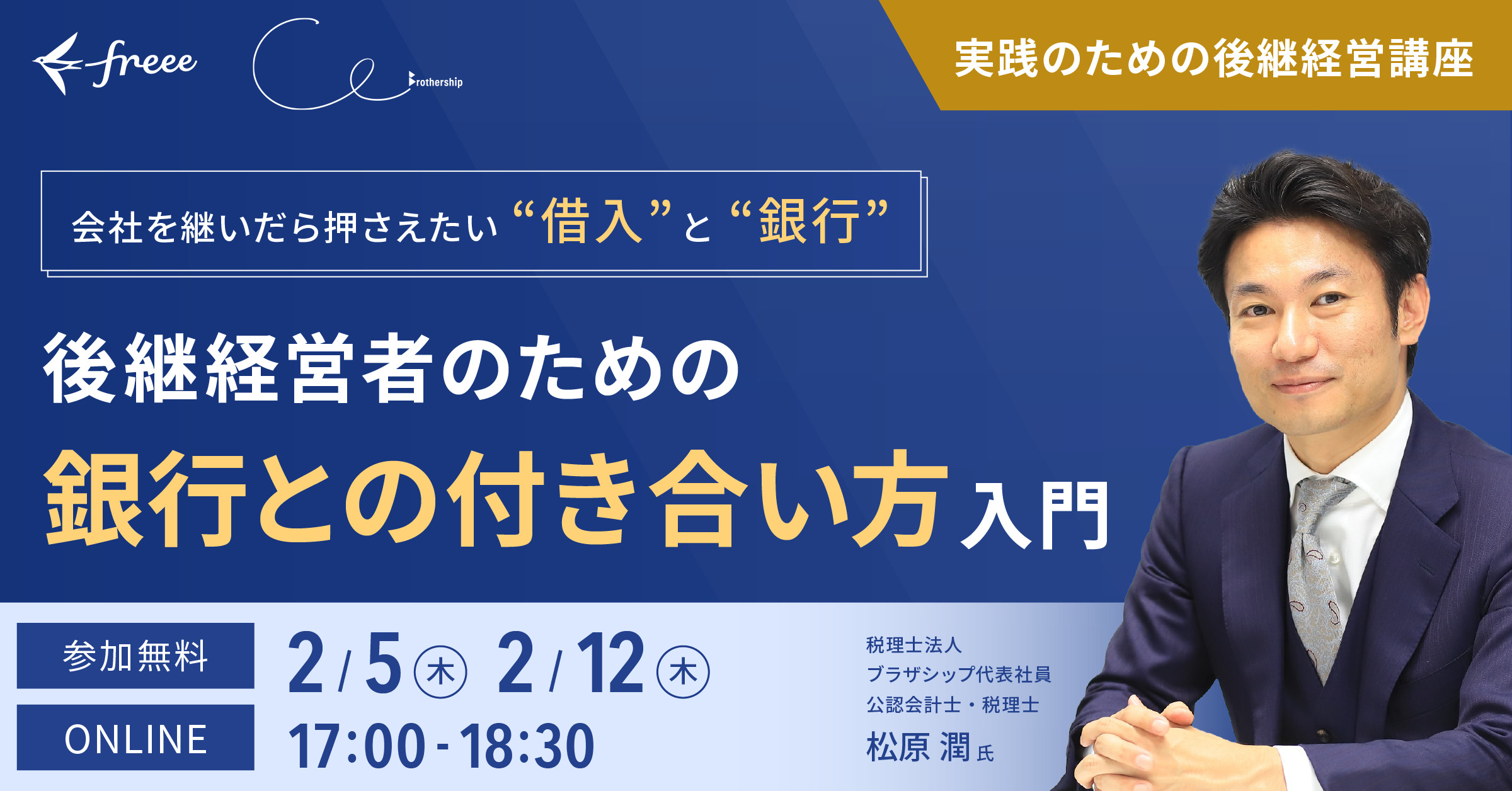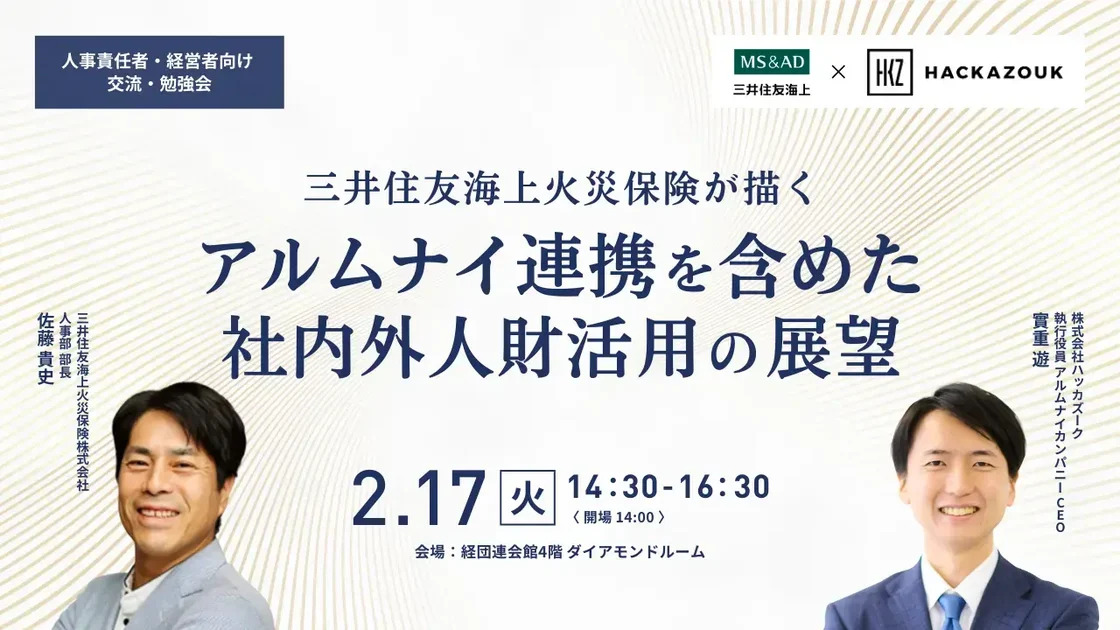公開日 /-create_datetime-/
総務・営業系社員が今さら聞けない振込手数料・請求書等の基礎知識
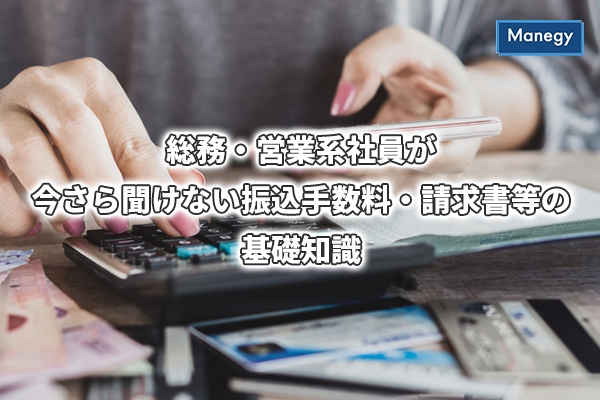
総務・営業系の社員が日常的に取り扱う機会が多い業務の一つが、振込手数料と請求書等の書類です。特に新卒採用社員の場合は入社直後からこの業務を取り扱い、OJT的に処理している人も多いでしょう。
しかし、処理を一つ間違えると自社に大きな損害をもたらす要因になる可能性があります。「今さら上司や先輩に聞けない振込手数料と請求書等の取扱い」。処理ミスを犯さないために知っておくべき基礎知識とはどのようなことでしょうか。
目次【本記事の内容】
商品代金の振込手数料はどちらが負担する?
振込手数料とは、製品・サービス等の商品購入代金を銀行振込する際に掛かる手数料のことです。振込手数料は「先方負担」と「当方負担」の2つに分かれています。
・先方負担
先方負担とは、商品代金の受領側(商品販売側)が振込手数料を負担する方式です。このため先方負担の場合、商品代金の支払い側(商品購入側)は商品代金から振込手数料を差し引いた金額を銀行振込することになります。
・当方負担
当方負担とは、商品代金の支払い側が振込手数料を負担する方式です。このため当方負担の場合、商品代金の支払い側は商品代金に振込手数料を加えた金額を銀行振込することになります。
振込手数料の負担に関する法律の取扱いはどうなっている?
1回当たりの出費は少額でも、年間を通せば100万円以上の出費になるケースもあるのが「振込手数料」です。振込手数料は支払金額が高いほど、取引頻度が多いほど、自社収益の圧迫要因になります。
したがって、振込手数料を先方負担にするのか当方負担にするのかは、実は自社収益上の重要事項の一つといえます。
ではこれに関する法律上の取扱いはどうなっているのでしょうか。
債権・債務の規定をしている民法第三編の第四百八十五条は「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」と定めています。
すなわち、販売側・購入側双方で振込手数料に関する取り決めや意思表示がない場合は、購入側が振込手数料を負担することになります。
ただし、販売側の事業所移転等により購入側の振込手数料が増加した場合は、その増加分を販売側が負担することになります。
民法ではこのように振込手数料をこのように規定しているものの、ビジネスの実務では振込手数料は先方負担が商慣習になっているのが現状です。
しかし、この負担が年間100万以上になっている場合は、自社の収益改善を図る上からも双方が信頼関係を壊さない範囲で穏便に交渉し、双方が納得できる妥結を図る必要があるでしょう。
請求書の役割とは?
企業間の商取引において、商品購入側に商品代金の支払いを求める際は、請求書を発行するのが通例です。
請求書とは、商品の販売側が購入側に商品代金の支払いを要請する書類のことです。請求書の役割は、購入側の商品代金の支払い遅延、支払い忘れ、支払い拒否などの「支払いトラブル防止」にあります。
ところが請求書の場合、振込手数料の場合と異なり法律上の規定は何もありません。したがって請求書の書式も法律上の規定はなく、企業ごとにその書式はまちまちです。
一般には請求先の社名と購入窓口部署・担当者名、請求書発行日、商品販売品目、商品販売金額、請求書発行元の社名・部署名などを記載するのがビジネス上の慣行になっています。
ちなみに、国税庁は請求書の記載事項として次のガイドラインを示しています。
1.書類作成者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.税率ごとに区分して合計した税込対価の額
5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
請求書はいつ発行するのか?
請求書を発行する時期は「掛売方式」と「都度方式」に分かれています。
・掛売方式
掛売方式は、商品購入側との売買契約で取り決めた請求締め日に、代金支払いを月単位で一括請求する方式です。請求書発行業務を効率化できるので、取引頻度が高い企業間の商取引では一般的に用いられている方式です。
・都度方式
都度方式は、商品を納品する度に請求書を発行する方式です。同方式は納品と同時に代金回収ができるメリットがある反面、納品の度に請求書を発行しなければならない煩雑さがあります。このため同方式は新規取引先、スポット取引先、入金確認後に商品を納品する取引などにおいて用いられます。
なお、発行した請求書は郵送するのが従来の通例でした。しかし近年は請求書をPDFファイル化して電子メールで送信するケースも増加しています。この場合は請求書PDFファイルの信頼性を保証する意味からも、PDFに電子印鑑を押印しておくのが無難です。
請求書と納品書・領収書・検収書・領収書との違いは何?
請求書発行の目的は、自社が販売した商品の記録と管理にあります。経理的には売掛金の管理に当たります。同時に購入側との間で支払いトラブルが発生した際は、「取引の実態」を証明する書類にもなります。
もしこのトラブルが双方の話し合いで円満解決せず、訴訟に発展した場合は、「取引の実態」を裁判で証明する必要があります。このときに必要になるが請求書のほかに納品書、受領書、検収書、領収書などの書類です。
これらも総務・営業系の社員が日常業務で何気なく取り扱っている書類ですが、その原本やコピーは支払いトラブル防止の観点から注意して取り扱う必要があるでしょう。請求書との基本的な違いは次の通りです。
- 納品書……販売側が納品した商品の内容を記載した書類。納品書を添付した商品を納入することで、購入側は納入された商品の内容と個数をチェックでき、在庫管理の的確性を図れるメリットがある
- 受領書……購入側が商品受け取りを販売側に通知するための書類
- 検収書……購入側が注目通りの商品を受け取ったことを証明する書類
- 領収書……販売側が購入側に商品代金の入金を証明するために発行する書類
これらの書類の中で、検収書は販売側が納品した商品の内容・個数が注文と間違いがない事実を証明した書類なので、請求書と並び取引の実態を証明する信憑性の高い書証(裁判の証拠書類)になります。
まとめ
請求書、納品書、受領書、検収書、領収書などは企業間取引において不可欠な書類です。これらの書類は、取引先との信頼関係を高めるツールにもなっています。このため近年、これらの書類の正確性を担保するため、書類記載事項も増加・煩雑化しています。取引件数や取引先数が多い会社の場合、書類の作成・管理に手間と時間がかかり、人為ミス発生の確率も高まってしまうのです。
これらの問題解決策として販売側は販売管理ツール、購入側は購買管理ツールを導入する企業も増えています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -
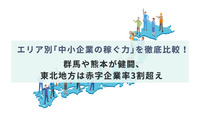
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え
ニュース -

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
ニュース -
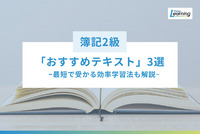
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説
ニュース -

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例
ニュース -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -
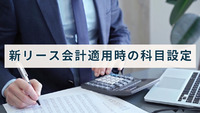
新リース会計適用時の科目設定
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース