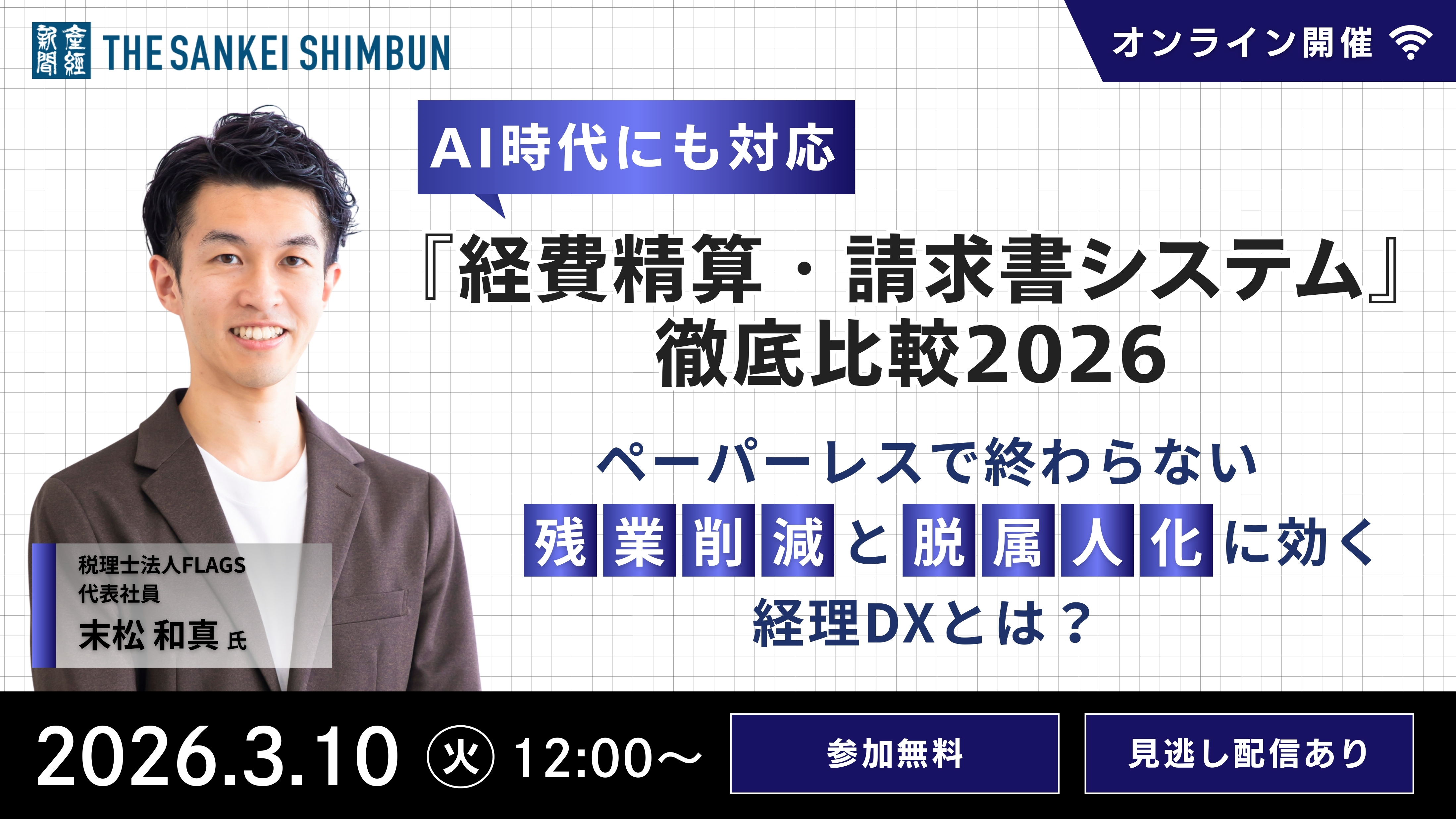公開日 /-create_datetime-/

Q:社員の突発休が増えていて困っています。とくに管理職に多く、下の社員に示しがつきません。
現在弊社の規定では有休申請はシステム上で行い、業務に支障がなければ上長に承認され、希望通りの日程で取得可能です。もちろん取得理由については自由ですのでよほどのことがなければ何事もなく承認されています。
しかし休み明け、とくに連休明けに急に休みを取り、事後申請で有休という申請が多いです。
事前の取得をされていない有休については承認されない、というわけにもいかないため承認はするのですが、企業の組織の在り方としてどうなのか疑問です。とはいえお局の小言でしかないとも思い、有識者の方からの意見を伺いたいです。よろしくお願いいたします。
A:労働者の方が有休取得をすることに関して、使用者が事前の申請期限を設けることには違法性はございません。
これは使用者側が、労働者の有休取得時季を変更できる「時季変更権」を持っており、この時季変更権の行使を判断するために必要な期間を有さなくてはならないからです。
つきましては、申請期限は「時季変更権の行使を判断するため」の合理的な期間でなければなりません。
ただし、この使用者が持つ「時季変更権の行使」には、使用者の側に相当な理由が必要です。
単に「忙しいから」などでは、時季変更権は認められません。
よって、労働者による当日の有休取得申請の、使用者側の拒否には、個別の判断対応が必要となり、一概に拒否することはできません。
有休の取得意思申請の期限を設ける一方、当日の有給申請には条件を設けることで対応をされてみてはいかがでしょうか。
例えば、当日の申請がやむを得ないことが証明できる書類(病院の領収書の写し等や理由書)を提出していただくなどです。
なお、条件をつけるのは、当日・事後の有給取得申請であって、事前の取得申請に対しては、有休の自由利用の原則により、条件をつけてはなりません。
ルールを明確にし、労使ともに気持ちよく、有休を消化できるといいですね。また、有休取得率の向上が叫ばれている今日では、労働者側が有休を取得しやすい風土も必要ですね。
年次有給休暇について
労働基準法(39条1項)は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」としています。
また、労働基準法(39条5項)には、「使用者は、前各号の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。つまり、継続勤務など年休成立の要件を満たしていれば、労働者は保有する年休の範囲内で、具体的に期間を指定すれば、使用者の承認は不要となります。
使用者が拒否できる時季変更権
社会保険労務士の西方克巳先生の回答にあるように、例外的に労働者が請求する時季指定を拒否できるのが時期変更権です。
労働基準法(39条5項但書)に「請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とあります。
では、どのような場合に時季変更ができるのでしょうか。
単に繁忙期だから、人員が不足しているから、といった理由で拒否することは認められません。年休の権利は、憲法(27条2項)で定められている休息権だからです。
つまり、使用者には、年休を全員がすべて消化してもやっていけるだけの人員を配置することが義務付けられているわけです。
ただし、そうした人員配置をしていても、突発的に大量の欠員が生じるような事態が発生した場合は、時季変更権を行使することができます。
ところで“時季”ですが、これは法律用語で“季節の季”です。年次有給休暇の請求は、季節を指定することができるというものです。いずれにしても、労働者に与えられた権利ですから、西方克巳先生の回答にもあるように、ルールを明確にしておくことで、労使双方が納得できる仕組みをつくりあげていくことが大切なようです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド
おすすめ資料 -
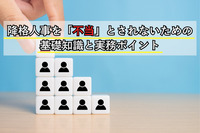
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント
ニュース -

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
ニュース -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査
ニュース -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -
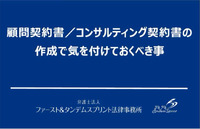
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
ニュース -
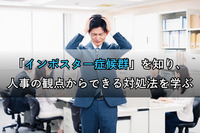
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース