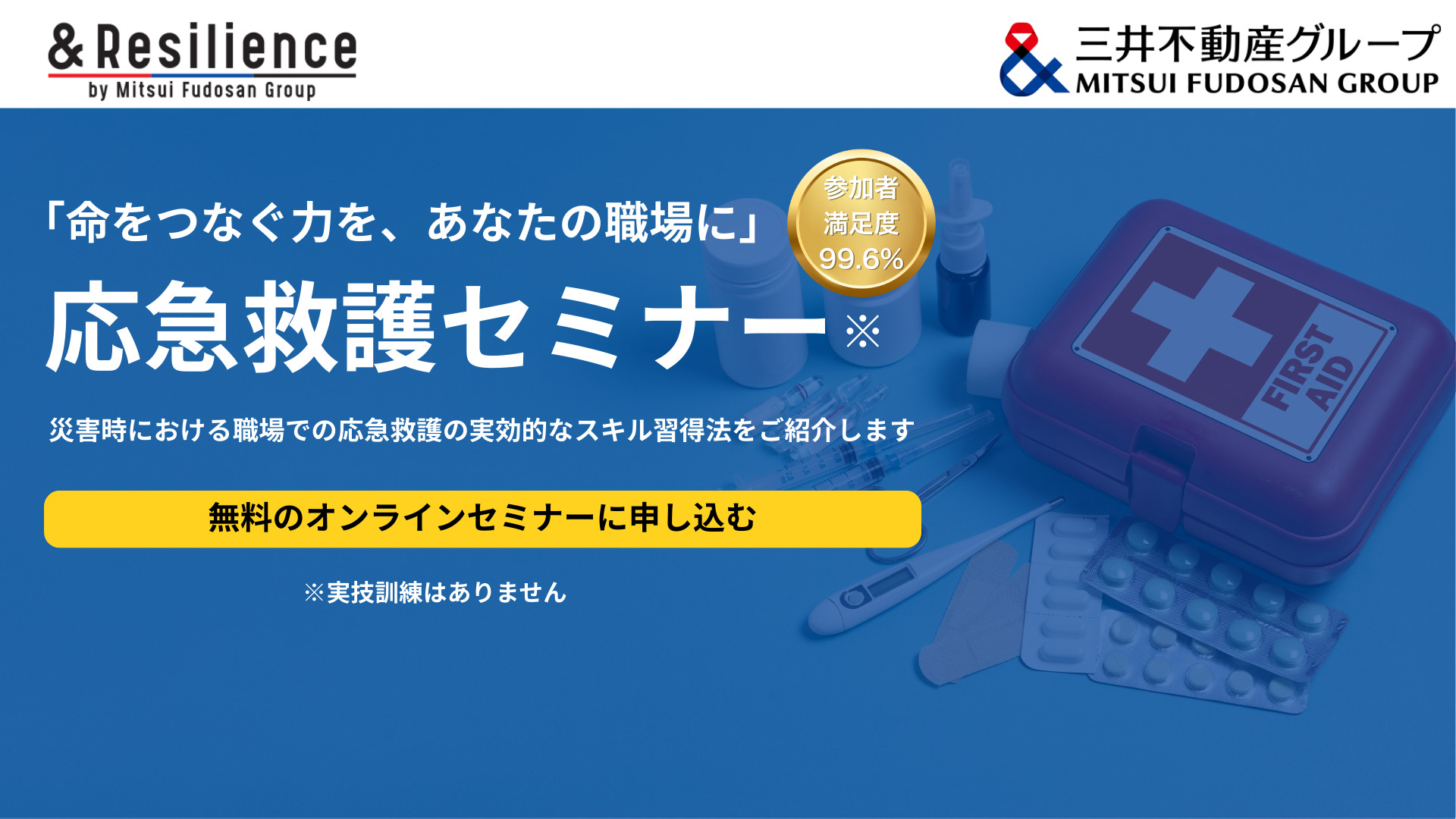公開日 /-create_datetime-/
メンタルヘルスケア「幸せホルモン」を増やそう

「なんだか身体がだるい」「やる気が起きない」「何を見ても心が動かされない」など、コロナ禍で心身の不調を感じている人も多いのではないでしょうか。症状が長引くようなら早めに医療機関を受診すべきですが、ひょっとしたら“幸せホルモン”が不足しているのかもしれません。
喜び・楽しみ・やる気などの幸福感を与える物質
「喜び」や「楽しみ」「やる気」などの幸福感を与える物質を「幸せホルモン」と呼ばれています。
幸せホルモンと呼ばれる代表的な物質は、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンの3種類です。これらには、心と身体が安らぐ作用があり、脳から分泌されると情緒が安定して幸福感を得られるとされています。
幸せホルモンが不足している状態が続くと、うつ病などの精神疾患になることもあります。ストレスが多くかかる社会で、日常生活でも増やせる幸せホルモンをみてみましょう。
「幸せホルモン」の増やし方
精神を安定させる重要な物質の一つに「セロトニン」があります。これは太陽の光を浴びることで分泌されるといわれています。実は、これはホルモンではなく自律神経を整える神経伝達物質です。
増やす方法の一つは日光を浴びることですが、大豆や乳製品を摂取することも効果があるとされています。セロトニンの原料となる必須アミノ酸のトリプトファンという物質は、体内で生成されないため、食べ物からの摂取を心がけましょう。
次に、楽しいことや嬉しいことがあったとき、目標を達成したときなどに分泌されるホルモンの一つが「ドーパミン」です。脳に快感をもたらすことから “快楽物質”または“脳内麻薬”と呼ばれることもあります。
仕事やプライベートで目標を達成していくことで、ドーパミンが分泌されますが、食事によっても増やすことができます。チーズなどの乳製品や、煮豆、豆腐、納豆、枝豆、おから、きな粉などの大豆食品がおすすめです。
そして、“愛情ホルモン“とも呼ばれる「オキシトシン」。心許せる好きな人やペットと一緒にいることで分泌されます。
思いっきり楽しいことをして前向きな思考を取り戻す
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、旅行も飲食も制限されていますから、なかなかストレスを発散することができない状態が続いています。しかし、ストレスは心身不調の要因となりますから、そのまま放置しておくことは危険です。
ストレス解消には、趣味や特技に熱中する、習い事を始める、仕事の目標を作る、朝のジョギングやウォーキングを日課にするなども効果的とされています。
また、ちょっと高級な入浴剤でお風呂に浸かる、お気に入りの紅茶やハーブティーを楽しむ、コーヒーを淹れるのも豆を挽くところから始めるなど、何か夢中になれることで「喜び」「楽しみ」「やる気」を味わってみてはいかがでしょうか。
思いっきり楽しいことをして気分転換することが、前向きな思考を取り戻すことにつながるはずです。
まとめ
精神科医・鹿目将至さんは、著書「1日誰とも話さなくても大丈夫 精神科医がやっている猫みたいに楽に生きる5つのステップ」(双葉社刊)で、心のセルフケアの方法として「自分のひざ小僧を手のひらでくるむように包んで“よしよし”する」ことをあげています。そういえば、子どもがどこかにぶつけて痛いと泣いているとき、母親が患部に手を置きながら「痛いの痛いの、飛んでいけ~」というのも、幸せホルモン効果なのかもしれませんね。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース