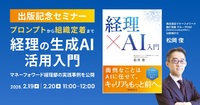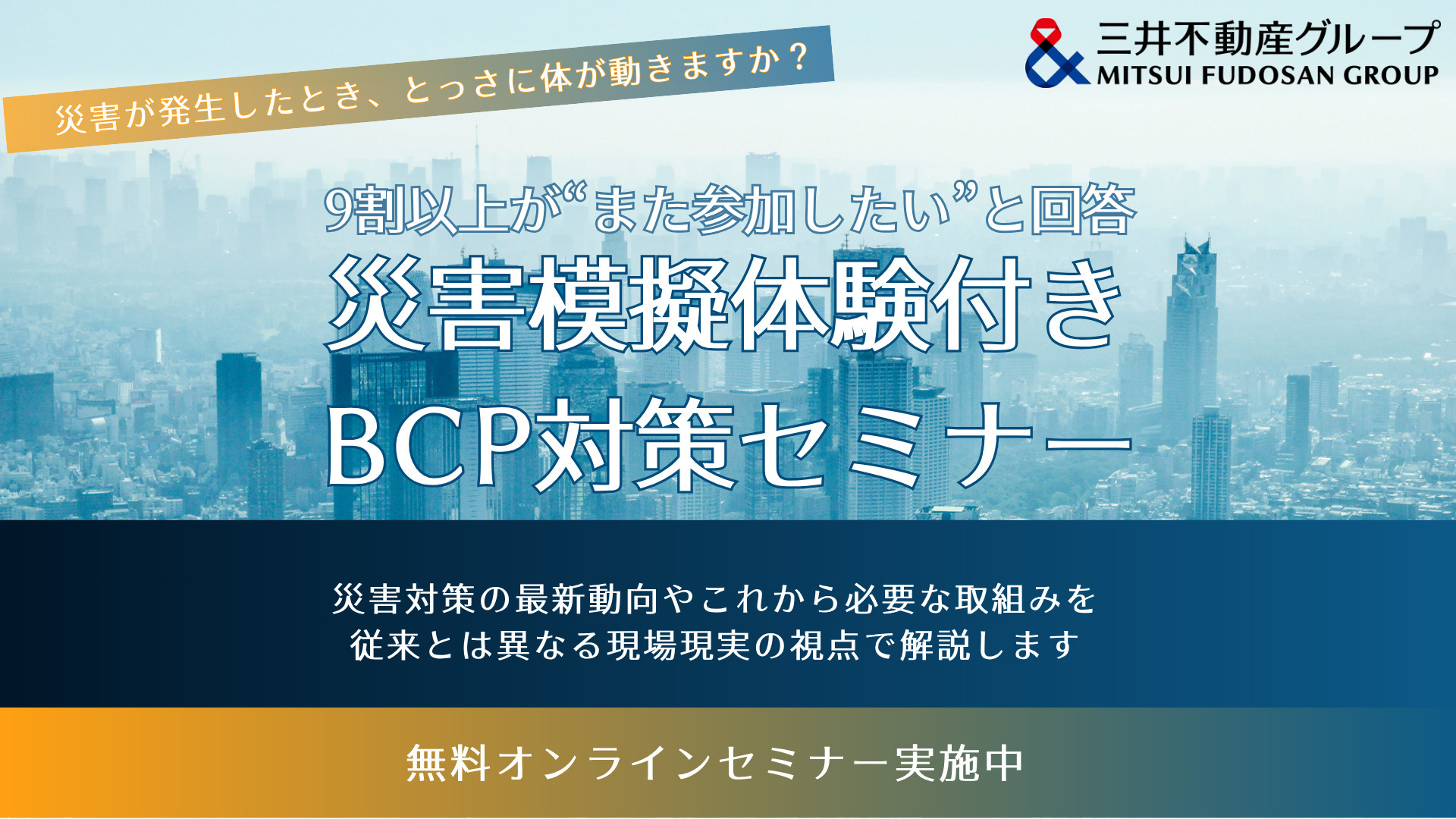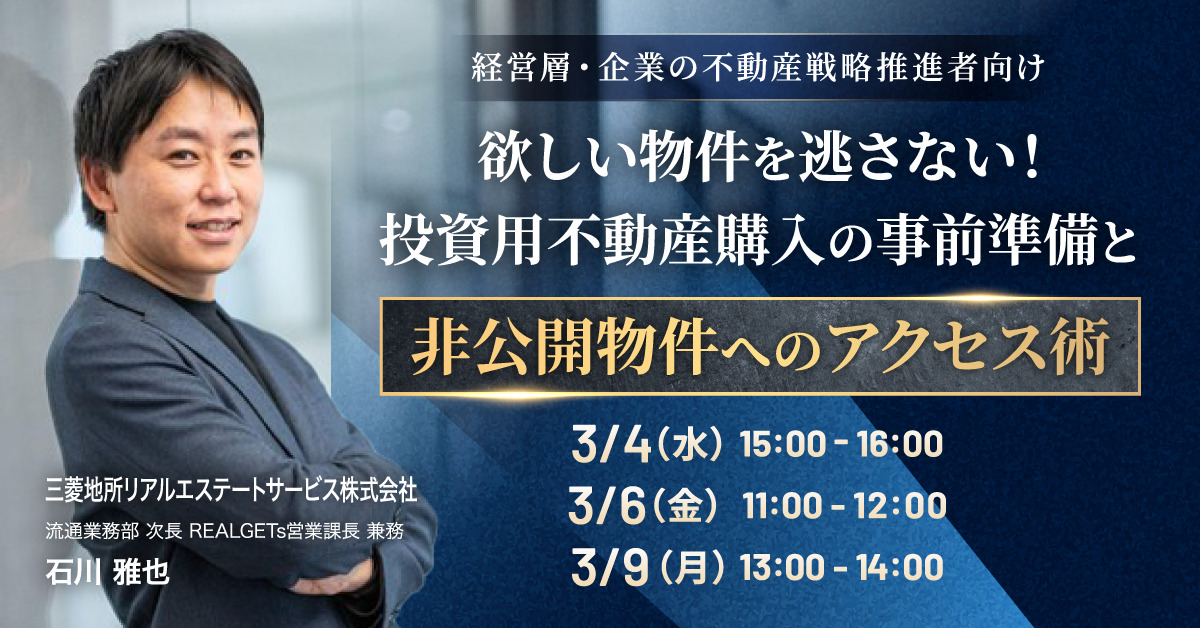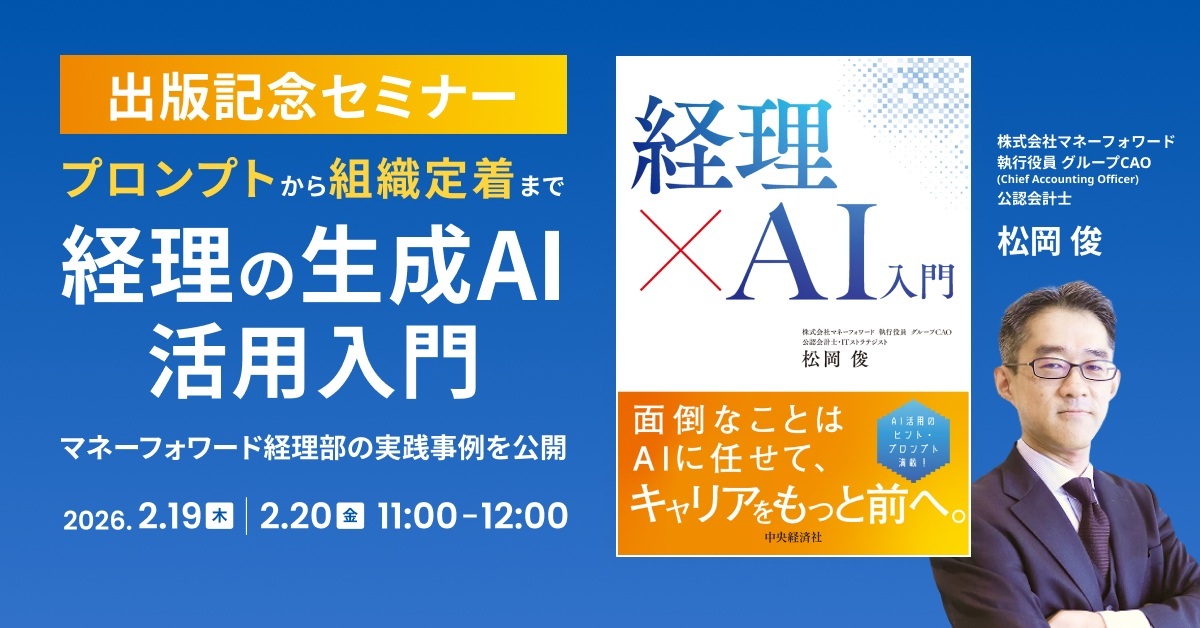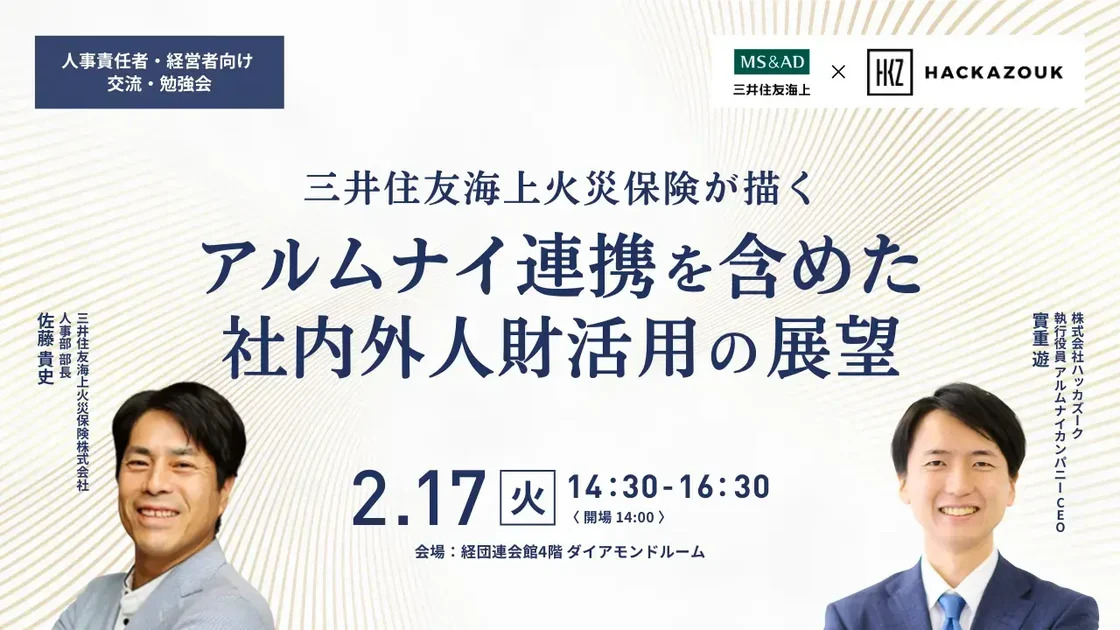公開日 /-create_datetime-/
東京証券取引所の新たな3つの市場区分について詳しく解説

2022年4月に東京証券取引所が3つの市場へと再編成されることをご存じでしょうか。現在の市場数は5つですから、よりコンパクトな市場区分へと移行されるわけです。
そこで今回は、新設される3つの市場のそれぞれの特徴や上場条件、さらに再編が行われた背景について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
東京証券取引所の市場区分が現状の5つから3つに再編
2020年現在、東京証券取引所には「市場一部」「市場二部」「ジャスダック・スタンダード」「ジャスダック・グロース」「マザーズ」の合計5つの市場があります(ジャスダックを1つにまとめて換算して4つの市場と区分されることもありますが、ここでは5つとします)。
この現行の市場区分は、2013年に東京証券取引所と大阪証券取引所が統合された際に作られたもので、双方の市場の構造をそのまま残す形で構成されました。上場していた企業や投資家への影響を最小限に抑えるためです。
しかし、市場構造のあり方があらためて見直された結果、2022年4月に新たに3つの市場へと再編されることが決まりました。「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つです。
プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の特徴と上場条件
この3つの市場区分をわかりやすくいうと、プライム市場がグローバルに事業を展開する大企業向け、スタンダード市場がそれに次ぐ規模の企業向け、グロース市場がベンチャーなど成長中の新興企業向けの市場です。
東京証券取引所は市場間の上下関係はないとしています。しかし、上場する企業の規模という観点からすると、3つの市場はプライムの上、スタンダードの中、グロースの下と「上中下」でイメージすることもできるでしょう。これまでの5つの区分よりも、明快でわかりやすい市場構造になると言えます。
上場の条件は以下の通りです。
・プライム市場・・・市場に流通する株式の比率が全体の35%以上、流通株式時価総額が100億円以上。
・スタンダード市場・・・市場に流通する株式の比率が全体の25%以上、流通株式の時価総額が10億円以上。
・グロース市場・・・市場に流通する株式の比率が全体の25%以上、流通する株式時価総額が5億円以上。
上場条件の内容を見ると、プライム市場とスタンダード市場の間に大きな差があることがわかります。流通する株式の時価総額がスタンダード市場だと10億円なのに対し、プライム市場はその10倍となる100億円です。
実際、東京証券取引所が発表した調査結果によると、東証一部上場企業2,190社のうち、プライム市場の上場条件を満たしていない企業が664社に上ると発表しています。現行の区分では最上位に位置する東証一部市場です。しかし、そこに上場する企業がそのまま横滑りでプライム市場への移行はできないわけです。
ただし、再編後の上場条件には経過措置が設けられ、東証一部上場企業の場合、当面は基準を満たしていなくてもプライム市場に上場できるとしています。
市場区分が3つに再編された理由とは
そもそもなぜこのような市場区分の見直しが行われたのでしょうか。その理由は大きくわけて2つあります。
1つは、現行の5つの市場区分が、投資家にとって利便性が低いという点です。
大企業向けの一部市場はわかりますが、それより規模の小さい企業向けの市場二部、マザーズ、ジャスダックが位置づけとしてやや重複したイメージがあります。ジャスダックはさらにスタンダードとグロースに分かれていて、市場区分のコンセプトがより曖昧になっているとも言えるでしょう。
再編によって形成されるプライム、スタンダード、グロースの区分なら、対象とする企業が明確で、よりスッキリとした市場構造となります。
もう1つは、現状の上場基準では上場後の企業が企業価値を高めようとする動機付けを引き起こしにくいという点です
現在の制度では、新規上場基準よりも上場廃止基準がかなり低いため、企業価値を高めようと努力しなくても上場企業としての地位を続けられます。とくに東証一部に上場することは優良企業としての証明書のようにもなっていて、一部上場後に企業努力を怠って業績が停滞し、売買の成立がしにくいといった流動性に欠けるケースも見受けられました。
一方、再編で設けられるプライム市場は上場条件が厳しいです。スタンダードからプライムに上場するには流通株式時価総額100億円以上、流通株式比率35%以上の基準を満たさねばならず、条件を満たせなくなると「プライム落ち」に直面します。
流通株式市場で評価を確保するには、企業価値を高めるための継続した努力が不可欠です。「プライム落ち」は企業として格下げとなったイメージは否めないので、企業としてはできるだけそのような事態は避けたいところでしょう。
今後「プライム落ち」する企業が続出する?
今回の市場再編におけるポイントの1つが、プライム上場にあたって経過措置が設けられているという点です。
先述の通り、基準を満たさなくても経過措置の間はプライムに上場できます。しかし、経過措置が終わるまでにプライム市場への上場基準を満たさないと、プライム落ちに直面せざるを得ません。
経過措置がなければ、上場基準を満たせる実力のある企業だけがプライム市場に上場するでしょう。しかし経過措置があることにより、実力不相応の企業がプライム市場に取りあえず上場し、経過措置期間が終わるとプライム落ちしてしまう、という事態が起こることも予想できます。
経過措置を利用してプライム市場に上場する場合、事前に時価総額向上に向けた改善策を提示し、その進行具合を定期的に公表することが条件として定められています。しかし当然のことながら、企業活動は予定通り順調にいくとは限りません。業績不振に陥れば、プライム落ちとなるでしょう。
こうしたプライム落ちに直面する企業が生じるのかどうかは、2022年4月以降の株式市場の動向における1つの注目点と言えます。
まとめ
現在5つの市場区分に分かれている東京証券取引所は、2022年4月にプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3区分とされます。この市場再編において注目されている点の1つは、プライム上場の厳しさです。
東証一部企業がそのまま横滑りでプライム市場に移行できるわけではなく、一部市場所属の企業のうち、プライム市場の上場条件を満たしきれない企業が600社以上あります(2021年7月時点)。これら企業がプライム上場を目指すのか、あるいは目指したものの将来的に「プライム落ち」してしまうのか、今後の動向に注目が集まっています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -
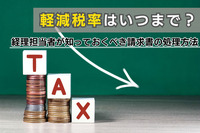
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略
ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット
ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説
ニュース