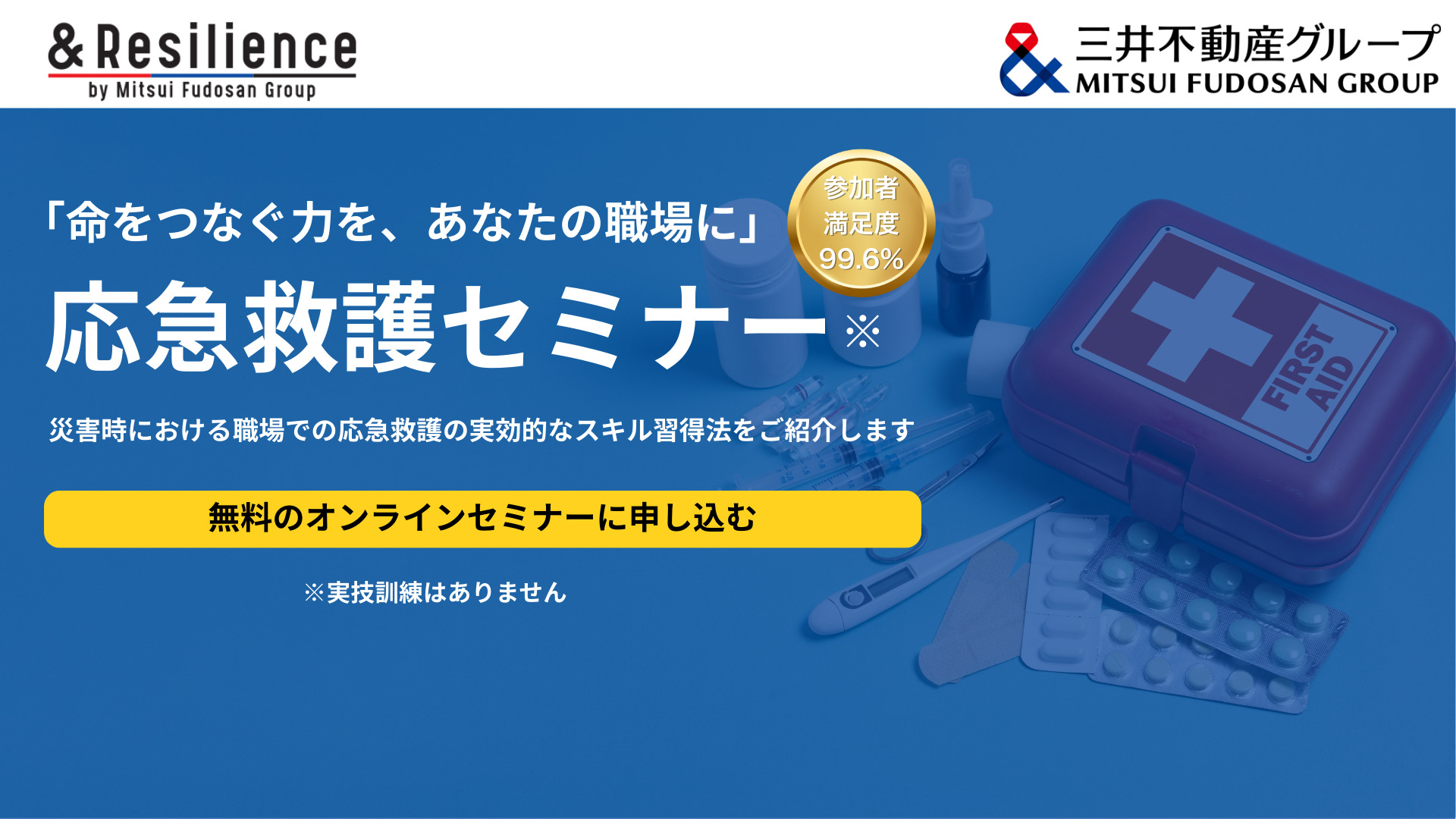公開日 /-create_datetime-/
過労死とは?定義・過労死ライン・前兆など幅広く解説!

過労死は、労働による過度な負担によって、急性心不全などの疾病によって突然死することです。月80時間の残業は「過労死ライン」として定められており、労働災害、いわゆる労災かどうかを判断する一つの基準となっています。
しかし残業が月80時間以上でなくても、労災として認められるケースがあります。2021年9月の改定では「過労死ライン」の基準が見直され、「残業時間がラインに達していない場合でも、身体的な負荷が考慮される」ようになりました。今回は、過労死について幅広く解説します。
目次【本記事の内容】
過労死とは?
過労死は、冒頭でも解説したように、労働での著しい負荷によって突然死をすることです。具体的な定義としては、以下の三つが考えられています。
・業務での過度な負荷によって疾病を発症し、死亡すること
・業務での過度な負荷(心理負荷)によって精神障害を引き起こし、それが原因で自殺すること
・脳血管疾患や心臓疾患、精神障害を発症すること
過労死といえば、「過労で死に至ってしまうこと」とイメージしている方も多いでしょう。しかし過労死等防止対策推進法によれば、脳血管疾患や心臓疾患、精神障害を発症した場合も「過労死等」に含まれます。
過労死はメディアによって取り上げられることも多く、労働者のあり方を考えるひとつのきっかけになっています。また働きすぎによって命を落とすケースは、世界的に見ても珍しく、海外では「Karoshi(過労死)」という単語が定着しているようです。
過労死ラインの定義
過労死を考えるにあたって理解しておきたいのが、過労死ラインです。過労死ラインは、以下の2種類が定義されています。
・健康障害の発症前から2〜6カ月間で平均80時間を超える時間外労働(残業)
・健康障害の発症前から1カ月間で100時間を超える時間外労働(残業)
もし労働が原因で過労死をしてしまった場合、この過労死ラインに合わせて、労災かどうかを判断します。もちろんこれはあくまで目安であって、このラインを超えたからといって、すぐさま過労死のリスクが生じるわけではありません。
では、過労死ラインをギリギリ越えなかった場合は、どのように処理されるのでしょうか。例えば、健康障害の発症前から2〜6カ月間で平均79時間の時間外労働があった場合は、労災として認定されるのでしょうか。
結論からいえば、過労死ラインを超えていない場合は、超えている場合に比べて労災認定される確率が低くなります。ただしすべてのケースで労災にならないわけではありません。
過去の例をみると、過労死ラインに満たなかったものの、労災として認定されたものもあります。これは政府によって打ち出された新しい基準が影響しています。それは、「労働環境を含めて総合的に判断する」ことです。
この例では、死亡した整備士の男性は、空調のない作業場で温水スチーム作業するなど、過酷な労働環境に身を置いていました。過労死ラインには達していませんでしたが、強い身体的な負荷があったとして、労災として認められています。
ケース別で見る過労死の前兆
過労死の前兆としては、様々なものが考えられます。例えば「脳に関する疾病を発症するか」「心臓に関する疾病を発症するか」で、現れてくる症状が異なるため、代表的なケースを整理しておきましょう。
過労死で最も多いとされているのは、脳卒中です。脳卒中の前兆としては、「顔や手足の麻痺」「呂律が回らない」「めまいや立ちくらみがする」などが考えられます。もしも心当たりがある場合は、すぐに病院に行かなければなりません。
また心疾患も、過労死ではよく見られるケースです。心疾患の前兆としては、「上半身の痛み」「吐き気や冷や汗」「奥歯や顎の痛み」「不自然な息切れ」などがあります。こちらも症状が認められたら、一度病院に行くようにしましょう。
また精神障害も、過労死として見られるケースです。こちらは脳卒中や心疾患とは異なり、直接死につながるわけではありませんが、「精神障害が原因で自殺してしまう例」はよく見られます。
精神疾患、つまり鬱病などの前兆としては、「睡眠障害」「理由もなくイライラしたり涙が出たりする」「何をやっても楽しくない」「集中力がまったく続かない」などがあります。
精神疾患は、過労死につながらなかったとしても、その後の人生に大きな影響を及ぼします。少しでも無理を感じたら、すぐに病院に行くのが重要です。直接過労死につながらないからといって、甘く見てはいけません。
まとめ
過労死を未然に防ぐためには、当たり前の話ではありますが、「長時間労働をしない・させない」ことです。まだ健康被害が出ていないとしても、いつ疾病を発症してしまうかは分かりません。労働時間を短くして、肉体的負担・心理的負担を軽減しておくのが、何よりも重要でしょう。
日本はサービスの質や、ホスピタリティの高さで知られていますが、その裏には過酷な労働の姿もあります。すべての企業が一丸となって、労働環境における正しい姿を、もう一度考え直してみる必要があるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -
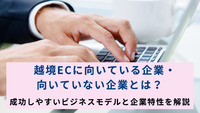
越境ECに向いている企業・向いていない企業とは? 成功しやすいビジネスモデルと企業特性を解説
ニュース -
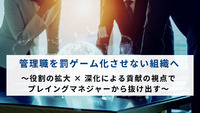
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -
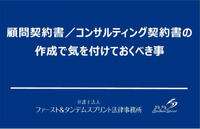
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -
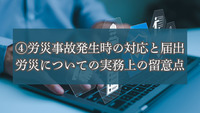
④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点
ニュース -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -
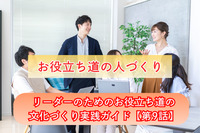
お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】
ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
ニュース