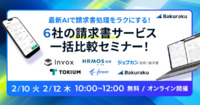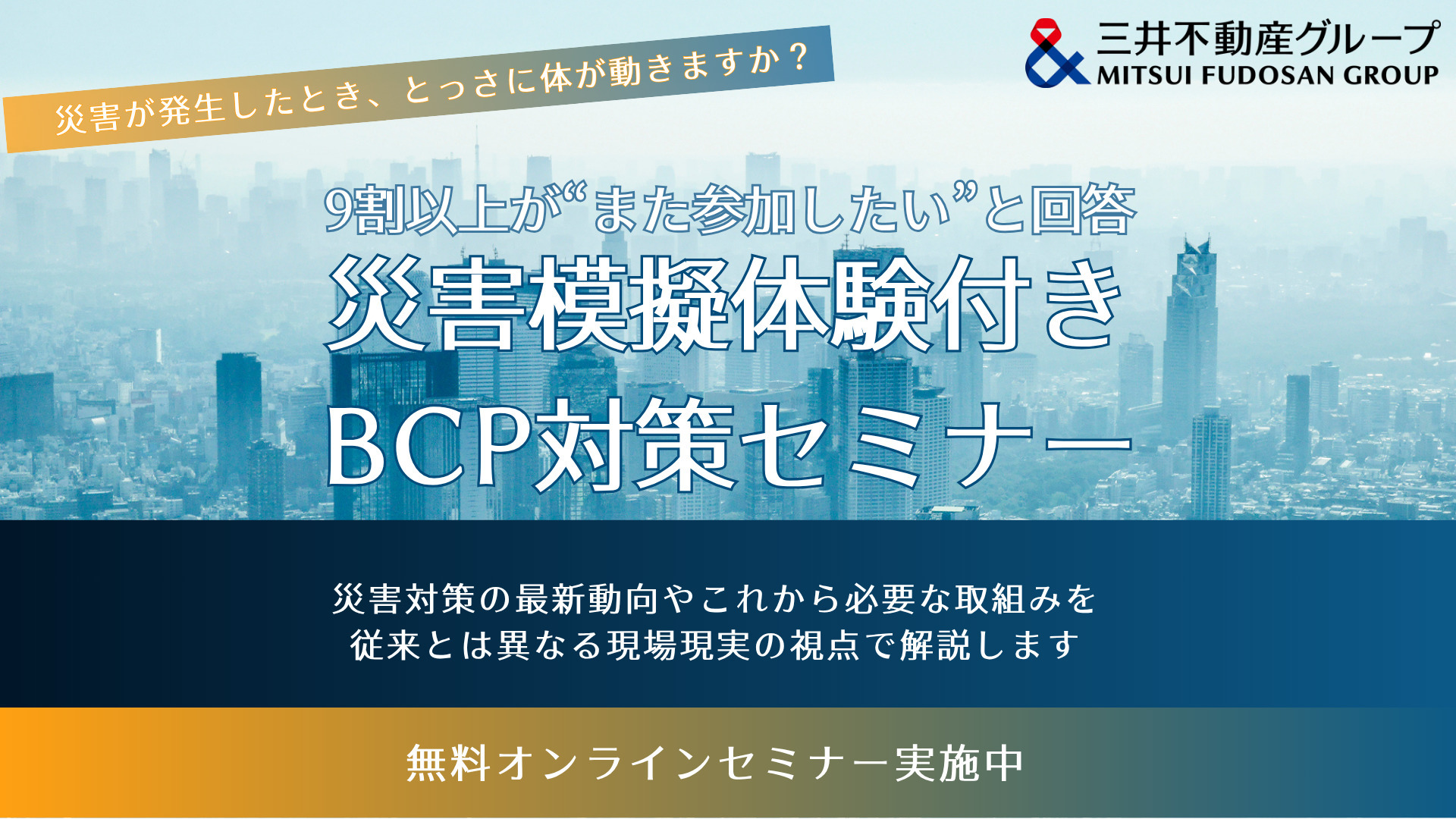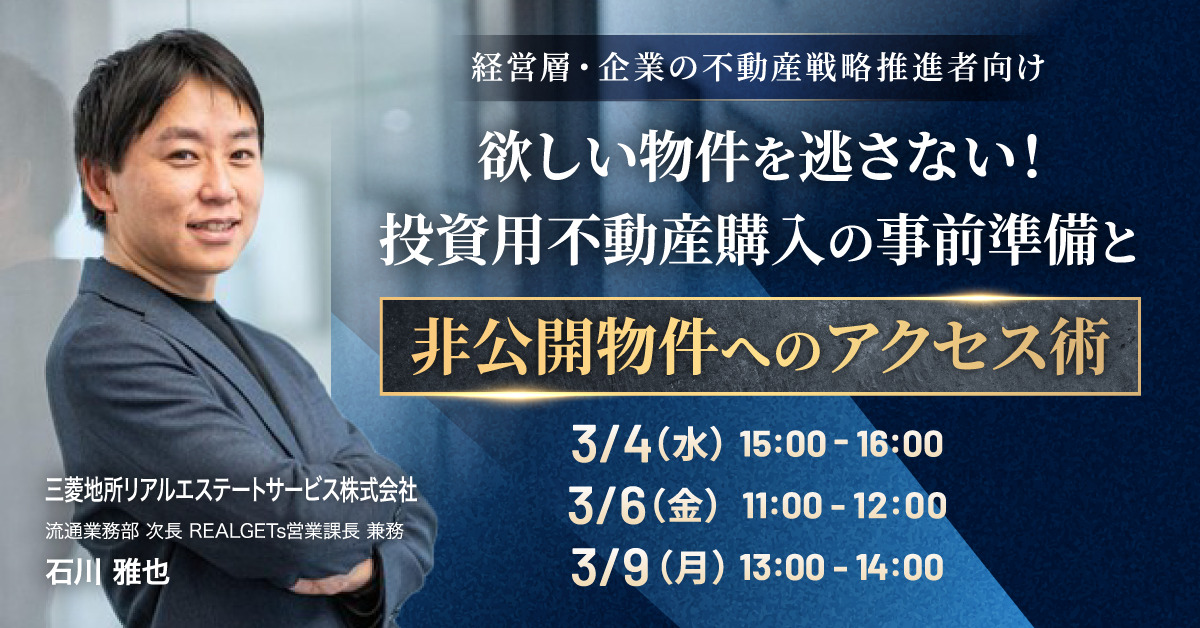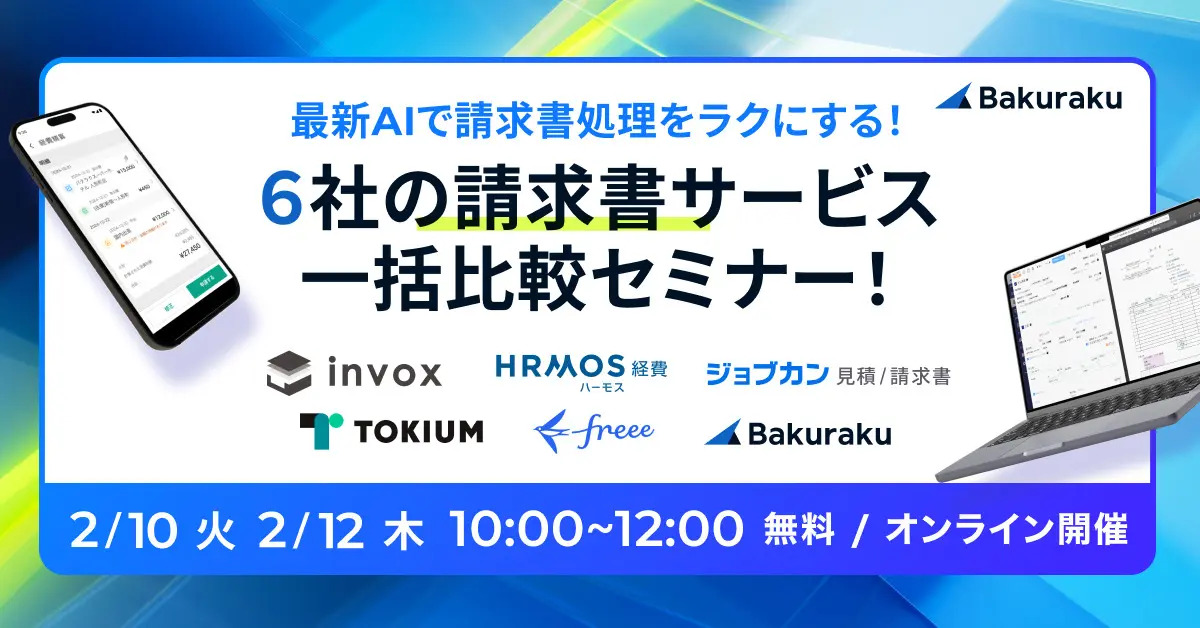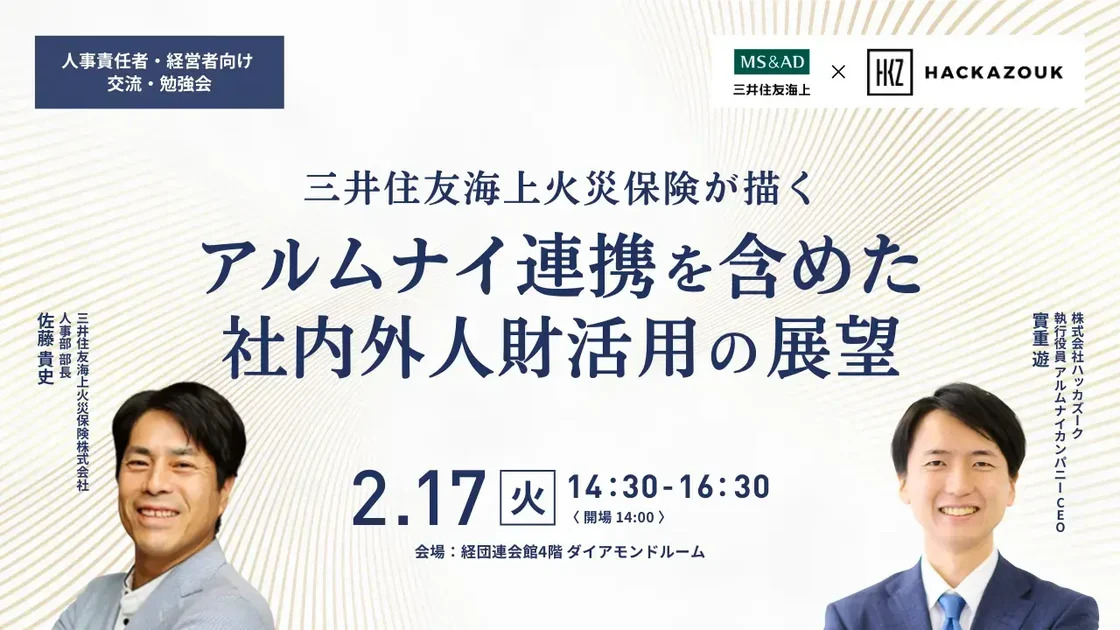公開日 /-create_datetime-/
女性が働く上で直面する問題とその対策について

先日、民間企業が、20~30代の働く女性500名に対して、問題視している社会課題(貧困・虐待・育児ノイローゼ・いじめなど)があるかを問うアンケート調査を行ったところ、6割以上が「ある」と回答しました。
就労者を男性・女性と区分した場合、女性だけが直面する課題が多く存在するのが日本社会の現状といえます。
今回は、働く女性が直面する問題・悩みの現状・実態について考えてみましょう。
働く女性が直面する問題とは
厚生労働省が毎年作成している白書・『令和元年版働く女性の実情』によると、2018年度に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に寄せられた、男女雇用機会均等法に関わる相談件数は1万9,997件に上っています。男女雇用機会均等法とは雇用の分野において男女の均等な機会および待遇の確保に関する法律で、この法律に関連する相談とは事実上、職場における女性に対する差別的扱いに対する相談とイコールです。
その相談内容の内訳は、最多だったのが「セクシュアルハラスメント」の35.4%で、以下「婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益取り扱い」(23.1%)、「母性健康管理」(14.0%)、「妊娠、出産等に関するハラスメント」(13.1%)、「その他(ポジティブアクション等)」(7.8%)、「性差別(募集・採用、配置・昇進、教育訓練、間接差別等)」(6.6%)と続いています。
「母性健康管理」とは、妊娠中や出産後に健康診査を行えるように時間を確保すること、および妊娠中の症状への対応措置を行うことで、男女雇用機会均等法において事業主に義務付けられています。この点の相談が1割強あるので、きちんと措置を行っていない・対応が不十分な事業主が一定数いると考えられます。
なお、この法律に違反している企業に対しては行政から是正指導が行われますが、それに応じない場合は企業名公表の対象とされます。
「その他」に含まれるポジティブアクションとは、男女間の固定的な役割分担を排除し、能力のある女性が活躍できるように企業が自主的に行うべき取り組みのことです。たとえば、かつては職場における「お茶くみ」は女性就労者の役割と考えられていましたが、この慣行を無くすことはポジティブアクションの一例といえます。
しかし、ポジティブアクション等に関する相談が7.8%含まれるということは、こうした差別に悩む女性就労者がまだまだ多いのが実情です。
企業側が取るべきハラスメント対策
セクハラや妊娠、出産等に関するハラスメント行為への対策としては、就業規則・労働協約において方針を明確化し、さらに研修などを通しての啓もう活動を行うことが基本です。ちょっとした言動や態度もハラスメントに該当するため、社員の意識変革を行うことが必須事項といえます。
また、女性が相談しやすい相談窓口の設置、問題が発生したときの苦情処理機関を設置することも重要です。なお、窓口・機関を設置して相談件数が0件であっても、そのことは社内にハラスメントが無いことを意味しません。むしろ、「相談しにくい」「相談すると内容が漏れて社内で噂される」との印象が持たれるなど、窓口・機関としての信頼性が失われている可能性が考えられます。
さらに、ハラスメント行為による問題が生じたときの対応策を事前に決めておくこと、もし発生した場合は再発防止策を早期に打ち出すことも大事です。
結婚・出産・育児に伴う働く女性の不利益を解消するには
結婚・出産・育児の不利益に関しては、企業によっては出産・育児が必要な場合は勤務形態を選択できる制度や、コアタイムを指定しての短時間勤務制度など取り組みを行っています。女性が働きやすい制度設計を行うことが、企業側には求められています。
ただ、企業ごとに研修等を通しての意識改革や制度改革をすることも大事ですが、育児休業制度を父親・男性も取得しやすくする雰囲気を社会全体で作っていくことも重要です。
厚生労働省の『令和元年度雇用均等基本調査』では全国の事業所3,460を対象に調査が行われていますが、それによると育児休業の取得率は女性が83.0%であるのに対し、男性は7.48%に過ぎません。3年前の平成28年度の調査では3.16%でしたから、ここ数年で急増してはいるものの、まだまだ少ないのが現状です。
育児休業制度に関しては、2022年10月から男性版産休制度がスタートします。これは子どもが誕生してから8週間以内に、最大4週間まで父親が産休を取得できるという制度。休みは2回に分けて取得できます。
すでに現行制度として、出産後8週間以内に父親が育児休業を取っていた場合、8週間以降に特別な事情がなくても再度育児休業を取得できる「パパ休暇制度」があります。また、両親ともに育児休業を取得する場合は1歳2か月まで休業取得可能期間が延長する「パパ・ママ育休プラス制度」(片方の親だけ育児休業する場合は1歳まで)も利用可能です。
ただ、いくら制度があっても、各企業の中で「男性社員が育児休業できる雰囲気」がなければ、取得しようとする人は増えないでしょう。日本企業に男性が育児休業しやすい組織文化が定着していけば、出産・育児によって女性に多大な不利益をこうむる状況を減らせます。
女性管理職・役員の登用
女性の就労者が雇用や昇進において男性よりも不利益が生じやすい点については、企業として女性管理職・役員を積極的に採用することが対策の一つとして挙げられます。女性管理職の存在は女性でも正当に能力が評価されることのモデルケースとなり、その増加は組織文化を変革するきっかけにもなり得ます。
まとめ
2016年4月に女性活躍推進法が施行されました。この法律では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業では「自社の女性の活躍に関する状況を把握して課題を分析する」「把握・分析の結果を踏まえた行動計画を策定して社内に周知し、公表すること」「都道府県労働局へ届け出ること」「女性の活躍に関する情報を公表すること」が義務付けられています(労働者数100人以下の企業は努力義務)。
企業において女性が活躍できるよう配慮することへの気運は、日本社会全体で高まりつつあります。女性が働く上で直面する問題・課題を解消していくことは、企業が当たり前のこととして取り組むべき事項になりつつあるわけです。
参照元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/19-02.pdf
女性活躍など、多様な働き方を実現したいと考えている方におすすめ
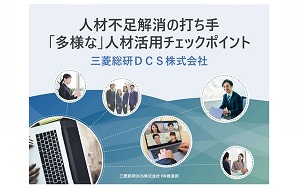
人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント
必要人員の確保と限られたリソースでどのように業務遂行するかは、政府も提唱する人材不足解消の手立てとなっています。
本資料では、ダイバーシティ領域(グローバル人材、シニア人材、女性の活躍、時短勤務の活用など)における人材活用と生産性の向上の2軸に分けて、人材不足解消のための手立てについて解説をしています。
詳細・ダウンロードはこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
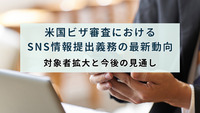
米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し
ニュース -

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -
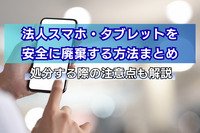
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
ニュース -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由
ニュース -

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表
ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース