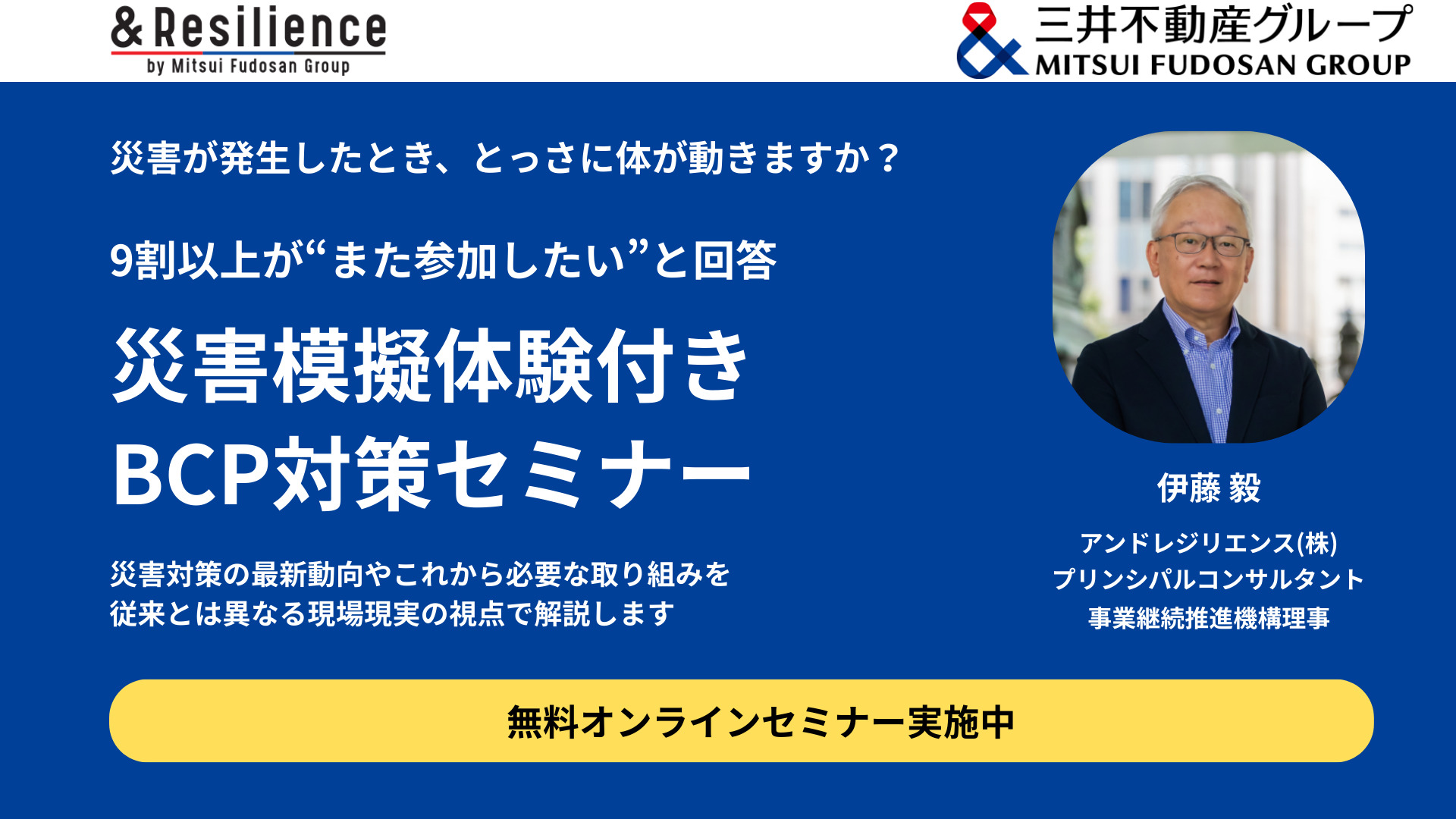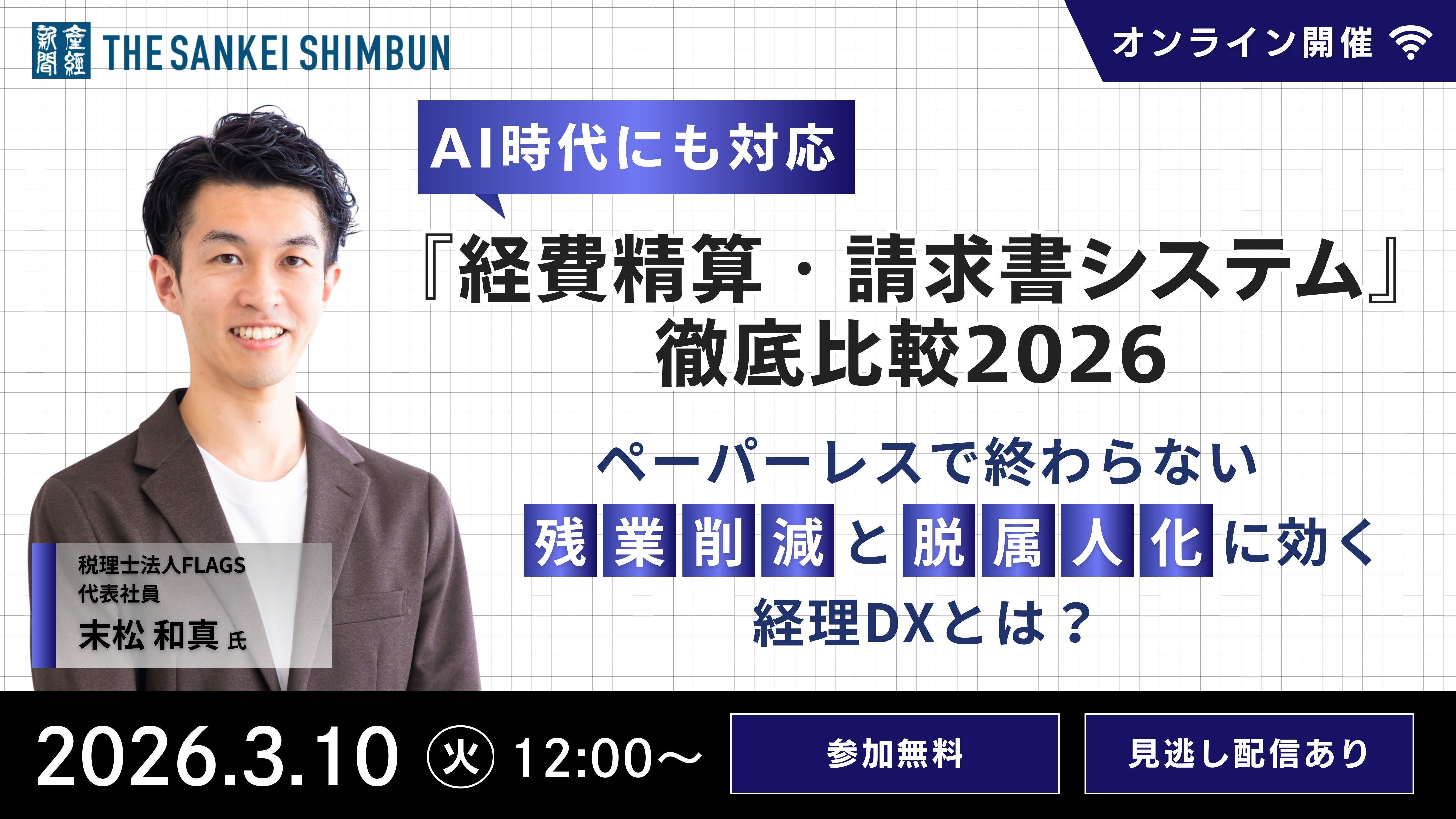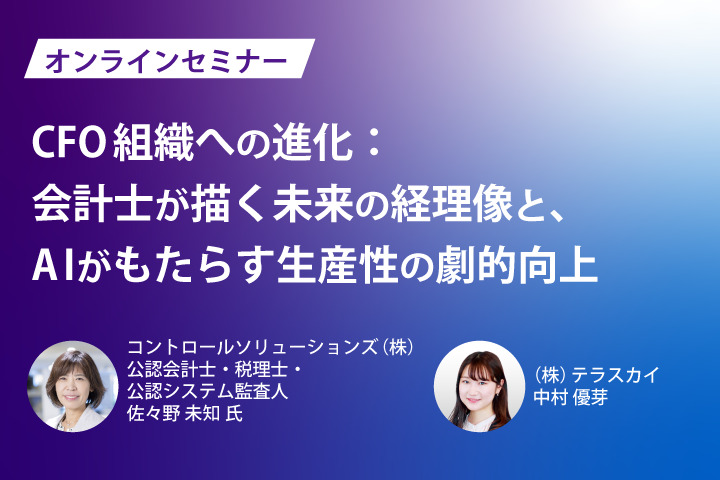公開日 /-create_datetime-/

プロダクトガバナンスは比較的聞き馴染みのある言葉ですが、金融業界ではあまり認識が共有されていません。金融庁が金融機関に対して適切な対応を求めているものの、「詳しい意味はよく分からない」という方も多いでしょう。
資産運用会社だけでなく、証券会社や銀行など、プロダクトガバナンスの強化が求められている組織も増えています。そこで今回の記事では、プロダクトガバナンスの概要について解説します。
目次【本記事の内容】
プロダクトガバナンスとは
プロダクトガバナンスは、金融庁が発表している資料「資産運用業高度化プログレスレポート」によって注目されるようになりました。レポート内では「商品組成・提供・管理(プロダクトガバナンス)」と記されています。
金融庁の資料の内容をまとめてみると、プロダクトガバナンスとは、「自社が提供しているプロダクト(金融商品)の運用の状態を確認・検証すること」といえます。つまり金融業者に向けて、商品の品質管理を徹底せよと呼びかけているわけです。
プロダクトガバナンスを理解しやすくするために、金融業界の基本的な構造を確認しましょう。まず金融商品を作るのは、「資産運用会社」です。ここで作られた投資信託が、証券会社や銀行などの「販売会社」を通して販売され、投資家からお金を集めることになります。
投資家から資金が集まった場合、それを保管しておくための銀行が必要です。まとめられたお金は、投資信託などの資産管理をする「信託銀行」で保管されます。「資産運用会社」「販売会社」「信託銀行」の三つが中心となって、資産運用に関するサービスが行われています。
シャープレシオの重要性
金融庁の資料のプロダクトガバナンスに関する項目で、最初に触れられているのが「シャープレシオ」です。シャープレシオとは、リスク1単位あたりの超過リターンを表す指標であり、要するに「効率良く収益が得られるかどうか」を測るためのものです。
公募アクティブファンドのシャープレシオを比較してみると、「ファンド数が少なく、旗艦ファンドに注力している会社」の方が、全体的に高いパフォーマンスを発揮している傾向がみられます。
一方で、資産運用会社の中には、100本以上のファンドを抱えているところもあります。効率良く運用が行われているファンドもありますが、シャープレシオがマイナスになってしまうファンドも多くみられるという結果になりました。
アルファの違い
金融庁は、「大手資産運用会社の商品ラインナップに、アルファがマイナスになっているとみられるファンドが存在している」と発表しています。アルファとは、期待収益率と予想収益率の差であり、超過リターンを指す言葉です。
投資家は一般的に、市場平均よりも高いリターンを得ることを期待して、投資をします。アルファがプラスになっていれば、超過リターンが得られ、逆にマイナスになっていれば市場平均よりも低いリターンとなります。
つまり、アルファがマイナスになっているのは、投資家の「市場平均よりも高いリターンが得られる」といった期待に応えられていないということです。大手資産運用会社の商品には、そうしたファンドが多くみられ、金融庁が警鐘を鳴らしています。つまり、「商品を使った後の品質管理を徹底せよ」ということです。
ちなみにアルファの推計値が高かったのは、中小型株の運用を中心としているタイプでした。これは、投資対象先の調査や銘柄選定など、運用担当者のパフォーマンスによって付加価値を付けやすいためです。
適切なコスト設定
金融庁は、金融商品に対して適切なコストを設定せよと発表しています。例えば、コスト控除前のリターンが市場平均を上回っていたとしても、その成果がコストに相殺されているパターンもあります。そうなれば、結果的に付加価値を出せないことになるでしょう。
特に信託報酬が横並びに設定されている場合、商品によっては「信託報酬の取りすぎ」が発生します。一律に信託報酬を取るのではなく、個別ファンドの商品性に応じた信託報酬水準を設定するのが望ましいとされています。さらに設定後のパフォーマンスを分析し、それに応じた信託報酬水準を決めることも重要です。
投資家側の視点で考えてみると、効率良くパフォーマンスを発揮するファンドを選ぶ際は、上記の項目で考えてみるのも良いでしょう。「大手だから信用できる」といった考えではなく、シャープレシオや信託報酬水準などの項目で、正しくスクリーニングする技術が重要です。
まとめ
金融庁が資料で伝えたいことをまとめてみると、「運用状況を分析・改善せよ」「金融商品に応じた適正なコスト水準を設定せよ」の2点です。資料ではこの二つに加えて、実効性のあるプロダクトガバナンス体制の確立や、顧客利益最優先の商品組成・償還についても触れられています。
重要なのは、中長期の視点で顧客利益を考えることです。現在、効率良くパフォーマンスを発揮しているとしても、それが10年後や20年後も続いているとは限りません。常にパフォーマンスをチェックし、顧客に付加価値を与えられるような取り組みが必要になってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -
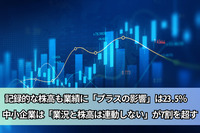
記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す
ニュース -

契約書の条ずれを発見したらどうする? 正しい修正方法と注意点を解説
ニュース -
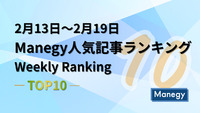
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
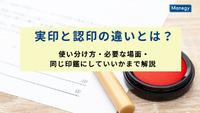
実印と認印の違いとは?使い分け方・必要な場面・同じ印鑑にしていいかまで解説
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド
おすすめ資料 -
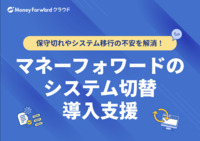
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

契約書のコンプライアンスチェックとは? 独禁法・2026年施行「取適法」・反社条項の論点とAI活用
ニュース -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に
ニュース -

海外拠点を持つグローバル企業の法務課題を解決するシステム導入とは?
ニュース -

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に
ニュース -
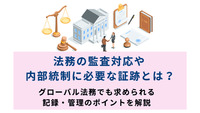
法務の監査対応や内部統制に必要な証跡とは? グローバル法務でも求められる記録・管理のポイントを解説
ニュース