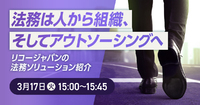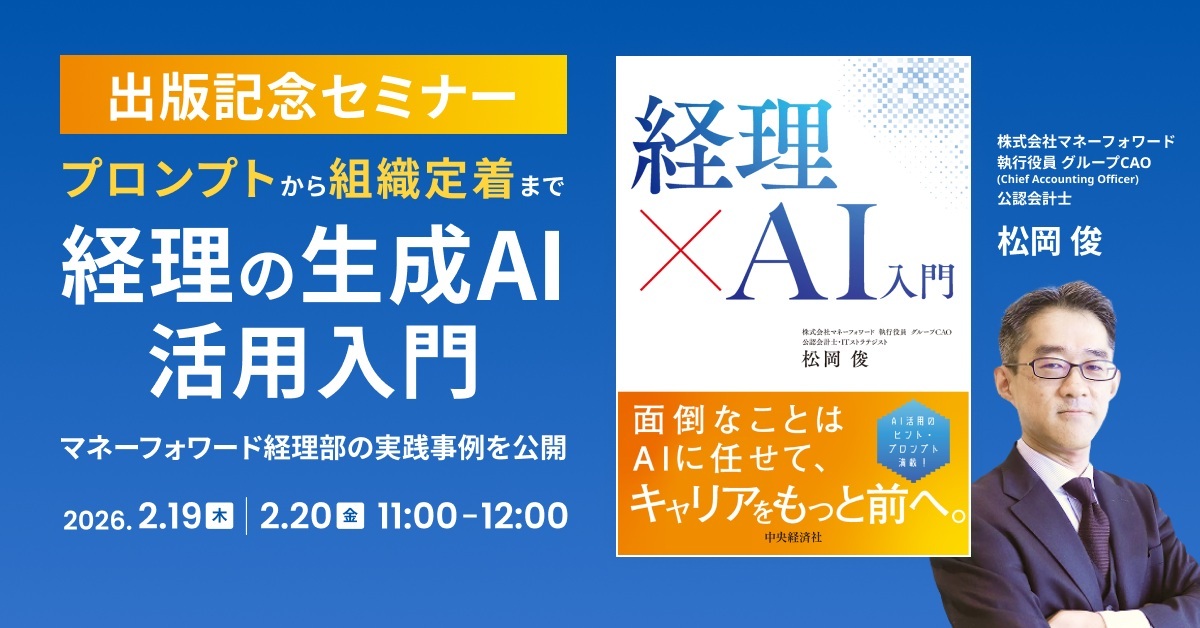公開日 /-create_datetime-/

過労による体調不良の改善やワークライフバランス重視などの観点から働き方改革が叫ばれて久しくなりました。2024年4月からは物流業界にもその影響がおよびそうです。法律の適用で労働環境の改善が期待される一方、さまざまな負の側面も懸念されています。
本記事では物流の「2024年問題」について解説します。
2024年問題とは?
働き方改革関連法によって、2024年4月1日から「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制」などが適用されることで起こる種々の問題を総称して「2024年問題」と呼びます。
長距離トラックドライバーの時間外労働時間の上限について具体的には、年間960時間へと規制されます。これによって1日に運べる物量や1日当たりの移動距離が減少するため、ドライバーの収入、運送会社の利益、消費者の負担する送料など、さまざまな面で問題が発生すると考えられているのです。
働き方改革関連法が制定された背景
2024年問題の原因となっている働き方改革関連法は正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。新たな法律が制定されたわけではく、これまでの労働関係の法律にいくつかの規制が加わりました。
なぜ働き方改革関連法が成立したのでしょうか?
その目的は「労働者が個人個人の状況に合わせて働き方を柔軟に選べる社会を実現するため」です。
日本では少子高齢化や長時間労働の規制の影響を受け、生産年齢人口の確保や生産効率の向上、女性や高齢者が働きやすい環境整備などが急務とされています。これらを背景に2019年から働き方改革関連法が段階的に施行され、ついに2024年には物流業界も対象となる予定です。
働き方改革関連法の主なポイント
法改正の内容は多岐にわたりますが、ポイントなる改正点は以下の3つです。
ポイント① 時間外労働時間の上限規制
主な改正点としてまず挙げられるのが先ほども紹介した「時間外労働時間の上限規制」です。時間外労働が年960時間に規制されますが、2022年1月に全日本トラック協会が行った調査ではドライバーの27.1%がこの上限を超えていました(※1)。
「厳しい時間指定への対応」「積み込みや荷卸しの負担」「配送効率の最適化不足」など、ドライバーの労働時間が長くなる原因は多くあります。これらを解決しなければ、上限時間の厳守は難しいでしょう。
違反した場合は6カ⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が罰則として科される可能性があるため、運送業界の経営者およびドライバーは注意が必要です。
※1)全日本トラック協会「第4回働き方改革モニタリング調査」より
ポイント② 同一労働同一賃金
同一企業において雇用形態による待遇差を解消するため、同一労働同一賃金を実現する法律が適用されます。物流業界の中には人件費削減などため、非正規でドライバーを雇っている企業も少なくないでしょう。
同一労働同一賃金はこれまで大企業を対象に適用されていましたが、2024年4月からは中小企業もその対象となります。給与体系や評価基準を見直さなければならない物流業界の企業も存在するでしょう。企業としては人件費を捻出した上で利益を確保する施策が求められます。
ポイント③ 月60時間超の時間外労働の割増賃金引き上げ
2023年3月現在、月60時間を超える時間外労働に対して中小企業では25%以上、大企業では50%以上の割増賃金の支払い義務があります。
しかし、2023年4月からは中小企業においても50%以上の割増が適用されるようになります。またドライバーは業務の性質上、深夜に運転をすることもありますが、その際には別途25%以上の深夜労働の割増賃金を支払わなければなりません。
先駆けて変更される内容ですが合わせて対応を検討する企業も多いのではないでしょうか?中小企業において、割増賃金による人件費の増加が経営に与える影響は決して少なくないでしょう。
2024問題が物流業界へおよぼす影響
これまで物流における2024年問題の詳細や背景について解説しました。続いて、働き方改革関連法の適用によって物流業界および消費者が受ける影響について、詳しく説明します。
ドライバーの収入減少
現在のドライバーの中には長時間の時間外労働による残業代や割増賃金によって、収入を増やしている人もいることでしょう。そのようなドライバーにとって、時間外労働時間の上限規制はそのまま収入の減少に直結します。
また企業によっては雇用形態における待遇差解消のため、現在の給与体系を変更する必要があります。新しい給与体系によって収入が減少する事例もないとは言い切れません。
給料のカットは業務効率の低下や離職につながるため、ドライバーの収入確保は企業にとって急務となります。
ドライバー不足の懸念
時間外労働時間の上限が減少するということは、一人当たりが運べる荷物の量や距離も減るということです。その中で従来と同じ物流環境を用意しようと思えば、必然的にこれまでよりも多くのドライバーが必要になります。
ドライバー不足は企業の業績悪化とそれによる離職へと発展し、負のスパイラルが続きかねません。女性や高齢者なども含め、誰もが働きやすい職場を用意することが2024年問題を解決するカギとなるでしょう。
送料の値上げ
2024年4月以降も物流関連の企業が利益を確保するための手段として、送料の値上げが考えられます。送料が上がれば消費者の直接的な負担はもちろん、商品の製造コスト増加による物価上昇など、間接的負担も増加するでしょう。
物流は経済やインフラを支える基盤であるため、2024年問題はすべての人に影響を与えるといっても過言ではありません。
まとめ
物流の2024年問題とは、働き方改革関連法の適用によって2024年4月以降に起こる諸問題の総称です。
・トラックドライバーの時間外労働時間の上限規制
・雇用形態による待遇差の解消
・時間外労働に対しての割増賃金の下限引き上げ
などの改定により、ドライバーの収入や企業の利益が減少するリスクも懸念されているため、2024年までの対策が急務となっています。
また、物流業界の停滞はさまざまな形で私たちの生活にも影響を与えるため、物流の2024年問題は社会全体で解決していく必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
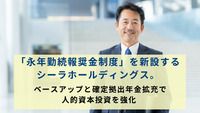
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
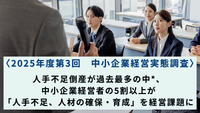
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
ニュース -
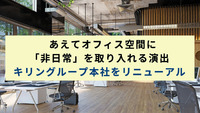
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド
ニュース -

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ
ニュース