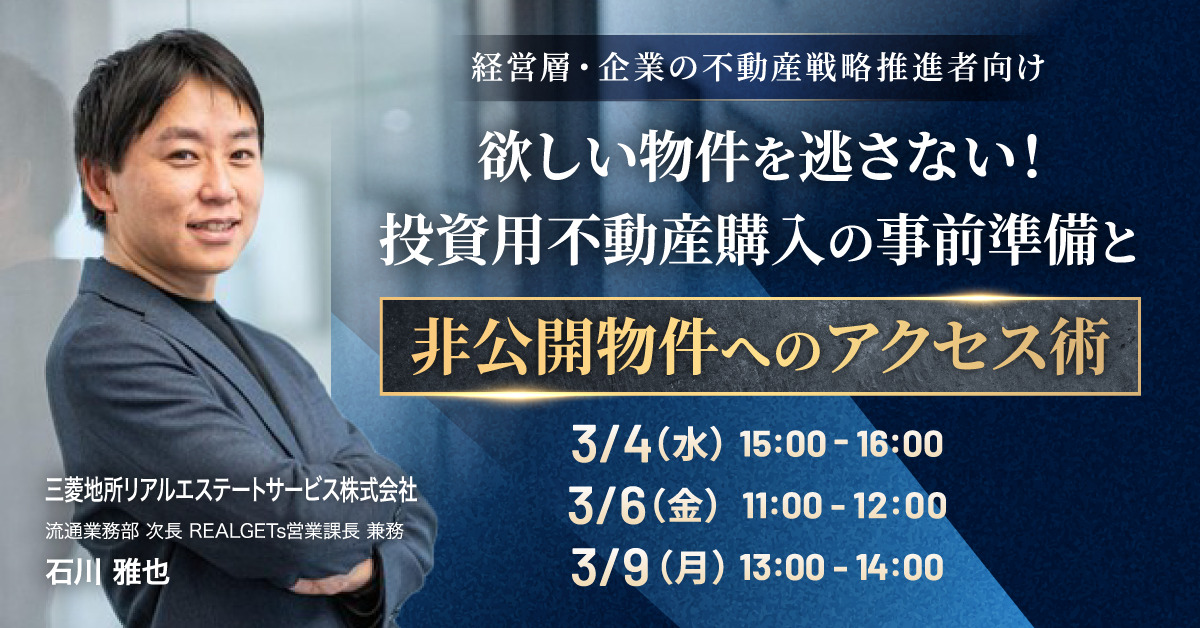公開日 /-create_datetime-/
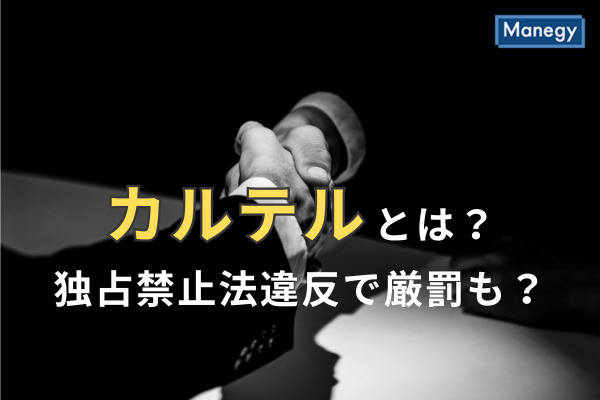
事業者が公正な取引を継続するため、日本国内では独占禁止法により「私的独占の禁止」と「公正取引の確保」が保障されています。カルテルとは独占禁止法に抵触する行為であり、不当な取引制限として禁止されています。
ニュースになるのは大手企業のカルテルがほとんどですが、カルテルは企業規模を問わず、あらゆる業界に関わるものです。企業を経営する上では、カルテルについても理解しておく必要があります。この記事では、カルテルの概要からリスク回避の方法まで解説します。
独占禁止法とカルテル
独占禁止法の目的は公正かつ自由な競争を促進することで、内閣府の外局である公正取引委員会が監督・運営を行っています。独占禁止法に違反した場合、対象の事業者には「排除措置命令」が出され、ペナルティーが科されます。
カルテルとは、独占禁止法で厳しく規制される行為の一つです。複数の事業者間で、契約や協定により価格や数量を取り決める「不当な取引制限」がカルテルにあたります。
そのためカルテルは業種・業態を問わず、企業規模にも関係なく起きる可能性があります。意図的ではない行為が該当するリスクもあるので、企業の経営者や管理部門担当者にとってカルテルの知識は不可欠です。
■関連ニュース
独占禁止法の内容と違反した場合のペナルティは?
主なカルテルの種類
カルテルとして調査・摘発される対象は、近年になって多様化しています。その中から、知っておくべき主なカルテルの種類を紹介しましょう。
価格カルテル(価格競争の制限)
基本的にカルテルは、競争制限行為と見なされます。業者間で特定の価格を設定したり、価格に上限や下限を設けたりすることは、すべてカルテルの対象になります。
数量カルテル(供給数量の制限)
生産数量・出荷数量・販売数量などを業者間で取り決めて、市場への供給量を制限する行為です。原材料の購入制限や設備の運転制限など、間接的な方法で供給量を制限する場合もカルテルです。
技術カルテル
事業者間で技術の開発や利用を制限する行為もカルテルに該当します。一見不当な取引制限にはあたらないように思えますが、品質や価格に影響が及ぶため、近年カルテルの対象になるケースが出てきているのです。
情報交換
事業者間で情報や資料を提供しあったりすることは、直接カルテルとは見なされません。しかしその情報により、価格に関する合意形成などが行われた場合には、カルテルの対象になる可能性があります。
これら以外にも、取引先や販路開拓に関する取り決めをする行為や、雇用条件に基準を設ける行為、人材の引き抜きを禁止する行為なども、場合によってはカルテルの対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、カルテルは明確な合意がない場合でも、暗黙の了解において取引制限などを行えば、それがカルテルと見なされることがあります。ちょっとした情報交換のつもりで交わした内容に従い、それぞれの事業者が同様の取引規制などをすると、独占禁止法に抵触するリスクがあるのです。
カルテルに対するペナルティー
もしもカルテルに該当すると判断されたら、公正取引委員会から排除措置命令が出され、違反行為の排除と再発防止の徹底が図られます。 さらに被害者が出た場合には、損害賠償や差し止めを請求される可能性もあります。
また、独占禁止法違反は犯罪行為にあたるため、刑事罰・過料・課徴金の対象にもなります。違反行為をした者に対しては、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人や団体の場合は5億円以下の罰金が科せられます。
カルテルが起こりやすい状況は?
カルテルはどんな条件でも起こり得るものではなく、発生しやすい状況はある程度限られます。以下に主なケースを挙げておくので、リスクを回避するための参考にしてください。
・同業者が同じような商品やサービスを、同様の価格や品質で提供している場合
・競合する相手が業界全体で少ない場合
・商品やサービスの値上げが、需要に影響を与えにくい場合
・新規参入が難しい場合
このような状況で事業を続けていると、事業者間での合意が生じやすくなり、違法と知りながらカルテルに同調する可能性があります。また、意図せずカルテルの条件が揃ってしまう場合もあるので注意が必要です。
独占禁止法の相談窓口
カルテルを含む独占禁止法違反は、加害者になる可能性と当時に被害者になる可能性もあります。また、独占禁止法には「下請法」という補完法があり、下請け事業者に対する不当な行為を規制しています。
独占禁止法に関する悩みが生じた時には、公正取引委員会が運営する「独占禁止法相談ネットワーク」に相談するとよいでしょう。全国の商工会議所と商工会が窓口になっているので、身近な場所で気軽に相談することができます。
まとめ
事業者間でカルテルが実行されると、市場での競争原理が働かなくなり、商品やサービスの価格上昇や品質低下を招く可能性があります。これは消費者に不利益を生じさせるだけでなく、事業者による公正な取引を阻害する要因にもなります。
そこで、日本国内では独占禁止法により、カルテルが厳しく規制されています。カルテルが起こりやすい状況で安易に違法行為に及んでしまうと、最悪の場合、刑事罰の対象になる可能性もあります。ビジネスは公正な取引環境のもとで行いましょう。
■参考サイト
公正取引委員会|独占禁止法
■関連記事
独占禁止法の内容と違反した場合のペナルティは?
SDGsと独占禁止法コンプライアンス、お互いの歩み寄りは可能なのか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -
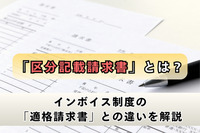
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
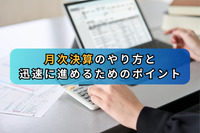
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース