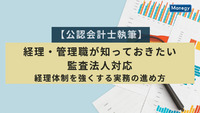公開日 /-create_datetime-/
増加する休職者、戦力ダウンを避けるため企業がとるべき対策とは?
休職とは単に仕事を休むことではなく、仕事が継続できなくなり長期的に職場を離れることです。休職は社員にとっては生活に関わる大問題であり、雇用する企業にとっては戦力低下につながる緊急事態です。
休職となる理由や、休職することで考えられる影響はどんなことがあるのでしょうか。休職の現状と対策について検証してみましょう。
目次【本記事の内容】
休職の現状と問題点
厚生労働省が公開している「治療と職業生活の両立等の支援の現状について」という資料によると、職業関連疾患の中で最も多いのはストレス性疾患です。その患者数はほかの疾患に比べると、突出して多くなっています。
また、離職理由の中でも定年退職を除けば、健康面の問題で職を離れた人の割合が最も高くなっています。こうしたデータからは、一時的にせよ職場を離れる社員にとって、仕事上で健康を害することが最大の問題になっていることが分かります。
では健康面の問題も含め、休職した場合には適切な支援が受けられるのでしょうか。この点についてのアンケートでは、「私傷病に関する休業制度がある」と回答したのは、対象企業全体の58.6%でした。
ただし企業規模により対応は異なり、従業員1,000人以上の場合85.3%で、50人未満では38.3%とかなりの開きがあります。
さらに「私傷病での休業中に賃金が支給される」と答えた企業は、全体では41.4%で、「支給されない」企業は58.2%にも上ります。ただしこの場合でも、企業規模が大きいほど支給するという割合が高くなります。
つまり、ストレスや健康面の問題で休職した場合、ある程度生活が保障されるのは全体の5割に満たず、休職制度の対象にすらならない人も4割程度であり、労働者にとって休職とは、非常にリスクの高い状況だといえるのです。
出典:「治療と職業生活の両立等の支援の現状について」厚生労働省
休職とは?
ここで改めて、休職とはどういう状況なのか考えてみましょう。実は休職とは法的根拠に基づいておらず、労働基準法などで制度として定義されていません。 実際には、それぞれの企業が就業規則などで独自に規定しています。
ほかにも社員の都合による休みについては、育児休業や介護休業などがありますが、これらは法的に認められた「休業」です。これに対して休職は、あくまでも社員本人が仕事を続けられないと判断して、会社と協議の結果、一定期間の休みをとることです。
休職がもたらす影響
休職した社員は、精神面や肉体面での問題が解決するまで、一定期間職場から離れることになります。結果的に本人のみならず、雇用する企業にも大きな影響が及びます。そのデメリットを双方の立場から見てみましょう。
社員にとってのデメリット
原則的に休職期間中は賃金が支払われません。休職に入った直後は、有給休暇などを消化することになりますが、その期間を越えると給与は保証されません。一方で社会保険料などは、企業に在籍する限りは支払い義務が継続します。
また厚生労働省の調査結果によると、企業内で規定された休職期限を越えた場合、復職が難しい場合には退職になるケースが半分以上を占めています。 企業の社内規定により異なるものの、休職した社員は自らリスクを背負い、生活の不安も抱えながら復職を目指すという、非常に厳しい現実に直面することになるのです。
企業にとってのデメリット
雇用する側で最大の問題は、貴重な人材が欠けてしまうことです。もしも社員が復職できない場合、完全に一人の人材を失ってしまうことになります。
複数の休職者を出した企業については、職場環境が問題視される可能性もあるでしょう。社会的イメージも下がり、企業ブランドの低下につながる可能性もあります。
こうしたデメリットを考えると、休職者が出た場合には制度面で支援して、なるべく早く安心して復職できる仕組みづくりが必要だといえます。
休職に関する仕組みづくりの重要さ
前述したとおり、休職者に対する現在の取り組みは決して整っているとはいえません。人材不足の日本で、貴重な社員が働けなくなることは何よりも企業の戦力を低下させてしまいます。
そこで、産業医をサポートする機関などでは、以下のような休職者支援制度を整備することを推奨しています。
・メンタルヘルス対策の強化
・管理職と社員それぞれに対する研修
・産業医の活用強化
・就業規則での休職規定の整備
・休職から復職に至るまでのマニュアル整備
・リワークプログラムの活用
こうした取り組みを強化することで、職場環境を改善することが重要です。休職者が出ないようにする仕組みづくりが、これからは一層強く求められるでしょう。
まとめ
現代では、働きやすいことや社員を大切にすることなども企業ブランドを高める要素として評価されます。休職者を多く出してしまうことは、顧客や取引先からの評価を下げる結果にもつながるのです。
企業にとって大切なことは職場環境を整え、休職者を出さないような仕組みをつくることと考えられます。もしも休職者が出てしまったら、その社員が安心して休みをとり、なるべく早く職場に復帰できる仕組みをつくることです。貴重な人材をいかに大切にするかによって、企業価値を問われる時代が来ているのです。
■併せて読みたい関連ニュース
GW明けの新入社員のメンタルケアは重要!ケアに役立つお役立ち資料集!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -
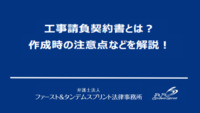
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
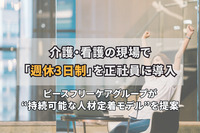
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案
ニュース -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
ニュース -
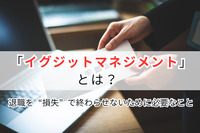
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと
ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
ニュース -
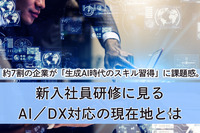
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
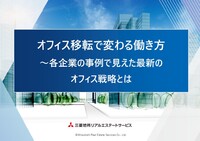
オフィス移転で変わる働き方
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
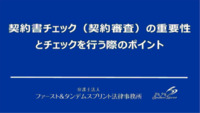
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
ニュース -

「退職金制度」の導入・見直しタイミングを解説
ニュース -

YKK AP、“社員幸福経営”に向けた新人事戦略「Architect HR」を策定。モノづくりの思想を人事に応用し、自律型人材と持続的成長の実現へ
ニュース -

「インシビリティ」が組織を蝕む。“微細な非礼”の悪影響と防止法を解説
ニュース -
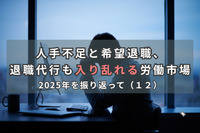
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)
ニュース