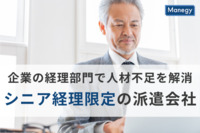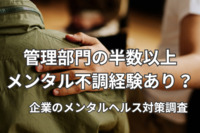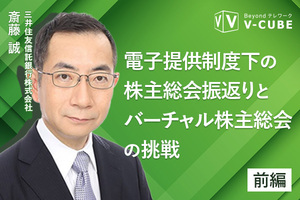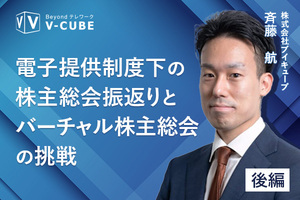公開日 /-create_datetime-/
名古屋工業大学などの発表によれば、「誤情報を信じた人の4割はファクトチェックを避ける」といった傾向にあるようです。最近ではコロナワクチン関連の記事や、ChatGPTの生成文など、ファクトチェックが求められる場面も多くなっています。
今回は、名古屋工業大学などのファクトチェックに関する調査や、どのようにファクトチェック活動を進めていくべきかを考えます。
ファクトチェックに関する調査結果
調査*では、誤情報であることがすでに分かっている記事と、事実にもとづいている記事を見せ、「それぞれの記事の内容は正確と思うかどうか」について尋ねました。誤情報であることが分かっている記事を「正確だ」と言った人に対して、ファクトチェック記事へのリンクを表示し、どれだけの人がクリックするかを調査しています。
その結果、訂正記事を選択的にクリックするグループ(57%)と、選択的にクリックを避けるグループ(43%)に分かれました。とくに後者のグループでは、訂正記事のうちの7%しかクリックされておらず、約90%のファクトチェック記事が届いていないことが分かりました。
*調査概要
・調査方法:インターネット調査
・調査対象:誤情報を信じていた20代から60代の506人
ファクトチェックとは
ファクトチェックとは、「真偽を検証」するもので、社会に浸透している情報が事実にもとづいているかどうかを確認する行為です。たとえば、あるニュース記事が話題になっていたとしても、それが本当に世の中で起こっているかどうか分かりません。
総務省の「日本におけるファクトチェック活動の現状と課題」でも、ファクトチェックの定義として、「社会に広がっている真偽不明の言説や情報が事実にもとづいているかを調べ、正確な情報を人々と共有する」と書かれています。
ファクトチェックの具体例として、「静岡県の水害写真」があります。これは静岡県の水害直後に、匿名SNSのTwitterで拡散されたもので、ドローンで撮影された水害の写真として話題になりました。しかし後に、その写真はAIで撮影したものだと分かりました。
ここで重要なのは、「誤情報であるかどうかをチェックする」だけでなく、「誤情報であることを人々に共有する」ことです。実際に、この水害写真の事例でも、ファクトチェック専門メディアである「リトマス」によって記事化・共有されています。
ファクトチェック活動の原則
国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)では、ファクトチェック活動の原則について定められています。綱領に定められている五つの原則は、以下の通りです。
・非党派性と公正性
・情報源の基準と透明性
・資金源と組織の透明性
・検証方法の基準と透明性
・オープンで誠実な訂正方針
見落としがちかつ重要なポイントが、一つ目の「非党派性と公正性」です。ファクトチェック活動を行う際は、特定の政党を批判するような内容になってはいけません。特定の政治的立場によるのではなく、すべてのファクトチェックに同じ手続きを用いて、公正な視点で判断する必要があります。
これはスポーツにおける「審判」と同じような原則です。特定のチーム(政党)に偏ったジャッジをするのではなく、すべての事象に対して同じ基準を持って関わる姿勢が重要になります。
ファクトチェックの3ステップ
ファクトチェックは、以下の3ステップで行います。こちらは、事実かどうかを確認するだけでなく、それを積極的に公表するケースを指します。
・対象となる言説や情報の選択
・エビデンスの調査と明示
・真偽や正確性についての判定
まずはファクトチェックの対象となる言説や情報を選びます。とくに優先したいのが、「社会的な影響が大きい言説・情報」です。たとえば、新型コロナワクチンに関する記事や自民党の政策といった、人々の生活に大きく関わってくるものになります。
対象となる情報が選べたら、真偽を判定するため、事実関係の調査をします。書籍を参照するだけでなく、関係者への取材を行うことも珍しくありません。こうした活動を通して、「エビデンス」と呼ばれる、誰にとっても明らかな証拠をそろえます。
事実関係を確認できたら、その言説・情報が「正確」もしくは「不正確」であるかどうかを判定します。「正確ではあるがミスリードの要素が強く含まれている」といった場合もあるので、完全なる二者択一にするのではなく、補足情報もしっかりと含めましょう。
まとめ
ファクトチェックは、個人が誤情報に騙されないようにする作業だけでなく、メディアが真偽検証の内容を公表・共有していく取り組みでもあります。名古屋工業大学の調査からも分かるように、誤情報を信じている人は、自分の考えが訂正される機会があまりないようです。
誤情報に騙される人を少しでも減らすためには、メディアが積極的に情報を発信するのと同時に、教育的な視点でアプローチをするのが重要です。義務教育や高校の授業、大学の講義などに、ファクトチェックに関する内容を盛り込むのもよいでしょう。
さらにこうした情報リテラシーの低さは、若者だけの問題ではありません。すでに社会人となった人にも、何らかの形での「学び」が必要です。企業の研修プログラムに、ファクトチェックの内容を含めるなど、さまざまな方法を使って浸透させる必要があるでしょう。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
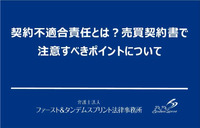
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
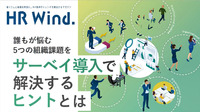
誰もが悩む5つの組織課題をサーベイ導入で解決するヒントとは?
おすすめ資料 -
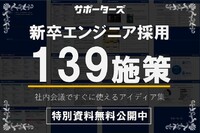
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -
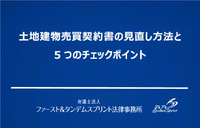
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
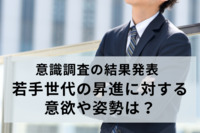
【若手の昇進意欲】昇進したい/したくないでほぼ2極化。学習意欲や上司・先輩からのアドバイスの受け止め方などに違いも
ニュース -
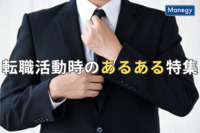
転職活動時のあるある特集
ニュース -
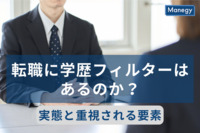
転職に学歴フィルターはあるのか?実態と重視される要素について解説
ニュース -

育児・介護・不妊治療中の管理職が最大3年間の職位変更を可能に 京王電鉄がキャリア形成を支援
ニュース -

ストレスチェックの対象者とは?基本情報と実施する際の注意点5つを紹介
ニュース -

「借り入れ」や「ファクタリング」に頼らなくても大丈夫!新たな資金繰り改善方法
おすすめ資料 -

日本の裁判手続きと電子署名
おすすめ資料 -

働く人の意識を変える定点観測
おすすめ資料 -
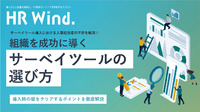
組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -
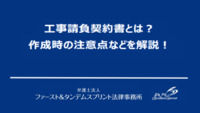
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
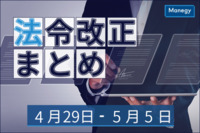
「サービス産業動向調査」2024年(令和6年)2月分(速報) など|4月29日~5月5日官公庁お知らせまとめ
ニュース -
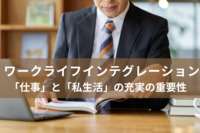
“静かな退職”を防ぐ「ワークライフインテグレーション」とは? 調査結果から見える「仕事」と「私生活」の充実の重要性
ニュース -

職場の働きやすさを左右する重大要素、若い世代が望む理想の上司像とは?
ニュース -

「衛生管理者」の仕事を分かりやすく説明!難易度や試験内容なども
ニュース -

「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~」の活用法
ニュース