公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

2024年1月1日、石川県の能登半島地方で、マグニチュード(M)7.6(気象庁暫定値)の大地震が発生しました。この「令和6年能登半島地震」は、石川県の志賀町で最大震度7となり、沿岸域では津波も観測されて広い範囲で大きな被害が生じました。
日本は自然災害が多く、地震のほか、台風や大雨による洪水、火山の噴火などはいつ起こるか予測不可能です。また、火災や土砂災害、建設現場や工場での事故など、人災が起きてしまう可能性もあります。
これらの災害や事故などの緊急事態が起こったときに、企業が真っ先に実施しなければならないのが、従業員の「安否確認」です。
本記事では、企業にとって重要な「安否確認」について解説します。
目次【本記事の内容】
企業には安否確認を行うこと、として法的な義務が定められているわけではありません。しかし、「労働契約法」では、5条「労働者の安全への配慮」にて、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。
これは、使用者(企業)には安全配慮義務があることを明文化したものであり、使用者の規模や労働者の立場の違いに関係なく、全労働者に対して当てはまります。つまり、安否確認は安全配慮義務の一環として取り組むべきものなのです。また、この対象には海外勤務をしている従業員はもちろん、自社で働く派遣社員なども含まれます。
企業にとって安否確認は、従業員の安全確保と早期の事業再開を実現するために必要です。災害や事故、事件、パンデミックなどの緊急事態において行なう安否確認には、以下の目的があります。
災害が発生した際に最優先すべきことは、自社の従業員やその家族など、関係者の安全を確保することです。そのために、まずは安否確認を行なって従業員やその家族の安否状況を把握します。
そして救助や支援が必要な場合は、一刻も早く行なうことが大切です。被災した従業員がいる場合は、居場所や状況を把握し、適切な救援活動が行われるように手配します。 また、安否確認で従業員に適切なサポートや情報提供を行なうことで、従業員の心理的な安全性が担保できるという効果もあります。
災害や事故などの緊急事態下では、誤った情報が広がる可能性があります。安否確認をすることで、自社の従業員や事業の継続可否に関する、正確で信頼性の高い情報を得ることができ、それをもとに的確な判断と行動が可能になるのです。
災害や事故などが発生すると、業務が中断し、企業の事業運営にも大きな影響が及びます。しかし、安否確認を通じて従業員や事業所などの被害状況を把握し、必要な措置を講じることで、事業が段階的にでも再開しやすくなります。その際に必要なのが「BCP(事業継続計画)」を事前に策定していることです。
「BCP」とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行なうべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
(中小企業庁公式サイト「中小企業BCP策定運用指針」より引用)
安否確認で状況把握と措置を行ない、BCPに基づき事業を再開することで、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出やマーケットシェアの低下、企業評価の低下などを最小限に防ぐことができます。
以上のことから、安否確認は企業が災害に対応する際に不可欠であり、その仕組みの構築と従業員への周知を徹底すべきです。
一般的に、安否確認の方法には主に以下の6つがあげられます。しかし、緊急事態時の状況によっては、適していないものもあります。一つずつご説明しましょう。
従業員に社用携帯電話を渡している企業は、個々に連絡を取りやすい電話で安否確認を行なおうと考えているところもあるでしょう。確かに、従業員に口頭で直接確認できるメリットはありますが、災害直後は利用者が殺到するために、つながりにくくなります。また、従業員数が多い企業では、確認に時間がかかるのがネックです。
メールも電話同様、災害時は送受信数が一気に増えてサーバーの処理が追いつかず、送受信にタイムラグが生じる可能性があります。また、被災状況やタイミングによっては、従業員がメールの着信に気付かないことがあるかもしれません。
LINEなどのSNSツールは広く浸透しており、グループ機能などを使って日常的に活用している企業も多いようです。一方で、個人的に利用していない、もしくは私生活のアカウントを勤務先に共有していない従業員がいる場合は、全員へ安否確認をすることができません。
チャットツールは、従業員全体の状況確認がしやすく、連絡を取れやすいツールの一つです。送付先が「既読」になれば会社からのメッセージが伝わったことが把握でき、個々に向けてメッセージを送ることもできます。
ただし、社内チャットツールを安否確認に使う場合は、従業員各自が社外でも使っているスマートフォンやパソコンなどにあらかじめツールを入れていなければ、緊急時に活用しにくいでしょう。
災害伝言ダイヤルや伝言板は、通信各社が災害時に提供するサービスで、被災地の人々の安否確認を行なえる声の伝言板です。企業での安否確認にも活用できますが、伝言の登録時間や1つの電話番号での使用回数に制限があるため、人数が多い企業には不向きかもしれません。
災害発生時に自動で従業員にメールを一斉送信できる専用サービスです。回答がない従業員には、メールやスマートフォンへのプッシュ通知を繰り返し行ない、電話なども使って通知することができます。
電話やメール、SNSツールなど他のものは、従業員からの回答をまとめる作業に時間を要しますが、安否確認サービスは回答も自動集計してくれるので、非常時でも状況を迅速に把握できます。数千人単位の大企業でも活用しやすいサービスです。 なお、ビジネスチャットツールなどのなかには、安否確認機能がついたものもあります。
以上から、災害や事故などの緊急事態下で安否確認をする場合に、最も活用しやすいのは、安否確認サービス、または安否確認機能がついたビジネスチャットツールと言えるでしょう。
ここでは、マネジーが特におすすめする安否確認サービスや関連製品をピックアップしました。
詳しい資料もご提供しているので、ぜひご確認ください。
「Safetylink24」は、地震災害やBCP対策として、従業員やその家族の安否確認に最適な安否確認サービスです。地震などの災害時に、登録ユーザー宛てにメールを一斉配信します。IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」の安否確認システム部門 Good Productを連続受賞!
世界140か国以上に製品を届ける救命医療機器のグローバルメーカー・ゾールメディカル社独自の「胸骨圧迫ヘルプ機能」をプラスしたAED。
CSS(コラントッテ・セーフティ・システム)は、自然災害や大事故、外出先での突発的な病気(脳梗塞・心筋梗塞)により意識不明の状態で救急病院に搬送された際に、24時間365日、速やかに勤務先と家族へ連絡することができる緊急時連絡サービスです。
使いやすく多彩な機能とシンプルな操作性で、災害時において従業員の安否状況を確認できるサービス。BCPの初動を確実にサポートします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

サーベイツールを徹底比較!
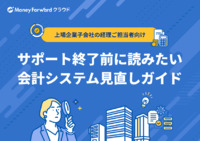
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

生成AIの成果物を会社資産にする管理術
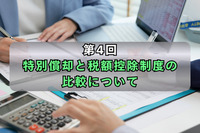
第4回 特別償却と税額控除制度の比較について

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

【調査】内定期間中に企業に求めるサポート1位「先輩との関係構築」。9割以上が人事の「不安・疑問への丁寧な対応」で入社意欲高まる

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

ラフールサーベイ導入事例集

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査

税制適格ストックオプションとは?メリットや要件、導入時・会計時の注意点
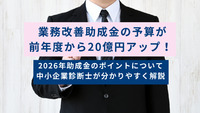
業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説
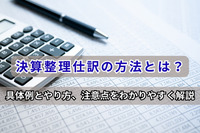
決算整理仕訳の方法とは?具体例とやり方、注意点をわかりやすく解説
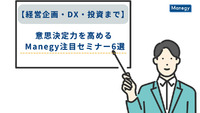
【経営企画・DX・投資まで】意思決定力を高める Manegy注目セミナー6選
公開日 /-create_datetime-/