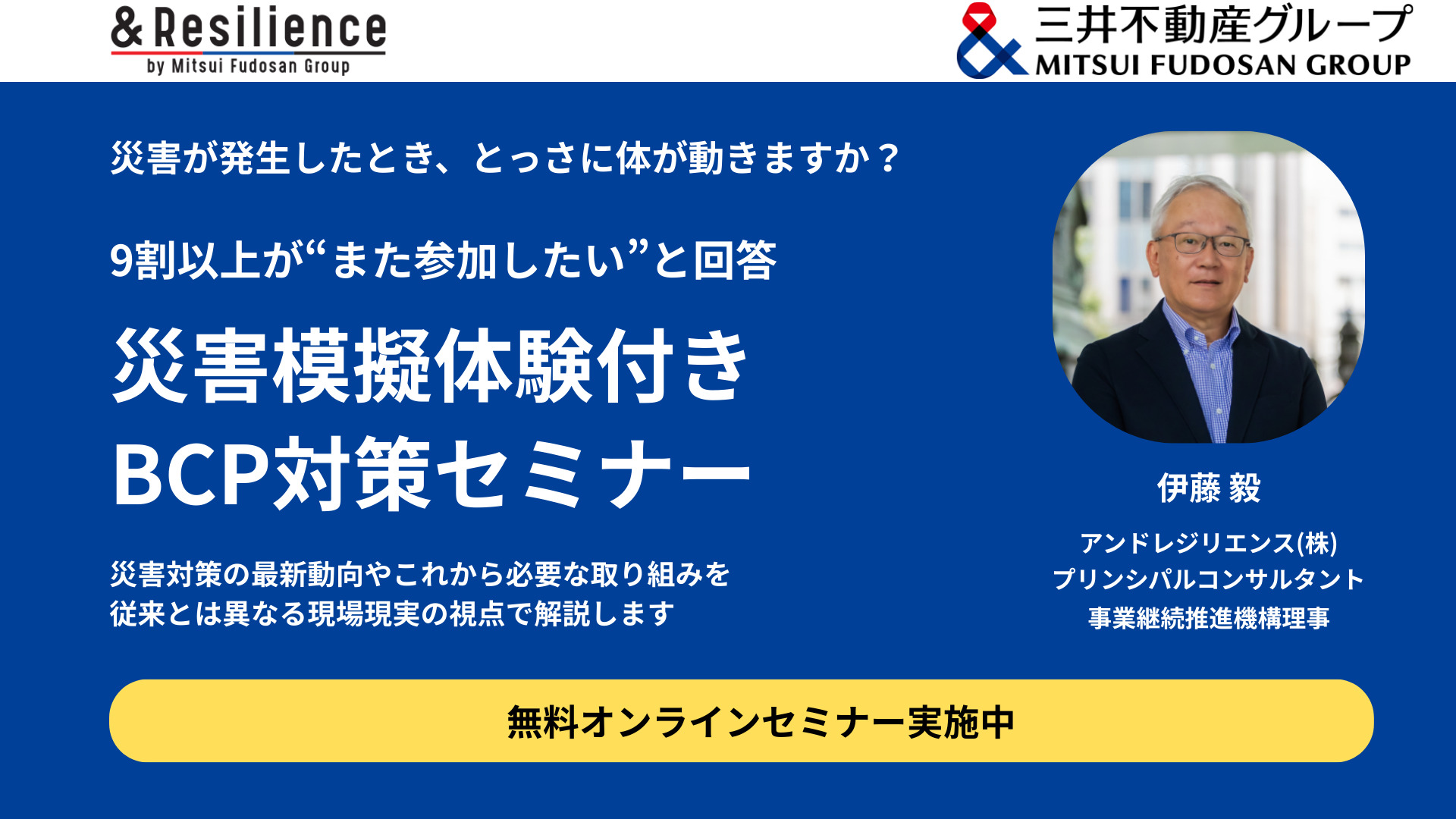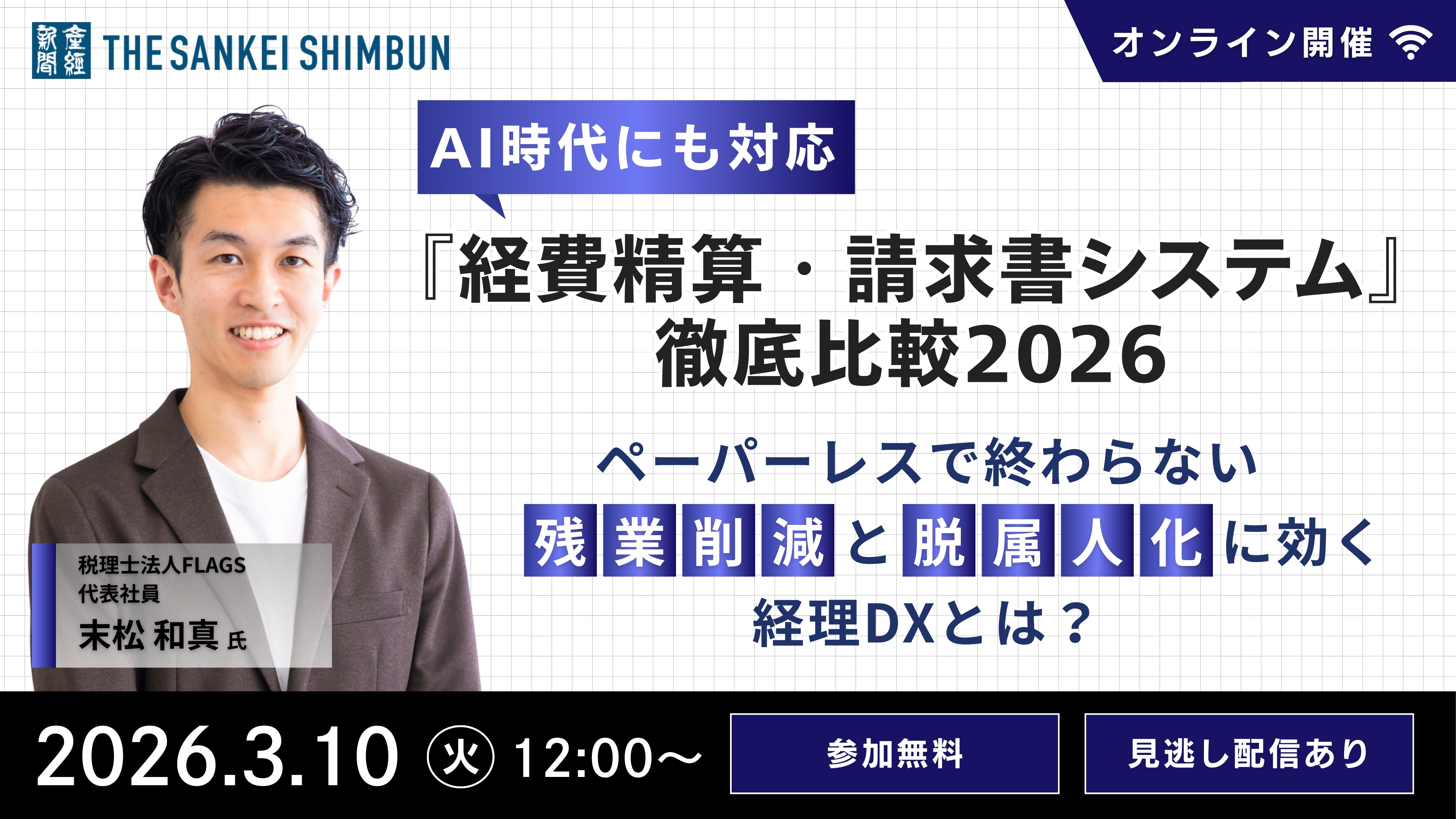公開日 /-create_datetime-/
【春闘2024】各業界大幅の賃上げ要求。実質賃金マイナスはどこまで改善できるのか?

毎年2月から3月にかけて、大手企業の労働組合がその年の春闘に向けて、企業側に賃上げ・待遇改善を求める要求書を提出するのが慣例です。2024年も2月14日、自動車大手各社の労働組合が賃上げを求める要求書を提出し、その内容に注目が集まっています。 今回は自動車産業をはじめ、主要産業でどのような要求書が労働組合から出されたのかをご紹介します。
自動車産業では過去最高水準の賃上げを要求
2月14日時点、自動車大手各社の労働組合が賃上げを柱とする要求書を提出しました。その内容は以下の通りです。
・
トヨタ自動車
ベースアップと定期昇給を合算して1人当たり月7,940~2万8,440円の賃上げを要求。一時金(ボーナス等)の要求額は7.6カ月分となり、1999年以降で最高の賃上げ要求。
・
日産自動車
ベースアップと定期昇給の合計で月1万8,000円、の賃上げを要求。賃上げ率は約5%。一時金の要求額は5.8カ月分となった。
・
ホンダ
ベースアップと定期昇給の合計は月2万円での賃上げを要求。賃上げ率は5%強。一時金の要求額は7.1カ月分。1992年以来の最高水準の賃上げ要求。
・
マツダ
ベースアップと定期昇給の合計で1万6,000円の賃上げを要求。賃上げ率は約5%。一時金の要求額は5.6カ月分。
・
三菱自動車
ベースアップと定期昇給の合計で2万円の賃上げを要求。賃上げ率は約6%。一時金の要求額は6.3カ月分。
・
スズキ
ベースアップと定期昇給の合計で2万1,000円の賃上げを要求。一時金の要求額は6.2カ月分で前年と比較して0.4カ月分引き上げ。
・
SUBARU
ベースアップと定期昇給の合計で1万8,300円の賃上げを要求。賃上げ率は5%強。一時金の要求額は6カ月分。
・
ダイハツ
ベースアップの要求はせず、一時金の要求額は5.0カ月分。
軒並み過去最高の水準の賃上げを要求しています。現在、物価高が家計を圧迫するとして問題視されていますが、自動車産業は、円安が追い風となり業績は好調といえるでしょう。業績好調により、日用品・食料品の物価高に十分見合うだけの賃上げを求めているといえます。
なお、ホンダ、マツダについては3月中旬の集中回答日を待たずして満額回答をしています。
各産業における賃上げ要求の動向
自動車産業の各社の労働組合が加盟する全日本自動車産業労働組合総連合会(自動車総連)は、すべての組合において目標とする賃金水準を実現すると表明しています。こうした傾向は自動車産業以外の業界でも同様です。基本的に2023年をさらに上回る積極的な賃上げ要求を行っています。
主な業界の動きは以下の通りです。
・全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電機連合)
ベースアップを月1万3,000円以上、ベースアップと賃金体系維持分を合わせて約2万円の賃上げ要求。
・全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(UAゼンセン)
4%アップの賃上げ要求。
・日本基幹産業労働組合連合会(基幹労連)
ベースアップを月1万2,000円以上要求。
・ものづくり産業労働組合(JAM)
賃金構造維持分を確保した上で、ベースアップを月1万2,000円基準で要求。
・全日本電線関連産業労働組合連合会(全電線)
賃金構造維持分を確保した上で、ベースアップを月1万円以上要求。
どの業界も、高い水準のベースアップを要求しています。2023年はバブル崩壊以降、最も高い水準での賃上げが実現しましたが、それをさらに上回る賃上げ要求です。
実質賃金は改善できるか
春闘を見る上でポイントとなるのは、実質賃金が上がるかどうかです。
実質賃金とは、労働者が受け取る額面上の名目賃金から、物価上昇分を差し引いた金額のことです。つまり、たとえば名目賃金が前年比5%上がったとしても、物価上昇が5%以上であれば、実質賃金は前年比マイナスとなります。もし実質賃金がマイナスになれば、労働者の購買力(財・サービスを購入できる量)は低下し、生活状況はより苦しくなることに直結するのです。
ここのところは実質賃金のマイナスが続いており、2022年4月から2年弱マイナスで推移しています。月単位で見ると、2023年の1月には前年同月比マイナス4%台にまでなり、その後もマイナス2~3%台で推移しています。
物価の上昇に賃金が追いついていない状況が続いているということは、「前の年よりも商品・サービスを買える量が減り続けている」状態が続いていることを意味します。こうした状態が続けば、国民生活はどんどん貧しくなってしまいます。
各社の賃金アップと動向も気になるところですが、実質賃金の改善により、どれだけ生活状況が明るくなる賃上げを実現できるかという点も、2024年春闘における注目ポイントといえるでしょう。
まとめ
名目賃金が上がっても実質賃金が上がらなければ、真の賃上げとはいいきれません。実質賃金がマイナスであれば、月給・賞与の額面だけを見て「去年よりも収入が増えた」と思っても、その収入で買えるものの総量は去年よりも減ってしまいます。
とくに製品を海外に輸出して販売している企業の多くは、円安により業績が向上しています。社員は会社の業績に伴った賃上げを期待しているでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
MS Agentに掲載中の求人
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
ニュース -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース -

生成AI導入の鍵はデータ整備|RAG精度を高める運用設計の極意
ニュース -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説
ニュース -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -
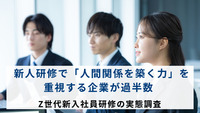
新人研修で「人間関係を築く力」を重視する企業が過半数 Z世代新入社員研修の実態調査
ニュース -

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
ニュース -

生成AIの成果物を会社資産にする管理術
ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応
ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査
ニュース