公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
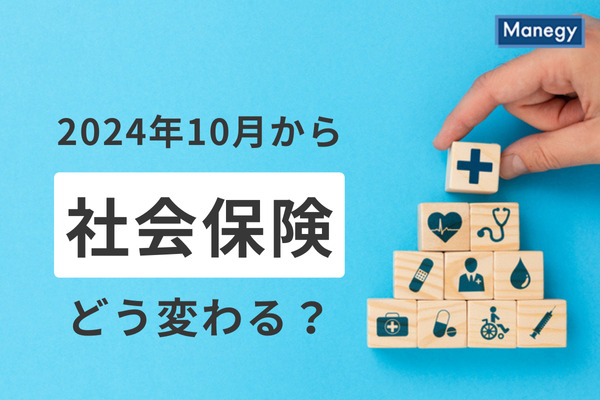
2024年10月から、社会保険(「健康保険」「厚生年金保険」等)の適用範囲や対象従業員が変わります。
これまで、社会保険の加入対象者でなかった短時間勤務の従業員も加入が義務化されるようになります。現在、対象企業は改正に向けた対応に追われていることでしょう。
この記事では改正のポイントや企業が求められる対応、改正のメリットなどについて解説します。
改正のポイントとなるのは「短時間労働者に社会保険を適用しなければならない企業の範囲が拡大される」という点です。
これまではパートやアルバイトなど、短時間勤務労働者にも社会保険を適用しなければならない企業は、従業員数が101人以上と定められていました。
しかし2024年10月からは、短時間勤務労働者の社会保険加入義務となる企業規模が従業員数51人以上へと変更されます。
従業員数については以下でカウントされます。
従業員数=「フルタイムの従業員数」+「週労働時間および月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数(パートやアルバイトを含む)」
この算出方法によって直近12カ月のうち6カ月で51人を上回れば、短時間労働者の社会保険加入義務の対象企業となるのです。
新たな加入対象者は、以下の項目をすべて満たす労働者です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
詳しくは下記で説明しますが、企業には新たな加入対象者を正しく把握する必要があります。
2024年10月の社会保険改正までに企業は「加入対象者の把握」「社内通知」「従業員とのコミュニケーション」「書類の作成・届出」の4つのステップをこなさなければなりません。
それぞれ解説します。
先ほど、改正後の新たな加入対象者について
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
のすべてに当てはまる従業員と説明しましたが、厳密には、各項目に細かい条件があります。
例えば「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」では、「週所定労働時間が40時間の企業の場合。契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含まない」という規定があります。
また「所定内賃金が月額8.8万円以上」という項目には「残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない」という条件があります。
企業は、各項目を理解し、対象者数を正しく把握しなければなりません、
新たな加入対象者に漏れなく、2024年10月からの改正内容が伝わるよう周知を徹底しましょう。
社会保険加入が義務化されることを望まない従業員もいるかもしれません。また、この度の改正の経緯を知らない従業員もいることでしょう。 こうした従業員に向けて説明会や個人面談を行い、改正についての理解を得る必要があります。
対象企業は、2024年10月7日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。オンラインでも申請できます。
社会保険改正によって企業が得られるメリットとしては「採用活動の強化」と「補助金の優先的支給」が挙げられます。
厚生労働省のアンケート調査によると、パート労働者のおよそ6割が、社会保険に加入できる求人を「魅力的」と考えているようです。社会保険加入範囲の拡大を行うことで、魅力的な求人が出せることにつながります。
中小企業生産性革命推進事業においては、取り組み内容によって「ものづくり補助金(最大1,250万円)」と「IT導入補助金(最大450万円)」などの補助金を受け取ることができます。
これらの補助金には審査が必要となりますが、選択的適用拡大に積極的に取り組む企業は応募要件が緩和されるなど、優先的に支援が受けられます。
従業員側に考えられる具体的なメリットとしては、「保険料の自己負担額の軽減」「年金の増額が期待できる」「保険・保障の充実」があります。
社会保険の変更によって、国民年金・国民健康保険が、厚生年金・健康保険に変わります。費用の半分を会社が負担するようになるため、働き方や収入によっては保険料の自己負担額が下がる可能性があります。
厚生年金に加入することで、年金が国民年金と厚生年金の2階建てになります。その結果、年金の受取額の増額が期待できるでしょう。
健康保険の加入によって、病気や怪我、出産による休業時の保障が充実します。そのため、以前に増して安心感をもって働けるようになるのです。
2024年10月から51人以上の従業員がいる企業で、短時間勤務労働者の社会保険の加入が義務化されます。加入対象者にはいくつかの条件があるので、対象企業は事前に確認、周知を行いましょう。
社会保険の充実は、企業と労働者それぞれにメリットをもたらします。規定に従って、積極的に拡大を進めていきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
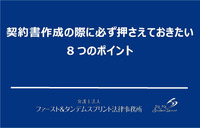
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
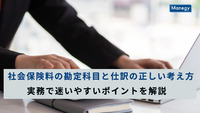
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説

法務FAQ構築の手順とポイントを解説|AIを活用した効率的な運用・更新手法も紹介

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
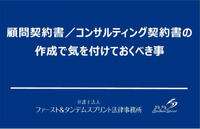
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
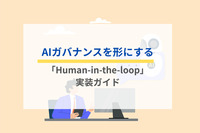
AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド
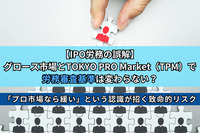
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得
公開日 /-create_datetime-/