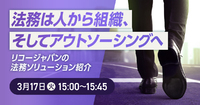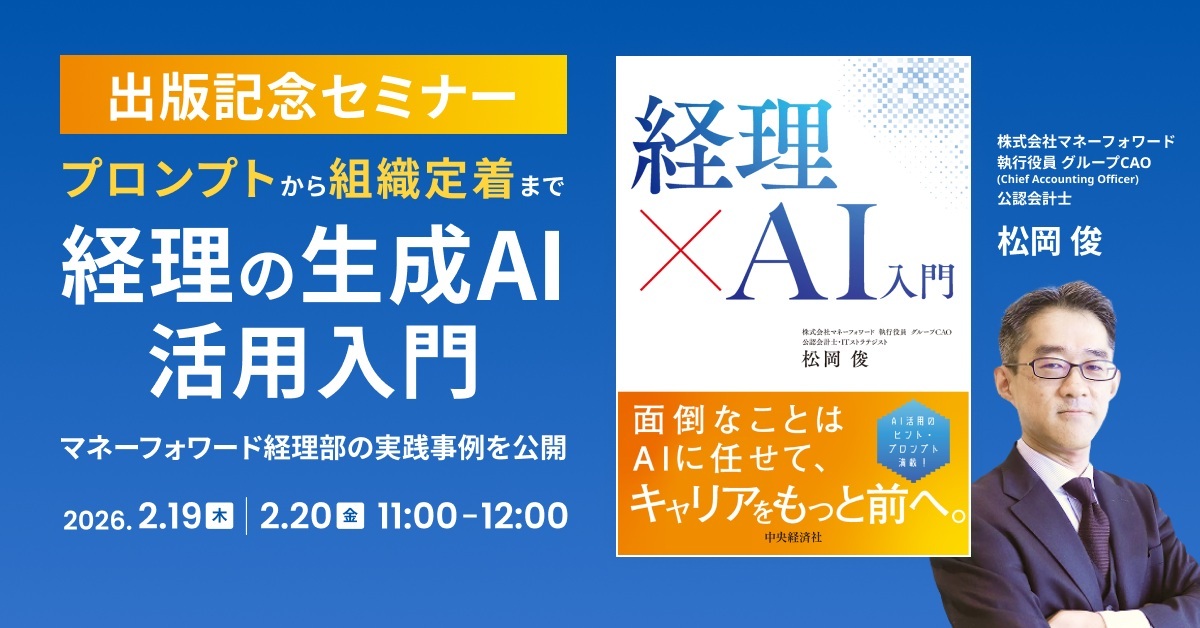公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】育児・介護休業法改正(2025年4月1日施行)法務対応時のポイント
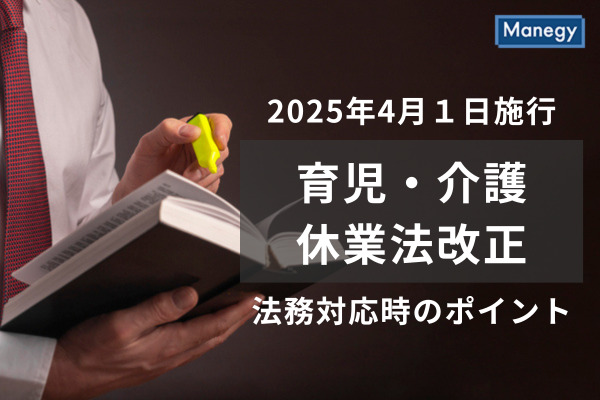
目次本記事の内容

香山 政人
アルク社会保険労務士法人
特定社会保険労務士・両立支援コーディネーター
大手社会保険労務士法人を経て、アルク社会保険労務士法人を開業。クラウドシステム「マネーフォワードクラウド」に特化した社労士事務所として、数多くの導入・運用実績を持つ。その他、ハラスメント研修や各WEBメディアへの執筆等多方面で活動している。
①2025年4月施行の育児・介護休業法改正の概要について
2024年4月に育児・介護休業法が改正され、翌2025年4月より順次施行となります。今回の改正の目的は、「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実」がポイントです。
育児休業取得率は、
女性80.2%
男性17.13%
短時間勤務制度の利用率は
正社員の女性51.2%
正社員の男性7.6%
となっており、育児休業・短時間勤務制度の利用ともに、男女間で大きな格差が見られ、日本社会は以前として女性側に育児負担が偏っている状況となってしまっています。
一方で、正社員の男性の約3割は、育児休業を利用していないものの「利用したかった」と回答しています。男女いずれも、子どもの成長段階にあわせて、残業をしないフルタイムでの働き方や、フルタイムであっても柔軟な働き方(出社や退社時間の調整、テレワークなど)を希望する割合が高く、柔軟な働き方に対するニーズが見られているのが現状です。
また、家族の介護問題については、状況は深刻です。家族の介護や看護による離職者は、年間約10.6万人となっており、1つの原因には、介護休業制度そのものはあるものの、制度の内容やその利用方法に関する知識が十分でなかったケースが多いとされている状況です。
こうした仕事と育児・介護の両立に関する課題を背景に、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、仕事と介護の両立支援制度の充実策として、主に次の改正が行われました。
【子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充】
・子の看護休暇が小学校3年迄に拡充、入学式等に活用できる看護等休暇へ
・小学校就学前までの所定外労働の制限(残業免除)の拡充
・3歳になるまでの子を養育する労働者へのテレワーク導入の努力義務
・3歳になるまでの子を養育する労働者への仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務
・3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対して柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
【育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化】
・育児休業取得状況の公表を1,000人超の事業主から300人超の事業主へ
【介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等】
・介護直面労働者への個別の周知・意向確認義務
・介護休暇の対象者の見直し
・介護離職防止のための雇用環境の整備(労働者への研修等)の義務化
・要介護家族の介護中の労働者へのテレワーク導入の努力義務
lockこの記事は会員限定記事です(残り3937文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
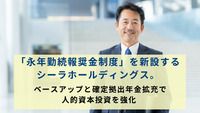
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
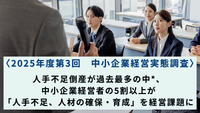
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
ニュース -
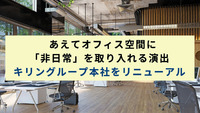
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース -

出産・育児期の不安を解消する支援策 子供1人当たり最大65万円を支給するペアレント・ファンド
ニュース -

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ
ニュース