公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

2024年5月15日、同年3月に国会に提出された「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が正式な法案として成立しました。今回の改正の注目ポイントとしては、「公開買付規制制度の改正」と「大量保有報告制度の改正」の2点を挙げられます。
M&A・資本市場に関わる変更点であるため、ビジネスパーソンとして基本的な概要はしっかり押さえておきたいところです。 そこで以下では、公開買付(TOB)・大量保有報告制度の概要とその改正点について詳しく解説します。
まずは公開買付制度と大量保有報告制度のおさらいをしておきましょう。法改正前の内容は以下の通りです。
公開買付制度とは、企業の支配権に影響をおよぼすような証券取引について、透明性と公正性を確保するための制度です。「会社の支配権に影響をおよぼすような証券取引」とは、一言でいえば大量の株式を取得することを指します。そして公開買付とは、不特定かつ多数の株主・投資家に対して、事前に株式の買付価格や買付期間などを広告することをいいます。
現行の会社法の規定に従うと、株式(発行済株式数)の10%以上を保有すると「主要株主」、半数以上の株式を保有する法人株主は「親会社」、最大の株式を保有している株主は「筆頭株主」などと呼ばれます。こうした企業支配に関わるような大量の株式購入を行う際、誰も知らないところで密かに株の取引が行われるとしたら、不透明・不公正であり健全とはいえません。そのような事態を避けるためにルールが定められているわけです。
改正前の公開買付制度の内容は、以下の5点にまとめられます。
・3分の1ルール・・・少数者が買付けをして、買付後の株式所有が3分の1超となる場合は、公開買付とする必要があります。ここでいう少数者とは、60日間で10名以内を指します。
・5%ルール・・・多数者が買付けをして、買付後の所有割合が5%超となる場合は、公開買付とする必要があります。ここでいう多数者とは、60日間で10名超を指します。
・全部買付義務・・・公開買付によって上場廃止等に至る場合は株主を保護するため、買付後の所有割合が3分の2以上になるときに、買付けに応募する株主の株式をすべて買付ける必要があります。上場廃止された株式は証券取引の対象外となるので「紙切れになる」とも呼ばれますが、そうした事態を防ぐためのルールです(2009年以降、株式は電子データ化されているので実際には紙ではありません)。
・急速な買付けに対する規定・・・取引・増資によって「急速な買付け」(3カ月の間に対象企業の株主の10%超の買付け)をする場合、購入後の所有割合が3分の1超になるなら必ず公開買付とする。
証券会社を通しての売買である市場内取引(立ち合い)については、公開性があるので規制対象外。
大量保有報告制度とは、買付け等により株式を大量保有した場合に、所有状況を開示することを義務付けた制度です。特定株式の大量保有は、企業経営への支配力や株式市場の価格変動に多大な影響を与える要素なので、市場の透明性や公正性、株主保護の観点から規定されているルールです。
改正前の大量保有報告制度の内容は以下の2点にまとめられます。
・5%ルール・・・株式の大量保有者に「大量保有報告書」の提出を義務化。ここでいう大量保有者とは、取得株式の割合が5%超の場合を指します。なおこのルールでは、株式の共同保有のケースも該当します。共同保有とは、たとえば投資家Aが3%、投資家Bが4%の株式を保有している場合、AとBが共同して7%分の議決権その他の権利を行使することを指します。共同保有により7%となって5%超となるため、大量保有報告書の提出が必要となるわけです。
・機関投資家への特例・・・株の取引を事業としている証券会社や銀行、機関投資家などについては、事務負担軽減のため、報告頻度を2週間ごと、5営業日以内にすればよいとされています。
今年3月に国会に提出され5月に成立した改正法における、公開買付・大量保有報告制度の変更点は以下の通りです。
市場外取引のみならず、市場内取引についてもルールの適用対象となりました。
市場内取引でも非友好的買収事例が増え、さらにM&Aの形態も多様化していることから、昨今の環境変化に対応し、透明性・公正性の向上を図るために実施されました。
公開買付が必要となる買付後の所有割合が、発行済株式の3分の1(約33%)から30%に引き下げられました。 つまり3分の1ルールが30%ルールに変わったわけです。また、30%超となる買付けに加えて、「すでに30%を超えている場合における買付」等も公開買付の対象です。
保有割合の合算対象となる「共同保有者」の範囲が、より明確に再規定されました。
具体的には、「経営に重大な影響をおよぼすような合意を行わない限り、共同保有者には該当しない」とされました。
企業が持続的な成長、企業価値向上を実現する上で、株主と企業側による建設的な目的のもとでの「対話(エンゲージメント)」は重要な役割をもちます。経営者と投資家が経営方針に関して直接話し合いをする、株主総会で議決権行使、株主提案をするなどがその一例です。
株主の共同保有者が行う対話は「協働エンゲージメント」と呼ばれ、複数の投資家が協力して行うので、より効果的な対話も可能となります。しかし改正前の制度では、この「共同保有者」の定義に不明確な部分がありました(何に対して協働するのかなど)。
ルール変更後の共同保有者に認定される株主は、それ以外の株主(配当方針、資本政策変更など、企業支配に無関係な提案だけする株主)よりも、密接に企業経営に関わります。共同保有者に強い協働エンゲージメントを発揮してもらい、企業の成長・企業価値向上への貢献を促進しようというのが法改正の目的です。
今回の公開買付制度・大量保有報告制度の見直しは、自社の企業支配のあり方そのものに関わる変更といえます。とくにM&Aを積極的に展開している企業、あるいは買収の防衛策を講じている企業にとっては、今回の法改正により施策・対策を改めて講じる必要もあるでしょう。
なお投資家のエンゲージメントについては、2014年に金融庁が策定した「日本版スチュワードシップ・コード(責任ある機関投資家の諸原則)」にも詳しく定められています。
■参考サイト
簡易株式交換とは?概要やメリット・デメリットを解説
PBR(株価純資産倍率)とPER(株価収益率)の概要と違いを解説
株価が高めか安めかを判断するための指標「PBR」を詳しく解説
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

サーベイツールを徹底比較!
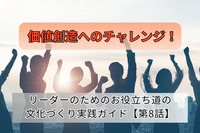
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
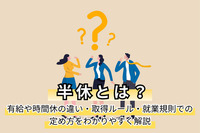
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説
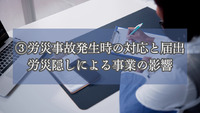
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
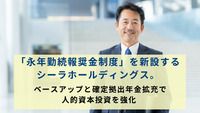
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
公開日 /-create_datetime-/