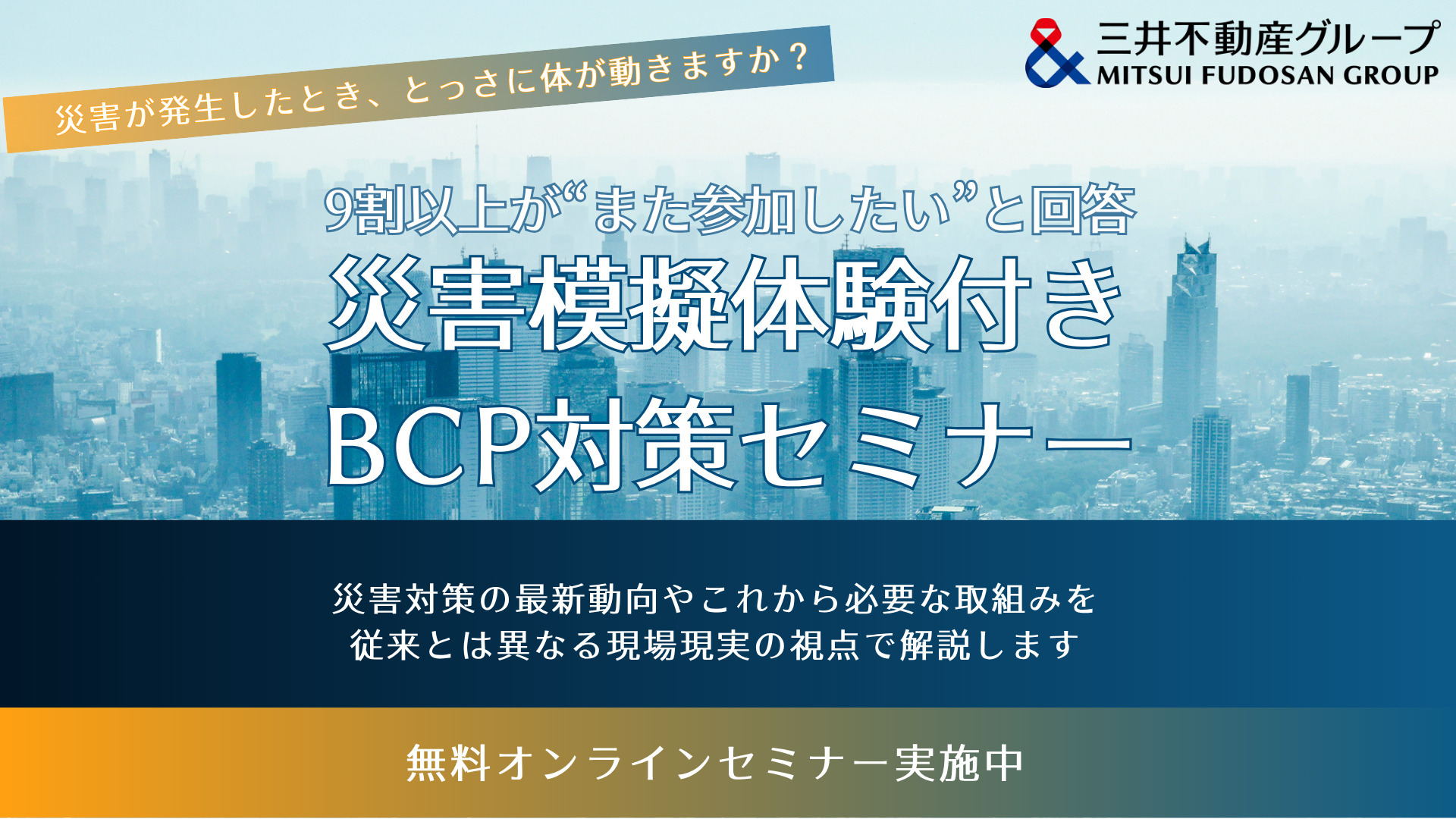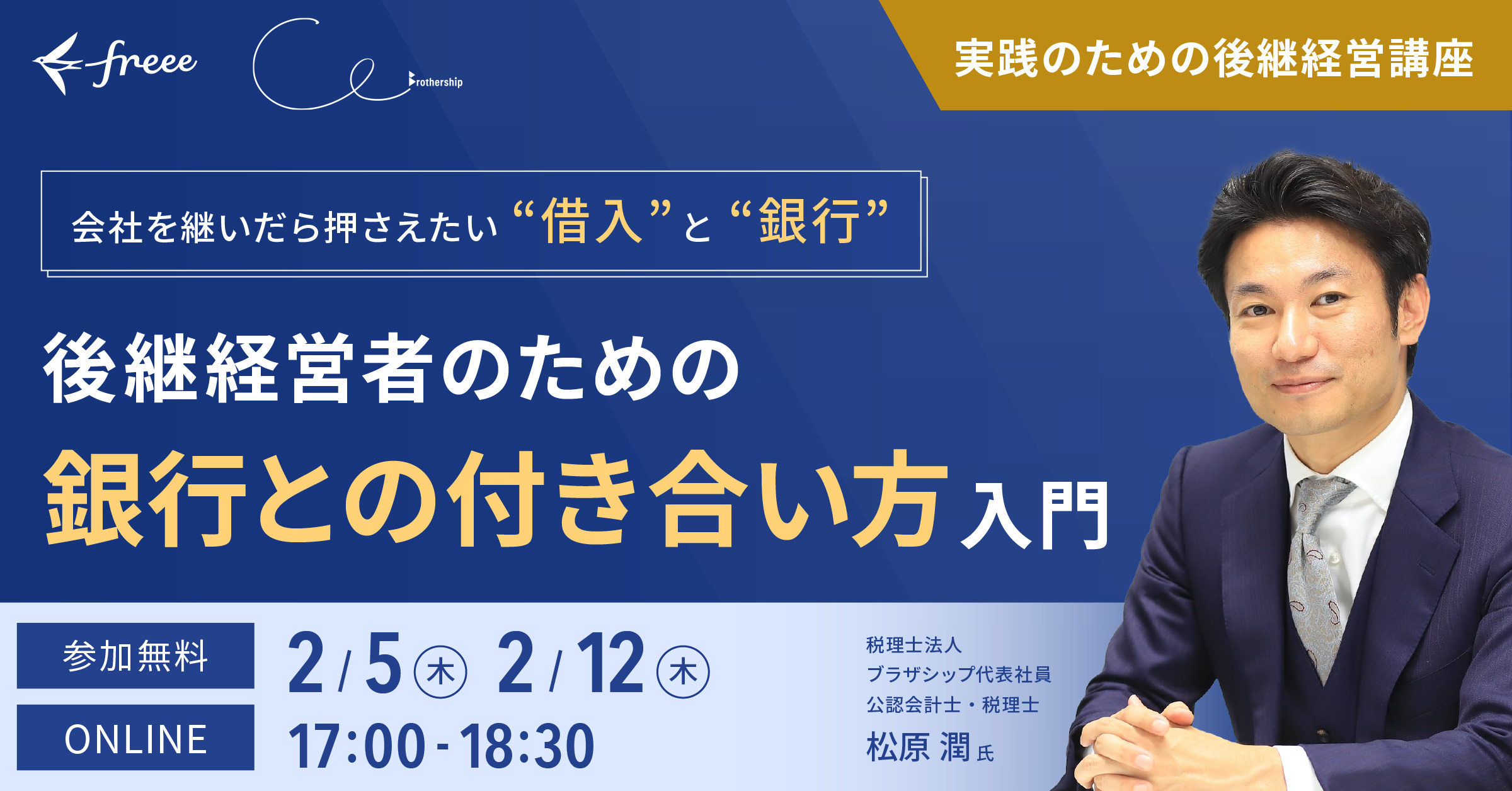公開日 /-create_datetime-/
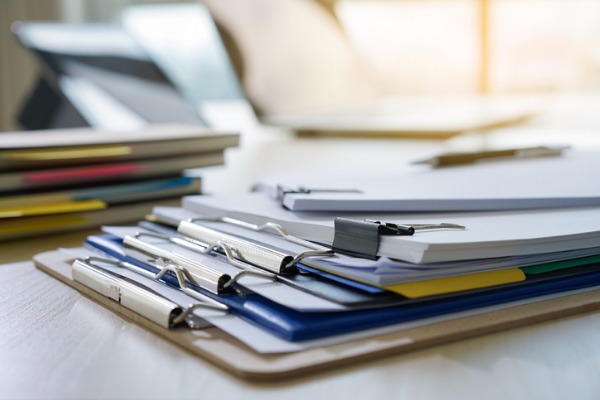
会社で作成される文書の中には、法律で保管期間が定められているものがあるのをご存知ですか?特に総務部・経理部が作成・保管する文書は、法律で細かく保管期間が決められているものが多くあります。また、法律の定めがなくても保存した方がよい文書もあります。
今回は、「人事・労務関係」に焦点をあて、保存すべき文書について紹介します。
目次【本記事の内容】
社内のハンコ文化はこんなに損?!文書業務はDXで今すぐ効率化
資料の無料ダウンロードはこちらから
保存すべき文書の根拠
保存すべき文書の多くは、「労働基準法」や「雇用保険法」など法律によりその保存期限が定められています。まずは、法律によって保存すべき文書と、その法的根拠がどのようなものか見てみましょう。
雇用保険法施行規則第143条
雇用保険法施行規則第143条によると、「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。」とあります。
「雇用保険に関する書類」とは、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届や、雇用保険の加入手続きがなされたことを労働者本人が確実に把握できるようにする、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書などの文書のことです。
労働基準法109条
労働基準法109条には、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」とあります。
雇用契約書や解雇通知書、タイムカード、残業命令書なども該当する文書です。
健康保険法施行規則第34条
健康保険法施行規則第34条には、「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」と明記されています。
「健康保険に関する書類」とは、資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書などの文書のことです。
その他にも、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働者派遣法などでも保管管理が求められる文書について定められているので、人事・労務関係を担当される方は、次の保管すべき文書についてぜひご留意ください。
保存が必要な文書
実際に保存が必要な文書について、保存期間ごとに計算起算日とあわせて整理しましょう。
保存期間2年
・雇用保険に関する書類(被保険者関係以外の一切):被保険者の退職・死亡の日~
・健康保険・厚生年金保険に関する書類(離職票、雇用保険被保険者資格取得確認通知書など) : 被保険者の退職・死亡の日~
保存期間3年
・雇入れ又は退職に関する書類(雇用契約書、解雇通知など):労働者の退職・死亡の日~
・労働者名簿:労働者の退職・死亡の日~
・タイムカード、残業命令書など労働時間の記録に関する重要な書類:最後の記入日~
・時間外・休日労働協定届:協定の有効期限満了日~
・派遣元管理台帳:契約完了の日~
・派遣先管理台帳:契約完了の日~
・賃金台帳:最後の記入日から起算(※労働基準法では、3年保存を義務付けていますが、国税通則法では7年保存を義務付けています)
・災害補償に関する書類:災害補償の終了日~
・労災保険に関する書類(請求書類):完結の日~
・労働保険の徴収・納付等の関係書類:完結の日~
保存期間4年
・雇用保険の被保険者に関する書類(離職票、雇用保険被保険者資格取得確認通知書など):労働者の退職・死亡の日~
保存期間5年
・健康診断個人票(雇入健康診断、定期健康診断):作成日~
保存期間7年
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:法定申告期限~
・源泉徴収簿:法定申告期限~
永久に保存すべき文書と文書の電子化
法律などによる定めがないものの、会社を運営する上で必ず永久保管しておいた方がよい文書もあります。会社が倒産などにより解散するまで、下記の文書については、必ず最新のものだけでなく更新履歴がわかるように、改定前の文書も保管するようにしましょう。
・定款
・就業規則作成・届出・変更
・規定関係
永久保管した方がいいといっても、紙文書での保管となると倉庫・保管室・保管庫等の保管場所の確保にコストがかかります。また、編集履歴を残しながらの文書保管は、人手に頼ることになり、抜け・漏れが起こりやすく、管理の徹底は困難です。
このような紙文書のデメリットをカバーするために、国内企業が紙文書を電子化して保存することを認めたe文書法が2005年に施行されました。
この法律の施行により、定款や規約など永久的に保管したい書類は、電子化して保存することができるようになっています。
「永久的に保管した方がいいといっても紙文書を管理しきれない」という方は、顧問税理士や弁護士等の士業の方に確認しながら、文書の電子化を進めるのもよいでしょう。
まとめ
今回は人事・労務関係に関わる文書保管期間を、法律で定められた根拠をみながら見てきました。また、法律上で定められていない文書であっても「会社の運営上必要」とみなされる文書については、永久的に保存が必要であり、電子化できるものも複数あることを紹介させて頂きました。
改めて法律上の定めや重要文書の意義を見直すことで、自社にとって有益な文書保管を心掛けて頂けたらと思います。
※各文書の保管期間に関する詳細は関連省庁等にお問い合わせください
編集部おすすめ情報
社内のハンコ文化はこんなに損?!文書業務はDXで今すぐ効率化
社内文書を電子化した場合のメリット をご紹介!
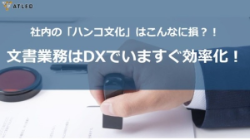
なぜ社内文書にハンコが必要なのか?そして社内文書を電子化するとどんなメリットがあるのか?
本書では時代と共に変化している「ハンコ文化」の背景や必要性。そして社内文書を電子化した場合のメリットなどを紹介しています。
ぜひ自社の課題改善にお役立てください。
資料詳細はこちら
■参考サイト
経費精算で領収書に必要な記載事項|保管方法や計上できる費用について徹底解説
必要なのは経理部だけじゃない? 知っておきたい会計・経理関係の書類保管について
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -
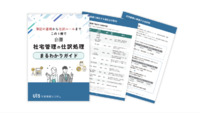
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -
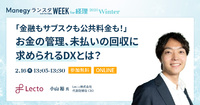
お金の回収を頑張らない時代へ!DXで変わる管理と回収の新常識【セッション紹介】
ニュース -

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応
ニュース -
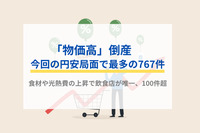
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
ニュース -
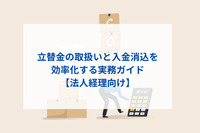
立替金の取扱いと入金消込を効率化する実務ガイド【法人経理向け】
ニュース -
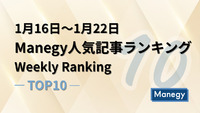
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース