公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
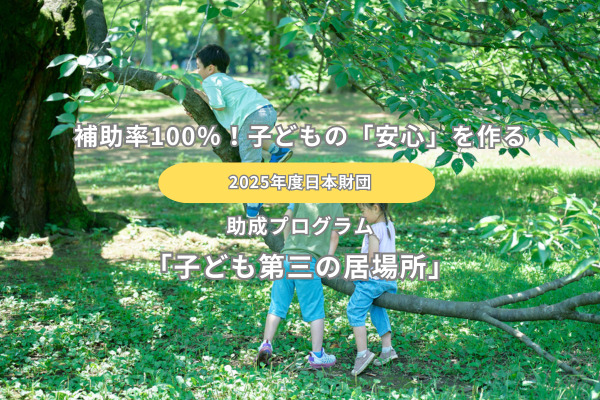
子どもたちが安心して過ごせる居場所として、「第三の居場所」「サードプレイス」の設置が進んでいます。子どもたちの「今」と「未来」を支えることは、大人世代の責任です。国内外の社会課題解決に取り組むNPOの事業への資金助成を行う日本財団では、第三の居場所の普及を促進するため、2025年度も「子ども第三の居場所」助成事業を設置しました。
今回は、日本財団の「子ども第三の居場所」助成事業の内容や申請方法をお伝えします。
キャッシュレス決済の導入では、業務効率の向上が大きなメリットのひとつです。現金管理の手間が軽減されるだけでなく、売り上げデータなどの管理も容易になります。
また、決済スピードが上がることで、利用者の待ち時間が短くなったり、回転率が上がったりすることも期待されます。さらに若者や外国人観光客といった、キャッシュレス決済に慣れた顧客層の取り込みにもつながります。
キャッシュレス決済の導入は、時代の流れに乗った経営戦略に、もはや欠かせないものとなりつつあるのです。
家庭の抱える困難は複雑・深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、子どもが孤立するケースが後を絶ちません。特に放課後の時間に、家庭や学校以外で、子どもたちが安心して過ごせる場として設置されているのが「子ども第三の居場所」です。2024年7月末時点で、全国に233の拠点があります。 (日本財団:子ども第三の居場所)
子ども第三の居場所では、健康を支える食事や正しい生活リズムの構築、学習サポートまで、子どもに必要なあらゆる支援が行われています。また、個別相談を通じて保護者にも日常的なフォローを行うなど、包括的な「居場所」としても機能する場所です。子どもの抱える困難は、外からは見えにくいことが多い問題です。必要な支援につながれず、苦しい思いをしている子どももたくさんいます。関係機関が連携して子どもの状況を共有し、支援につなげるアウトリーチが必要です。
「子ども第三の居場所」は、学校や地域、専門機関と積極的に連携し、「誰一人取り残さない地域子育てコミュニティ」のハブとしての機能も担います。日本財団では子ども第三の居場所を通じて、地域、行政、NPO、市民、企業、研究者と協力し、「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会を目指しています。

日本財団:子ども第三の居場所
日本財団では、「子ども第三の居場所」助成事業として、各地域で「子ども第三の居場所」の開設・運営を希望する団体を支援しています。まずは「子ども第三の居場所」助成事業の概要を見ていきましょう。
対象となるのは、日本国内で以下の法人格を取得し、非営利活動・公益事業を行う団体です。
記事提供元

補助金ポータルは、補助金・助成金などの最新公募情報などをわかりやすく説明し、またカテゴリ毎にまとめて情報を発信していく補助金・ 助成金専門の国内最大級の公的支援メディアです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

生成AI時代の新しい職場環境づくり

経理業務におけるスキャン代行活用事例

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
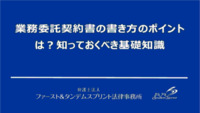
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
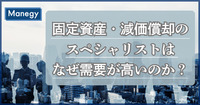
固定資産・減価償却のスペシャリストはなぜ需要が高いのか?(前編)

従業員サーベイの動向ー定期実施は5割弱、そのうち年1回以上の実施が8割超ー

【累計視聴者92,000人突破!】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』2月に開催決定!

税務・会計業務で使える生成AI実践セミナー【セッション紹介】
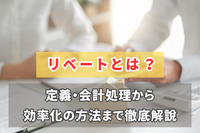
リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説
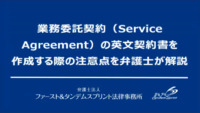
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
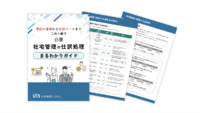
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
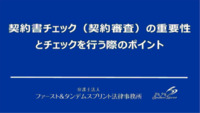
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

子どもが生まれた正社員に最大100万円を支給。大和ハウスグループの若松梱包運輸倉庫が「次世代育成一時金」を新設
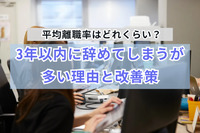
平均離職率はどれくらい?3年以内に辞めてしまう人が多い理由と改善策
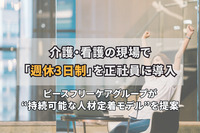
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
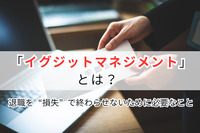
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと
公開日 /-create_datetime-/