公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
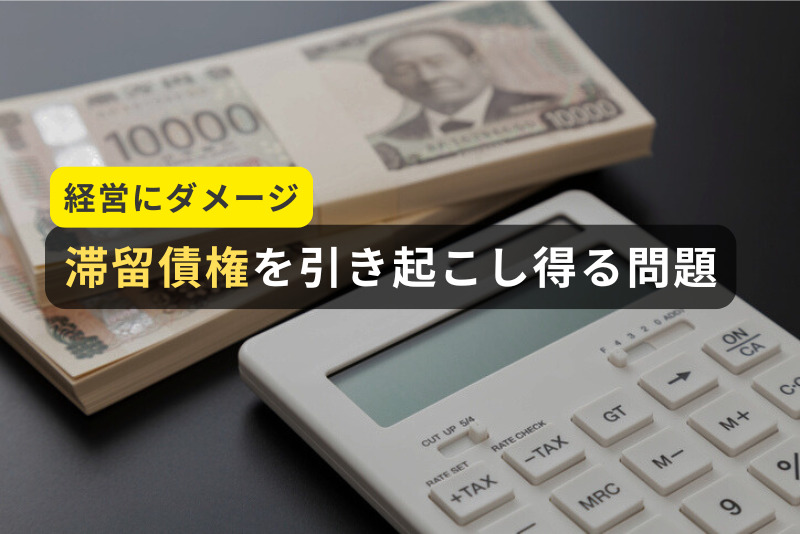
取引先からの支払が期日までになされない場合に発生する「滞留債権」。
事業を続ける上で避けられない問題のため、「滞留債権をどのように管理すべきか」「間違った督促を避けるには」などと悩む企業も少なくないでしょう。
今回は、滞留債権を引き起こし得る問題や、その対処法について解説します。
多くの企業にとって、「売上を伸ばす」ことは大きな目標です。特に起業から間もない時期は、売上に直結する「営業」や「企画」など、いわゆるフロントオフィスの人員や業務フローの改善に注力することでしょう。
一方で、「総務」や「経理」などのバックオフィスは、事業に欠かせない業務であるにも関わらず、「事業が成長した”後に”改善しよう」と考えられがちです。
たとえば社員数10人未満のスタートアップなど、これから取引先を開拓していくステージの企業の場合、「とりあえず税務申告に必要な経理で十分」と考え、Excelなどを用いて、手作業による人海戦術で経理業務を回す場合もあるでしょう。
しかし、企業は常に成長過程にあるため、いったん後回しにした経理業務の改善に、いつまでたっても着手できないということになりがちです。結局、経理業務を本格的に見直すのは、企業がある程度成長し、会計士の監査や株式上場の審査をクリアする必要に迫られ、初めて着手するということにもなりかねません。
このように経理業務の改善を後回しにすることは、企業の成長を長い目で見ると、決して賢い選択とは言えないのです。
商品やサービスを販売したのに、期日を過ぎても入金を確認できない。こうして発生する「滞留債権」は、売主側としてはできる限り避けたいものです。しかし、事業の成長と取引先が多くなると、請求書の発行数も増えるため、滞留債権が生じるリスクがどうしても高まってしまいます。
では、なぜ支払遅れが発生してしまうのでしょうか?その理由の多くは”うっかりミス”です。毎月、何十件、何百件という取引件数になると、請求書の見落としや支払期日の勘違いなどが生じがちです。企業によっては「複数の請求書に対してまとめて支払う」といった独自ルールもあるため、売主側に一時的に滞留債権が発生してしまうのです。
うっかりミスは”売主側”にも起きる可能性があります。請求に対する入金をチェックする「入金消込」の遅れや見落としから、本当は期日以内に支払われているにも関わらず、滞留債権として扱ってしまうこともありえるでしょう。
では、滞留債権はどのような問題を引き起こすのでしょうか?
複数の可能性がありますので、順を追って説明します。
記事提供元

株式会社アール・アンド・エー・シー
R&ACは創業から2024年で20周年を迎え、長きに渡り入金消込業務を中心とした入金消込・債権管理システム「Victory-ONEシリーズ」の開発に特化してきました。2024年に累計導入実績1,500社を突破した導入実績No.1の「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
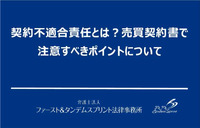
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

サーベイツールを徹底比較!

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
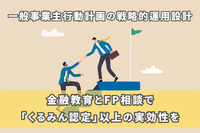
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

令和7年度 税制改正のポイント

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
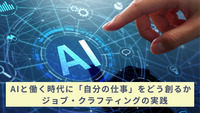
AIと働く時代に「自分の仕事」をどう創るか —ジョブ・クラフティングの実践
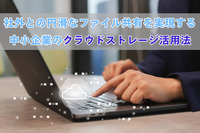
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理
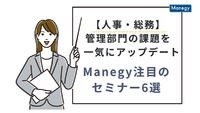
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選

クラウドストレージの安全な導入ガイド
公開日 /-create_datetime-/