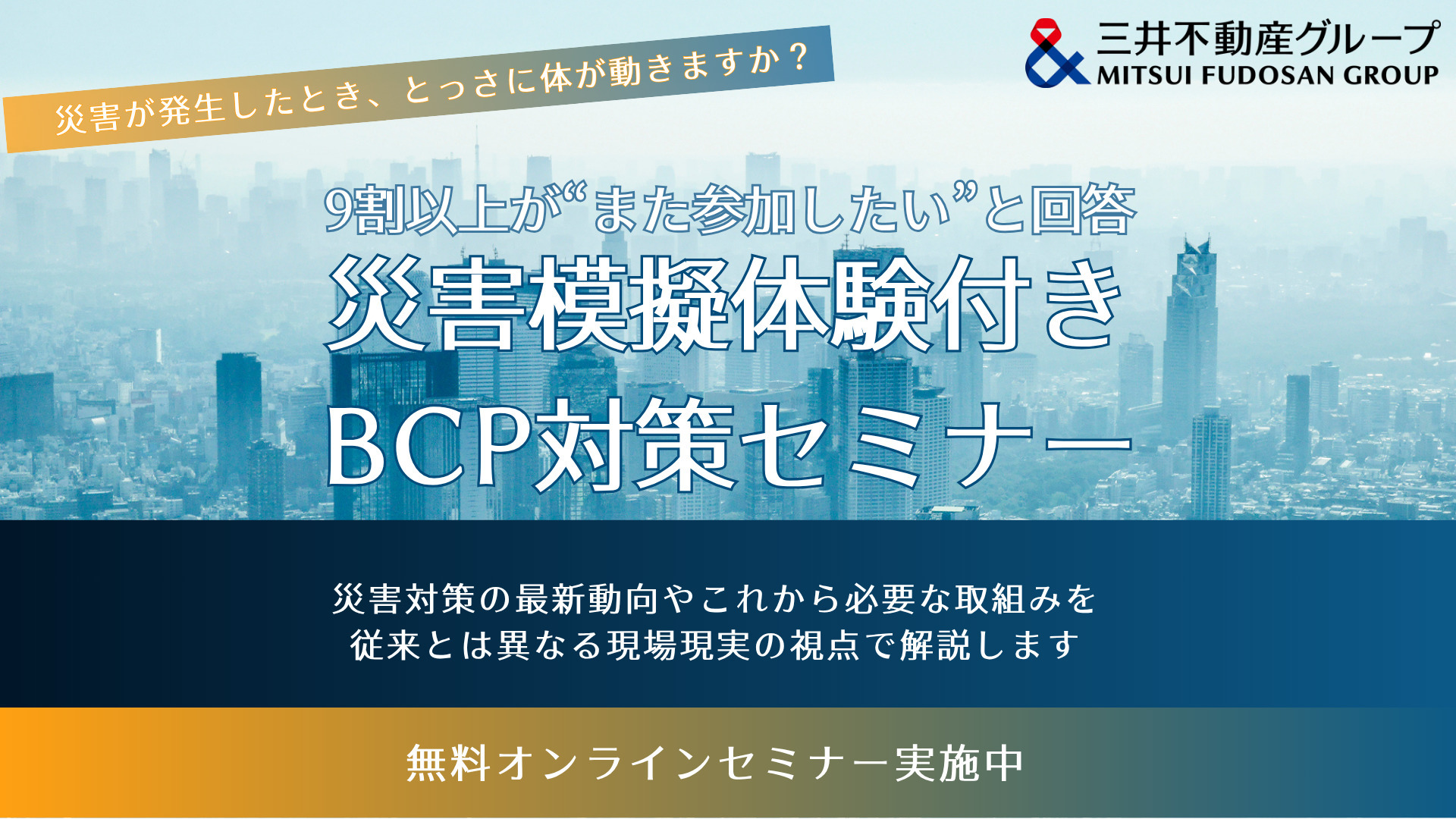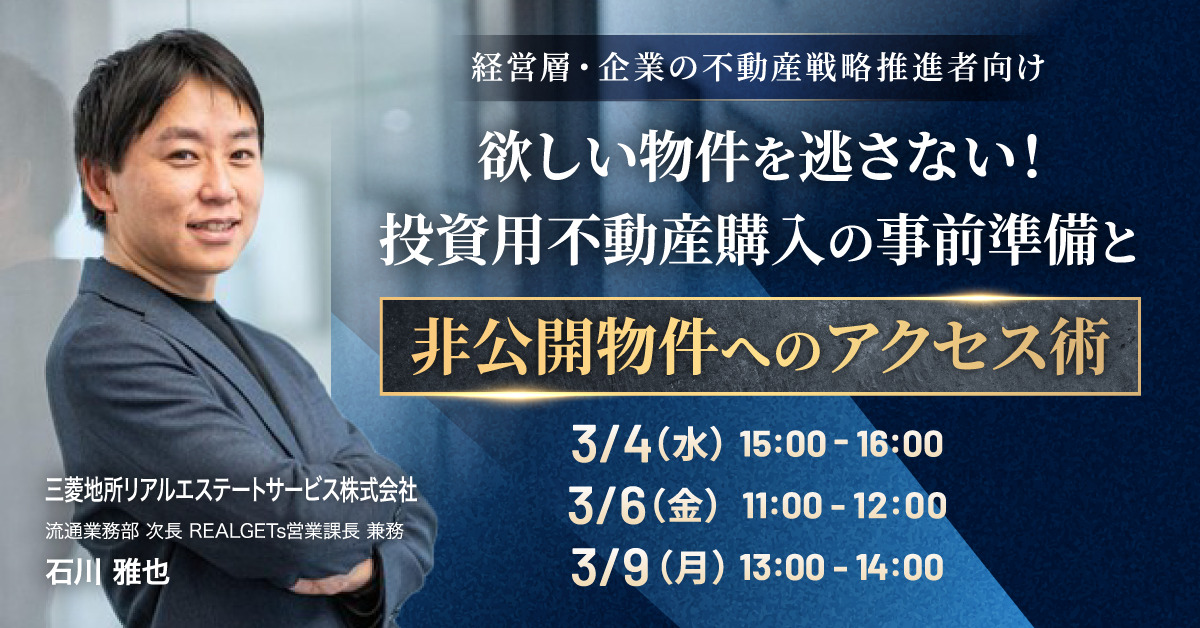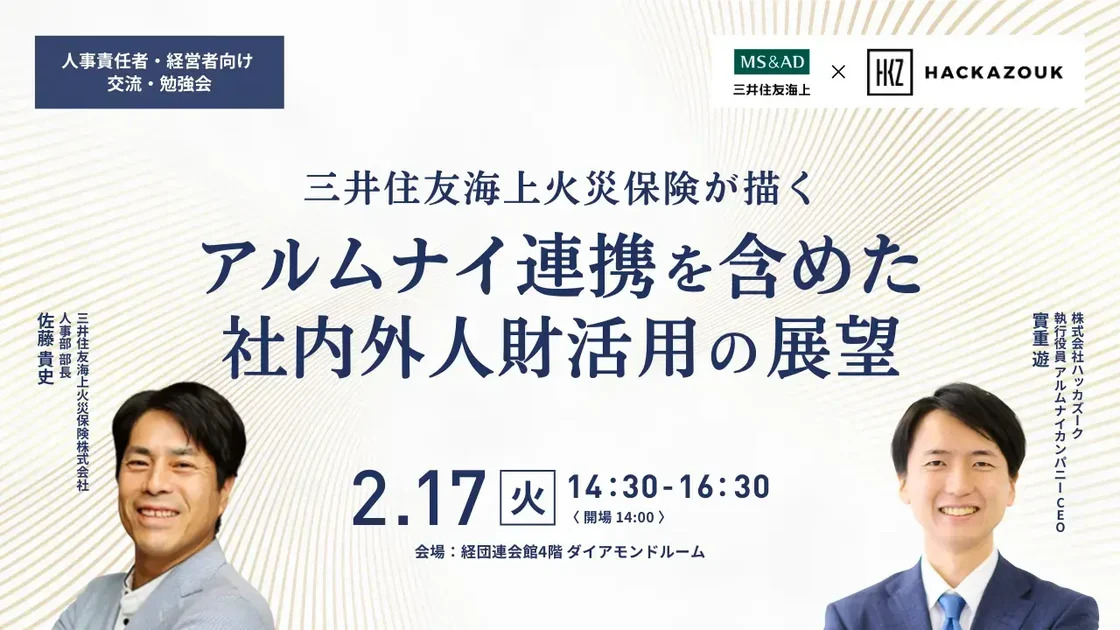公開日 /-create_datetime-/

天皇陛下が2019年4月末に退位され、5月1日に皇太子殿下が新天皇に即位されます。これに先立って4月1日には「令和」という新元号が発表され、マスコミを始め日本中がその話題でもちきりとなりました。
では、なぜ即位の日、つまり新元号の改元日が、新年を迎える1月1日や新年度の開始月である4月1日ではなく、5月1日とされたのでしょうか。
今回は、改元が5月1日となった理由について紹介します。
目次【本記事の内容】
生前退位が行われるのは憲政史上初、200年ぶり
皇位の継承に関しては、1947年(昭和22年)に定められた「皇室典範」において規定されています。ただ、皇室典範の中には生前退位に関する規定は盛り込まれていません。そのため、天皇陛下の退位、新天皇の即位を行うにはまず法改正が必要となりました。
天皇陛下は2016年8月に、退位のご意向を示すビデオメッセージを国民に向けて公表されましたが、翌2017年6月に、生前退位について取り決めた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が制定されます。天皇が生前中に退位するのは約200ぶりのことで、明治、大正、昭和と続いた日本の憲政史上において始めてのことです。
改元日が1月1日とならなかった理由
政府官邸は当初、国民生活への配慮と政治日程の状況を踏まえて、2018年末に新天皇が即位され、2019年の元旦を改元日にするとの案を考えていました。年が変わると同時に改元が行われれば国民にとって分かりやすく、区切りも良いからです。
しかし、年末年始は皇室の重要な行事が続くことから、宮内庁側が強く反発。また、昭和天皇が崩御されてから30年目となるため、陛下がご自身で30年式祭などの儀式を執り行いたいとのご意向もあり、1月1日は対象から外されることとなりました。
改元日が4月1日にならなかった理由
国民への影響を減らすという点では、新年度が始まる4月1日が最も望ましい選択肢の一つといえるでしょう。国や企業の会計年度は4月開始のケースが多く、学校も4月に入学、学年変更が行われるので、業務上、生活上の観点からすると、新年度に合わせて改元が行われれば何かと都合が良いわけです。実際、宮内庁側は、「2019年3月31日に天皇陛下が退位し、4月1日に新天皇の即位、そして改元を行う」という案を持ち、政府側に提示しています。
しかしこの点については、官邸側が難色を示しました。ちょうど統一地方選挙が行われている最中であり、また予算成立に向けて政府・国会が忙しくなるため、改元に伴う行事に力を入れられないというのがその主な理由だといわれています。天皇陛下が退位される際は「退位礼正殿の儀」、新天皇が即位されるときは「剣璽等承継の儀」、「即位後朝見の儀」、「即位礼正殿の儀」など多くの儀式・国事行為が行われるため、政治的に多忙な時期と重なることは避けたいという思いがあったのでしょう。
なぜ改元日が5月1日に定められたのか?
最終的に政府は、大型連休により国民が落ち着き、「昭和の日」の直後という点で一つの区切りになるという観点から、政府は第三案ともいえる「5月1日」を新天皇即位の日および改元の日と定めます。それに伴い、政府は改元が行われる5月1日を「天皇の即位の日」として新たに祝日にすることを決定しましたが、これにより、今年についてはその前後の日である4月30日と5月2日も休日となりました。これは「国民の祝日に関する法律(いわゆる祝日法)」における「祝日に挟まれている平日は休日とする」という規定に基づくもので、結果として今年のゴールデンウィークは10連休となったのです。
これだけ休みが長いと、国民はマスコミが報じる新天皇即位と改元に対するニュースを連日見る時間ができ、祝福ムードはより高まると期待できます。また、まとまった休みを利用した国内観光地への旅行者が増えるので、経済効果も大きいです。今年の10月に行われる消費増税によって、その後に消費の落ち込みが生じる恐れもあり、10連休によって消費を底上げしておくことは、日本経済にとってメリットだといえるでしょう。さらに休日中なので、元号を用いたシステムの改修による国民への影響が少なく、混乱を抑制できるという効果もあります。
5月1日を新天皇即位の日・改元日とすることにはデメリットも
一方で、改元日を5月1日とすることにはデメリットも少なくありません。1日が祝日となって10連休になり、観光地に向かう人が増えると、避けられないのが交通渋滞です。また連休中は医療機関が休みとなるので、適切な医療サービスを受けられない「医療難民」の発生が懸念されます。ほかにも、銀行窓口が長期にわたって休業すること、あるいは小売業における仕入れの困難や人手不足など、問題点は多いのも実情です。
まとめ
天皇陛下の退位、皇太子殿下の新天皇即位、そして新元号への改元については、年始案や年度初め案も政府、宮内庁で検討されていました。しかし、宮内庁側、政府側それぞれの意向があり、最終的に、連休中で国民の関心を集めやすい上に元号改元による混乱が小さく、経済面でも大きなメリットが期待できる5月1日に決定されたわけです。
5月1日となったことで、10連休という大型連休になった反面、交通渋滞や医療難民発生の危惧などの問題もあります。実際に問題に直面する前に、早い段階から対策を採っておくことが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

「ピアコーチング」で横のつながりを強め、組織パフォーマンスに結びつけていく方法とは
ニュース -

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう
ニュース -

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜
ニュース -

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順
ニュース -
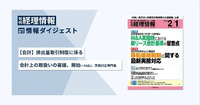
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース