公開日 /-create_datetime-/
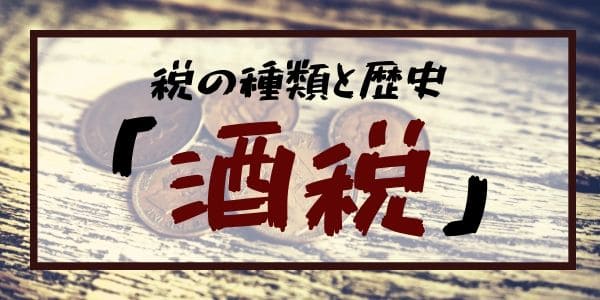
仕事帰りにキュッと飲む一杯のビールを楽しみにしているビジネスパーソンも多いでしょう。しかし、ビールは酒の中でも一番税率が高く、約4割が税金であることをご存知でしょうか。もちろんビールだけでなく、それ以外のお酒にもそれぞれ税金はかけられています。
花見で飲んだビールも、歓送迎会で傾けた徳利も、税金を飲み干していたのかと思うと悪酔いしそうですが、今回は、酒税について取り上げてみました。
酒税の税率はお酒の種類とアルコール度数
お酒には、酒税という名の税金がかけられています。酒税法により、アルコール分1%以上の酒類に課せられており、そのうえに消費税もプラスされています。
酒税を納めるのは酒類を製造する業者や販売業者ですから、お酒を飲むにしても買うにしても、税金を負担していることをそれほど意識することはありません。
しかし、税負担を少しでも軽減するために、発泡酒や第3のビールなどが続々と登場したこともあって、消費者の側にも酒税に関する意識が、否が応でも高まってきています。
酒税の税率は、お酒の種類(酒税法では、お酒の種類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類と17品目に分けています)と、アルコール度数によって、アルコール分ごとに1キロリットル当たりの税率が酒税法で決められています。
しかし、ビールや果実酒は、アルコール度数にかかわらず定額となっているため、他の酒類よりも税額が高く設定されているのです。
発泡酒・第3のビールが生まれた背景は酒税
平成24年度の酒税の総額は1兆3,496億円ですが、そのうち酒類の中で一番税率が高いビールが44%を占めています。
税金分がビールの販売価格にスライドするわけですから、当然、ビールの売り上げにも大きく左右することになります。ビールメーカーはその対抗手段として、税金が安くなる発泡酒や第三のビールを生み出したわけです。
しかし、政府にとっては、貴重な財源です。ビールの税収をなんとしても確保しておきたいところでしょう。そこで、平成29年度の「税制改正大綱」で、10年間で、ビール・発泡酒・第三のビールの税率を一本化する方針を示しましたが、当然、大きな波紋が広がっています。
では、酒類の中でビールの税額がなぜ高いのでしょうか。それを知るためには、酒税の歴史を振り返る必要があります。
酒税の始まりは室町時代
酒税は、お酒の売買が盛んになった室町時代、酒造業者に課せられたのが始まりのようです。江戸時代になり、幕府は、酒造株制度によって、今でいう酒税を徴収していたそうですが、思い通りに税収が上がらないことから、新たに“酒運上”を設けました。
酒運上とは、「造り酒屋の営業税」と「酒造株」という「免許」の発行手数料ですが、価格の5割という高いもので、酒造業者は生産を控え、お酒の値段も高騰したことから、これまた幕府の思惑とは裏腹に、思うように税収アップとはならなかったそうです。
江戸幕府から明治政府となり、地租改正条例によって税体系が整備されていきますが、お酒の税金は、時の政府がどうしても手放したくなかったようで「酒類税」として残り、現在の酒税法の元となっています。
ビールの税率は日本酒のおよそ5倍
酒類の製造免許は明治28年(1895)、販売免許は昭和13年(1938)に制度化され、昭和28年(1953)に酒税法が制定されています。
もちろん、この間何度も改正され、増税が行われてきたことは言うまでもありません。ちなみに、明治20年代後半から30年代前半には、国税に占める酒税の割合は3割から4割を占めるようになり、国税税収のトップになりましたが、現在は3%程度に落ち込んでいます。
さて、ビールの税率ですが、日本酒と比較するとおよそ5倍です。その理由は、日本にビールが輸入されたのは明治3年(1870)で、いわゆる舶来品、高級品、贅沢品といった扱いだったからのようです。
ちなみに、明治8年(1875)の酒類税則では、酒造営業税と酒精請売営業税、さらに醸造税が課されていました。課税対象となったのは清酒、濁酒、味醂などで、ビールは醸造税の対象外だったのですが、明治34年(1901)にビールへの課税が始まりました。
まとめ
酒税は間接税ですから、普段消費者は納税しているという意識は薄いでしょう。しかし、ビール類の税額が一本化されることになると、価格が安いことがウリの発泡酒や第3のビールが値上がりとなります。
会社での飲み会を仕切る幹事役にとっても、酒税の行方は気になるところではないでしょうか。
関連記事:税の種類と歴史を解説「消費税」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース



































