公開日 /-create_datetime-/

株式会社の根本的な経営方針や経営陣の人事を決定するのが、最高意思決定機関である株主総会です。株主総会は、定款や株式の変更、取締役の選任や解任をはじめ、さまざまな重要事項を決議する場です。
梅雨の時期になると、大企業の株主総会の様子が経済ニュースでよく取り上げられるのを目するため、「株主総会=6月」と思っている人も少なくないかもしれません。実は、6月に限らず1年中開催されている株主総会なのですが、集中する時期が決まっています。
この記事では、株主総会の役割を簡単におさらいするとともに、株主総会が集中する3つの月をお伝えします。
目次【本記事の内容】
株主総会は株式会社の経営を左右する
会社を動かしているのは社長や取締役など、一般的にイメージしやすい経営陣と思っている人が多くいるかもしれません。確かに、通常の実務の最高責任者はトップの経営陣であり、取締役会で経営全般や業務の遂行、監督や指示を日々行っています。
その一方、年に1度開催される株主総会では、会社のあり方や経営陣の人事、株式の売買や移動など、株主の利害関係に関わる重要事項が決められます。
パソコンで例えれば、取締役会は株式会社のソフト面を担当しているのに対し、株主総会はハード面やOSといった普段の業務からは目に見えない重要な部分に、大きな影響を及ぼしているのです。
株主総会は6月、5月、3月の順に集中する
株主総会とは、会社法の定めによって毎年開催されている定時株主総会を指します。定時株主総会は、決算に連動して開催されることが多く、年度末決算で決算期が3月に集中する日本では3ヶ月以内の5月や6月に開催されることが大半です。
これは、前年度の経営状況を報告しやすい点と合わせて、法人税の税務処理の関係も影響しています。
ちなみに、会社経営において重大かつ緊急性が高い問題が発生した場合には、経営陣は臨時で株主を招集します。これが臨時株主総会です。
臨時株主総会は、一般的に開催されること自体珍しいものの、いざ開かれる場合は企業の買収のような会社の存続に関わる重要事項の議決が行われます。
6月開催が多いのは3月決算のため
先程も触れたように、株主総会の開催は6月に集中することが多くなっています。これには、定時株主総会が開催される理由が決算と連動していることが挙げられます。
日本の企業の多くは、3月末を決算に設定しています。4月始まりで3月終わりという、日本の年度に合わせた対応であり、さらに商法では決算期に合わせ、毎年決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催するよう、株式会社に義務を負わせているからです。したがって、3月期決算である大企業の多くは、3ヶ月以内となる、6月下旬に定時株主総会を開催しているのです。
さらに、6月開催が多い理由としては、経理業務の必要性が大きく影響しています。決算に合わせて経理は5月に決算短信と有価証券報告書の作成を行う必要があり、財務局への決算書提出も加わります。
さらに、株主総会を招集する旨を株主に通知する必要があるため、その招集状の用意は発送を含めると6月下旬の開催なら滞りなく業務を行えるからです。
総会屋対策で6月開催が多いといわれる理由
高度経済成長期からバブル崩壊後しばらく、株主総会のニュースの度に総会屋の存在が大きく取り上げられていました。総会屋とは、株主総会の会場で脅迫めいた質問や議決事項にすべて反対するなど、議事の進行を妨げていた存在です。企業から金品や便宜を見返りに要求するために行っていたため、株主総会を開催する企業にとっては大きな問題でした。
そこで、業界内で自然と株主総会を6月下旬、しかもなるべく他社と同日に開催することで、総会屋の出席を分散させるようになっていきました。
現在では、総会屋の活動を禁止する法律が整備されて、取り締まりが強化されており、株主総会が6月開催に集中する理由としては過去のものとなっています。
流通・小売は5月開催が多い
6月の次に株主総会が多く開催されるのは5月です。5月はその3ヶ月前となる2月に決算を迎える企業が株主総会を開催します。
2月決算の企業が多いのは、スーパーや百貨店、コンビニなど流通業や小売業で、大企業から中小企業まで5月開催が続きます。また、株式非上場企業には5月開催のケースも少なくありません。これは、有価証券報告書の作成が不要なため、株主総会の招集までに3ヶ月を必要しないこと、招集通知の発送が1週間前で良いことなどが主な理由です。
12月決算の企業は3月開催
6月、5月の次に株主総会の開催が多いのは、3月です。これは、3月から3ヶ月遡った12月に決算期を設定している企業があるからです。
具体的に大手企業から例を挙げると、キャノンや山崎製パン、不二家などが並びます。
まとめ
ここまで見て来たように、株式会社は決算後3ヶ月以内に経理業務と連動して株主総会を開催する義務があることから、決算期から3ヶ月後の時期が集中する6月開催がもっとも多くなっています。ちなみに、流通・小売など業種によっては5月や3月の開催も多いため、業界や業種による違いも押さえておかなければなりません。
こうした流れを知っておくことで、必要な情報が得やすくなります。関連する企業の、株主総会の時期は、把握しておくようにするのが良いでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -
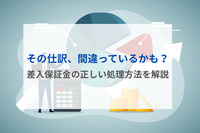
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計
ニュース



































