公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
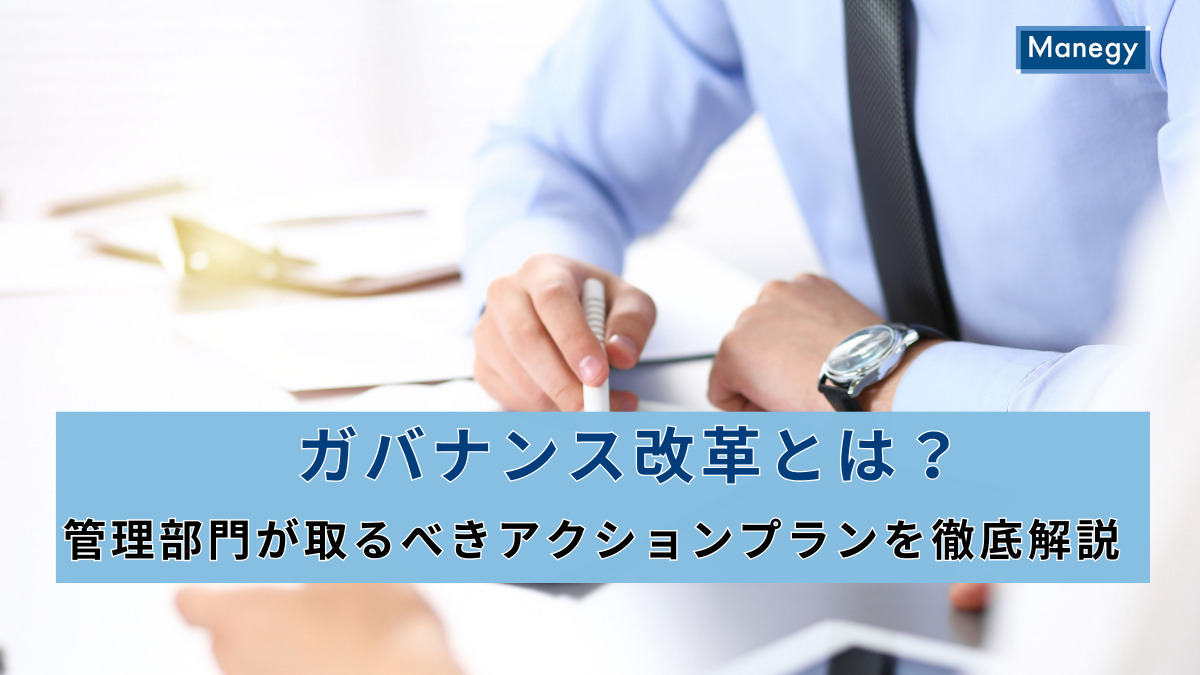
「経営陣の交代」「株主提案の可決」「事業売却」といったニュースが、近年頻繁に報じられています。
これらは、企業経営に積極的に意見を述べる「物言う株主」(アクティビスト)の影響力が強まっていることの表れです。
彼らは企業の将来性や経営のあり方を厳しく評価し、変革を求めています。
この「ガバナンス改革」の波は、もはや経営層だけのものではありません。
会社の屋台骨を支える管理部門、特に経理・人事・総務・法務といった部署の実務そのものを大きく変えようとしています。
外部からのプレッシャーに対応し、経営の透明性を高めるためには、管理部門が受け身ではなく、自ら能動的に動くことが不可欠です。
この記事は、ガバナンス改革の基本から、なぜ今この動きが加速しているのか、そして各部門が具体的に取るべきアクションプランまで、分かりやすく解説します。
ガバナンス改革を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「コーポレートガバナンス」という言葉です。
ニュースや企業のIR資料などでよく使われますが、具体的に何を意味するのか曖昧に感じている方も少なくありません。
ここでは基本的な定義と目的を整理したうえで、日本の企業が取り組むべき指針である「コーポレートガバナンス・コード」について解説します。
コーポレートガバナンスとは、日本語で「企業統治」と訳されます。
簡単に言えば「会社を健全かつ効率的に運営するための仕組み」のことです。
企業には経営陣と株主、従業員、取引先、地域社会など、さまざまな利害関係者(ステークホルダー)が関わっています。
そのため、経営陣が独断的に判断を下すと、不正や不祥事、株主の利益を損なうような事態につながりかねません。
コーポレートガバナンスの目的は、こうしたリスクを防ぎつつ、透明性の高い意思決定を行い、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することにあります。
具体的には、取締役会や監査役によるチェック機能の強化、社外取締役の導入、経営情報の適切な開示といった取り組みが代表的です。
つまり、ガバナンスは「経営の暴走を防ぐブレーキ」であると同時に「企業を成長に導くアクセル」の役割も担っています。
日本企業がガバナンスを整備する際の基準となるのが、金融庁と東京証券取引所が策定した「コーポレートガバナンス・コード」です。
これは上場企業に対して「どのような仕組みを整えるべきか」を示した原則集であり、法的な強制力はありませんが、上場企業はその遵守状況を開示することが求められています。
ガバナンス・コードは2015年に導入され、その後も社会や投資家のニーズに合わせて改訂されてきました。
たとえば2021年の改訂では、取締役会の機能強化やサステナビリティ(持続可能性)への対応が盛り込まれています。
特に近年は、女性や外国人、企業外の専門人材など多様性を重視した取締役の登用が強く求められるようになりました。
このように、コーポレートガバナンス・コードは日本の上場企業にとって「最低限守るべき基準」であると同時に、「企業価値を高めるための道しるべ」として位置付けられています。
管理部門の担当者にとっても、今後の実務を考えるうえで避けて通れない重要なキーワードといえるでしょう。
最近、日本企業の間でガバナンス改革の動きが加速している背景には、主に以下の3つの大きな潮流があります。
これらの変化は、外部からの圧力だけでなく、企業が自ら成長するためのエンジンとしても捉えられています。
近年、日本の株式市場における海外投資家の存在感は非常に大きくなっています。
彼らは、日本の企業が持つ「稼ぐ力」をより引き出すことを強く期待しており、そのために経営陣に対して積極的に意見を述べるようになりました。
特に注目すべきは「物言う株主」(アクティビスト)と呼ばれる存在です。
彼らは、単に株価の上昇を待つだけでなく、経営陣の交代や不採算事業の売却、大規模な自社株買いなどを株主総会で提案し、経営に直接的な影響を与えようとします。
【事例】
・東芝:過去には、海外の複数のファンドから経営改革や事業の分離を求められ、最終的に非公開化に至るという大きな動きがありました。
・セブン&アイ・ホールディングス:一部の株主から、中核事業であるコンビニエンスストア事業に集中するため、百貨店事業などの売却を求める提案が出されました。
こうした事例からもわかるように、株主の声が経営を直接動かす時代になったことが、ガバナンス改革を後押しする大きな要因となっています。
以前は、投資家が企業の価値を判断する際、売上や利益といった財務情報が中心でした。
しかし、近年はそれだけではなく、E(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)への取り組みを重視する傾向が強まっています。
これを「ESG投資」と呼びます。
・E(Environment):環境への配慮(例:脱炭素への取り組み、再生可能エネルギーの導入)
・S(Social):社会への貢献(例:多様な人材の活用、働きやすい職場づくり)
・G(Governance):企業統治(例:透明性の高い経営、適切なリスク管理)
投資家は、これらの取り組みが企業の持続的な成長に不可欠だと考えています。
環境問題や社会課題に真剣に向き合い、ガバナンスを強化している企業は、長期的に安定して高いリターンを生み出すと評価されるため、多くの投資マネーが集まるようになりました。
日本のガバナンス改革を加速させているもう一つの大きな要因は、東京証券取引所(東証)による市場改革です。
東証は、海外の主要な市場と比べて、日本企業全体の「稼ぐ力」が低いと指摘してきました。
その象徴がPBR(株価純資産倍率)です。
PBRは、企業の純資産に対して株価が何倍になっているかを示す指標で、一般的に1倍を下回ると「会社の価値が純資産を下回っている=成長が見込めない」と判断されます。
東証は、PBRが1倍を下回る企業に対し、株価を向上させるための具体的な経営改善策を開示するよう強く求めました。
この動きは、多くの企業が抜本的な経営改革に着手するきっかけとなり、ガバナンス強化の取り組みをより一層加速させています。
ガバナンス改革は、経営層だけの仕事ではありません。
日々の業務を通じて、企業の基盤を支えている管理部門の行動こそが、改革の成否を左右します。
ここでは、各部門が具体的に取り組むべきアクションを解説します。
経理・財務部門は、企業の「お金」の流れを管理する、いわば経営の心臓部です。
ガバナンス改革において、この部門に求められるのは、単に正確な決算書を作成するだけでなく、企業価値向上に貢献する「攻め」のIR(投資家向け広報)と、株主が安心して投資できる透明性の高い情報開示です。
【具体的なアクションプラン】
財務情報の「見える化」:決算短信や有価証券報告書はもちろん、投資家が知りたい情報を、グラフや図を多用して分かりやすく開示します。
非財務情報の開示強化:ESG投資の観点から、環境への取り組み、従業員の働きやすさ、女性役員の比率など、財務諸表には現れない情報も積極的に開示します。
投資家との対話のサポート:IR担当者と連携し、投資家からの質問に迅速かつ丁寧に答えられるよう、根拠となるデータや情報を整理しておきます。
人事部門は、企業の成長を支える「人」の戦略を担います。
ガバナンス改革では、特に経営陣の人選と、企業全体の「多様性」の確保が重要な役割となります。
【具体的なアクションプラン】
役員人事の透明性向上:取締役の選任理由や、報酬の決定プロセスを明確化し、社外取締役が適正に機能する体制を整えます。
多様性のある人材登用:女性や外国人、中途採用者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に登用します。
従業員満足度調査の実施と開示:従業員の意見を吸い上げ、働きがいのある職場づくりを進めることで、組織の健全性を高め、投資家へのアピールポイントにもします。
総務部門は、株主総会の運営や株主とのコミュニケーションを担う「株主の窓口」です。
ガバナンス改革の潮流の中で、株主総会は単なる儀式ではなく、株主との重要な対話の場へと変化しています。
【具体的なアクションプラン】
株主総会のデジタル化:オンラインでの参加や議決権行使を可能にし、より多くの株主が参加しやすい環境を整備します。
「バーチャルオンリー株主総会」の開催検討:リアル会場を設けず、オンラインのみで株主総会を開催する方法も検討対象です。
株主との日常的な対話:株主からの問い合わせに迅速に対応し、議決権行使助言会社との対話を通じて、株主総会での混乱を未然に防ぎます。
法務・コンプライアンス部門は、企業活動が法律やルールに則って行われるようチェックする役割を担います。
ガバナンス改革では、経営の監視機能である取締役会の実効性を高め、あらゆるリスクを事前に察知する体制を構築することが求められます。
【具体的なアクションプラン】
取締役会の議事録作成・情報提供の高度化:取締役が適切な意思決定を行えるよう、会議に必要な情報を事前に、かつ分かりやすく提供します。
コンプライアンス研修の徹底:全従業員に対し、不正や不祥事を未然に防ぐためのコンプライアンス研修を定期的に実施します。
内部通報制度の整備と周知:不正行為を早期に発見できるよう、従業員が安心して通報できる窓口を設置し、その存在を周知徹底します。
ガバナンス改革は、まだ多くの担当者にとって馴染みの薄いテーマかもしれません。
ここでは、読者の皆さまから寄せられることが多い質問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
A. はい、大いに関係があります。
コーポレートガバナンス・コードは上場企業向けの指針ですが、その考え方自体は非上場の中小企業にとっても非常に重要です。
たとえば、後継者への事業承継をスムーズに進めるためには、家族経営であっても経営の透明性を高めておく必要があります。
また、金融機関からの融資や取引先との信頼関係を築く上でも、適切なリスク管理やコンプライアンス体制は不可欠です。
中小企業こそ、ガバナンスを意識することで、より盤石な経営基盤を築くことができます。
A. 社外取締役は、会社と利害関係のない第三者の視点から経営をチェックする役割を担います。具体的には、
・経営の監視:経営陣の意思決定が適切か、客観的な立場で厳しくチェックします。
・助言:外部の豊富な経験や知見を活かし、経営戦略や事業課題について助言します。
・経営陣の選任・報酬決定:経営陣の人事や報酬が適切であるかを、公平な立場で評価します。
このように、社外取締役は経営の健全性を保ち、企業の信頼性を高める上で非常に重要な存在です。
A. まずは、ガバナンス改革が「外部からの圧力」ではなく「企業価値向上のためのチャンス」であることをデータや事例を用いて説明しましょう。
たとえば「PBRが1倍割れのままでは投資家から評価されず、資金調達が難しくなる可能性がある」といった具体的なリスクを提示することが有効です。また、他社の成功事例を共有したり、経理・法務・総務など各部門の連携を通じて、ボトムアップで変革の機運を高めることも重要です。
A. コーポレートガバナンス・コードは法律ではないため、違反しても罰則はありません。
しかし、東証が定めるルールに基づき、コードに従わない場合は、なぜ従わないのかを株主や投資家に対して説明する義務があります(コンプライ・オア・エクスプレイン原則)。
この説明が不十分だったり、正当な理由がないと判断された場合、企業の信頼性が損なわれ、株価が下落したり、投資家から見放されたりする可能性があります。
罰則がなくても、事実上の「ペナルティ」を受ける可能性があるため、多くの企業がコードの順守に努めています。
ガバナンス改革は、しばしば「コンプライアンス遵守」「外部からの圧力」といった「守り」の側面で語られがちです。
しかし、この記事を通して見てきたように、それは単なる守りではなく、経営のあり方を根本から見直し、企業価値を磨き上げていくための「攻め」の経営改革に他なりません。
そして、その改革の成否は、外部からの要請をただ待つだけでなく、日々の実務を通じて経営基盤を支えている管理部門の主体的な関与にかかっています。
経理・財務部門は攻めの情報開示で投資家との信頼を築き、人事部門は多様な人材戦略で組織を活性化させる。
総務部門は株主との対話を深め、法務・コンプライアンス部門は盤石なリスク管理体制を構築する。
ガバナンス改革は、管理部門が受け身の立場を脱し、自社の未来を創る「変革の担い手」へと進化する絶好のチャンスです。
この記事を読んだ方にオススメ!

管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
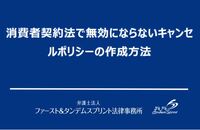
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
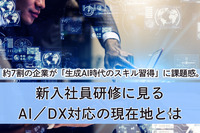
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは

2026年の展望=2025年を振り返って(13)

「退職金制度」の導入・見直しタイミングを解説

YKK AP、“社員幸福経営”に向けた新人事戦略「Architect HR」を策定。モノづくりの思想を人事に応用し、自律型人材と持続的成長の実現へ

「インシビリティ」が組織を蝕む。“微細な非礼”の悪影響と防止法を解説

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
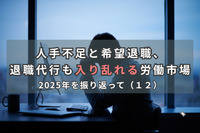
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

専門人材向けに「ジョブ型人事制度」を本格導入した三井住友カード。“市場価値連動型”の評価・処遇でデジタル人材獲得へ

事業再生を取り巻く環境の変化=2025年を振り返って(11)
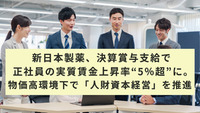
新日本製薬、決算賞与支給で正社員の実質賃金上昇率“5%超”に。物価高環境下で「人財資本経営」を推進

外注と業務委託の違いとは?契約形態や活用シーンをわかりやすく解説
公開日 /-create_datetime-/