公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
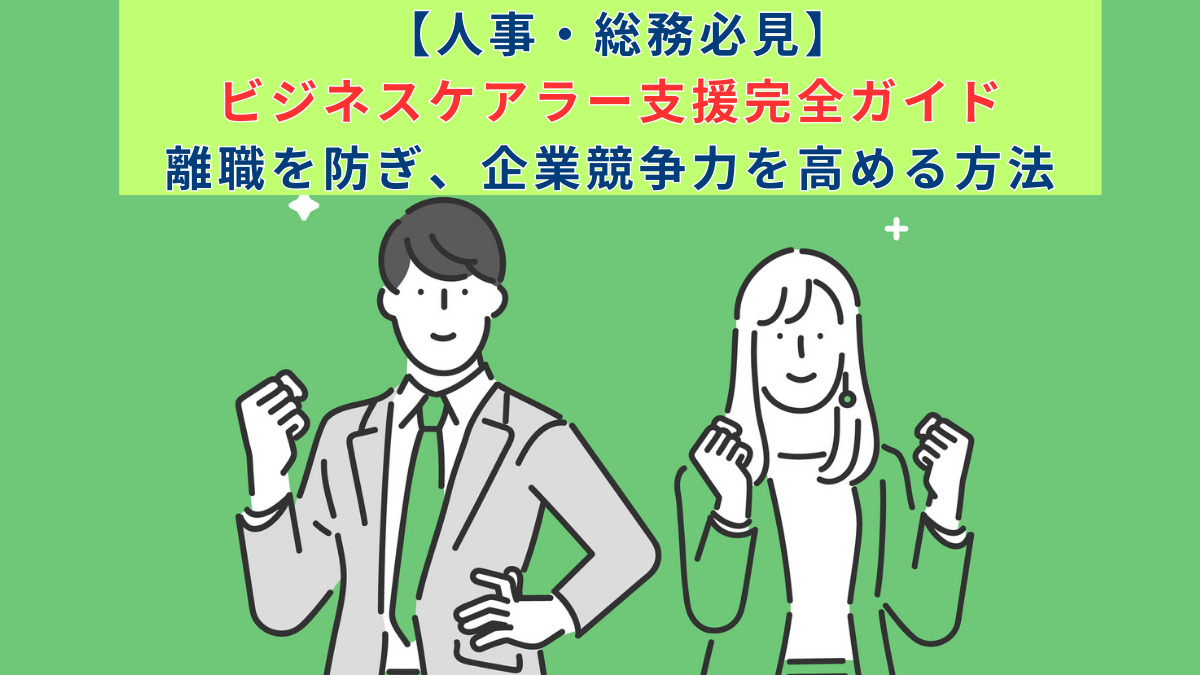
「優秀な中堅社員が、突然『親の介護で辞めたい』と申し出てきた…」――このような場面は、決して珍しいことではありません。
少子高齢化が進む日本において、介護は誰にでも突如として降りかかるリスクです。
しかも、育児と異なり「いつ始まるか予測できない」「終わりが見えない」という特性があり、企業にとって静かに進行する経営リスクとなっています。
この記事では、従業員の窮状に寄り添い、貴重な人材の離職を防ぐために、人事・総務部門が取り組むべき支援体制のつくり方を解説します。
日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、その影響は私たちの働き方にも大きな変化をもたらしています。
特に注目すべきは、仕事と家族の介護を両立する「ビジネスケアラー」の急増です。
経済産業省の推計によると、2020年には約262万人だったビジネスケアラーが、2030年には300万人以上に達すると予測されており、これは家族介護者全体の約4割に相当する規模です。
つまり、日本の労働力人口の約21人に1人が、介護を抱えながら働いている計算になります。
この問題がさらに深刻化しているのが、2025年です。
いわゆる「2025年問題」とは、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となることで、医療や福祉といった社会保障費の増大に加え、ビジネスケアラーの増加が加速すると予測されている社会課題です。
この「待ったなし」の状況は、企業にとって、もはや「他人事」では済まされない喫緊の経営課題として認識されるべきでしょう。
「ビジネスケアラー」とは、仕事を続けながら家族の介護を担う人を指します。
日本国内には推計で360万人以上のビジネスケアラーが存在するとされており、働く世代の介護負担は年々増加しています。
介護は1日数時間に及ぶこともあり、突発的な通院や入退院の付き添いなどで勤務時間を調整せざるを得ません。
その結果、仕事の生産性が低下し、本人にとっても精神的な疲弊や経済的な困窮を招きやすいのが現実です。
介護を理由にした離職者は年間およそ10万人。
経済産業省の推計では、介護離職による社会全体の経済損失は年間6500億円にのぼるとされています。
さらに、介護を続けながら就業を継続する従業員の生産性低下も無視できず、企業経営に深刻な影響を与えかねません。
ビジネスケアラー支援の第一歩は、法律で定められた支援制度を正しく理解することです。
ここで紹介する制度は、すべての企業に義務付けられている最低限の仕組みであり、社員が安心して介護と仕事を両立するための土台となります。
家族の介護が必要になった際、対象家族1人につき通算93日まで休業できる制度です。
3回まで分割取得が可能であり、突発的に始まる介護にも柔軟に対応できます。
要介護状態の家族がいる社員は、年5日まで介護のための休暇を取得できます。
1時間単位での利用も認められており、通院の付き添いや一時的なケアにも活用できます。
介護を行う社員は、残業や深夜労働を免除してもらうことが可能です。
また、短時間勤務など柔軟な働き方を選べる制度も法的に整備されています。
厚生労働省が提供する「両立支援等助成金」は、介護と仕事の両立を支援する制度を導入・運用した企業に対して支給される仕組みです。
助成金を活用することで、制度設計や環境整備の費用負担を軽減できます。
法定制度を理解したうえで、企業独自の支援体制を整えることが重要です。
以下の4ステップを踏むことで、従業員にとって安心できる環境を築くことができます。
匿名アンケートや面談を通じて、介護を担う従業員の人数や困りごとを把握します。
介護休業中の給与補填やフレックス制度の拡充など、実態に即した制度設計を行います。
「相談しても不利益を被らない」という心理的安全性を確保し、管理職に研修を行うことで、サポート文化を根付かせます。
地域包括支援センターや外部相談窓口と提携し、従業員が専門家へスムーズにアクセスできる環境を整備します。
大手メーカーでは、介護休業制度に加えて「在宅勤務」「時短勤務」「復職支援プログラム」などが整備されています。
従業員がキャリアを諦めずに介護と両立できる環境を提供しています。
がん領域を中心に革新的な医薬品の研究・開発・販売を行っている「中外製薬株式会社」では、「ワークライフシナジーの追求」を目標に掲げ、介護を含むライフイベントと仕事の両立を支援するための様々な施策を実施。
社長からのメッセージ発信や介護支援制度の利用推奨、人事研修、セミナー、動画や紙媒体での情報提供など、多層的な施策で徹底的にサポートしているようです。
人事部門のリソースが限られる中小企業では、外部の介護相談窓口と提携する取り組みが進んでいます。
従業員は専門家に直接相談できるため、会社負担を最小限にしながら安心感を提供できます。
その他、フレックスタイムやテレワークなど柔軟な働き方の導入、社内用支援制度の整備などが推進されているようです。
ビジネスケアラー問題は、個人の努力や家庭内の問題にとどまらず、企業全体の競争力に直結する経営課題です。
介護離職による人材流出や生産性低下は、放置すれば年間数千億円規模の損失につながります。
一方で、法定制度の活用や、自社独自の支援体制の整備、外部サービスとの連携を通じて、従業員の「仕事と介護の両立」を後押しすることは十分に可能です。
支援を制度として整えることはもちろん、「安心して相談できる職場環境」を築くことが、離職防止とエンゲージメント向上につながります。
人事・総務部門が主導して取り組むことで、社員一人ひとりが安心して長く働ける企業文化をつくりあげることができます。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
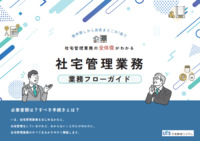
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

生成AI時代の新しい職場環境づくり

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
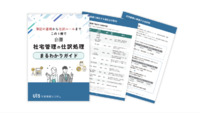
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

オフィスステーション導入事例集

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
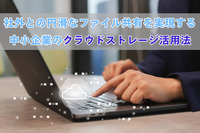
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法
公開日 /-create_datetime-/