公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

近年、職場におけるマタニティハラスメント(以下、マタハラ)が社会問題として注目されています。厚生労働省の令和5年度調査によると、直近3年間にマタハラに関する相談があった企業は10.2%にのぼり、令和2年度から5.0ポイント増加しています。さらに、そのうち企業がマタハラと判断した割合は50.1%と半数を超え、深刻な課題であることが浮き彫りになっています
参考:職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)|厚生労働省
まずは、マタハラの正しい定義と関連する他のハラスメントとの違いについて解説します。
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠、出産、育児休業等を理由として、職場において不利益な取り扱いを受けることや、妊娠・出産・育児休業等に関する制度や措置の利用を阻害する行為を指します。
厚生労働省の指針では、マタハラを2つに分類して解説しています。
1つは、育児休業や産前産後休業など制度を利用しようとする際に妨害や嫌がらせを受ける 「制度等の利用への嫌がらせ型」、2つ目は、妊娠や出産そのものを理由に否定的な言動を受ける 「状態への嫌がらせ型」 です。
マタハラと混同されやすいハラスメントとして、セクハラやパタハラがあります。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動によって相手に不快感を与える行為全般を指します。
マタハラが妊娠・出産に特化しているのに対し、セクハラはより広範囲な性的言動が対象となります。
また、パタニティハラスメント(パタハラ)は、男性が育児参加する際に受けるハラスメントです。
「男性の育休は会社のお荷物」といった発言が典型例で、マタハラの男性版とも言えるものです。
実際の職場でどのようなマタハラが発生しているのか、具体的な事例を通じて理解を深めていきましょう。
妊娠を理由に昇進機会を奪うのは明確なマタハラです。
参照:労働基準法第65条第3項
では、妊娠中の女性が請求した場合には軽易な業務への転換をさせなければならないとされていますが、本人が請求していない場合に一律に責任ある業務から外すことは違法行為に該当する可能性があります。さらに、妊娠後の人事考課で不当に低い評価を受け、結果として賞与が大幅に減額されました。
このような経済的不利益も、男女雇用機会均等法に違反する重大なマタハラです。
B社の経理部では、妊娠した女性社員に対して複数の同僚から継続的な嫌がらせが行われました。
「つわりで休むなら最初から働くな」といった発言が日常的に繰り返され、女性社員は精神的に追い詰められました。
この事例は同僚による集団的なマタハラの典型例です。
継続的な嫌がらせ行為は職場環境を著しく悪化させ、被害者の就業継続を困難にします。
特に問題となるのは、管理職がこうした状況を把握していたにも関わらず、適切な対応を取らなかったことです。
企業には職場環境配慮義務があり、ハラスメントの兆候を察知した段階で迅速な対応が求められます。
マタハラを根本的に解決するには、その原因を正しく理解することが不可欠です。
多くのマタハラの背景には「男性は仕事、女性は家庭」という性別役割分業の考え方があります。
この価値観は「出産後は家庭に入るべき」「育児を優先すべき」といった偏見を生み出します。
さらに、管理職世代が男性中心の職場で育ったため、妊娠・出産を経験しながら働く女性を想像しにくく、適切な支援ができないことも要因です。
慢性的な人員不足もマタハラの大きな要因です。
妊娠による一時的な人手減少は職場全体の負担を増やし、特に中小企業では不満が妊娠した社員への強い言動として表れやすくなります。
代替要員の確保が難しい場合、管理職が妊娠報告を「困ったこと」と捉え、無意識に否定的な反応を示すこともあります。
たとえ悪意がなくても、こうした対応は明確なマタハラに当たります。
効果的なマタハラ防止には、包括的かつ継続的な取り組みが必要です。
企業ができる具体的な対策を解説します。
企業がまず取り組むべきは、明確な防止方針と相談体制の整備です。
就業規則にマタハラ防止を明記し、社員へ周知徹底することで、組織としての姿勢を示します。
相談窓口では、プライバシー保護・不利益取り扱いの禁止・迅速な対応を徹底し、必要に応じて外部専門機関とも連携します。
さらに、「妊娠を理由とした降格」「つわりによる休暇への嫌がらせ発言」など、具体的な禁止行為を規程に明示することで理解を深められます。
加えて、発生時の懲戒処分を就業規則に定め、事前に対処法を整えておくことが重要です。
継続的な教育と環境整備は、マタハラ防止の核心です。
管理職研修では、法的定義や企業責任、適切な対応を学びます。
妊娠・出産に関する知識、コミュニケーション、業務調整方法を盛り込み、妊娠報告時の初期対応をロールプレイで訓練すると効果的です。
職場環境では、テレワークやフレックスタイム、短時間勤務制度の導入が有効です。
さらに業務分散システムを構築し、特定の社員に負担が偏らない体制を整えることで、妊娠による一時的な戦力減にも柔軟に対応できます。
あわせて読みたい
A.逆マタハラは、妊娠・出産した社員への過度な配慮や特別扱いにより、他の社員が不公平感を抱き職場環境が悪化する現象です。
業務負担の偏りや昇進での不適切な優遇などが典型例です。
防止には、本人の体調や希望、医師の意見を踏まえて業務を調整し、他の社員にも配慮の理由を丁寧に説明して理解を得ることが重要です。
A.企業が適切に対応しない場合、損害賠償請求などの民事責任、労働局からの指導・改善命令といった行政処分を受ける可能性があります。
過去には数十万〜数百万円の賠償命令例もあります。
さらに企業イメージの悪化による採用難や信頼低下といった深刻な影響も生じます。
これらを防ぐには、予防策と迅速な対応が不可欠です。
人事担当者にとって、マタハラ防止は優秀な人材の定着と企業成長を支える重要課題です。
法令遵守にとどまらず、多様な働き方を支援する制度や文化づくりとして積極的に取り組む姿勢が求められます。
マタハラ防止策の柱は「制度整備・教育研修・職場環境改善」です。
特に管理職の意識改革と対応スキルの習得を推進することが、人事部門の大きな役割となります。
マタハラ対策は女性社員だけでなく職場全体の働きやすさを高め、社員の定着率や生産性の向上につながります。
人事担当者は法改正や社会動向を常に把握し、自社に合った施策を継続的に見直していくことが不可欠です。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
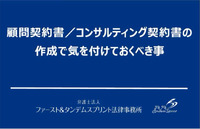
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

サーベイツールを徹底比較!

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
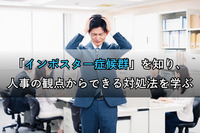
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
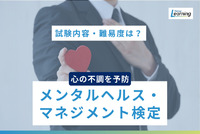
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
公開日 /-create_datetime-/