公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
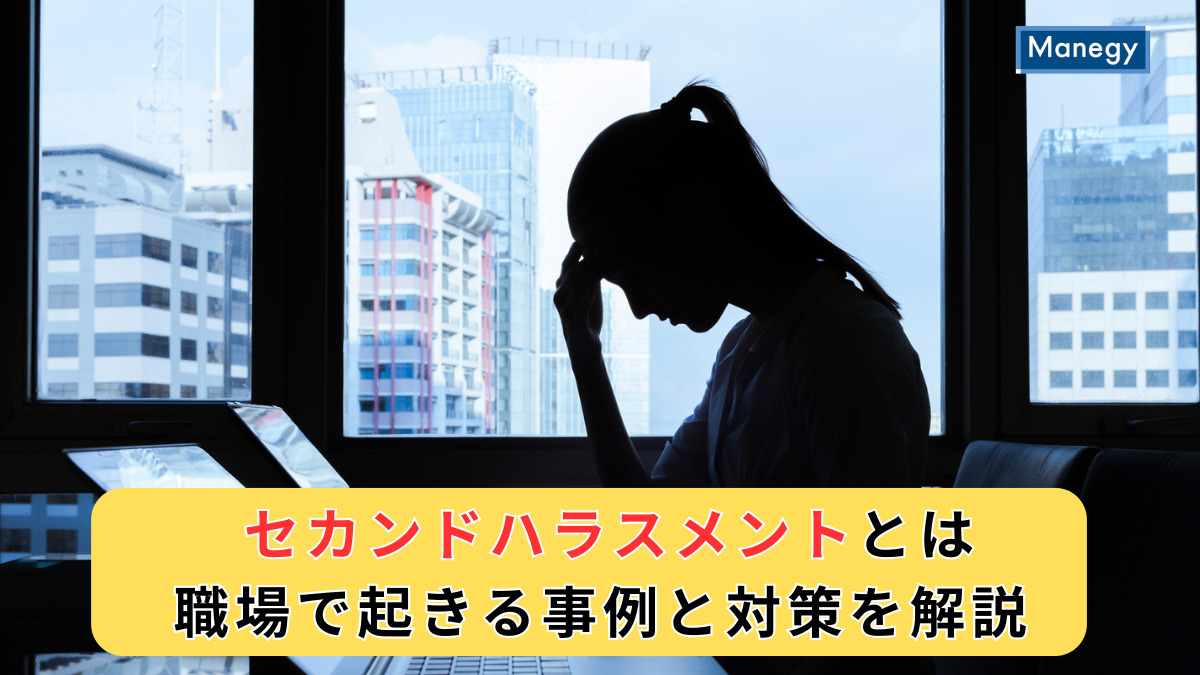
職場でハラスメントが発生した際、適切な対応を怠ると「セカンドハラスメント」という二次被害を引き起こすリスクがあります。一次被害そのもの以上に被害者の心身を追い詰め、職場全体の信頼関係を損なう深刻な問題になりかねません。
人事労務担当者にとって、セカンドハラスメントの理解と対策は、単なる「ハラスメント対応」の延長ではなく、被害者保護と組織防衛の観点から必須の知識です。
本記事では、セカンドハラスメントの具体的な事例や発生しやすい原因、そして人事が実務で取るべき対策について詳しく解説します。
セカンドハラスメントとは、ハラスメントの被害を受けた人が、その被害を相談したり訴えたりした際に、周囲から受ける二次的な嫌がらせや不利益取扱いのことです。
「二次被害」「二次加害」とも呼ばれています。
セカンドハラスメントは、元々のハラスメントとは異なる特徴を持ちます。
被害者が勇気を出して声を上げた後に発生する点が最大の問題であり、被害者の心理的ダメージを深刻化させる要因となります。
セカンドハラスメントが発生すると、被害者は「相談しなければよかった」と感じ、他の従業員も「相談すると不利益を受ける」と判断してしまいます。
その結果、組織全体でハラスメントが隠蔽されやすい環境が形成され、根本的な解決が困難になります。
職場で実際に発生するセカンドハラスメントには、様々なパターンがあります。
「それくらい大したことない」「我慢すれば済む話だ」といった発言で、被害を軽視するケースです。
被害を認めてもらえないことで、相談者はさらに孤立感を深めてしまいます。
ハラスメントを受けた側に落ち度があるかのように扱うのも、典型的なセカンドハラスメントです。
被害者は「相談することで自分が悪者になる」と感じ、泣き寝入りにつながります。
相談内容を無断で同僚に話したり、加害者本人に伝えてしまうケースです。
噂が広まると、被害者は「相談したこと自体が間違いだった」と感じ、精神的に追い詰められます。
セカンドハラスメントの発生には、組織文化や個人の認識に関わる複数の要因が関係しています。
根本的な対策を講じるためには、これらの原因を正確に理解することが不可欠です。
多くの組織ではハラスメントへの理解不足がセカンドハラスメントの主要な原因となっています。
管理職や従業員が「これくらい普通」「昔からこうだ」と考えると、被害者の訴えを軽視しがちです。
特に正しい知識を持たない管理職は「我慢すべき」「大げさだ」と発言しやすく、被害者をさらに傷つけます。
また、相談時に「なぜ早く言わなかったのか」「証拠はあるのか」と問うことも、責められている印象を与え、二次被害につながります。組織が問題の早期収束を優先し、根本解決を避ける姿勢もセカンドハラスメントの要因です。
多くの企業はハラスメントを「組織の恥」と捉え、内々に処理しようとするため、被害者に「穏便に」「大事にしないで」と圧力をかけがちです。
こうした対応は被害者に罪悪感を与え、精神的負担を強めます。
さらに加害者が重要ポジションにいる場合、「彼がいないと困る」「優秀な人材を失いたくない」と問題を矮小化し、被害者の人権を軽視する判断につながります。
まずは、相談者の話を遮らず最後まで聞き、「相談してくださってありがとうございます」と共感を示すことが大切です。
秘密保持を徹底し、内容は必要最小限の関係者にのみ共有しながら同意を得て進めます。
また、今後の流れや調査スケジュールを具体的に説明し、不安を和らげることで心理的負担を軽減できます。
セカンドハラスメント防止には、相談者を責めたり軽視する発言を避けることが重要です。
「なぜ早く言わなかったのか」「あなたにも原因があるのでは」と責任を示唆する言葉や、「よくあること」「気にしすぎ」と苦痛を軽んじる表現は禁物です。
また「会社の評判を考えて」と組織の都合を優先する発言も有害です。
さらに証拠の有無を最初に問うと信頼を損なうため、まず体験を受け止め、その後に事実確認へ進むことが望まれます。
セカンドハラスメント防止には、被害者への継続的な支援と職場全体での仕組みづくりが欠かせません。
調査後も定期的に面談を行い、必要に応じて専門家によるケアを手配します。
被害者が働きやすいよう座席変更や業務調整を行いますが、不利益とならないよう十分に相談することが重要です。
加害者には規則に基づいた処分と指導を行い、管理職を含む全体研修で再発防止を徹底します。
さらに内部・外部の相談窓口を整備し、不利益取扱い禁止を明確に周知して安心して相談できる環境を整えます。
相談者の要望があっても、企業には職場環境配慮義務があり放置はできません。
まず理由を丁寧に聞き取り、「報復が怖い」「周囲に知られたくない」などの不安に具体的な保護策で応えます。
そのうえで「会社として対応が必要である」ことを説明し、相談者の意向を尊重しつつ最小限の対応を提案します。
相談者への不利益取扱いがあれば即時に是正し、被害拡大を防ぎます。
具体的内容と実行者を特定し、厳重注意を行います。
また、相談者には保護姿勢を示し、心理的サポートや業務上の配慮、カウンセラーによるケアを提供します。
秘密保持や保護策を強化し、信頼回復に努めます。
セカンドハラスメントは、ハラスメント被害者にさらなる苦痛を与える深刻な問題です。
人事労務担当者は、その定義と影響を正確に理解し、予防と対応の両面で積極的な取り組みを行う必要があります。
適切な初期対応、継続的な被害者ケア、組織全体での意識改革により、セカンドハラスメントを防止し、すべての従業員が安心して働ける職場環境を構築することが可能です。
法的義務の履行と同時に、組織の信頼性向上にもつながる重要な取り組みとして、継続的に推進していきましょう。
他にも知っておきたいハラスメント
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

ラフールサーベイ導入事例集

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
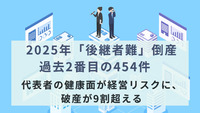
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

事業用不動産のコスト削減ガイド

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
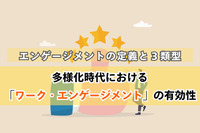
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
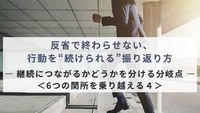
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
公開日 /-create_datetime-/