公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

福利厚生は、社員の定着や採用競争力を高めるうえで重要な役割を担っています。
しかし「導入しているが利用率が上がらない」「コストばかり増えて効果が見えにくい」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
本記事では、福利厚生の見直し方法と、コストを抑えつつ満足度を高めるための具体的な手順を解説します。
福利厚生は従業員の働きやすさを支える重要な制度ですが、導入後に放置されると時代やニーズの変化に対応できず、コストばかり増えて効果が薄れる恐れがあります。
定期的に見直しを行うことで、コストを最適化しつつ従業員満足度を高めることができます。
福利厚生は、導入して終わりではなく、企業や従業員を取り巻く環境の変化に合わせて継続的に調整することが重要です。
見直しのきっかけとなるタイミングを把握しておくことで、制度の形骸化を防ぎ、効果的な改善につなげられます。
長年続く制度は、従業員ニーズや社会情勢の変化とずれている可能性があります。
特に5年以上手を加えていない場合は、利用状況やコスト、導入目的を再点検しましょう。
形だけ残っている制度は、見直しや廃止も含めて検討するタイミングです。
利用者が少ない制度は、コストに対して効果が見合っていない可能性があります。
従業員アンケートなどで利用しない理由を把握し、改善・縮小・廃止のいずれかを検討することで、無駄な支出を抑えつつ満足度向上を図れます。
福利厚生への不満を放置すると、社員の信頼感やモチベーションが低下し、結果としてエンゲージメントにも影響を及ぼします。
調査結果で改善要望が多く寄せられた場合は、制度の優先度を見直し、早期に改定を計画しましょう。
社会保険料の負担変更や非課税枠の見直しなど、法改正や税制改正によって既存制度の条件が変わることがあります。
最新の法令・通達に適合しているかを定期的に確認し、必要に応じて制度設計や運用ルールを見直すことが大切です。
福利厚生は導入して終わりではなく、現状を分析し、改善を重ねることで従業員満足度やエンゲージメントの向上につながります。
次の5つのステップを実行することで、従業員の満足度とコスト効率を両立した見直しが可能です。
最初のステップは、既存の福利厚生制度がどの程度活用されているかをデータで把握することです。
制度ごとの利用率・年間コスト・従業員満足度を一覧化することで、優先的に見直すべき制度が明確になります。
データに基づいた議論ができるため、経営層への説明や意思決定もスムーズになります。
次に、従業員が実際に求めている制度を把握します。
アンケートやグループヒアリングを活用し、年代・ライフステージ・職種別の違いも分析しましょう。
現場の声を反映することで、導入後の利用率や満足度が高まり、効果の薄い施策の追加を防止できます。
収集したデータやニーズをもとに、企業の経営戦略との整合性を確認します。
たとえば、人材定着を重視する企業なら育児・介護支援を優先するなど、目的に応じた優先順位づけが重要です。
目的が明確であれば、経営層の納得も得やすくなります。
優先順位が決まったら、具体的な改善案を立案し、導入コストや削減可能な経費を試算します。
複数案を比較しながら費用対効果を示すことで、経営層の承認を得やすくなります。
承認前には財務・人事部門と連携し、実現可能性をすり合わせておくとスムーズです。
制度導入後は、周知と定期的な効果測定が欠かせません。
導入初期は特に利用促進のための社内コミュニケーションを強化し、利用率・満足度を継続的にモニタリングします。
この改善サイクルを回すことで、常に従業員ニーズに合った福利厚生制度を維持できます。
福利厚生は従業員のモチベーションやエンゲージメント向上に直結しますが、企業予算には限りがあります。
限られたコストを最大限に活かすためには、制度の見直しと優先順位をつけた投資が欠かせません。
ここでは、コスト削減と満足度向上を同時に実現するための3つのポイントを紹介します。
まずは、各制度の利用状況を精査し、ほとんど活用されていない制度を見直し候補としましょう。
利用率が低い制度は、従業員ニーズとのミスマッチが起きている可能性があります。
ただし、福利厚生の変更・廃止は労働契約法(第8条~第10条)で定められる「不利益変更」に該当する場合があるため、慎重な対応が必要です。
合理的な理由や必要性を説明し、労働組合や従業員代表との協議・合意形成を経て周知することで、トラブルを防ぎつつ無駄なコストを削減できます。
従業員の価値観が多様化するなかで、自分に合った福利厚生を選べるポイント制制度の導入が広がっています。
旅行・書籍購入・オンライン研修など、用途を自由に選べる仕組みは利用率が高まりやすく、結果として満足度とコスト効率の両立につながります。
一律提供型の制度に比べて、従業員の世代やライフステージに応じた柔軟な支援が可能です。
限られた予算は、従業員満足度や定着率に直結しやすい重点分野に再配分しましょう。
特に健康維持・育児介護支援・スキルアップ支援はニーズが高く、生産性向上や離職防止にも効果があります。
利用率の低い制度を整理し、重点分野に戦略的に投資することで、福利厚生全体のROI(投資対効果)を最大化できます。
福利厚生は、一度導入して終わりではなく、時代の変化や従業員ニーズに合わせて継続的に見直すことで本来の効果を発揮します。
利用率の低い制度の整理や予算の重点配分、ポイント制の活用などを通じて、コストと満足度のバランスを取りながら企業の魅力を高めていきましょう。
まずは、現状の利用率やコストをデータで可視化し、課題を洗い出すことから始めてみてください。
小さな改善を積み重ねることで、従業員に選ばれ続ける持続可能な福利厚生制度へと育てていくことができます。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
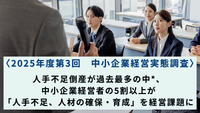
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
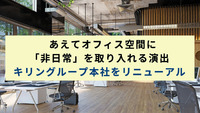
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策
公開日 /-create_datetime-/