公開日 /-create_datetime-/

面倒くさがらずに電子署名法3条に従った電子署名を行うと、そのご褒美として電子情報の真正性を法律が推定してくれます。簡単に言うと「ちゃんと電子署名してあるから、この電子契約書は本物の契約書(情報)と推定してあげるよ。」とったところです。もう少し詳しく中身を見ていきましょう。
これまで頑なに利用されてきた「紙、実印」の世界をイメージしてみます。
あえて契約書に実印を押していたのはなぜなのでしょうか、ここに答えがあります。実印を押してあれば、後日紛争になっても、契約書に記載してある内容で当事者が合意した事実は基本的には揺らがないからです。
なぜ揺らがないのでしょうか。その答えは法律にあります。民事訴訟法228条4項(「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」)は簡単に言うと、「その人の印鑑」が「その人の意思で書類に押してあれば」、その書類はその人の意思に従って作成されたものと推定してあげますといった条文です。
「その人の印鑑」であることを証明しやすくするために、あえて三文判ではなく実印が利用されるのです。実印はその人だけが利用できるものです。実印の利用により印鑑とそれを押す「個人」ないし「法人」が紐づけられるのです。
「その人の意思で押した」という部分は、判例の理論でざっくりいうと「その人の印鑑が押してある以上、普通に考えれば、押したのはその人でしょ」、ということで推定されることになっています(いわゆる二段の推定の一段目)。
電子署名の場合もパラレルに考えられます。電子署名法3条により、電子署名を行うと、「その人の電子署名」が「その人の意思で書類(データ)に押してあれば(正確には電子情報なので押すわけではありませんが)」、その書類(データ)はその人の意思に従って作成されたものと推定してくれるのです。
「その人の意思で押した」という部分については、上記したように判例からの理論であり、電子署名の場合にも適用があるか明確にはされていません。
しかし、この判例の理論の適用はあると考えるべきでしょう(多少の変容はあるかもしれませんが。)。というのも、電子署名の機能上、その人が署名したと判断するのが合理的ですし、この部分の推定を認めなければ、あえて電子署名法3条の推定規定を設けた意味が半減してしまい立法者の意図に反するからです。
そして、「その人の電子署名」であることを証明しやすくするために、電子証明書付きの電子署名が行われ、署名者本人と紐づけられるのです(そもそも電子情報はその性質上、本人との結びつきが弱いという弱点を持っているのですが、その弱点をクリアします。電子情報ゆえにこの「本人との紐づけ」は慎重に行ったほうがよいのです)。ちなみに、広義の電子契約がつつがなく行われているのは、クレジットカードにより、本人との結びつきがはっきりしているからですね(不正利用はありますが。)。
このように電子署名が行われると、その電子情報、電子契約は成立の真正が推定されるので、不幸にも電子契約を行った取引が債務不履行などの理由により紛争になったとしても、電子契約書(情報)をプリントアウトし、電子署名の電子証明書、電子署名の検証結果と一緒に提出すれば、とりあえず契約締結の事実に対する立証はおわります。これまでの訴訟手続きと連続性がありますね。
逆にこの推定がないと、極論をいうと、「署名はないが、契約書である。」といって提出した電子情報が、そもそも何の情報であるのか、どのようなシステムで作成された情報であるのか、そのシステムの構造上契約当事者の意思が正確に反映されたものであるといえるのか・・・等々、その無個性な電子情報について一から(個別のシステムの構造から)説明して立証していかなければならないという立証負担増大の危険があるのです。
「電子署名あります!」
「電子署名はありませんが、●は×なシステムでして▽なので◇であります。◇なので〇ですから、この部分は電子署名と同じ機能があります。」
この違いです。
もちろん、相手が電子契約の成立自体を争わなければそのような危険は生じませんし、裁判官によっては、電子署名がなされた場合と同じように見てくれるかもしれません。
しかし、電子署名をしない場合には紛争発生時に予期せぬ事態が起こる可能性が高まることは頭にいれておくべきでしょう。
これまで、頑なに紙、実印で契約締結業務を行ってきた分野には「確率はかなり低いが失敗は許されないので、しっかりやっておく」という価値判断が根底に流れていたはずです。
この価値判断は、電子契約を導入しても揺るがない部分です。だからこそ電子署名の意義を理解しておくことは大事なのです。
連載記事一覧
1.電子契約って何?(広義の電子契約と狭義の電子契約)
2.電子署名を当事者が行うシステムが重要なのはなぜ?
3.電子署名法からのプレゼント?
執筆者情報

啓明法律事務所 弁護士 小山 征史郎(おやま せいしろう) 第一東京弁護士会所属
2005年弁護士登録(58期)。
弁護士法人ポート法律事務所を経て、2016年から啓明法律事務所に所属。これまでは訴訟を中心に活動していたが、近年は電子契約に関心を持ち、これまでの訴訟を通じた弁護士経験を電子契約にフィードバックすることに注力している。
本年1月より、ペーパーロジック株式会社のLegal Teamとして、コラムの執筆や法的アドバイスを行っているほか、ペーパーロジックの各法対応製品(特に電子契約)に対して、関係法律法令等をふまえた法的バックグラウンド強化を支援している。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -
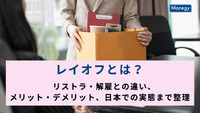
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較
ニュース -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
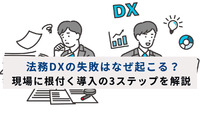
法務DXの失敗はなぜ起こる?現場に根付く導入の3ステップを解説
ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース




































