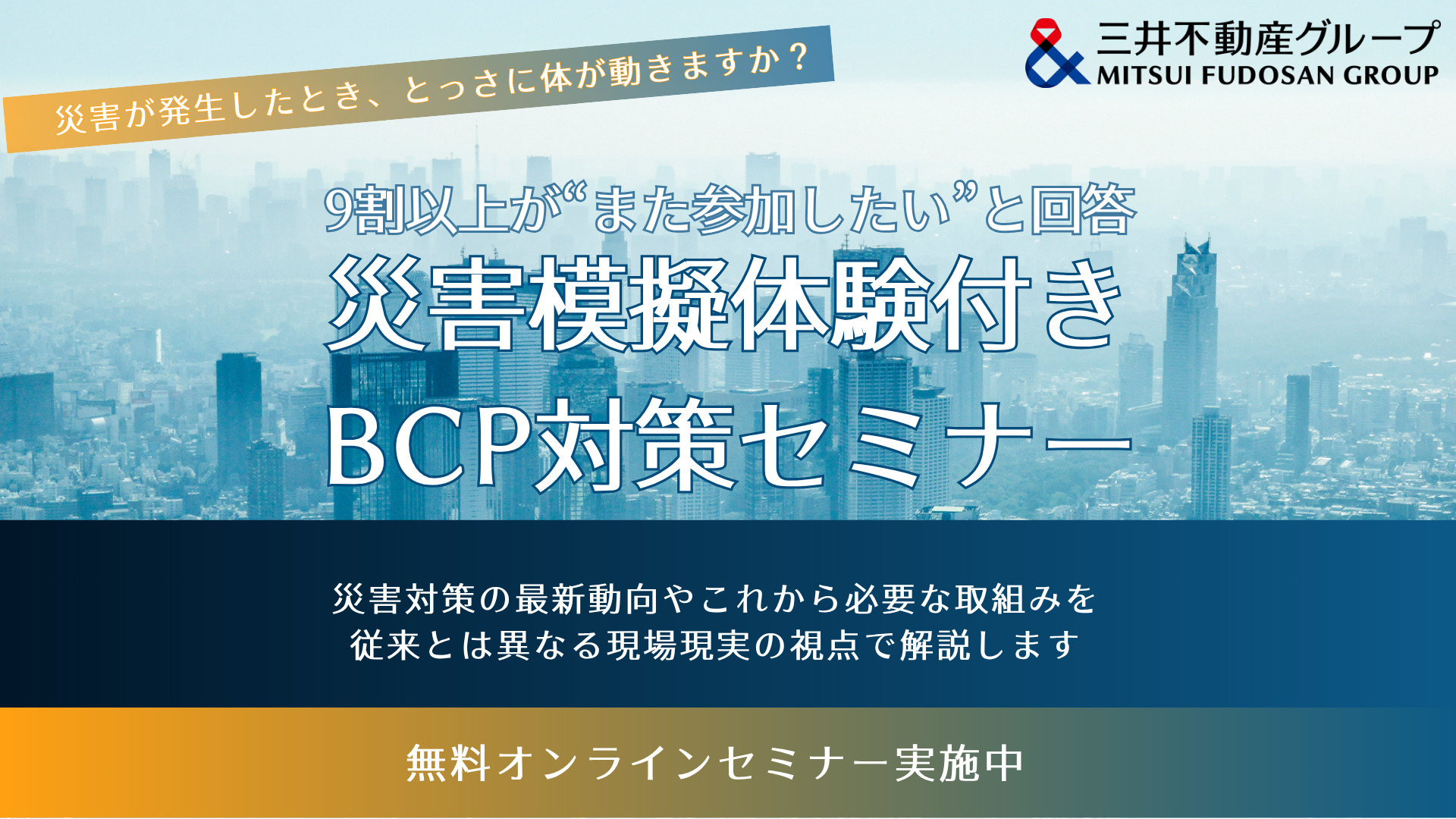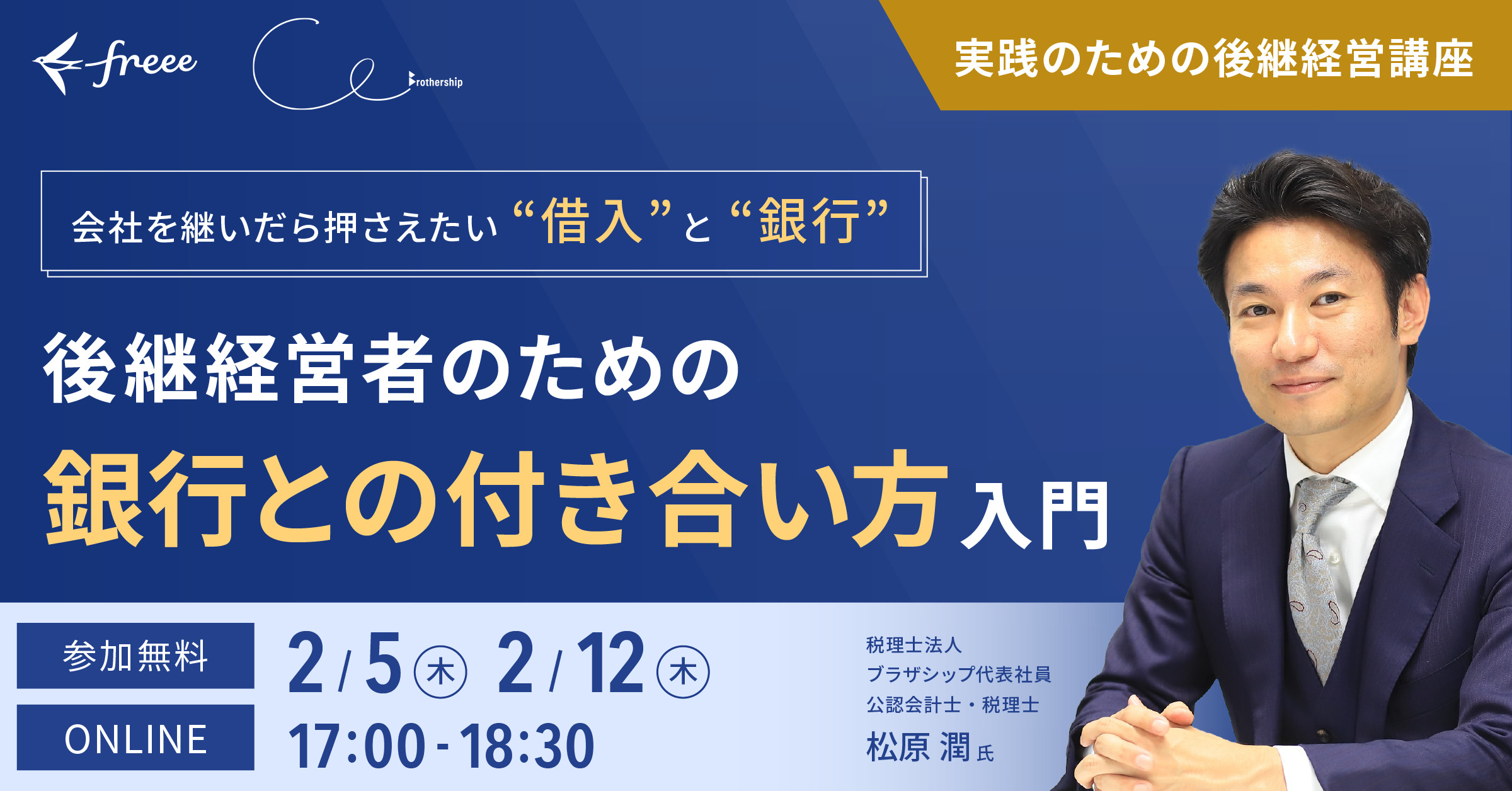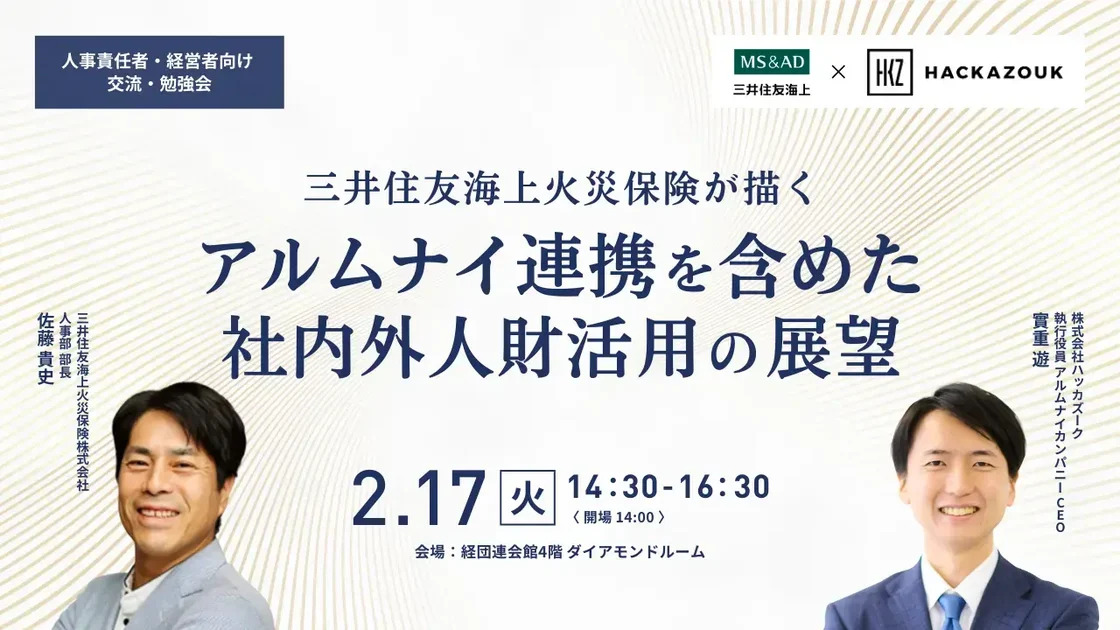公開日 /-create_datetime-/

経営環境の変化が速く、技術革新も日々進展する中、ビジネスパーソンには新たな知識、スキルを身に付けていくことが常に求められています。しかし会社での日常業務に追われ、自ら学ぶ機会、意欲をなかなか持てないのが実情ではないでしょうか。そこで今回は「どうすれば人は学ぶのか」という点に注目し、日本のビジネスパーソンで意欲的に学びに取り組んでいる人はどのくらいいるのか、学びにつながる心の持ち方や学びの意欲を高める方法は何か、について解説していきます。
「学べていない人」が全体の約7割
リクルートワークス研究所が発表した「全国就業実態パネル調査2018」(5万677人から有効回答)によると、過去1年間に自らの意志で仕事に関わる知識、技術の向上のための学習(読書等)に取り組んだ雇用者の割合は、全体の33.1%でした。数字で見ると、約7割近くの雇用者が、学習習慣を持っていないわけです。
雇用形態別にみると、「正社員」が36.9%、「非正社員」が27.0%となっており、長期就労を前提とする正社員であっても、日頃から学習している人は4割に届いていません。
さらに企業から学びの機会を提供されているかどうかを尋ねたところ、「OJT」(日常業務の中で上司・先輩から指導を受けて学習すること)が提供されていると回答した雇用者の割合はわずか23.6%。「Off-JT」(日常業務以外の場で研修等を受けて学習すること)が提供されているとの回答割合は22.5%にとどまっています。
かつて日本のビジネスパーソンは、日本型雇用システムによる長期雇用を前提に、OJTやOff-JTといった企業主導型の教育システムが充実しているといわれていました。ところが実態として、全体の8割近くの雇用者が「学習できた」と実感できるような教育を企業から受けていないのです。
自発的に学ぶ機会を持つ必要性を理解する
高度成長期の頃は、日本型雇用システムが当然のごとく行われ、従業員は企業が指導するOJTやOff-JTを受動的に受けることで自ら学習し、スキルアップを図ることができました。日本型雇用システムとは年功序列と終身雇用を原則とする雇用・人事体系のことで、当時はこの枠組みの中で企業が従業員に教育を行っていたわけです。しかし今やそのような時代は終焉し、「会社主導によるキャリア・スキル形成」という考え方が薄れつつあります。さらに近年では「働き方改革」によって労働時間が短くなり、先輩や上司から長時間指導を受けるという既存の教育体制に変化が生じてきました。
そのため現在では、ビジネスパーソンとしてキャリアアップ・スキルアップを図るには「自らの能力は、自らの学習によって高める」という意識が必要になりつつあります。
先のリクルートワークスのアンケート調査では、全体の約3割の人が自らの意志で学習に取り組んでいましたが、どうすれば自ら意欲的に学ぶ姿勢を身に付けることができるのでしょうか。
学びにつながる心的傾向を意識して持つ
スタンフォード大学に所属するキャロル・ドゥエック教授によると、人間が学習に取り組むときの心理状態には2種類あるといいます。
1つは「成長につながる心的傾向(Growth Mindset)」で、自らの能力は努力によって成長させることができ、学習こそが成長につながるという心的傾向です。この考え方を持つ人であれば、自らのスキルや知識を充実させ、失敗を恐れることなく挑戦し続けることができます。
もう1つは「固定的な心的傾向(Fixed Mindset)」で、自らの能力は努力しても変わらず、失敗を恐れ、他人からの評価だけを気にする心的傾向です。この場合、学習による自らの成長を期待していないので、現状の自分の評価をいかにして高めるかのみ重要となります。また、もし失敗しても自分の成長で補おうとせず、他人のせいにすることが多いのも、この心的傾向の特徴です。
「勉強の意欲が沸かない」という人は、いつの間にか固定的な心的傾向を強く持ってはいないでしょうか。学ぼうとする気持ちを高めるためには、成長につながる心的傾向を意識的に持つことが大切です。
学べる場や学びの支援があることを知る
学ぶ意欲を持っても、具体的にどこでどう学べばよいのか分からないと実行には移せません。
現在、企業以外の場で、学習意欲のある社会人が学べる場所は数多くあります。やる気をやる気のまま終わらせないためにも、学ぶ場があることを知ることが大切です。
社会人が学ぶ場としては、まず大学・大学院が挙げられるでしょう。各大学・大学院では社会人入試も行われ、MBAを取得できる大学院等では夜間・土曜日のみ授業を開講しているケースもあります。また、最近ではインターネットを利用したeラーニングやMOOC(ムーク)で学ぶ社会人も多いです。MOOCとは大学が主催する大規模公開オンライン講座のことで、もともとはアメリカで始まった教育手法ですが、現在では東京大学をはじめ日本でも積極的に導入が進められています。
経済的支援を活用できる機会も少なくありません。例えば雇用保険の加入者を対象とする教育訓練給付制度を活用すれば、学びに必要なお金の支給を受けつつ資格取得・キャリアアップを目指すことができます。さらに先ほど挙げた大学・大学院では奨学金制度が整っているので、入学の際は必要に応じて活用すると良いでしょう。
まとめ
今や社会人としての「学び」は、企業側の指導に任せておけばよい、という時代ではありません。将来的にキャリアアップ、スキルアップを図っていきたいなら、OJTやOff-JTのみに頼るのではなく、自分の力で学ぶ意欲を持ち、実践していくことが求められます。
人が学ぶ上では、学ぼうとする心的傾向を意識的に持つこと、そして学べる機会が社会の中に豊富にあると知ることが大事です。自分を変えたい、成長させたいと考えている方は、自発的、積極的に学びの場に参加することをお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -
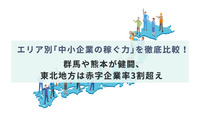
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え
ニュース -

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
ニュース -
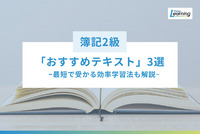
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説
ニュース -

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例
ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -
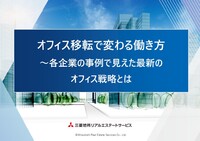
オフィス移転で変わる働き方
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -
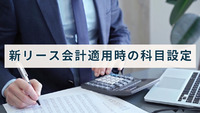
新リース会計適用時の科目設定
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース