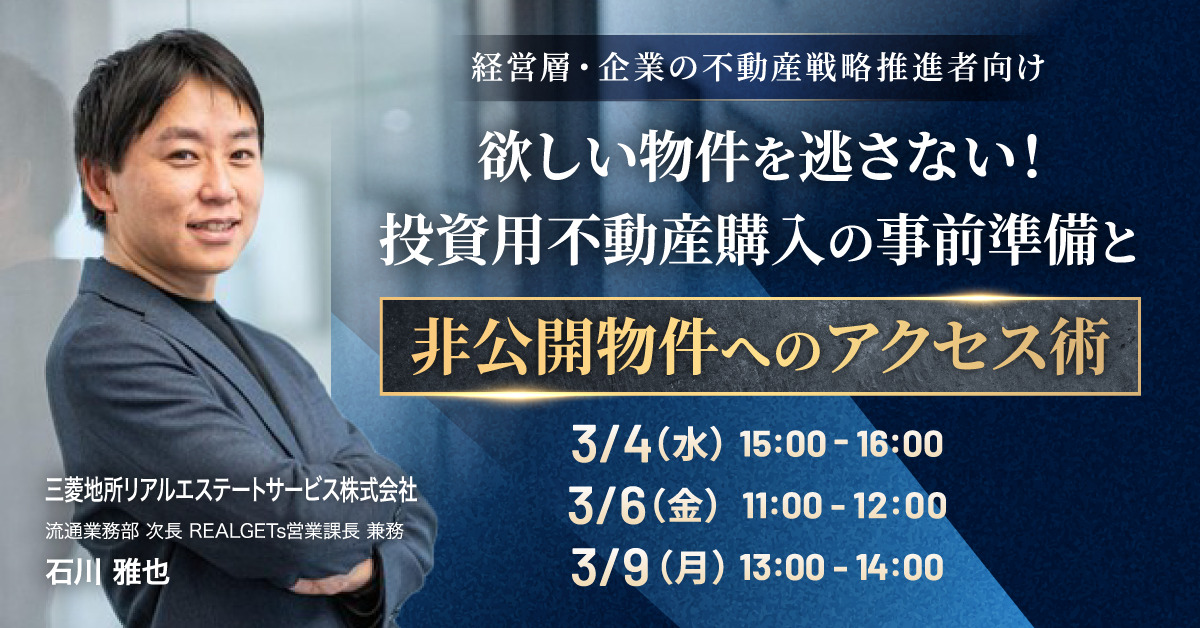公開日 /-create_datetime-/
決算賞与とは?いつ支給されるのかから通常賞与(ボーナス)との違いとは?
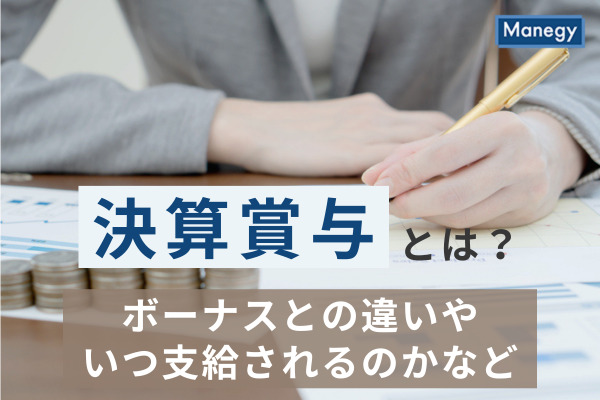
会社員のボーナスといえば夏・年末の年2回支給の賞与が通例です。しかし中には、これに加え「決算賞与」を支給する企業もあります。決算賞与とボーナスはどこが違うのでしょうか。これには、経理担当者なら知っておかなければならない問題も含まれています。
目次【本記事の内容】
資料ダウンロードで最大5,000円分のギフト券プレゼント
情報収取キャンペーン実施中!!
決算賞与とは
決算賞与とは、「その企業の事業年度の業績に応じて支給される給与」のことです。簡単にいえば「社員への利益還元」といったところです。
一般に夏・年末の年2回支給される賞与は「通常賞与」と呼ばれますが、決算賞与の場合は「臨時賞与」、「年度末手当」、「特別賞与」など、その名称は企業により様々です。
決算賞与はいつ支給される?
決算賞与は決算が確定してから支給される給与です。このため、決算賞与は決算月後の給与支給日に通常の給与と一緒に支給されるのが通常です。
日本の場合、企業の決算月は3月、6月、9月、12月が一般なので、決算賞与の支給日はこれらの月の翌月の給与支給日となります。
決算賞与とボーナスの違い
賞与には通常賞与(ボーナス)と決算賞与の2種類に分かれていることが分かりましたが、その違いは何でしょうか。これを正しく知るには、賞与そのものの定義を知る必要があります。
賞与は労働基準法第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義されています。
賞与が「労働の対償(対価)なのか、社員に対する恩恵的給付なのか」は、労使で議論が分かれるところですが、賞与支給を就業規則や労働協約に明記している企業の場合は「労働の対償」と見做されるのが通例です。
ただし、賞与の支給要件、支給時期、計算方法、支給額、支給対象者などは企業が自由に定めてよいもので、賃金や手当のように「必ず支給しなければならない労働の対償」とはされていません。
したがって、企業の業績、社員の業績貢献度や勤続年数など一定の支給基準を設け、「未達成の場合は賞与を支給しない」との規定を定款などに盛り込んでも違法にならないとされています。
こうしたことから、賞与とは「給与の一種ではあるが、支給の有無、支給要件、支給時期などは企業が自由に決定できる給与」といえます。
(1)通常賞与の意味と起源
通常賞与とは「決算月と無関係に夏・年末の年2回、定期的に支給される特別給与」といえます。
企業の場合、夏季賞与は6月中旬から7月初旬にかけて、年末賞与は12月初旬から中旬にかけて支給されるのが通常です。
日本で通常賞与が年2回支給されるのは、歴史的な背景が理由といわれています。
すなわち江戸時代、商家が使用人に対し盆と暮れに「仕着」(盆は「氷代」、年末は「餅代」とも呼ばれた)を配ったのが通常賞与の起源とされています。仕着は商家の主人の裁量で決められたので、これには褒章の意味があったようです。
また、企業としての通常賞与支給は1876年(明治9年)、当時の三菱商会が社員の労苦に報いるため同年末に支給した「賞与」が嚆矢とされています。
このような歴史的背景から、通常賞与には「社員への半期ごとの労い賃的な意味合いがある」ともいわれています。
なお、賞与の歴史的背景が異なり、かつ実力主義的傾向が強い外資系企業の場合、通常賞与は支給せず決算賞与のみを支給している例は珍しくないようです。
(2)決算賞与の意味とメリット
決算賞与とは、既述のごとく「事業年度終了の日の翌日から1カ月以内」に支給される特別給与のことです。この時期に支給されるのは、これも既述のごとく「その企業の事業年度の業績に応じて支給される」特別給与だからです。この2つが通常賞与と決算賞与の一番の違いといえるでしょう。
また、メリット的には次のような違いがあります。
<通常賞与のメリット>
①人件費の調整弁にできる
毎月の賃金は業績の如何にかかわらず、企業は就業規則や労働協約に明記した規定額を支払う義務があります。対して通常賞与の場合、業績不振の年は支給額を減らしたり支給ゼロにしたりできるので、業績に合わせて人件費を調整できるメリットがあります。すなわち、毎月の賃金は固定費ですが、通常賞与は変動費として取り扱うことが可能になります。また通常賞与は、残業手当、休日出勤手当、退職金の算出などに用いる必要がないので、この面でも人件費の抑制要因になります。
②福利厚生的な役割ができる
夏と年末年始は旅行や帰省、その他で社員の出費が何かと嵩みます。したがって、通常賞与はその出費を補う福利厚生的な役割も果たせます。また好業績の時、支給額を増やして好業績でない時とのメリハリをつければ、社員のモチベーションアップも期待できます。
<決算賞与のメリット>
①節税対策になる
決算賞与を支給する一番のメリットは、節税対策といわれています。決算賞与支給額は損金算入ができるからです。
例えば決算で法人税の課税対象利益額が1500万円となり、法人税の税率が40%だった場合、法人税額は600万円になります。しかし、この課税対象利益額のうちの1000万円を決算賞与として社員に利益還元すれば課税対象額は500万円になり、法人税額は200万円となります。差し引き400万円の節税になります。つまり企業は決算賞与を支給することで社員に喜ばれ、国に対しても適正な納税義務を果たす一石二鳥の効果を得られるのです。
②社員のモチベーションやロイヤリティが高まる
決算賞与は業績と連動した給与という特性を持っています。したがって、決算で確定した余剰利益を社員に還元することで、社員には「業績向上に貢献した」との実感が生まれ、「今期も頑張ろう」とのモチベーションや会社へのロイヤリティが高まります。
どれぐらい貰えるのか
決算賞与は、決算により確定した余剰利益を原資としている給与なので、通常賞与のような○○万円、あるいは基本給の○月分といった業界平均や相場はありません。すべては余剰利益額に左右される賞与といえるでしょう。
支給額は通常賞与より少ないのが一般ですが、同一企業でも通常賞与額より多い年があれば支給ゼロの年もある、勤続年数や業績貢献度の違いで支給額に差があるなど、まさに千差万別です。
まとめ
決算賞与を支給する場合、次の3要件を満たす必要があります。
1.決算日までに支給額と支給日を支給対象となるすべての社員に通知していること
2.通知をした支給額を通知したすべての社員に対し、決算日の翌日から1カ月以内に支給していること
3.支給額を①の通知をした日の属する事業年度において損金処理をしていること
この3要件は、決算賞与で節税する際の要件でもあるので、経理担当者は要注意です。
また決算賞与を支給することで、法人税額は減少しますが、手元のキャッシュフローは一時的に悪化します。このため「決算賞与支給で社員満足と節税の一石二鳥は得られたが、資金繰りが悪化した」と、本末転倒にならぬよう、経理担当者は資金計画においても細心の注意を払う必要があるでしょう。
■関連記事
日本企業の役員報酬は平均でいくら!?
気になる他社の賞与支給額、ボーナスはこうして決まる!?
決算賞与とは?経理・財務担当者が知っておくべき決算賞与の基礎知識
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
MS Agentに掲載中の求人
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査
ニュース -
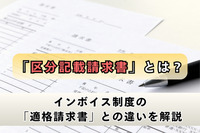
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -
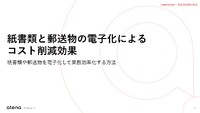
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース