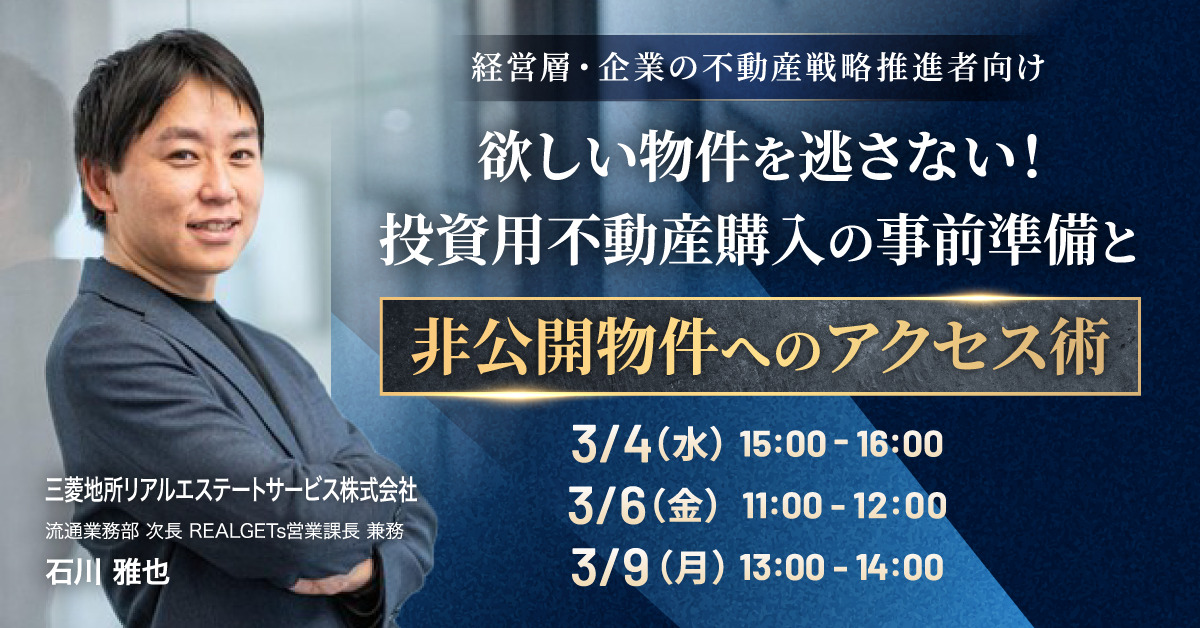公開日 /-create_datetime-/

よく新聞やテレビで目にする完全失業率という言葉ですが、正確な意味をご存じでしょうか。
「失業者の割合」という大まかなイメージはあるものの、具体的にどのように計算されるのか、分かりにくい面もあります。そこで今回は、完全失業率の定義、さらに過去最高の時期と過去最低の時期について詳しく説明しましょう。
完全失業率とは?
完全失業率とは、労働力人口における完全失業者の割合のことです。総務省統計局が全国の約4万世帯を対象に「労働力調査」を毎月行っていますが、その際に必ず発表されています。具体的な計算方法は、「(完全失業者÷労働力人口)×100」です。
分子の「完全失業者」とは現在職がなく求職活動をしている人のことであり、総務省統計局の定義によると、次の3つの条件を満たす人のことをいいます。
①労働力調査週間中、仕事がなくて、少しも仕事をしなかった(就業していない)。
②もし仕事があれば、すぐに就く。
③労働力調査週間中、仕事を探す活動もしくは事業を始める準備に取り組んでいた(以前に行った求職活動の結果を待つ状態を含む)。
「分母」の労働力人口とは、15歳以上人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせた人口数のことです。専業主婦や学生、年金収入で生活している高齢者など、働く意思がなくて働いていない人は、労働力人口には入りません。就業している人と、就業する意思はあるものの働けていない15歳以上人口の総数が、労働力人口になるわけです。
最近の完全失業率の推移
総務省統計局によると、完全失業率の年平均は、2016年が3.1%、2017年が2.8%、2018年が2.4%と年々低下しているのが現状です。日本経済は2012年12月以降、現在までの7年以上にわたって緩やかな景気回復期間が続いており、「景気回復期間」としては戦後最長となりました。内閣府によると、今回の景気回復期間の背景にあるのは、企業の収益改善と設備投資への需要、世界経済の同時回復、そして雇用所得環境の改善です。このような経済情勢を背景に、完全失業率はここ数年低下しつつあるわけです。
ただ、2018年末~2019年にかけて世界経済はやや減速し、日本経済もその影響を受けました。緩やかな景気回復傾向は続いているものの、景気の不透明さが増し、特に製造業の業況が悪化しています。それでも2019年に完全失業率が大幅に上昇したという状況はなく、2019年7月には26年9カ月ぶりに完全失業率は2.2%の低水準となりました。
完全失業率が一番高かったのはいつ?
独立行政法人労働政策研究・研修機構がまとめたデータによると、1948年~2018年までの間で年平均としての完全失業率が最も高かったのは、2002年の5.4%です。以下、2003年の5.3%、2009年と2010年の5.1%と続いています。
日本経済は90年代初頭にバブル経済が崩壊して長期的な低迷期を迎え、その後2001年頃まで回復期を迎えないまま推移しました。完全失業率もその影響を大きく受け、1990年には2.1%でしたが、経済悪化の影響を受けて1994年には2.9%、1999年には4.7%にまで上昇しています。日本経済が景気回復局面に入ったのは2002年からとされていますが、その年に完全失業率の戦後最高値となる5.4%を記録したのです。
この就職難の時期である90年代半ば~2000年代前半に新卒となった世代は「就職氷河期世代」と呼ばれ、フリーターや派遣社員など非正規労働者として働く人が多く生じています。
完全失業率が3番目に高かった2009年と2010年は、リーマンショックの影響によるものです。アメリカの投資銀行・証券会社のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年9月に経営破綻し、その影響が連鎖的に世界に広がり、日本経済も大きな打撃を受けます。完全失業率は2002年以降に経済回復局面に入ってから少しずつ低下し、2007年には3.9%となっていました。ところがリーマンショックの影響により再び上昇し、2009年と2010年に5.1%となったのです。
完全失業率が一番低かったのはいつ?
では、完全失業率が最も低かったのはいつでしょうか。1948年~2018年までの年平均のデータでは、最も低かったのは統計開始年である1948年の0.7%で、以下、1949年の1.0%、1951年・1964年・1969年・1970年の1.1%と続いています。
やはり戦後間もない時期~高度成長期にかけては、日本経済が敗戦期から立ち直ろうとして急成長を遂げる時期と重なるので、完全失業率は低いです。その後、経済が成熟する70年代になって2%台まで上昇します。そしてバブル経済が崩壊した90年代に3%~4%台、2000年代に入ると5%台まで上がりました。
まとめ
完全失業率は労働力人口に占める完全失業者の割合で計算されます。ここでいう労働力人口とは、15歳以上の「就業者」と「完全失業者」を合わせた人口数のことです。また、完全失業者とは、働く意思があるにもかかわらず、就労できていない人のことを指します。緩やかな景気回復が続いている2010年代後半は、バブル期並みに完全失業率が低いです。なお、1948年~2018年の間で、年平均で完全失業率が最も高かったのは2002年の5.4%で、最も低かったのは戦後間もない1948年となっています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
ニュース -
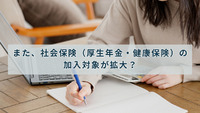
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース