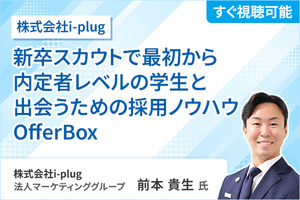公開日 /-create_datetime-/
人的資本経営とは?その概要とメリット、デメリットについて解説

先日、民間調査会社が人的資本経営における「本音」と「建前」を調査するため、従業員1,000名以上の大企業の経営者・役員を対象にアンケートを実施しました。その結果によると、人的資本を充実させるために時間をかけて人を育てるよりも、「コスト」「生産性」に重点を置きたいとする経営者・役員が約5割いることが明らかとなりました。建前では人を大事にすると言いつつも、コスト優先の意識は根強い状況であり、人的資本経営の命題は今後どのように広がっていくのでしょうか?
そこで今回は、人的資本経営とは何か、その利点と難点について考えてみましょう。
人的資本経営とは?
人的資本経営とは、人材を企業の「資本」として考えて、その価値の最大化を図り、中長期的な視野で企業価値を高めていく経営手法のことです。
人的資本経営の最大の特徴は、人材を「資本」と捉えている点にあります。従来の企業経営では人材は「カネ」「モノ」と同様の「資源」として扱われ、日本では年功序列や終身雇用によって囲い込みを行うのが基本的なあり方でした。
一方、人的資本経営では、企業が従業員を囲い込むのではなく、自律的な関係性の中で雇用する側と雇用される側それぞれがお互いに選択しあうことを想定しています。
また、従業員がもつ能力・経験を「無形資本」として捉え、企業としてどのような人的資本=無形資本をもつべきなのかを定量的に把握し、それを実現するための施策(人材育成策)を企業として考えていきます。
つまり、人材を「資本」として捉え、企業がその価値を引き出し、高めていくために「投資」をする(育成する)というのが人的資本経営の基本的なスタイルです。現在、各企業がどのような人的資本をもつのかは、投資家が企業全体の価値を判断する上での重要な要素です。
そのため、人的資本に関する情報を、適切な形で投資家に開示することも必要になってきます。2022年度現在、金融庁は「有価証券報告書」への記載の義務化を進めています。
人的資本経営を実現し、その情報を開示するには、人的資本の可視化・データ化が不可欠です。また、各企業が策定している経営戦略と連動する形で実施していくことも、企業が成長・存続していく上では必須事項でしょう。
■関連ニュース
「人的資本経営」の実現に向けて「戦略人事」採用が活発化
経済産業省が人的資本経営のあり方を提示
現在経済産業省は、国内企業の持続的な企業価値向上を支援するための人的資本経営=人材戦略のあり方として、一橋大学CFO教育研究センター長伊藤邦雄氏が策定した「人材版伊藤レポート」を公表しました。企業が取り組むべき人的資本経営の内容を提示しています。
この「人材版伊藤レポート」によると、人的資本経営を進める上でのポイントとして、「経営戦略と人材戦略の連動」「As is-To beギャップの定量的な把握」「企業文化への定着」の3点が挙げられています。
・経営戦略と人材戦略の連動・・・自社が定める経営戦略の実現を支えるために、人材戦略(人材育成方針)を策定することです。
・As is-To beギャップの定量的な把握・・・As is-To beとは「目標」と「現実」という意味で、「As is-To beギャップの定量的な把握」とは、目標と現実の間にどのくらいのギャップがあるのかを定量的に把握することです。経験や勘といった定性的な把握ではなく、可視化できる形でデータ化し、その上で具体的にギャップを埋めるための施策を考えます。
・企業文化への定着・・・人的資本経営を行うことで、企業価値向上につながる企業文化の醸成を目指すこと。自社事業の成功につながるような従業員の行動、姿勢を企業文化に定着させることを目指します。
人的資本経営が重視される背景要因
人材を「資源」ではなく「資本」とみなし、企業価値を示す基準となるという考え方は、欧米では2018年ごろからはじまりました。欧州では2018年に「国際標準化機構」において、人的資本情報開示のガイドラインが策定。2020年にはアメリカ証券取引委員会が上場企業を対象として、人的資本の情報開示の義務化をスタートさせています。
日本でもこうした欧米の動きに合わせて、2020年から取り組みを開始。2021年には、上場企業が取り組むべきコーポレートガバナンスの内容を示した「コーポレートガバナンスコード」を改訂し、人的資本の開示の内容が盛り込まれました。
■関連ニュース
ESG投資で注目の人的資本情報開示のグローバルメガトレンドとは?HRテクノロジーコンソーシアムがISO 30414をメインテーマとした日本初のオンラインイベントを開催
「人的資本の開示」が企業の未来の価値を計るものさしになる日は近い!?「コーポレートガバナンスコード改訂と人的資本開示」シンポジウムレポート
人的資本経営のメリット
人的資本経営の最大のメリットは、人材育成を合理的に行えるという点です。経験や勘といったものではなく、定量的・科学的・計画的にトレーニング、教育、研修を行えるように企業が「投資」を行います。従業員自身も、自分のキャリア・スキルを高めるという自律的な視点をもって能力開発に取り組めるので、モチベーションも高まります。
さらに、人材・従業員を資源とみなして徹底的に利用するのではなく、資本として保有する能力を活かしてもらうという視点をもつことで、従業員の働き方は自然と変わってくるでしょう。従業員に対して無理強いな残業や強制的な労働を要求する関係性はなくなり、現在政府が進めている「働き方改革」の理念や目的とも合致する就労形態を実現できます。
人的資本経営のデメリット
最大の課題は時間がかかることです。人的資本経営を実現するためには、人材育成プログラムを根本的に見直し、さらに今なお多くの企業で一般的な年功序列・終身雇用の慣行を変える必要があります。また、組織文化の整備も必要なため、「中長期的」な視点での取り組みが求められます。
そのため、冒頭で取り上げたアンケート結果のように、短期的に成果が必要な企業は、人的資本経営をあくまでコスト削減や生産性の向上に資するものとして考える「本音」が出てくるのです。
また、コストや生産性の観点にも関連していますが、人的資本経営の考え方に従って中長期的な視点で人材育成プログラムの策定や組織制度・文化の改善などに取り組んでも、望ましい成果が出るかどうかは不透明です。業績が苦しい企業の場合、そこまで将来を見据えた戦略を策定することが難しくなるでしょう。
まとめ
人的資本経営とは、人材を資源ではなく資本として捉え、人材育成を通して無形資本の価値上昇を図ることで、「企業価値」の上昇を図るという経営の手法です。日本独自の取り組みではなく、いわゆる欧米の経営手法の流用ではありますが、経済のグローバル化が進む中で、欧米が先導するスタンダードに合わせていくことも必要でしょう。
ただ、日本には根強く残る年功序列・終身雇用の慣行があるという点で、欧米企業とは異なります。「建前」と「本音」を使い分ける日本企業において、人的資本経営を「文化」として定着させていくには時間がかかるかもしれません。
■併せて読みたい関連ニュース
今年注目される人的資本の情報開示と人的資本経営の実体に迫る
人的資本の情報開示で、離職率の公表に躊躇していませんか?健康データを活用し、休職・離職を防ぐ具体的な方法を解説!
■参考サイト
PR TIMES|【人的資本経営、大企業経営者の「本音」とは?】「生産性の可視化・向上」の観点から、約8割が「従業員の勤怠と工数の一致」の重要性を認識
経済産業省|人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~
経済産業省|「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめました
経済産業省|人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
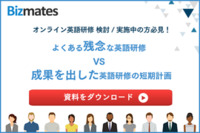
よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
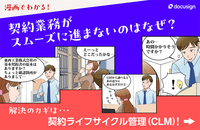
マンガでわかる!契約業務の課題と解決策 〜解決のカギはCLMにあり〜
おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与アウトソーシング導入チェックポイント
おすすめ資料 -
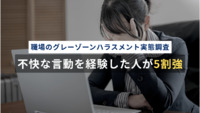
【職場のグレーゾーンハラスメント実態調査実施】ため息や舌打ち、飲み会や接待への参加強制、無視や仲間外れ等不快な言動を経験した人が5割強、抑制を規定する企業3割程度
ニュース -

夏の働き方、「出社したい派」が約半数に 物価高が影響「テレワークは光熱費がかかる」との声も
ニュース -

ドキュメント管理の基本と導入メリット|失敗しないためのポイントを解説
ニュース -

社会保険の随時改定とは?「月額変更届と算定基礎届ではどちらが優先されるか」などのポイントも解説します
ニュース -
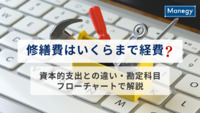
修繕費はいくらまで経費?資本的支出との違い・勘定科目・フローチャートで解説
ニュース -
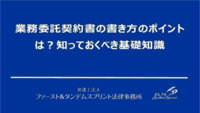
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -
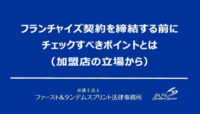
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -
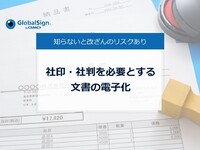
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -

企業の経理部門が押さえるべき“コスト削減”の実態。「ペーパーレス化」に「IT投資」…優先すべき施策とは?
ニュース -
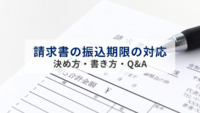
請求書の振込期限の対応はどうする?決め方・書き方・Q&Aまで網羅
ニュース -

2025年3月期決算(6月27日時点) 上場企業「役員報酬1億円以上開示企業」調査
ニュース -

DX時代を勝ち抜く!戦略的「電子データ管理」の重要性と実践ガイド
ニュース -

ドキュメント共有を効率化するクラウド活用術
ニュース









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました